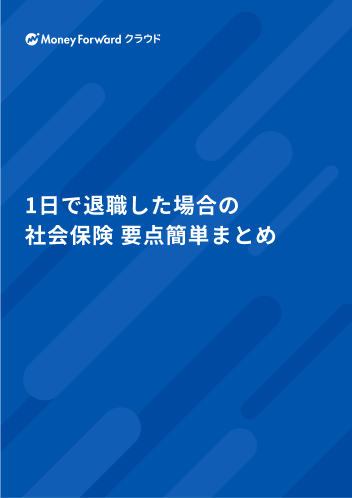- 更新日 : 2025年4月24日
一日で辞めた社員も社会保険料が発生する?退職日と保険料の関係を解説!
健康保険や厚生年金保険などの社会保険料は月単位で計算されます。また、月の途中で従業員が退職した場合には、原則として資格喪失月の保険料は発生しません。では、入社してすぐに従業員が退職するようなケースでは、社会保険料は徴収されるのでしょうか。
ここでは、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料と退職日の関係について解説します。
目次
一日で辞めた社員も社会保険料が発生する?
入社してすぐに従業員が退職した場合でも、社会保険料が発生します。これは、社会保険料が月単位で計算されるためです。以下で、社会保険料の基本と保険料の算出方法について解説します。
そもそも社会保険とは?
そもそも社会保険とは、病気や怪我・失業などのリスクに対して社会全体で備える制度をいいます。被保険者と呼ばれる加入者が保険料を支払い、何かあった場合の補償を保険料・税金をもとに行う仕組みが社会保険です。
会社が従業員に対して加入させる必要がある代表的な制度は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の4種類です。「狭義の社会保険」は健康保険・厚生年金保険など被用者保険各法と被用者年金各法を含めた公的医療保険と公的年金の2つの制度を指しますが、残り2つの労働保険の分野を含め、公的保険制度全体を指して「広義の社会保険」と呼ぶことがあります。
健康保険
業務外の病気・怪我、出産などに備える公的保険制度です。サラリーマンなど企業に雇用される方が主に加入し、健康保険に加入している被保険者は、医療機関での受診料の自己負担額が3割などと少なくなります。また、出産手当金や傷病手当金なども健康保険から支給されます。
厚生年金保険
働いている間に保険料を支払い、一定年齢以上になった際に年金として給付が受けられる公的年金制度です。厚生年金保険は、公務員や企業に雇用される人々が加入します。一方、自営業や無職の人々に対しては、国民年金制度があります。
雇用保険
雇用保険は、失業して給料が得られなくなった場合や就業の継続が困難となる事由が発生した場合に、労働者に対して給付を行う公的保険制度です。失業手当(基本手当)だけでなく、労働者のキャリアを支援するために就業機会を提供し、労働者が失業した際の生活を守り、就職を促進します。また、離職防止・雇用継続を目的とした介護休業給付や育児休業給付などの制度もあります。
労災保険
業務上や通勤途上の怪我や病気、死亡、障害など、被災した労働者や遺族を守るために給付を行う公的保険制度です。事業主は、一人でも従業員を雇用する場合には労災保険に加入する義務があります。
社会保険制度について、さらに詳しく知りたい場合はこちら
月の途中で退職した社員の社会保険料の取扱いは?
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、月単位で計算されます。月の途中で退職した場合、その前月分までの保険料を納める必要があります。
社会保険料は日割り計算ができない
社会保険料は、日割り計算ができません。月単位で徴収されますので、月の途中で従業員が退職した場合、資格喪失月(退職日の翌日のある月)の前月分までの社会保険料の納付が必要です。ただし、退職日が月の末日になる場合には、資格喪失日が翌月1日となるため、退職月の分まで社会保険料の納付が必要となります。
入社後すぐに退職しても1ヶ月分の社会保険料が給与から徴収される
入社して2週間で退職するなど、社会保険に加入した月と資格喪失した月が同月の場合には、ひと月分の社会保険料の納付が必要です。
従業員負担分の社会保険料は、退職時の給与から控除します。会社は、事業主の負担分とあわせて、翌月末までに保険料を納付しなければなりません。ただし、健康保険と厚生年金保険とでは以下の点で取り扱いが異なるため注意が必要です。
健康保険と異なり、厚生年金保険については、資格を取得した月に喪失し、さらに同月に他の事業所で厚生年金保険または国民年金の資格を取得した場合には、先に資格喪失した厚生年金保険料の納付の必要はありません。このような場合、企業としては一旦保険料を納付することとなりますが、後日年金事務所から保険料還付の連絡が来ます。保険料が還付されたら、会社経由で退職した従業員に従業員負担分の保険料を返金する必要があります。
退職したら保険証はいつまで使える?
保険証は、退職した翌日から効力を失効します。そのため、保険証が利用できるのは退職日までです。そのため、退職する従業員については、扶養家族分も含め、退職日に保険証を返還してもらう必要があります。
参考:会社を退職した場合、保険証が使用できるのは退職日までです|全国健康保険協会
退職・転職時に必要な社会保険の手続きは?
従業員の退職に伴い、事業主は社会保険の資格喪失の届出を行います。健康保険・厚生年金保険については、退職日の翌日から5日以内に届出が必要です。雇用保険については退職の翌々日から10日以内に届出を行う必要があります。
退職後の国民健康保険の手続き
会社を退職したあと、自営業になる、または求職活動中など無職の状態であれば、国民健康健康保険の加入手続きを本人が行います。国民健康保険は、市区町村によって運営される医療保険制度ですので、市区町村の窓口で加入の手続きを行います。
なお、健康保険の任意継続を選択した場合や、配偶者の被扶養者になる手続きを退職日の翌日付で行った場合には、国民健康保険への加入の必要はありません。
扶養家族も個別で国民健康保険に加入する必要がある
退職した本人が、転職し他の事業所で健康保険に加入する、または健康保険の任意継続を選択しない限り、それまで扶養に入っていた家族は個別で国民健康保険に加入する必要があります。
入社月に退職した場合、社会保険料が発生する
社会保険料の計算は月単位で行われます。退職した翌日が含まれる資格喪失月は保険料の納付は原則として発生しませんが、加入月(入社月)と資格喪失月(退職月)が同じ場合には、保険料の納付が必要です。ただし、厚生年金保険料は後日還付されることがありますので注意が必要です。還付後があった場合には、退職した従業員に保険料を返金することを忘れないようにしなければなりません。
退職が決まった従業員がいる場合には、必要となる手続きを事前に確認し、手続き漏れが発生しないように準備しておきましょう。
よくある質問
一日で辞めた社員も社会保険料が発生する?
社会保険料は月単位で計算されます。入社して社会保険に加入した月と、退職して資格喪失した月が同月の場合、在籍した日数に関わらずひと月分の社会保険料の納付が発生します。詳しくはこちらをご覧ください。
退職したら保険証はいつまで使える?
保険証は退職日の翌日に効力を失効します。退職し社会保険の資格を喪失したにも関わらず使用することはできません。そのため、被保険者である本人と被扶養者である家族の分の保険証を返還する必要があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
退職時の社会保険資格喪失日はいつ?社会保険喪失届の書き方も解説!
従業員の退職にあたっては、社会保険資格喪失の手続きをしなければなりません。5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。退職日の属する月の社会保険料はかかりませんが、月末である場合は保険料が発生します。喪失…
詳しくみる週30時間未満の従業員、パートの社会保険加入とは?適用範囲の拡大の変更点を解説
労働時間が週30時間未満のパート・アルバイトについて、2022年10月より社会保険の適用範囲が広がりました。さらに、2024年10月からは常時雇用される従業員数が51人以上の企業まで適用が拡大しています。 ここでは、社会保険の適用範囲の拡大…
詳しくみる社会保険と年金の関わり – 厚生年金と同じ?
社会保険における年金は、生活を送るうえでの万が一のリスクに備えるための保険です。厚生年金や国民年金を支払うことで老後だけでなく、就労が困難になってしまった場合も年金受給者としてお金を受け取れます。 この記事では、社会保険における年金の概要や…
詳しくみる企業年金は3種類!厚生年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金の違いと特徴を解説
退職時または60歳以降に受け取ることができる給付に企業年金があります。企業年金は、3階建ての年金の3階部分(1階部分の「基礎年金」、2階部分の「被用者年金」)を担っている年金制度で、3種類の制度が存在します。 今回は、企業年金の種類とそれぞ…
詳しくみる健康保険とは?被用者保険と国民健康保険の違い
健康保険は、日本の医療制度を支える重要な保険制度です。会社員や公務員が加入する政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合のほかに、個人事業主や自営業者が加入する国民健康保険があります。 ここでは、日本の健康保険制度の種類や加入対象者について解…
詳しくみる雇用保険の手続きについて
雇用保険の手続きには、事業主が行うものと受給者が行うものの2種類があります。ここでは、事業主と受給者にわけて雇用保険の必要な手続きについて解説します。 事業主が行う雇用保険の手続き 雇用保険は国が管理および運営している強制保険であるため、労…
詳しくみる