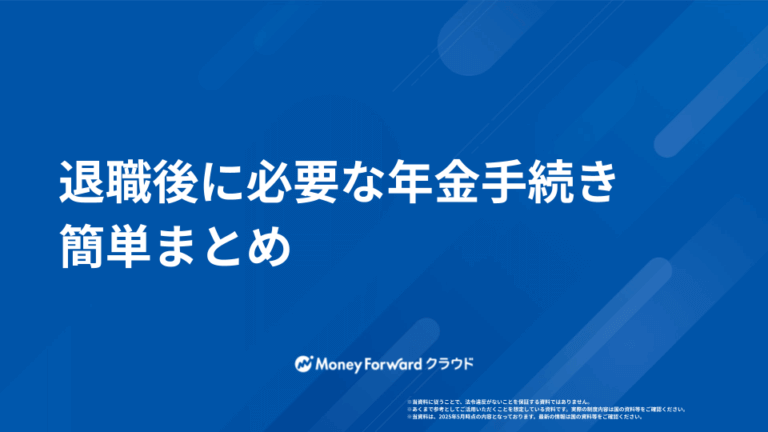- 更新日 : 2025年6月23日
退職後に必要な年金手続きは?ケースごとに流れや準備するものを解説
退職後は、厚生年金や国民年金への加入に関する手続きが必要です。ただし、退職時の状況や年齢に応じて、手続きが異なることがあります。とくに、年齢が60歳以上の方は任意加入の手続きを検討することも重要です。スムーズに手続きするために、必要な書類や流れを事前に確認しておきましょう。
本記事では、退職後の年金に関する具体的な手続きの流れや準備すべきものを解説します。
目次
退職後、年金に関する手続きはどうすればいい?
退職後は、必要に応じて年金の加入手続きを行います。たとえば、フリーランスになる場合は、国民年金第1号被保険者に加入しなければいけません。しかし、個人の状況や年齢により年金に関する手続きは異なるため、注意が必要です。
年金の切り替え手続きは、以下のように区分されます。
| ケース | 区分 |
|---|---|
| 配偶者が適用事業所に勤務している場合(健康保険・厚生年金加入)で、配偶者の被扶養者となる場合 | 国民年金第3号被保険者 |
| 配偶者が適用事業所に勤務している場合(健康保険・厚生年金加入)で、配偶者の被扶養者とならない場合 | 国民年金第1号被保険者 |
| 配偶者がいない、または配偶者が適用事業所に勤務しない場合(自営業・主婦等) | 国民年金第1号被保険者 |
以下では、各年金手続きについて解説します。
国民年金に加入するケース(第1号被保険者)
健康保険(協会けんぽ)および厚生年金保険に加入している被保険者が退職し、転職まで間があく場合や、自営業・フリーランスになる場合は、国民年金第1号被保険者に加入しなければいけません。該当の期間中は、国民年金保険料を納める義務があります。
60歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方は、65歳まで国民年金に任意加入できます。また、受給資格期間を満たしていても、保険料の納付期間が短く満額の年金を受け取れない方も同様です。
ただし、国民年金第1号被保険者となる場合は、退職した時期により手続きが異なるため注意が必要です。詳しい手続きについては、後ほど紹介します。
国民年金に加入するケース(第3号被保険者)
退職後、もし配偶者が働いていてその保険に加入している場合、被扶養者となることで国民年金第3号に加入できます。
加入するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 日本国内に住んでいること
- 20歳以上60歳未満であること
- 厚生年金保険に加入する配偶者(※)に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること
※65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く
ただし、日本国内に住んでいても、日本国籍でなく「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する方は、被扶養者には該当しません。
詳しい手続きについては、後ほど紹介します。
厚生年金に加入するケース
退職後、厚生年金保険を適用する職場に転職する場合は、引き続き70歳まで厚生年金に加入します。
厚生年金保険は、会社単位の適用事業所であり、事業所に使用される人は、国籍や性別、賃金の額にかかわらず、すべて被保険者とみなされます。
ただし、従業員が複数の会社で働いている場合、どの会社で厚生年金に加入するかを決める必要があるため注意が必要です。従業員が70歳未満であれば「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」、70歳以上なら加えて「厚生年金保険 70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出が求められます。提出期限は、働き始めてから10日以内とされているため期日を守って提出しましょう。
上記を提出することにより、どの会社を年金のメインとするか決めて、保険料の計算や給付内容が整理されます。
厚生年金に加入する際の詳しい手続きは、後ほど紹介します。
国民年金の第1号被保険者となる場合の手続き
第1号被保険者になるための基本情報は、以下のとおりです。
| 必要書類の提出期限 | 退職日の翌日から14日以内 |
|---|---|
| 手続きする場所 | 住所地の市区役所や町村役場 |
| 手続きする人 | 本人または世帯主 |
| 手続きに必要な書類 | 基礎年金番号通知書や年金手帳のなど、基礎年金番号がわかる書類 |
以下では、各手続き方法について解説します。
手続き時期
第1号被保険者となる場合、退職日の翌日から14日以内に提出する必要があります。
会社を退職して厚生年金の加入資格がなくなった場合や、学生で任意加入する場合、または海外在住の日本人が帰国後に対象になる場合は速やかに手続きが必要です。
手続きは住所地の市区町村役場で行い、期限は該当する状況が発生した月から14日以内に行いましょう。
手続きを行う人
第1号被保険者への加入手続きは、原則本人が行います。ただし、特別な事情で本人が手続きできない場合、世帯主が代行して手続きすることも可能です。
世帯主が手続きする場合は、世帯主の本人確認ができる書類、たとえば運転免許証、マイナンバーカードなどが必要です。
加入手続きは、本人または世帯主が行うようにしてください。
準備するもの・必要書類
退職後に第1号被保険者になる場合、以下の書類が必要です。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 被用者年金制度の資格喪失日を証明できるもの
- 退職証明書
- 健康保険喪失証明書
- 雇用保険被保険者離職証明書(離職票)
- 第1号・第3号被保険者資格取得推奨状
- 他に必要な書類がある場合
参考:厚生労働省「【国民年金】加入・喪失・変更 必要書類リスト」
上記の書類を持参し、住所地の市区役所または町村役場に提出して手続きを進めましょう。
保険料の納付方法
第1号被保険者になった際は、1ヶ月あたり16,980円(令和6年度)を以下の5つの方法で納付します。
- 納付書
- 口座振替
- クレジットカード
- スマートフォンアプリ
- ねんきんネットを活用した納付書によらない納付
上記の中でも、口座振替はまとめて前払いすることで国民年金保険料が割引されるため、おすすめの方法です。
金融機関の窓口やコンビニエンスストアでの支払いが難しい場合でも、口座振替ですぐに支払いできます。
また、近年では国民年金保険料納付書が手元になくても、ねんきんネットからインターネットバンキングを利用してPay-easy納付が可能です。
必要に応じて適切な支払い方法を選択しましょう。
国民年金の第3号被保険者となる場合の手続き
国民年金の第3号被保険者に加入する場合、配偶者の勤務している会社を通して手続きする必要があり、第1号被保険者とは方法が異なります。
| 必要書類の提出期限 | 退職してから5日以内 |
|---|---|
| 手続きする場所 | 配偶者の勤務先または日本年金機構 |
| 手続きする人 | 配偶者の勤務先 |
| 手続きに必要な書類 |
|
参考:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
以下では、具体的な手続きについて解説します。
手続き時期
国民年金の第3号被保険者の手続きの時期は、退職してから5日以内です。被保険者が事業主を経由し、被扶養者届を提出する必要があります。
たとえば、結婚や配偶者の就職により扶養に入った場合や扶養の条件を満たした場合が該当します。
手続きが遅れると未加入期間が生じ、将来の年金に影響を与える可能性があるため注意が必要です。速やかに対応することで、適正な年金記録を確保できます。
手続きを行う人
国民年金の第3号被保険者の手続きは、配偶者の勤務先を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。
ただし、協会けんぽ以外の健康保険の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号関係者届」のみを日本年金機構に提出してください。
準備するもの・必要書類
国民年金の第3号被保険者に加入する場合、以下の書類が必要です。
- 続柄確認できる書類
- 被扶養者の戸籍謄(抄)本
- 住民票の写し(被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である場合に限る)
※ただし、被保険者と扶養認定を受ける方の双方のマイナンバーが届出書に記入されていれば「続柄確認できる書類」は省略できます。
- 収入要件確認できる書類(事業主の証明があれば添付書類は不要)
- 仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(被保険者と別居している被扶養者がいる場合)
- 内縁関係を確認するための書類
- 内縁関係にある両者の戸籍謄(抄)本
- 被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
上記の書類を退職後5日以内に、事務センターまたは管轄の年金事務所に提出しましょう。
保険料の納付方法
第3号被保険者になる場合、自身の保険料を納付する必要はありません。
保険料の支払いが必要ない理由は、第2号被保険者が支払いを負担しているからです。第2号被保険者とは、70歳未満の会社員や公務員など、厚生年金の加入者です。
そのため、原則本人は保険料の支払いはありません。
厚生年金に加入する手続き
厚生年金は任意継続できないため、退職後に引き続き加入できません。しかし、退職後に厚生年金保険の適用事業所に転職する際は、引き続き厚生年金保険に加入します。
| 必要書類の提出期限 | 再就職日から5日以内 |
|---|---|
| 手続きする場所 | 日本年金機構 |
| 手続きする人 | 事業主 |
| 手続きに必要な書類 |
|
参考:日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」
以下では、厚生年金に加入する手続きの流れを紹介します。
手続き時期
厚生年金保険の適用事業所に転職する際は、再就職日から5日以内に提出が必要です。
健康保険・厚生年金保険は、会社単位で適用事業所となり、事業所で働く人が対象となります。対象者には国籍や性別、賃金の額に関係なく適用されます。
手続きを行う人
厚生年金は、事業主が被保険者資格取得届を日本年金機構へ提出することで、加入できます。そのため、従業員は、事業主が手続きに必要な書類を用意する必要があります。
原則、自身で行う手続きはないため、必要書類を用意しておきましょう。
準備するもの・必要書類
厚生年金に加入するために、従業員が確認するものは以下のとおりです。
| 対象者 | 手続き内容 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 適用事業所に雇用された70歳未満の従業員 | 「被保険者資格取得届」の記入に必要な書類を準備しておく | 基礎年金番号通知書 年金手帳またはマイナンバーカード |
| 同時に複数(2か所以上)の適用事業所に勤務したことにより、年金事務所または保険者を選択する | 健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 | |
| 適用事業所に雇用された70歳以上の従業員 | (引き続き同一の事業所に使用されるとき) | 厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届 |
| (複数の適用事業所に使用されることになったとき) 同時に複数(2か所以上)の適用事業所に勤務したことにより、年金事務所または保険者を選択する | 厚生年金保険 70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届 |
参考:日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」
事前に準備すべき書類を揃え、期限内に事業主に提出しましょう。
保険料の納付方法
厚生年金では、標準報酬月額と標準賞与額に保険料率をかけた額を、本人(被保険者)と事業主が折半で支払います。
標準報酬月額は、従業員の月々の給料を1〜50(厚生年金は1〜32)の等級に分けて表したものです。主に、厚生年金保険料や健康保険料の金額を計算する際に利用します。
標準賞与額は、実際の税引き前の賞与から1千円未満の端数を切り捨てたもので、支給1回につき150万円が上限です。
算出された標準報酬月額と標準賞与額を基に、保険料が計算されます。
本人が負担する保険料は、給料から天引きされ、事業主負担の保険料を合わせて事業主が納付します。
厚生年金加入者の退職後、扶養されている配偶者が行う手続き
厚生年金加入者が退職した場合、扶養されている配偶者の手続きは、退職者の状況により異なります。
まずは、退職者が国民年金第1号被保険者になる場合は、扶養配偶者は「国民年金第3号被保険者」から外れます。そのため、配偶者自身が国民年金第1号被保険者として加入手続きを行い、保険料を直接支払わなければいけません。手続きは市区町村役場の年金窓口で行います。
また、退職者が新たな勤務先で厚生年金に加入する場合、扶養配偶者は「第3号被保険者」のままとなり、とくに手続きは不要です。ただし、転職後の会社から「健康保険被扶養者異動届」が求められる場合があり、必要に応じて配偶者の収入状況を証明する書類の提出をします。
どちらの場合でも、状況に応じて健康保険の扶養資格や手続き内容が変わるため、早期に確認することが重要です。
退職後の確定拠出年金(企業型DC)に関する手続き
在職中に確定拠出年金(企業型DC)に加入していた場合、退職後に必要になる手続きを進めなければいけません。確定拠出年金は、企業が掛金を毎月積み立てし、従業員が自ら年金資産を運用する制度です。以下では、退職後の確定拠出年金の手続きについて解説します。
転職先に企業型DCがある場合
まず、退職した企業の確定拠出年金資産は、新たな転職先の企業型DCへ移管するか、個人型確定拠出年金(iDeCo)に移管します。資産を移管しない場合は、原則として「国民年金基金連合会」に一時的に預けることになりますが、預けている期間は運用益が発生しません。そのため、早期に移管することが推奨されます。
転職先での手続きは、会社が用意する書類に従い、資産の移管申請を行います。また、退職前の企業のDC窓口にも「資格喪失届」や移管手続きの確認を依頼することが重要です。
転職先に企業型DCがない、自営業や専業主婦・主夫になる場合
退職後、転職先に企業型DCがない場合や自営業、専業主婦・主夫になる場合、確定拠出年金の資産管理方法を決める必要があります。
最も一般的なのは、個人型確定拠出年金(iDeCo)への移管です。iDeCoに移管すれば、引き続き運用を行え、税制優遇を受けられます。手続きはiDeCoを取り扱う金融機関で行い、移管申込書類を記入・提出してください。
移管を行わない場合、資産は国民年金基金連合会に自動移管されますが、期間は運用が行われず、管理手数料が発生するため注意が必要です。移管手続きは退職日の翌日から6ヶ月以内に行う必要があります。
適切な手続きを行い、資産を有効活用しましょう。
退職後は自身の状況に応じて適切に年金手続きをしよう
退職後は、迅速に厚生年金や国民年金の手続きを行いましょう。手続きを怠ると未加入期間が発生し、将来受け取る年金額に影響を及ぼす可能性があります。
まずは、自身の状況に応じて必要な手続きを確認することが大切です。不明点があれば、市区町村の窓口や年金事務所に相談し、確実に手続きを進めましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
賞与査定表とは?評価基準やテンプレートなども紹介!
ボーナスは、会社の業績と個人の実績を総合的に判断し支給額を決定します。ボーナスの支給額を決める際、個人の実績を査定するのに用いられるのが賞与査定表です。査定項目は大きく分けて業務考課・能力考課・情意考課の3つがあります。当記事では、賞与評価…
詳しくみるバリキャリとは?特徴や年収、多い職業、目指し方を解説
バリキャリとは、バリバリ働く女性を指す言葉です。バリキャリと呼ばれる女性には、キャリア志向があり、昇進や昇給に意欲的という特徴があります。 近年では、女性の社会進出に伴い、バリキャリと称されるように働く女性が増えています。ここでは、バリキャ…
詳しくみる体調不良で休めないのはパワハラ?欠勤が多い従業員への対応も解説
体調不良で休めない状況は、パワハラに該当する可能性があります。一方で、欠勤が多い従業員への対応に悩む企業も少なくありません。本記事では、体調不良時の休暇取得とパワハラの関係、そして欠勤が多い従業員への適切な対応方法を解説します。 体調不良で…
詳しくみる忌引き休暇は有給扱いになる?日数や申請方法について徹底解説
忌引き休暇が有給の休暇扱いになるかは、会社の規定により異なります。法律上の決まりはなく、企業ごとに運用が異なるため、事前にルールを定めて準備しておくことが重要です。 本記事では、忌引き休暇の概要や導入の流れについても詳しく解説します。忌引き…
詳しくみる工事のお知らせ例文・テンプレート付き!近隣挨拶の範囲やマナーも解説
マンションの大規模修繕など、工事を行う際、近隣住民への配慮は欠かせません。騒音や振動、粉じんなどによる影響を最小限に抑えるためにも、事前の工事のお知らせは重要です。 しかし、具体的にどのような内容を記載し、どの範囲まで配布すべきか悩む方も多…
詳しくみるディーセントワークとは?定義や取り組み内容についてわかりやすく解説
ディーセントワークを目指す職場が増えています。働き方や職場環境を改善する動きが広がっているのです。そこでこの記事ではディーセントワークという言葉の意味や、ディーセントワークの実現に向けた取り組みのメリットなどについてわかりやすく解説します。…
詳しくみる