- 更新日 : 2025年11月5日
労働時間が月200時間とは?手取りの目安や残業の上限を解説
厚生労働省では、時間外・休日労働時間が月80時間を超えたら医師による面接指導が必要なレベルであると言及しています。では、労働時間が月200時間の場合、見直すべき状況かどうかは内容次第で変わります。
本記事では、労働時間が月200時間の状況について、実態と手取りの目安や残業の上限を解説します。
目次
労働時間が月200時間とは?
労働時間が月200時間とは、法定労働時間を超えている状況です。労働基準法で定められている1日8時間・週40時間を基準にした月の法定労働時間を指します。ここでは、月200時間の労働時間に対して、必要な対応などを詳しく解説しましょう。
そもそも労働時間とは?
労働時間は、単純に労働と認められた時間が労働時間に該当します。厚生労働省の公開している2000(平成12)年3月9日の最高裁判決では、労働時間が次のように定義されています。
- 労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間
- 使用者の明示または黙示の指示により業務に従事する時間
- 使用者の明示または黙示の指示にもとづき、参加などが事実上強制されている時間
引用先:厚生労働省|そもそも『労働時間』とは?『通勤時間』とは?
労働基準法では、使用者の指示のもと、強制され業務に従事した時間が労働時間だと考えられるでしょう。勤務地に移動を強いられる場合も労働時間と判断される可能性は高いです。
休憩時間が労働時間になる可能性
労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に設けなければなりません。
休憩時間は、労働時間に含まれないため、指揮命令下にあると認められる業務に従事した場合、その時間は労働時間として扱われます。つまり、休憩時間も何らかの業務(指揮命令下にあると認められるもの)をすると労働時間とみなされます。休憩時間が労働時間とみなされた場合は、時間外労働の扱いおよび、別途休憩時間の設置が必要になるでしょう。
法定労働時間と所定労働時間
労働基準法第32条では、「労働時間・休日に関する原則」が定められています。
- 労働基準法で制定された労働時間の限度:1日8時間および週40時間までの労働時間
- 労働基準法で制定された休日:毎週少なくとも1日
1日8時間および週40時間は、労働基準法で定められた法定労働時間のことです。そして1週間に少なくとも1日の休日を設けることは、法定休日と呼ばれています。
※参考:「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」厚生労働省
| 法定労働時間 |
|---|
|
法定労働時間をもとに、年間休日を設定します。
| 法定休日 |
|---|
365日÷12カ月=30.416日 →30.416日÷7日(1週間)=4.345週 →4.345週×12カ月=52.14日(端数を切り捨てる) 法定休日:52日(週1日休日の場合の年間休日) |
| 法定労働時間を反映させた年間休日の最低ライン |
52日(365日÷7日)×40時間(労働基準法で定める週労働時間)=2080時間 2080時間÷8時間(労働基準法で定める1日の労働時間)=260日 365日-260日=105日 |
所定労働時間は、会社や事業所ごとに就業規則で定める労働時間です。法定労働時間に抵触しないように作成する必要があります。
労働時間が月200時間で発生する残業時間の目安
労働時間が月200時間ある場合は、年間休日105日の法定労働時間をもとにした所定労働時間と比較すると次の結果になります。
| 法定労働時間をもとにした所定労働時間 | 労働時間が月200時間の場合 | 労働時間が月200時間の場合による残業時間 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 2,080時間 | 2,400時間 | 320時間 |
| 1カ月 | 173.3時間 (2,080時間÷12カ月) | 200時間 | 26.7時間 |
| 1週間 | 40時間 | 46時間 | 6時間 |
| 1日 | 8時間 | 9.4時間 | 1.4時間 |
この結果はあくまで目安になりますが、労働時間が200時間の場合は、ほぼ毎日1.4時間以上の残業と考えられるでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール
年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。
本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。
労働時間管理の基本ルール【社労士解説】
多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。
労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。
36協定の締結・更新ガイド
時間外労働や休日労働がある企業は、毎年36協定を締結して労働基準監督署に届出をしなければなりません。
本資料では、36協定の役割や違反した場合の罰則、締結・更新の手順などを社労士がわかりやすく解説します。
割増賃金 徹底解説ガイド(時間外労働・休日労働・深夜労働)
割増賃金は、時間外労働や休日労働など種類を分けて計算する必要があります。
本資料では、時間外労働・休日労働・深夜労働の法的なルールを整理し、具体的な計算例を示しながら割増賃金の計算方法を解説します。
労働時間が月200時間は多いか少ないか
法定労働時間をもとにした所定労働時間は、1年で2,080時間、1カ月173.3時間(2,080時間÷12カ月)を目安にしています。労働時間が月200時間の場合は、200時間×12カ月=1年2,400時間の労働時間です。
月の労働時間が200時間の場合は、法定労働時間よりも年間320時間多くなります。そのため、月200時間は法定労働時間と比較したら多いと判断できるでしょう。一方、日本の平均労働時間は、法定労働時間よりも低くなります。
日本や世界の平均年間総実労働時間は、2022年の状況が次の通りです。
- アメリカ:1,811時間
- 日本:1,607時間
- イタリア:1,694時間
- スウェーデン:1,440時間
- フランス:1,427時間
- イギリス:1,532時間
- ドイツ:1,341時間
※引用「⼀⼈当たり平均年間総実労働時間(就業者)|データブック国際労働比較2022」独立行政法人 労働政策研究・研修機構
労働時間のデータは、一般社員だけではなくパート社員も含んでいるため、法定労働時間で算出した年労働時間よりも低くなっています。
労働時間が月200時間の手取りの目安
労働時間 が月200時間の場合は、手取りでどのくらい受け取れるのか目安について解説します。
労働時間の計算方法
労働時間の計算は、法定内時間と法定外時間、法定休日労働時間、深夜労働時間を分類して算出します。
| 労働時間 | 計算式・割増しなど |
|---|---|
| 法定内労働時間 (1日8時間および週40時間まで) | 月給÷1カ月の平均所定労働時間=1時間当たりの賃金額 |
| 法定外労働時間 (勤務日に発生した法定時間超過の残業) | 1時間当たりの賃金額×25%増し ※1カ月50時間以上を超えた場合は50%増し |
| 休日労働時間 | 1時間当たりの賃金額×35%増し |
| 深夜労働時間 (22時~翌朝5時までの時間帯) | 1時間当たりの賃金額×25%増し |
※参考:「割増賃金の計算方法」厚生労働省
労働時間は、仮に基本給が20万円として、法定労働時間の基準となる173.8時間で割ると、1時間当たりの賃金が1,151円(四捨五入)です。労働時間200時間の場合は、次のような計算結果になるでしょう。
法定時間外となる26.2時間は、残業代として25%以上の割増率で計算されます。合わせた給料は、23万7,702円になるでしょう。
給料ごとの手取り額の目安
給料ごとに税金や社会保険料などで手取り額は、変化します。ここでは、月給20万円~50万円までの手取り額について表にしてみました。
例:東京都在住30代会社員
| 20万円 ※月収 | 25万円 ※月収 | 30万円 ※月収 | 35万円 ※月収 | 40万円 ※月収 | 45万円 ※月収 | 50万円 ※月収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 3,191円 | 4,500円 | 5,950円 | 7,508円 | 10,166円 | 13,708円 | 16,833円 |
| 住民税 | 7,216円 | 9,833円 | 12,741円 | 15,858円 | 19,125円 | 22,666円 | 25,791円 |
| 健康保険料 | 10,000円 | 13,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 20,500円 | 22,000円 | 25,000円 |
| 厚生年金 | 18,300円 | 23,790円 | 27,450円 | 32,940円 | 37,515円 | 40,260円 | 45,750円 |
| 介護保険 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 雇用保険 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,400円 | 2,700円 | 3,000円 |
| 手取り額 | 160,091円 | 197,376円 | 237,058円 | 273,593円 | 310,293円 | 348,665円 | 383,625円 |
東京在住で扶養家族がいない場合の30代会社員は、おおよその手取り額の目安になると考えられます。
月の労働時間の上限は何時間まで?
月の労働時間200時間が常態化してしまうと、月額固定給の額にもよりますが、毎月3万後半〜5万円台の残業代が発生する可能性があります。なお、人事担当者が注意すべきことは、法定労働時間の上限と時間外労働の上限です。
法定労働時間の上限
労働時間の計算方法の項でも触れましたが、法定労働時間(1日8時間まで、週40時間まで)を超えた労働をさせる場合は労使の合意にもとづく所定の手続きが必要です。
- 労働基準法第36条にもとづく労使協定(36協定)
- 所轄労働基準監督署長への届け出
法定労働時間は、労働者保護のための法律上の規制ですが、企業の現実の経済活動では対応できないこともあります。そこで、労使で合意のうえ、時間外労働のための協定を締結し、監督官庁である労働基準監督署に届け出ること例外を認めています。
この労使協定が、いわゆる「36協定」であり、本来であれば、労働基準法違反となって罰則を受けるところを免れる法的手続きとなります。
時間外労働の上限
時間外労働は、前述した36協定や所轄の労働基準監督署への手続きにより、罰則から免責されます。2019年以前では、36協定で合意できれば、時間外労働の限度時間(月45時間・年360時間)は目安に過ぎず、法的拘束力はありませんでした。しかし、大企業向けの改正(2019年4月から)と、中小企業向けの改正(2020年4月から)を行った時間外労働の上限規制では、臨時的な特別な理由があっても上限を超える例外は認められなくなりました。
改正後の時間外労働の上限は、月45時間および年360時間です。この上限は、臨時的な特別な理由があれば超えられる上限でもあります。次に示す時間外労働の上限は、36協定で合意しても、いかなる事情があっても超えられません。
- 年720時間の時間外労働
- 月100時間の時間外労働と休日労働の合計
- 時間外労働と休日労働の平均が1月当たり80時間※
最後の80時間は、2カ月平均や3カ月平均、4カ月平均、5カ月平均、6カ月平均とすべてが80時間以内に収まっていれば問題ありません。
また、月45時間以上を超えられる状況は、年6カ月が限度となっています。もし違反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金などの罰則が科せられるので注意しましょう。
参考:2019年4月「時間外労働の上限規制分かりやすい解説」厚生労働省
時間外労働が月80時間超で過労死ラインに
時間外労働は、月80時間を超えると過労死するリスクが高まるとされています。厚生労働省の提示する面接指導制度では、医師による面接指導により、月80時間超えの時間外・休日労働で疲労が認められる労働者の申し出を推奨しています。
月80時間以上の時間外・休日労働により健康状態に異変がある労働者は、医師による面接指導など適切な処置が受けられます。
参考:「長時間労働者への 医師による面接指導制度について」厚生労働省
労働時間が月250時間超は違反になる?
労働時間が月250時間を超えている場合は、法令違反の可能性が高い状況と判断しておくべきでしょう。例えば、法定労働時間をもとにした月の労働時間が173.8時間だとすると、月250時間の時間外労働時間は次のように算出されます。
月80時間に満たないため、36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ている場合は認められますが、限度時間を超えないことが必要です。ただし、6カ月以内の平均時間が80時間を超え、6カ月以上続けることは労基法違反となります。
月250時間の労働を知らずに続けてしまうと、罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金など)の対象になるため、早めに対応しましょう。時間外労働などの労働条件の相談先は、次の機関がおすすめです。
時間外労働・休日労働に関する協定届のテンプレート(無料)
時間外労働・休日労働に関する協定届(エクセル)のダウンロードはこちら
時間外労働・休日労働に関する協定届(ワード)のダウンロードはこちら
月の労働時間を減らす取り組み
月の労働時間は、一つひとつの現状を見直すことで改善の糸口が見えてくることが考えられます。会社や事業所では、組織的に労働時間を減らす方向で取り組むことが必要です。
ノー残業デーを設定する
残業は、周囲の誰かが残っているからやらざる負えないという場合もあれば、定時で帰ったら白い目で見られるという場合もあります。「残業をしないで定時に帰ろう」と通達しても、職場の雰囲気が定時に帰宅できないムードであれば時間外労働を減らせません。
残業を「善業」とする社風を改めて、「残業は利益を生み出さないもの」というイメージに切り替え、あえて「ノー残業デー」を設定することも必要です。「毎週水曜日はノー残業デー」とか、「毎月7の付く日は、定時で帰る日」など社内で共通認識できるテーマを決めましょう。
勤怠管理システムで管理する
業務が定時に終わらない要因は、社内のあらゆる部分に存在するでしょう。社員全員が、時間を意識した行動をできるようになれば、無駄な残業が少なくなる可能性があります。
その一つとして、勤怠管理システムによる勤怠管理で残業の発生を早めに検知できるようにしましょう。勤怠管理システムの導入は、社員の仕事開始から終了までの一部始終を管理できます。タイムテーブルと行動内容の中に問題が生じれば残業の原因にもなるでしょう。勤怠管理システムは、その部分を早めに指摘できる役割としても有効です。
業務を効率化する
月の労働時間を減らすには、現状の労働時間に費やしている業務プロセスをすべて洗い出す必要があります。その際には、属人的な業務や定型的な業務などを抽出し、IT技術などに代替できる部分は、移行しましょう。業務効率化は、一部の人間だけで取り組まないで、全社的な取り組みで効率化できれば、労働時間の削減も実現可能でしょう。
適切な人員配置をする
時間外労働が常態化している職場は、適切な人員配置のできていない状態かもしれません。無理な状態を続けて、離職者を増やしている状態は、慢性的な人手不足にもつながります。この状態では、長期的な目線で考えれば担当者の健康状態を損ね、仕事を続けることが難しくなるでしょう。適切な人員配置をする業務内容に対して、必要な人材の見直しが必要です。
労働時間が月200時間を放置せずに社内全体で改善しよう
会社や事業所の人事担当者は、労働時間が月200時間以上の社員を放置したままではないでしょうか。日常的に時間外労働をくり返す社員は、健康面や精神面などどこかに異常をもたらすかもしれません。本記事で取り上げた通り、時間外労働時間の上限規制は、今後も厳しくなる可能性があります。
重要なことは、労働時間に対しての人員配置や既存システムの見直しではないでしょうか。業務の一つひとつを見える化して、改善できる部分は効率的な方法に差し替えてみましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
自宅待機とは?給与は発生する?出勤停止との違いも解説!
自宅待機とは、会社が従業員の出勤を禁止し自宅で待機させることです。自宅待機は従業員の働く権利を制限することになるため指示するときは注意が必要です。 本記事では、自宅待機の意味と具体…
詳しくみる変形労働時間制の届出は必要?不要?1カ月単位と1年単位の違いや書き方、記入例も
「変形労働時間制を導入したいが、届出が必要なのかわからない」「書類の書き方が複雑で困っている」企業の労務担当者様にとって、変形労働時間制の届出は間違いの許されない重要な業務です。 …
詳しくみる週3日勤務のパートの有給休暇は何日?計算方法・企業の正しい対応を解説
週3日勤務のパートでも、有給休暇は法律で定められており、一定の条件を満たし、入社後6ヶ月を経過すれば5日以上取得できます。有給休暇の付与日数は勤務日数に応じて決まり、週3日勤務の場…
詳しくみる【テンプレート付】出勤簿をエクセルで作成するには?
労働基準法で整備が義務づけられている法定帳簿の一つに出勤簿があります。様式は任意ですが、5年(民法改正の経過措置に伴い、当分の間3年)の保存義務があります。従来は、紙に記録して管理…
詳しくみる1日13時間労働は違反?認められる条件や労働基準法のルールを解説
1日13時間労働は、原則として労働基準法に違反する可能性があります。法律で定められた労働時間は「1日8時間・週40時間」が上限であり、これを超えるには特別な労使協定が必要です。しか…
詳しくみる36協定の年間上限とは?特別条項やペナルティについてわかりやすく解説
36協定(さぶろくきょうてい)とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことです。日本の労働基準法では原則として労働時間は「1日8時間・週40時間以内」と定められており(法定労働時…
詳しくみる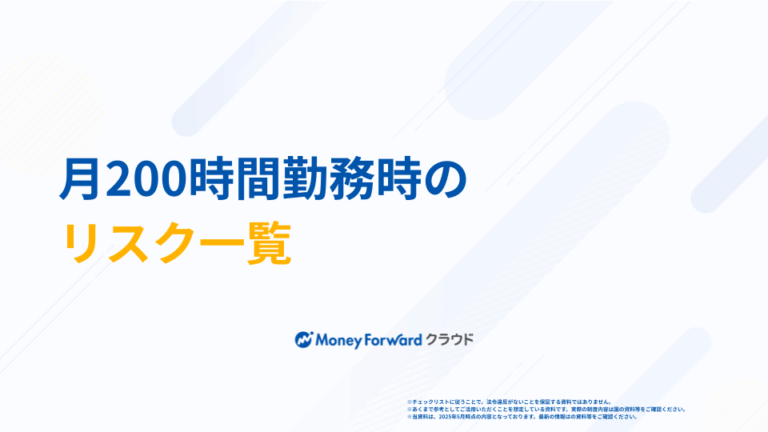



.png)