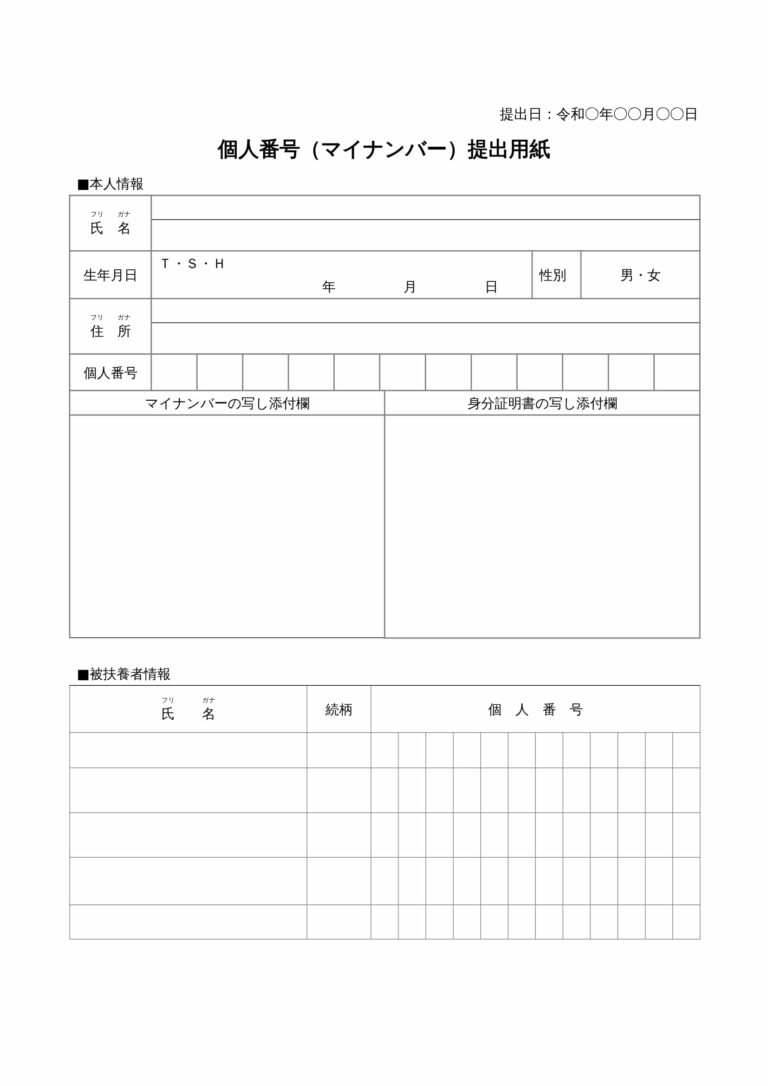- 更新日 : 2024年12月19日
マイナンバーの桁数は何桁になるの?
マイナンバーの桁数が12桁なのは、ご存じですか?
この数字、実は無作為に選ばれることはありません。住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)で使用されていた住民票コードが基になっています。
マイナンバー(個人番号)の桁数は12桁
マイナンバー(個人番号)の桁数は12桁。すべて数字で構成されます。実はこの数字、無作為に選ばれる訳ではありません。住基ネットで使用されている住民票コードが基になっています。とはいえ、マイナンバーと住民票コードがまったく同じ数字になることはありません。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」)施行令第8条に「個人番号とすべき番号は、(中略)作為が加わらない方法により生成する次に掲げる要件に該当する11桁の番号及びその後に付された1桁の検査用数字(中略)により構成されるものとする」の規定があります。
1.住民票コードを変換して得られるものであること。
2.前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。
3.他のいずれかの個人番号を構成する検査用数字以外の11桁の番号とも異なること。
つまり、住民票コードを復元不可能な何らかの方法で変換した11桁の数字に、検査用数字1桁が加えられた12桁の数字がマイナンバー(個人番号)となります。検査用数字とは、数字の入力間違いなどを防止するため、検査用数字の前11桁の数字を規定の計算式で計算した結果、算出された数字のことです。
このように、マイナンバー(個人番号)の付番については、住基ネットにかなり依存したシステムとなっています。このため、マイナンバーが付番されるのは住民票がある方だけに限られ、長期にわたり海外に住んでいるため、住民票がない人などには、日本国民であってもマイナンバーが付番されない場合があります。逆に、中長期在留者などの外国人は、住民票があるために、マイナンバーが付番されます。
企業のマイナンバー「法人番号」の桁数は、13桁です。すべて数字で構成されます。法人番号は、原則として商業登記法に基づく「会社法人等番号(12桁)」と1桁の検査用数字で構成されます。設立登記がされていない法人又は人格なき社団は、会社等法人番号と重複することのない12桁の基礎番号を国税庁長官が指定します。
各国の国民共通番号制度(海外のマイナンバー制度)の桁数と指定方法
国民に番号を付与して個人情報の管理をするものを国民共通番号制度といいます。国民共通番号制度を導入している国は少なくなく、アメリカ、イギリス、イタリア、オランダ、オーストラリアなど多岐に渡っています。今回、日本で導入されるマイナンバー制度も国民共通番号制度の一つです。
他の国々では共通番号の桁数をどのように定めているのでしょうか?いくつかの国の例を見てみましょう。
アメリカ
・社会保障番号(SSN:Social Security Number)
・桁数は9桁。すべて数字。地域、発行グループ、連番で構成される。
スウェーデン
・個人番号(Personnummer)
・桁数は10桁。すべて数字。生年月日、生誕番号、チェック番号で構成される。
韓国
・住民登録番号
・桁数は13桁。すべて数字。生年月日、出生世紀別性別コード、生誕番号、チェック 番号で構成される。
ここで紹介した国では、番号の数字に何かしらの意味があるようですね。日本では住民票コードを基に生成された数字を用いますが、この住民票コードはランダムに決定される数字となりますので、数字自体は意味を持たないことになります。
どちらかがいいかは個々人の判断ですが、マイナンバーは生涯不変の番号、一度決められれば一生付き合っていく数字になります。好きな数字が選べないのは残念ですが、その数字がどのように決められたかを知ることで、少しは納得できるのではないでしょうか?
まとめ
日本でも、ついに国民共通番号制度であるマイナンバー制度が始まります。国民共通番号制度は諸外国でも採用され、行政の効率化などに成果をあげています。一方、プライバシーや基本的人権などでの面での問題、情報流出や「なりすまし」被害などの可能性なども指摘されています。
特にアメリカでは「なりすまし」被害が大きな社会問題となっており、その解決のために様々な政策を打ち出しているのですが、根本的な解決にいたっていません。
マイナンバー制度とうまく付き合っていくためには、その制度の意義と役割を理解しつつ、危険性についても認識し、マイナポータルやマイナンバー保護の第三者委員会である特定個人情報保護委員会などを通して、自らの情報を上手にコントロールしていく必要があるようです。
また、その桁数、数字に込められた意味などを理解することによって、一層マイナンバーに対する理解が深まり、今後のマイナンバー関係事務などをするときに役に立つかもしれません。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
マイナポータルの便利な機能と利用するための注意点
平成29年1月より運用開始となったマイナポータルは、パソコンや携帯端末から自分の個人番号に関する情報にアクセスすることのできるサービスです。 マイナポータルを利用することによって、 ・誰がどのように自分の個人番号にアクセスしたのか確認するこ…
詳しくみるマイナンバーの本人確認方法をわかりやすく解説
マイナンバーを適切に取り扱うために、番号確認と合わせて本人確認が必要となります。個人番号カードを提示することによって番号確認と本人確認を同時に行なうことができますが、通知カードの場合には本人確認をするための書類の提示が必要となります。 マイ…
詳しくみるマイナンバーの本人確認に必要な番号確認書類・身元確認書類とは?
マイナンバー制度は、個人番号(マイナンバー)によって行政手続きなどにおける特定の個人を識別するための仕組みです。 行政機関だけでなく、民間事業者も税や社会保障の手続きで従業員のマイナンバーを取り扱うことになります。その際、本人確認をしなけれ…
詳しくみるマイナンバーの安全管理措置とは?具体的な運用方法を解説
マイナンバーの取り扱いについては特に厳しい安全管理が求められています。マイナンバーにおける安全管理措置とは、マイナンバーとそれに関連付けて管理される住所や氏名などの特定個人情報の漏えいや消失の防止のために行う対策のことです。 それでは、実際…
詳しくみる海外転出や赴任においてマイナンバーカードはどうする?
2015年にマイナンバー法が施行され、市町村から住民票を有するすべての人にマイナンバー(個人番号)が通知されています。 マイナンバーカードについても、ポイント付与のキャンペーンなどの影響もあり、ここにきて取得する方は増えているようです。 と…
詳しくみるマイナ保険証の使い方とは?使える場所〜利用時に知っておくべきことを解説
「マイナンバーカードを保険証として使えるって本当?」 「マイナ保険証に登録すると、従来の健康保険証は不要になる?」 上記のような疑問を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「マイナ保…
詳しくみる