- 更新日 : 2025年3月27日
通勤手当は課税それとも非課税?限度額やルールを解説
会社が従業員に対して支給する「通勤手当」は、支給する金額によって課税・非課税の対応が分かれます。福利厚生の一種でもあり、通勤手当があることで従業員の満足度も上がりますが、ケースによっては所得税が増えてしまう場合もあります。
ここでは、通勤手当の非課税限度額など基本ルールについて解説します。
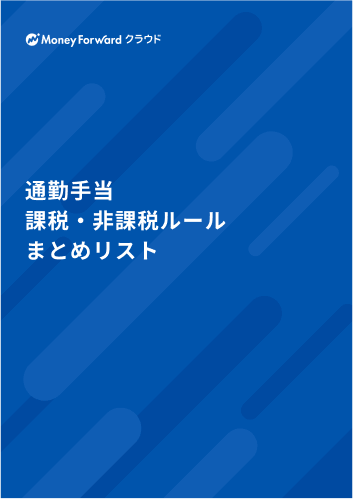
通勤手当 課税・非課税 まとめリスト
「通勤手当 課税」「交通費 非課税」などでお調べの方向けに「通勤手当 課税・非課税ルール まとめリスト」を無料で提供しています。ぜひダウンロードしてご活用ください。
目次
通勤手当は課税それとも非課税?
通勤手当とは、従業員の自宅からオフィスまでの通勤にかかる費用を支給する手当をいいます。
通勤手当は一定額までは非課税であり、非課税の範囲内の通勤手当は給与所得の対象とはなりません。以下で、通勤手当の課税範囲について解説します。
通勤手当は非課税限度額内であれば非課税
会社が支給する通勤手当は、一定の限度額内であれば非課税です。非課税の限度額の定め方は、電車やバスといった交通機関を利用するケースと、マイカーや自転車で通勤するケースで異なります。
交通機関を利用する従業員への通勤手当は、1ヵ月15万円までが非課税です。マイカーや自転車での通勤は、最大で「片道55km以上」が1ヵ月「3万1600円」、最低が「片道2km~10km」で1ヵ月「4,200円」と距離に応じて非課税の上限額が定められています。
なお、マイカーや公共交通機関を併用する場合の非課税の上限額は1ヵ月15万円です。
参考
マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁
限度額を超えた場合は通勤手当も課税される
通勤手当が上述の上限額を超えている場合、上限額を超えた部分の通勤手当の金額は、課税対象、つまり給与所得の対象となります。所得税が発生する年収ライン(103万円)を、通勤手当によって超えてしまう場合もあるため注意が必要です。
たとえば、年収100万円で片道2km以下の自転車通勤を行うパート社員に、月3,000円の通勤手当を支給した場合、通勤手当は全額課税対象です。そのため、年収が100万円+通勤手当3万6000円=103万6000円となり、所得税の対象となります。
通勤手当と交通費は違う
通勤手当と混同しやすいものに交通費があります。交通費とは、営業活動や出張などにかかった移動費用を指します。交通費は、通常あらかじめ社員が立て替え、あとから経費精算として会社が支払う方法が一般的です。
交通費は経費として「交通費」という勘定科目で処理されます。通勤手当は「給与」の勘定科目に当てはまります。
交通費の場合は非課税
通勤手当とは異なり、交通費は企業が事業活動に必要となる経費にあたるため全額非課税です。給与に含まれる交通費には、所得税はかかりません。
通勤手当における非課税限度額のルール
通勤手当の非課税限度額のルールを解説します。
バスや電車などの公共交通機関を利用する場合
公共交通機関を利用する場合の通勤手当は、1ヵ月あたり15万円が非課税の限度額です。このとき、非課税の対象となる限度額は、最も経済的かつ合理的な経路や方法であることが求められます。
よく知られている例としては、新幹線通勤への通勤手当も上限額以内であれば非課税になりますが、グリーン車の料金は経済的かつ合理的な経路や方法とはいえないこともあって、非課税の対象にはなりません。
マイカーや自転車通勤への通勤手当の場合
自転車やマイカーを利用して通勤する場合の通勤手当は、距離に応じて非課税の限度額が定められています。
| 片道の通勤距離 | 1ヵ月あたりの非課税限度額 |
|---|---|
| 55km以上 | 31,600円 |
| 45km以上55km未満 | 28,000円 |
| 35km以上45km未満 | 24,400円 |
| 25km以上35km未満 | 18,700円 |
| 15km以上25km未満 | 12,900円 |
| 10km以上15km未満 | 7,100円 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
通勤手当は、労働基準法などの法律で何か定めがあるわけではありません。民法上では、本来債務者となる労働者が負担すべきものです。そのため、支給の基準や運用ルールについて、トラブルを避けるためには、各企業が明確に定める必要があります。就業規則に、支給対象や支給基準などを明記し、不正受給等を防ぎましょう。
通勤手当の課税・非課税における注意点
通勤手当を支給する際には、非課税対象となる範囲を明確にするとともに、「定期代を支給する」など明確な金額の根拠を設け、従業員が混乱しないようにすることが大切です。以下の点にも注意しましょう。
通勤手当における課税と非課税を間違えた場合
なんらかの原因で、本来であれば課税するべき通勤手当を非課税にしていた場合、所得税の未納分が発生します。こうした事実が判明した時点で、会社専任の税理士または税務署に確認し、その後の処理を行いましょう。
また、通勤手当の取り扱いでは、健康保険や厚生年金保険の標準報酬月額の計算で気を付ける必要があります。通勤手当は、非課税・課税範囲関係なく、全額が健康保険法や厚生年金保険法上の報酬に含まれます。報酬月額の計算を間違えると、社会保険料が変わってしまう可能性があるので注意してください。
3ヵ月・6ヵ月の定期代が一度に支払われる場合
労働基準法では、会社は毎月1回以上、一定の期日を定めて賃金を支払わなければならないと規定しています。通勤手当も会社が支給する「賃金」に含まれますが、臨時に支払われる賃金や賞与、その他これに準ずるものとして、必ずしも1ヵ月に1回以上支払わなければいけないというものではありません。そのため、「3ヵ月分」「6ヵ月分」というように、まとめて通勤手当を支給する方法も可能です。
公共交通機関の定期代は、一般的に長期間分をまとめて購入するほうが割安となっています。「6ヵ月分の定期代」として年に2回の通勤手当を支払う運用にすれば、通勤手当の金額を抑えられるばかりか、給与計算業務の効率化につながるメリットがあります。
定期代をまとめて支払う場合には、「先払い」という形で、従業員に有利なように運用ルールを設定するのが一般的です。さらに、就業規則などで支給基準を明記しておきましょう。
通勤手当の支給規定を明確にして運用しよう
通勤手当は、非課税上限額を超えない部分には所得税は発生しません。従業員が納得のいく運用をするためには、法律の規定を担当者が理解し、わかりやすいルールを明記することが重要です。
近年、都心から離れたところに住居を写し、毎日出社を必要としない働き方も増えています。新幹線通勤やマイカー通勤など、自社の勤務形態で考えられるケースに合わせた支給規定を作成しましょう。
よくある質問
通勤費は非課税ですか?それとも課税対象ですか?
非課税上限額以内であれば所得税は発生しません。公共交通機関を利用する場合は1ヵ月15万円以内、マイカーや自転車を利用した通勤であれば、片道の距離に応じて非課税上限額が設定されています。詳しくはこちらをご覧ください。
通勤手当の課税・非課税を間違えた場合の対応について教えてください
通勤手当を間違って課税してしまった、または間違えて非課税で扱ってしまった場合、本来納めるべき所得税との差額が発生します。正しい処理については税務署に確認し、対応しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
通勤届の車種とは何を書く?主な車種や書き方をテンプレートとあわせて紹介
通勤届における「車種」とは、通勤に使用する自家用車や二輪車などの種類を指します。車種の法律上の区分に基づいて分類されるほかにも、自動車業界や保険業界による区分もあり、それぞれ分類方法が異なります。 この記事では、車種の定義や車名との違いを明…
詳しくみる二重派遣とは?禁止理由や罰則、確認方法、起こりやすい業界
二重派遣とは派遣先企業がさらに別の会社に労働者を派遣し、第2の派遣先での指揮命令を受けて働かせることを指します。二重派遣は職業安定法や労働基準法に抵触するため、罰則が課されます。本記事では二重派遣が禁止される理由や二重派遣にならないケース、…
詳しくみる年休は時間単位でとれる?日数の上限や給与計算方法、導入について解説
年次有給休暇(年休)は、労使協定を締結することで時間単位での取得が可能です。上限は年5日(所定労働時間×5日分)までです。 本制度は、通院や子どもの学校行事など、短時間の用事に対応できる柔軟な休暇取得を可能にしています。本記事では、年休の日…
詳しくみる深夜残業と割増賃金を解説 – 定義や計算方法
深夜労働が労働時間の中のどの時間帯のことを指すのか知っていますか?22時から翌朝5時の間に行う労働を「深夜労働」といい、深夜労働した場合は通常より割増しした額の賃金を払わないといけません。 この時間帯が残業時間にあたる場合には、さらに割増し…
詳しくみる介護休暇とは?同居していない場合や取得条件、介護休業との違いを解説
介護休暇は、介護を要する必要な家族を持つ従業員が取得できる法定休暇です。従業員が申し出れば、会社は原則として断ることができません。家族の世話や入院の付き添いをしながら働く従業員にとって、介護休暇制度は重要なサポートです。 こちらの記事では、…
詳しくみるどのような待遇差は不合理?同一労働・同一賃金ガイドラインのまとめ
同一労働・同一賃金ガイドライン案の概要 同一労働・同一賃金を含む働き方改革関連法が2018年6月29日に成立しました。同一労働・同一賃金とは、同一企業・団体における正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者…
詳しくみる