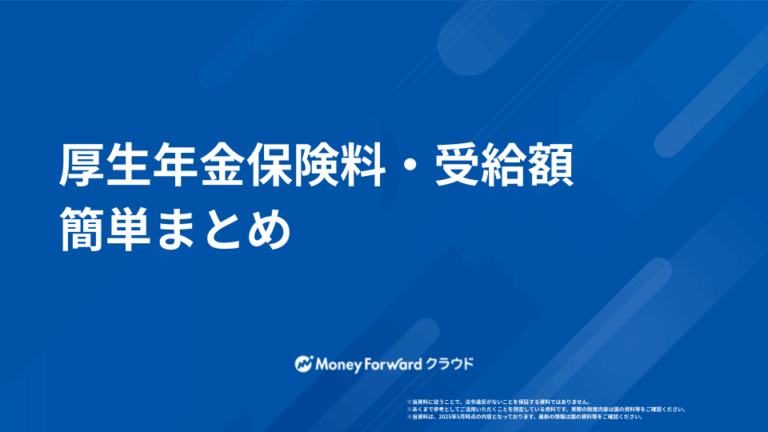- 更新日 : 2025年7月3日
厚生年金の加入で年金が2万増える?保険料と受給額の計算方法を解説!
会社員や公務員の方が加入する厚生年金保険。厚生年金保険に加入すると、将来もらえる年金額が増加します。
厚生年金保険料は会社から受け取る給与をいくつかの等級に分けて区分した標準報酬月額によって決定されますが、厚生年金保険の年金受給額の計算方法はご存知でしょうか。この記事では、保険料と年金受給額の計算方法について解説します。
目次
そもそも厚生年金保険とは?
厚生年金保険とは、会社員や公務員のように雇われて働く方が加入する公的年金です。個人で事業を行う方や無職の方は国民年金に加入します。しかし、国民年金は「基礎年金」と呼ばれ、20歳以上60歳未満の日本に住所があるすべての方が加入することになっているため、厚生年金保険の被保険者は国民年金にも加入していることになります。
厚生年金に加入していると、将来、国民年金(基礎年金)のほかに厚生年金保険からも年金がもらえるため、国民年金のみ加入している方よりも年金額が多くなります。
厚生年金保険と国民年金の違いは以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
厚生年金保険料の計算方法は?
厚生年金保険の保険料はどのようにして決められるのでしょうか。保険料の計算方法の仕組みを確認していきましょう。
標準報酬月額等級表と厚生年金保険料額表
厚生年金保険料は、会社から受け取る給与をいくつかの等級に分けて区分した「標準報酬月額」とボーナスの金額から計算した「標準賞与額」に厚生年金保険料の保険料率をかけて計算します。
厚生年金保険の標準報酬月額は32等級に区分されており、この標準報酬月額を等級表に当てはめれば、厚生年金保険料は計算しなくても簡単に確認することができます。
標準賞与額は支給された賞与額の1,000円未満を切り捨てた金額のことであり、保険料は標準報酬月額から計算する保険料と同率の保険料率で計算します。1カ月に受け取った賞与額の上限は150万円と決まっているため、150万円を超える賞与を受け取ったときの標準賞与額は150万円になります。
厚生年金保険料は会社と従業員で折半し、給与から控除した従業員負担分を会社がまとめて納付します。全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している会社の場合、都道府県ごとに分けて作成された「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」から標準報酬月額等級表とそれぞれの等級ごとの健康保険料、厚生年金保険料が確認できますので、活用するとよいでしょう。
参考:令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)|全国健康保険協会
なお、令和4年度の厚生年金保険料率は「18.300%」となっています。厚生年金保険料の計算方法は、以下の記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。
標準報酬月額はどのように決まる?
標準報酬月額の決定方法は、「資格取得時決定」「定時決定」「随時改定」「産前産後・育児休業終了時改定」の4つです。それぞれの決定方法について見ていきましょう。
資格取得時決定
従業員が入社したときに、雇用契約書に記載されている給与や手当などの合計金額を被保険者資格取得届に記入して提出することで標準報酬月額が決定されます。
資格取得時決定で決定された標準報酬月額は入社した月から適用されます。適用期間は資格取得時決定が行われた時期、つまり従業員が入社した時期によって異なるので注意が必要です。1月1日から5月31日までに入社した場合はその年の8月まで、6月1日から12月31日までに入社した場合は翌年の8月まで適用されます。
定時決定
毎年4月・5月・6月に支払われた給料の平均額をもとに標準報酬月額を決定するのが定時決定です。7月1日時点で在籍する被保険者が対象となり、「被保険者報酬月額算定基礎届」を提出することで標準報酬月額が見直しされます。
定時決定で決定された標準報酬月額は、9月から翌年8月まで適用されます。7月1日から7月10日までが「被保険者報酬月額算定基礎届」の提出期間となりますので、手続き漏れがないように気をつけましょう。
随時改定
年の途中で昇格や昇給などにより給与に変更があり、給与に大幅な増減があった場合に標準報酬月額を変更するのが随時改定です。随時改定は「被保険者報酬月額変更届」を提出することで行われます。
随時改定は、昇給や降給、各種手当の金額の変更、給与や歩合の単価の変更など支給額や支給率が決まっている賃金に変更があった場合に、実際の給与の額と標準報酬月額が大きく乖離しないようにするための手続きです。以下の3つの条件すべてに該当した場合に手続きが必要となるので注意しましょう。
- 固定的賃金の変動、給与体系の変更があった
- 変動した給与が支払われた月から継続した3カ月の給与の平均額に該当する標準報酬月額と現在適用されている標準報酬月額との間に2等級以上の差がある
- 変動があった月以後3カ月の給与の支払基礎日数が、いずれも17日以上(特定適用事業所に勤務するパートやアルバイトなどの短時間労働者の場合は11日以上)ある
なお、変更された標準報酬月額は、1月から6月までの間に随時改定が行われた場合は8月まで、7月から12月までの間に随時改定が行われた場合は翌年8月まで適用されます。
産前産後・育児休業等終了時改定
産前産後休業や育児休業をしていた従業員が、復帰後に時短勤務となることや所定外労働をしないことで、給与が休業前よりも下がってしまうことがあります。このようなケースでは、従業員が標準報酬月額の改定を会社に申し出た場合に「産前産後休業終了時報酬月額変更届」または「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで、産前産後休業・育児休業等終了時改定が行われます。
復職したばかりの従業員は、以前のようには働けないことが多く、給与が下がっても支払基礎日数が17日以上ないことが多くあります。この場合は随時改定の対象にはなりません。しかし、産前産後休業・育児休業等終了時改定では、産前産後休業や育児休業から復帰した従業員の社会保険料の負担軽減を目的に改定の対象とすることができます。
従業員が標準報酬月額の改定を会社に申し出るには、以下2つの要件を満たす必要があります。
- 休業前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差がある
- 休業終了日の翌日が属する月から継続して3カ月のうち、1カ月以上支払基礎日数が17日以上※となる月がある
※特定適用事業所に勤務するパートやアルバイトなどの短時間労働者の場合は11日以上、それ以外のパートやアルバイトの従業員は、支払基礎日数が3カ月すべて17日未満の場合は、15日以上の月での平均で算定できる。
給付終了日の翌日が属する月から3カ月の給与にもとづいて標準報酬月額が決定され、4カ月目から新しい標準報酬月額が適用されます。適用期間は随時改定と同じ期間です。
標準報酬月額の決定・改定については以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。
厚生年金に加入すると将来の年金額が増える?
厚生年金保険に加入すると将来受給できる年金額が増加します。年金の受給額は、加入期間が長いほど、年収が多いほど、金額が増加する仕組みです。具体的な事例から、年金額がどのくらい増えるかを見ていきましょう。
厚生年金の平均受給額
厚生労働省の調査資料「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金保険受給者の老齢年金の平均月額は14万6,145円です。年金計算にあたって重要となる標準報酬月額の平均は令和2年度末で31万3,099円であり、年収が少なくなれば、当然年金額も減少することとなります。
厚生年金保険(老齢厚生年金)を65歳から受給する場合には、以下の計算式で年金額を計算します。
厚生年金保険に加入することで増えていくのは、主に報酬比例部分の年金額です。報酬比例部分の年金額の原則的な計算式は、以下のとおりになります。
①2003年3月以前
②2003年4月以降
※給付乗率は、受給者の生年月日によって異なる
この計算式をもとに、厚生年金保険に加入するとどれくらい年金額が増えるのかを具体的に見ていきましょう。
年収120万円なら1万円増える
年収が120万の場合、月の給与は10万円となり、標準報酬月額は9万8千円となります。上記②(2003年4月以降)の計算式で厚生年金保険に20年(240カ月)加入した場合の報酬比例部分の年金額を計算してみましょう。
平均標準報酬額 98,000円 × 5.481/1,000 × 240カ月 = 128,913円(便宜的に1円以下切り捨て)
年金額が12万8,913円増加することになり、月額10,742円の年金額の増加につながります。国民年金(基礎年金)は厚生年金保険に加入していなくても加入する必要があるため、増加額には加味していません。このケースでは、報酬比例部分が増加することで、月額1万円以上年金額が増えることになります。
2022年10月以降、社会保険の適用拡大によりパート従業員でも厚生年金保険に加入する方が増えています。月額10万円の給与でも、20年働けば毎月の年金額が1万円増加しますので、厚生年金保険に加入するメリットは大きいといえるでしょう。
年収150万円なら2万円増える
年収が150万の場合、月の給与は12万5千円となり、標準報酬月額は12万6千円となります。上記②(2003年4月以降)の計算式で厚生年金保険に30年(360カ月)加入した場合の報酬比例部分の年金額を計算してみましょう。
平均標準報酬額 126,000円 × 5.481/1,000 × 360カ月 = 248,618円(便宜的に1円以下切り捨て)
年金額が24万8,618円増加することになり、月額20,718円の年金額の増加につながります。このケースでは、報酬比例部分が増加することで、月額2万円以上年金額を増やすことが可能です。
年収が150万円でも、長く勤めることで厚生年金保険の受給額は増加します。現在は厚生年金保険に70歳まで加入することが可能ですので、65歳以降も年金を受給しながら働き、年金額を増やしていくのもよい方法です。
厚生年金のメリットは老後の資産形成だけではない!
厚生年金保険のメリットは老後の資産形成だけではありません。遺族年金・障害年金の制度もあり、厚生年金保険加入中に大きな病気やケガで障害が残った場合に、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が上乗せされます。また、不幸にも亡くなってしまった場合には、遺族厚生年金で残された配偶者の生活を守ることも可能です。
また、厚生年金保険に加入することで健康保険にも加入することができ、病気や怪我に備えることも可能です。健康保険には、業務外の病気やケガで働けない場合や、出産のために働けない場合に、給与の代わりに標準報酬月額の2/3相当額の傷病手当金や出産手当金が支給されます。
社会保険の130万円の壁や所得税の103万円の壁など、扶養の範囲を意識する必要がないため、労働時間を延長して収入アップを図ることもできるでしょう。その他、国民健康保険や国民年金よりも保険料が安くなる可能性もあります。健康保険や厚生年金保険では、会社が保険料を半分負担するため、国民年金や国民健康保険に自分で加入するよりも、トータルで保険料が安くなる可能性があります。
国民年金だけでなく厚生年金への加入も検討しましょう
厚生年金保険は、会社員や公務員の方のように雇われて働く方のための公的年金です。国民年金よりも将来もらえる年金額が多くなるため、老後の資産形成に役立ちます。
厚生年金保険に加入するメリットは年金額の増加だけではありません。遺族年金・障害年金の制度もあり、事故などで障害が残った場合や死亡した場合など、万が一への備えにもなります。また、厚生年金保険に加入することで健康保険にも加入できるため、傷病手当金や出産手当金など、病気やケガ、出産に備えることも可能です。
保険料が天引きされて給与の手取り額が減ってしまうというデメリットばかりに目が行きがちですが、厚生年金保険の加入で得られる多くのメリットがあるのも事実です。これらのメリットもよく考え、厚生年金保険への加入も検討しましょう。
よくある質問
厚生年金に加入すると将来の年金額が増える?
厚生年金保険に加入すると将来受給できる年金額が増加します。年金の受給額は、加入期間が長いほど、年収が多いほど、金額が増加する仕組みになっています。詳しくはこちらをご覧ください。
厚生年金のメリットは老後の資産形成だけではない?
厚生年金保険に加入するメリットは年金額の増加だけではありません。遺族年金・障害年金の制度もあり、また、健康保険にも加入できるため、傷病手当金や出産手当金など、病気やケガ、出産に備えることも可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
退職者は算定基礎届が必要?対象者・書き方・記入例を紹介
退職者は基本的に算定基礎届の提出は必要ありません。ただし、退職日によっては届出の対象になる場合があり、誤った対応をすると年金事務所から指摘を受ける可能性があります。 本記事では、退職者の算定基礎届について解説します。基本的な記入例や対象者別…
詳しくみる労基署の臨検とは?書類の確認ポイント、是正勧告があった場合の対応
「立ち入り検査で何を見られるのか分からない」 「準備が整っていなかったらどうしよう」 労基署の臨検に対して不安を抱く人事労務担当者もいるでしょう。 臨検は企業の問題点を明らかにし、改善するための機会であり、適切な準備と対応を知れば、不安を軽…
詳しくみる厚生年金の受給額はいくら?計算方法も解説
企業などに雇われている方のほとんどは、給与から社会保険料として年金や健康保険、雇用保険などを天引きされていることでしょう。このうち年金については、実際にはどのような仕組みで将来いくらもらえるのかなど、気になる方も多いのではないでしょうか。 …
詳しくみる社会保険の標準報酬月額・標準賞与額とは?保険料を求める計算方法
給与や賞与にかかる社会保険料は、実際に支給された金額ではなく、標準報酬月額および標準賞与額に基づいて決定されます。それぞれに計算方法が異なるため、対象となる報酬の範囲や、保険料の徴収が免除される条件など、正しく理解した上で処理することが重要…
詳しくみる傷病手当とは?金額や条件・期間、もらえない場合の具体例を解説
病気で長期間会社を休むことになった場合、頼りになるのが健康保険から支給される傷病手当金です。傷病手当金はいつまで、いくら受け取れるのか、気になる人もいるでしょう。 本記事では、傷病手当金の支給条件や申請方法、支給金額などについて解説します。…
詳しくみる通勤中の事故は労災になる?認められないケースは?
通勤途中に発生したケガや交通事故は、状況によっては「労災保険」の対象になります。とはいえ、すべての通勤中の事故が労災として認定されるわけではなく、判断には法律上の基準や過去の運用実例が関係します。企業の人事担当者にとって、従業員から通勤中の…
詳しくみる