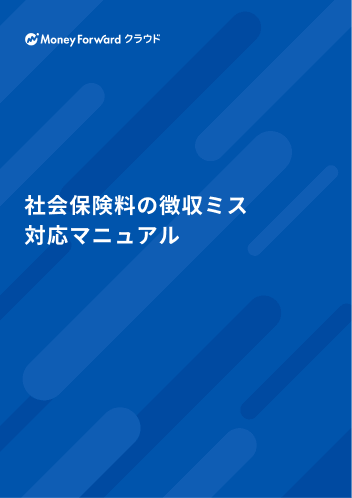- 更新日 : 2025年5月27日
社会保険料の徴収漏れが発覚したときのお詫びの仕方は?|原因や対策を解説
社会保険料の徴収漏れが発覚した場合は、速やかに原因を特定し、適切な対応とともに従業員へ謝罪することが重要です。
原因を特定し、再発防止策を講じることで、信頼を回復し業務の改善を図れます。本記事では、社会保険料の徴収漏れの原因や具体的な対応方法と対策について解説します。
目次
社会保険料の徴収漏れが発覚した際の対応|お詫びの例文も紹介
社会保険料の基礎となる「標準報酬月額」の算定は毎年7月に行われます。4月から6月の平均給与を標準報酬月額表に当てはめ、等級を決定する仕組みです。
上記の手続きを「社会保険料の定時決定」といい、定時決定された標準報酬月額は同年の9月から1年間有効となり、翌年8月まで同じ等級で社会保険料が算出されます。なお、標準報酬月額には基本給のほか、残業手当や賞与、通勤手当、住宅手当、扶養手当なども含まれます。
一方、見舞金や出張旅費などは含みません。標準報酬月額の算出は、対象となる報酬の確認や各種手当の月額換算など、複雑な計算を要します。
また、標準報酬月額を決定する定時改定では、7月1日時点で被保険者である全従業員が対象となるため、同時期に膨大な計算をこなさなければなりません。そのため、担当者の負担が大きく、ミスが発生しやすくなります。
では、実際に社会保険料の徴収ミスが発覚した場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか。以下では、各対応方法について解説します。
従業員にお詫びをする
社会保険料の徴収漏れが発覚した場合、速やかに従業員にお詫びし、状況を説明することが重要です。まず、具体的なミスの内容や原因を明確に伝えます。
たとえば、計算ミスやシステム設定の誤りなど、ミスが発生した経緯を説明し、再発防止策を示すことで信頼回復につなげます。影響が複数の従業員に及ぶ場合は、お詫び状を作成し、書面やメールで一斉に報告するのが適切です。説明を怠ると不信感を招くため、誠実な対応を徹底しましょう。
社会保険料の徴収漏れに関するお詫び文書の例文
社会保険料の徴収漏れに関するお詫び文書の例文は、以下のとおりです。
〇〇年〇月〇日
〇〇株式会社
〇〇部〇〇 〇〇(担当者名)
拝啓
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、弊社において社会保険料の徴収に誤りがあり、本来控除すべき金額が適切に徴収されていなかったことが判明いたしました。詳細を確認したところ(具体的なミスの内容、たとえば計算処理の誤り、システム設定ミスなど)が原因であることが判明いたしました。
本来であれば正確に控除すべき社会保険料を適用しなければならないところ、弊社の確認不足によりこのような事態を招いてしまいましたことを深くお詫び申し上げます。
不足分の社会保険料については、以下のいずれかの方法で対応いたします。
- 翌日以降の給与にて分割徴収
- 当月中の現金または振込による精算
- 会社負担による対応(必要に応じて)
お手数おかけし恐縮ではございますが、ご希望の対応方法について、〇月〇日までにご返信くださいますようお願い申し上げます。
今回の件を受け、社内の管理体制を見直し、チェック体制の強化および担当者への教育を徹底することで、再発防止に努めてまいります。今後はミスの発生を防ぐため、管理を徹底してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
改めまして、本件によりご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。ご不明点がございましたら、〇〇(担当者名・連絡先)までご連絡ください。何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
上記のように、お詫びの文書を作成する際は「徴収ミス」「ミスの原因」「対応」「再発防止策」「謝罪」というように順序立てることが重要です。
当月中に現金精算する
社会保険料の徴収漏れが発覚した場合、できるだけ当月中に精算することが重要です。控除額が過大であれば過剰分を現金で返還し、不足していれば追加徴収します。
精算の際は、労働基準法第24条の賃金支払いの五原則に注意が必要です。
- 通貨払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月1回以上払いの原則
- 一定期日払いの原則
精算の遅れは違反とみなされる可能性があります。
また、給与計算システムの社会保険料の項目も修正が必要です。修正を怠ると年末調整時に控除額がずれ、所得税額に誤差が生じます。結果的に再調整や従業員の確定申告が必要となるため、適切な修正を行い、正確な処理を徹底しましょう。
当月中が難しい場合は翌月以降に精算する
社会保険料の徴収漏れが当月中に精算できない場合、翌日以降の給与で調整します。徴収不足があれば翌月の控除額に上乗せし、過剰に徴収していた場合は翌月の控除額を減額して調整しましょう。
たとえば、定時決定により健康保険料が10,000円と算出されたにもかかわらず、10月に誤って12,000円控除した場合、2,000円多く徴収したことになります。上記の場合、11月の控除額を8,000円に調整し、12月からは正しい10,000円を控除しましょう。
調整時には、必ず社会保険料の項目内で処理することが重要です。別の項目で処理すると、年末調整の際に所得税の計算に不整合が生じ、再調整が必要になる可能性があります。正確な計算と管理を徹底し、適切に精算することが重要です。
必要に応じて会社が負担する
社会保険料の徴収漏れが発覚した場合、会社は不足額を従業員から徴収する必要があります。しかし、状況によっては会社が負担することも可能です。
上記の場合、会社が不足分を負担し、経理上「法定福利費」として処理することが一般的です。なお、会社が負担した金額は、従業員の課税所得となります。
社会保険料は、給与をもとに算出される「標準報酬月額」に保険料率を掛けて算出され、事業主と従業員が折半します。健康保険・厚生年金保険の保険料の徴収元は、日本年金機構です。納付対象月の翌月末日が納付期限であるため、遅れることなく支払いましょう。
徴収漏れが発生した場合は、適切に対応し、速やかに納付を完了させることが重要です。
年末調整で精算する
社会保険料の徴収漏れが発覚した場合、原則として翌月までに精算します。しかし、翌月末までに対応できない場合や計算ミスによって徴収漏れの金額が大きい場合は、年末調整で精算します。
社会保険料は翌月末までに納付が必要です。そのため、徴収漏れが翌月末以降に発覚した場合、すぐに対応できないことがあります。また、標準報酬月額の誤りによる徴収漏れは、金額が大きくなる可能性があるため、通常の給与からの控除が難しい場合もあります。
上記のような場合、年末調整で一括精算することが一般的です。年末調整で精算する際は、従業員に徴収漏れの内容や金額を説明し、給与からの控除時期を事前に伝えることが重要です。
適切な対応を行うことで、従業員の理解を得ながら精算を進められます。
年末調整に関する詳しい情報は、下記の記事で紹介しているため、参考にしてみてください。
社会保険料の徴収漏れが生じる原因
社会保険料の徴収漏れが発生すると、後に清算が必要となり、従業員や企業の負担が増えます。適切に対応するには、まず徴収漏れの原因を理解することが重要です。
徴収漏れは、計算ミスや標準報酬月額の誤りなど、さまざまな要因によって発生します。以下では、具体的な原因について解説します。
社会保険料の詳しい情報については、下記の記事をご覧ください。
標準報酬月額の計算が誤っていた
社会保険料の徴収漏れは、標準報酬月額の計算ミスが原因で発生することが多くあります。標準報酬月額は定時決定により毎年見直され、被保険者や70歳以上の被用者の報酬額と大きな差が生じないように見直されます。
定時決定では、7月1日時点で使用する全被保険者について、4月・5月・6月の報酬月額をもとに算定し、事務センターまたは管轄の年金事務所へ算定基礎届を提出することが重要です。計算ミスがあると誤った等級が適用され、社会保険料の徴収額に影響を与えます。
誤りが発覚した場合、速やかに訂正書類を提出し、適正な標準報酬月額に修正しなければいけません。
標準報酬月額は翌年8月まで適用されるため、誤りが長期間にわたって影響を及ぼす可能性があります。徴収漏れを防ぐには、算定基礎届の作成時に報酬額を正確に計算し、提出前に内容を十分に確認することが重要です。
従業員からの徴収額が誤っていた
社会保険料の徴収漏れは標準報酬月額が正しく決定されていても、給与からの控除額が誤っていることで発生する場合があります。
上記のような場合、年金事務所には正しい標準報酬月額が通知されているものの、実際に従業員から控除される金額に誤っていることになります。
社会保険料は従業員の給与から会社が控除し、納付する仕組みです。徴収額が多ければ過徴収、少なければ徴収不足です。誤りがあると会社と従業員の間で不足分や過剰分を清算する必要がありますが、その際は適切に調整する必要があります。
また、社会保険料の控除額は年末調整や所得税額にも影響します。年末調整後に徴収漏れが発覚すると、再調整や確定申告の修正が必要となるため、注意が必要です。
退職者の社会保険料の徴収漏れが発覚したときの対応
退職者の社会保険料は、被保険者資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月まで発生します。事業主は毎月の給与から前月分の保険料を控除しますが、計算ミスや手続きの遅れによって徴収漏れが発生することがあります。
退職者の徴収漏れが発覚した場合、原則として現金で清算し、必要に応じて会社が負担することも可能です。以下では、退職者の社会保険料の徴収漏れが発覚した際の具体的な対応方法について解説します。
当年の徴収漏れの場合
退職者の社会保険料の徴収漏れが当年内に発覚した場合、年末調整で正確な所得税を計算できます。社会保険料は給与から控除されるため、控除額が増えれば給与が減少し、結果的に所得税も減少します。
年末調整後に徴収漏れが判明した場合でも、1月31日までに再計算し、提出書類の修正を行えば、正しい所得税額を反映可能です。ただし、年末調整は社会保険料の過不足を直接調整する仕組みではなく、実際に支払った社会保険料をもとに所得税額を再計算する手続きです。
そのため、社会保険料控除を適用する際は、実際の支払額を正確に申告する必要があります。
過年度の徴収漏れの場合
過年度の退職者の社会保険料の徴収漏れが発覚した場合、年末調整の期限(1月31日)を過ぎている場合は、速やかに年末調整をやり直す必要があります。
確定申告を行っている従業員は、所得税額が変わるため、修正申告または更生の請求をしなければいけません。事業主は源泉徴収義務者であるため、所得税の不足分については、元従業員との清算が完了していなくても、税務署へ納付する必要があります。
徴収漏れが発生しないよう、社会保険料の控除額を正確に管理することが重要です。
社会保険料の徴収漏れを起こさないための対策
社会保険料の徴収ミスは、手取り給与だけでなく、年末調整や確定申告にも影響を及ぼします。社会保険料の誤りは、社会保険料控除額の誤りにつながり、結果として所得税額も誤ってしまうことになります。
社会保険料の徴収ミスを防ぐためには、まず社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額の計算を正確に行うことが重要です。標準報酬月額は定時決定を経て1年間有効であるため、計算ミスがあると多大な影響を及ぼすことになるため注意が必要です。
また、標準報酬月額の計算が正しくても、控除額の誤りが生じる可能性があります社会保険料は会社側と従業員で折半となるため、従業員から徴収した金額の2倍が保険料納入告知書に記載の保険料と一致していることを確認します。
また、定時決定で決まった標準報酬月額が正確に給与計算システムに入力されていることを確認することも重要です。定時決定や、大幅な固定的賃金の増減時に実施される随時改定の前後で、社会保険料が適切に変更されていることを確認しましょう。
社会保険料の徴収ミスは、会社と従業員間での清算が必要になるだけでなく、場合によっては再年調整や確定申告・修正申告も必要となります。そのため、徴収ミスが発生しないよう、正確にチェックすることが重要です。
社会保険料の徴収漏れがあればお詫びをして再発防止に努めよう
社会保険料の徴収漏れが発覚した場合は、発覚した時点でお詫びをし、従業員と協力して不足分を精算しましょう。
また、原因を特定して再発防止策を講じることが重要です。早期に適切に対応して信頼回復と業務の改善を図り、今後のミスを防ぐための対策を徹底しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
適応障害の労災認定は難しい?手続きや証拠の重要性、デメリットなども解説
適応障害は、強いストレスが原因となって心や体の調子を崩し、仕事や日常生活に支障をきたす精神疾患の一つです。現代の職場では、長時間労働や人間関係のトラブル、業務上のプレッシャーが大きなストレスとなり、適応障害を発症するケースが少なくありません…
詳しくみる被保険者資格喪失届とは?提出先や記入例、雇用保険の喪失届との違いも解説!
健康保険・厚生年金保険の被保険者が資格を喪失する際は、被保険者資格喪失届を提出する必要があります。被保険者資格喪失届の提出期限は、資格を喪失した日の翌日から5日以内に、会社を管轄する年金事務所に持参するなどして提出します。インターネットでp…
詳しくみる社会保険料について本人は何割負担?負担割合を解説!
社会保険の保険料は毎月給与から天引きで徴収されるため、本人は何割負担か意識したことがないかもしれません。健康保険と厚生年金保険の保険料は労使折半となっています。医療費の自己負担割合は、昔は1割負担や2割負担でしたが、現在は3割負担です。この…
詳しくみる退職後に雇用保険(基本手当)を受給するための手続きは?必要書類も解説!
会社退職後に失業手当(基本手当)を受け取るには、ハローワークで説明会の出席や失業の認定などの手続きが必要です。 ここでは、離職票などの基本手当を申し込む際の必要書類や、手続きの流れを紹介します。また、基本手当がいくらもらえるのか、計算方法を…
詳しくみる厚生年金の平均受給額はいくら?
日本の年金制度には、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する「国民年金」と会社員などが加入する「厚生年金」があります。厚生年金の加入者は自動的に国民年金にも加入しており、国民年金だけの方とは年金の受給額が異なります。本記事では、年金の平…
詳しくみる社会保険における健康保険とは
業務外で病気やけがをしたとき、またはそのために休業してしまったときに頼れる公的な医療保険制度が社会保険制度のひとつである健康保険です。出産時や死亡時にも給付金を受け取れます。 整理しておきたい点ですが、「社会保険」には二つの意味があります。…
詳しくみる