- 更新日 : 2025年12月24日
借り上げ社宅制度とは?従業員・会社側のメリットや節税シミュレーション
借り上げ社宅制度とは、企業が契約した賃貸物件を従業員に貸し出す制度のことです。従業員は相場より安い家賃で住めるうえ、企業側にも節税などのメリットがあるため、双方にとって魅力的な制度といえるでしょう。
この記事では、借り上げ社宅制度の基本的な仕組みから、混同されがちな社有社宅や住宅手当との違い、そして従業員・企業それぞれの視点から見たメリット・デメリットを、具体的なシミュレーションを交えて詳しく解説します。
目次
借り上げ社宅制度とは?
借り上げ社宅制度とは、企業が賃貸物件を契約し、従業員に住宅を貸し出す制度のことです。地方に支社や営業所を持つ従業員の転勤が多い企業や、海外事業を展開する企業が、借り上げ社宅制度を導入している傾向があります。
借り上げ社宅制度があると、従業員は慣れない場所で不動産物件を探す必要がありません。地方の場合は、支社や営業所の近くに物件を借りることで、従業員の通勤の負担を減らすメリットもあります。
借り上げ社宅と社有社宅の違い
借り上げ社宅と社有社宅の大きな違いは、物件の所有者が誰かという点です。社有社宅は企業が自社で所有する物件ですが、借り上げ社宅は企業が外部から借りた物件です。この所有者の違いが、コストや管理の手間、物件の自由度に影響します。
| 比較項目 | 借り上げ社宅 | 社有社宅 |
|---|---|---|
| 物件の所有者 | 不動産会社・オーナー | 企業 |
| 初期コスト | 比較的低い(敷金・礼金など) | 高い(土地・建物の購入・建設費) |
| 管理・維持の手間 | 少ない(管理は物件の管理会社) | 多い(自社での維持管理・修繕が必要) |
| 物件の自由度 | 高い(必要な時に必要な数だけ契約) | 低い(一度建てると移転や縮小が困難) |
| 固定資産税 | かからない | かかる |
コストや管理の負担を抑えつつ、事業所の移転などにも柔軟に対応しやすい点から、近年では社有社宅よりも借り上げ社宅を導入する企業が増えています。
借り上げ社宅と住宅手当の違い
住宅手当は、従業員が個人で契約した住居の家賃の一部を、企業が現金で補助する制度です。一見似ていますが、税金や社会保険料の扱いに大きな違いがあり、これが従業員の手取り額や企業の負担額に直接影響します。
| 比較項目 | 借り上げ社宅 | 住宅手当 |
|---|---|---|
| 契約者 | 企業 | 従業員個人 |
| 支給方法 | 物件を貸与(現物支給) | 給与に上乗せして現金支給 |
| 税金の扱い | 非課税(一定の条件あり) | 課税対象(給与所得に含まれる) |
| 社会保険料 | 算定基礎の対象(従業員負担分を除く、負担分が評価額より高い場合は報酬とならない) | 算定基礎の対象 |
住宅手当は給与の一部とみなされるため、所得税や住民税、社会保険料が増加します。一方、借り上げ社宅は条件を満たせば給与扱いにならないため、従業員・企業双方の負担を軽減できるのが大きな特徴です。
関連:最適な住宅系福利厚生は?借り上げ社宅/社有社宅/住宅手当を徹底比較
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
エンゲージメント向上につながる福利厚生16選
多くの企業で優秀な人材の確保と定着が課題となっており、福利厚生の見直しを図るケースが増えてきています。
本資料では、福利厚生の基礎知識に加え、従業員のエンゲージメント向上に役立つユニークな福利厚生を紹介します。
令和に選ばれる福利厚生とは
本資料では、令和に選ばれている福利厚生制度とその理由を解説しております。
今1番選ばれている福利厚生制度が知りたいという方は必見です!
福利厚生 就業規則 記載例(一般的な就業規則付き)
福利厚生に関する就業規則の記載例資料です。 本資料には、一般的な就業規則も付属しております。
ダウンロード後、貴社の就業規則作成や見直しの参考としてご活用ください。
従業員の見えない不満や本音を可視化し、従業員エンゲージメントを向上させる方法
従業員エンゲージメントを向上させるためには、従業員の状態把握が重要です。
本資料では、状態把握におけるサーベイの重要性をご紹介いたします。
税制面でお得?借り上げ社宅のメリット
シミュレーションで示した節税効果以外にも、借り上げ社宅制度は従業員と企業の両方に多くのメリットをもたらします。それぞれの立場から、主なメリットを整理してみましょう。
従業員側のメリット
借り上げ社宅制度は、従業員にとっては、可処分所得が増えるだけでなく、住まい探しの手間やコストを大幅に削減できる点が魅力です。
- 手取り額が実質的に増える:
税金や社会保険料の負担が軽減されるため、同じ額面の給与でも生活に使えるお金が増えます。 - 引越しの初期費用を抑えられる:
敷金・礼金・仲介手数料といった数十万円にのぼる初期費用を会社が負担してくれるため、自己資金が少なくてもスムーズに新生活を始められます。 - 物件探しの手間が省ける:
とくに転勤や就職で土地勘のない場所へ移る場合、会社が物件を探してくれたり、提携不動産会社を紹介してくれたりすることで、大きな負担軽減につながります。 - 契約・更新手続きが不要:
賃貸借契約や面倒な更新手続きは会社が行うため、従業員は手間がかかりません。
従業員が借り上げ社宅の家賃の一定額を支払えば、賃料相当額は給与所得として計上しなくてよいため、所得税や住民税の負担額を軽減できます。
加えて、社会保険の計算上、企業に支払う家賃は対象となる給与から差し引くことが可能なため、社会保険料の負担が少なくて済みます。
会社側のメリット
企業にとっては、コスト削減効果に加え、人材戦略の面でも有効な手段となりえます。
借り上げ社宅の家賃は、福利厚生費として計上することが可能です。福利厚生費とは、従業員に支払う給与や賞与以外の費用のことで、経費として扱われるため原則として非課税の扱いとなります。ただし、従業員から賃料相当額の50%以上を徴収しないと、課税対象になることに注意しましょう。
また、社会保険の計算上、企業に支払う家賃は対象となる収入から差し引けるため、従業員の社会保険料の負担が軽減できます。社会保険料は企業と従業員が折半して負担するため、企業側にとってもメリットです。
参考:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁
借り上げ社宅の節税シミュレーション
借り上げ社宅の最大のメリットである節税効果は、どれほどのインパクトがあるのでしょうか。ここでは従業員側と企業側、それぞれの視点から具体的なモデルケースを用いてシミュレーションします。
【従業員】年収400万円・家賃10万円の場合
額面年収400万円(月収約33.3万円)、家賃10万円の物件に住む独身の従業員を例に、「借り上げ社宅」「住宅手当」「補助なし」の3パターンで年間の手取り額を比較してみましょう。
※借り上げ社宅の自己負担は2万円、住宅手当は8万円支給と仮定します。
※社会保険料率は東京都(40歳未満)の令和7年度のものを参考にし、簡略化して計算しています。
※社会保険料は、健康保険料・厚生年金保険料を合計したものです。
※所得税・住民税も概算であり、実際の金額とは異なる場合があります。
※社宅の自己負担額は、評価額を上回っているものとします。
| 項目 | ① 借り上げ社宅 | ② 住宅手当(8万円) | ③ 補助なし |
|---|---|---|---|
| 額面月収 | 333,000円 | 333,000円 + 80,000円 = 413,000円 | 333,000円 |
| 課税対象額 | 333,000円 | 413,000円 | 333,000円 |
| 社会保険料(月) | 約48,000円 | 約58,000円 | 約48,000円 |
| 所得税・住民税(月) | 約16,000円 | 約24,000円 | 約16,000円 |
| 手取り月収 | 約269,000円 | 約331,000円 | 約269,000円 |
| 住居費(月) | 20,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 生活に使えるお金 | 249,000円 | 231,000円 | 169,000円 |
| 年間の差額 (vs 住宅手当) | +220,000円 | – | – |
このシミュレーションからわかるように、住宅手当をもらうよりも借り上げ社宅を利用した方が、年間で約22万円も生活に使えるお金が増える計算になります。これは、住宅手当が課税対象となり、税金や社会保険料が増えてしまうためです。
【企業】経費と社会保険料の負担をシミュレーション
次に、企業側の負担がどう変わるかを見てみましょう。従業員に月8万円の家賃補助を行う場合で比較します。
| 項目 | ① 借り上げ社宅 | ② 住宅手当 |
|---|---|---|
| 費用計上 | 福利厚生費:80,000円 | 給与手当:80,000円 |
| 法人税への影響 | どちらも損金算入でき、効果は同等 | |
| 社会保険料の会社負担 | 増加しない(自己負担額が評価額を上回る場合) | 増加する(月額約10,000円) |
| 年間の差額 | – | 約120,000円の負担増 |
企業にとっても、社会保険料の負担が増えない点は大きなメリットです。従業員1人あたり年間約12.0万円の負担軽減となり、対象従業員が多ければ多いほど、その効果は大きくなります。
借り上げ社宅のデメリットと注意点
メリットの多い借り上げ社宅制度ですが、いくつかのデメリットや注意すべき点もあります。導入や利用を検討する際には、これらの点もふまえておくことが大切です。
従業員側のデメリット
従業員にとっては、住居の自由度が制限される可能性や、将来の社会保障にわずかな影響が出ることが考えられます。
- 自由に物件を選べないことがある:
会社が指定した物件に入居する場合や、家賃上限・エリア・間取りなどに会社の規定がある場合、希望どおりの住まいを選べないことがあります。 - 将来受けとる社会保障額が減る可能性がある:
社会保険料の負担が減るということは、その保険料を基準に算定される将来の年金額や、失業時に受けとる雇用保険の給付額がわずかに減少する可能性があります。 - 退職時には退去が必要:
会社の契約物件であるため、退職する際には原則として退去しなければなりません。
あらかじめ借り上げ社宅が用意されている場合は、従業員は希望する立地や間取りの物件を選べません。
また、企業に支払う家賃が収入から差し引かれるため、失業保険や将来受け取れる年金額が減ってしまう点がデメリットといえるでしょう。支払わなければいけない社会保険料が減るのはメリットである一方で、社会保障額も減ってしまうことに注意しましょう。
会社側のデメリット
企業にとっては、管理業務の手間やコスト、そして契約上のリスクが主なデメリットとなります。
- 契約や支払いなどの事務手続きが発生する:
物件の契約、毎月の家賃支払い、従業員の入退去に伴う手続きなど、人事・総務部門の業務負担が増加します。 - 空室でも家賃が発生する:
従業員が退職したり転勤したりして部屋が空いた場合でも、次の入居者が決まるまでや契約が切れるまでは家賃を支払い続けなければなりません。 - 解約時に違約金が発生する場合がある:
契約期間の途中で解約すると、違約金が発生することがあります。とくに従業員の急な退職などがリスクとなります。
借り上げ社宅制度を導入すると、契約や支払いなどの事務手続きが発生するため、手間がかかります。また、借りている部屋が空き部屋でも家賃が発生する、解約時に違約金を支払うリスクがあるといった点もデメリットです。解約時に違約金を支払うケースとしては、従業員が入居後すぐに退職したり、転勤が決まったりしたような場合が該当します。
借り上げ社宅の家賃負担額を決めるコツ
借り上げ社宅のメリットを最大限に活かすには、会社と従業員の家賃負担割合を適切に設定しましょう。この設定を誤ると、非課税メリットが受けられなくなるため注意しましょう。
会社と従業員の負担割合のルール
会社が家賃を全額負担してしまうと、その家賃分が従業員への給与とみなされ、課税対象になってしまいます。これを避けるためには、従業員から一定額以上の家賃を徴収しなければなりません。その基準となるのが、国税庁の定める「賃料相当額」です。
従業員から賃料相当額の50%以上を受け取っていれば、会社が負担する家賃は給与として課税されません。
この「賃料相当額」は、実際の家賃とは異なり、以下の3つの要素を合計して算出される、税法上の特殊な金額です。
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 0.2%
- 12円 ×(その建物の総床面積(㎡)/ 3.3㎡)
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 0.22%
参考:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁
一般的に賃料相当額は実際の市場家賃よりもかなり低くなる傾向があります。そのため、従業員負担が市場家賃の1〜2割程度であっても、賃料相当額の50%以上という条件をクリアできるケースがほとんどです。
役員社宅の場合の注意点
役員に対して社宅を貸与する場合、従業員よりも厳しいルールが適用されます。物件の規模によって計算方法が異なりますが、原則として算出した賃料相当額の全額(100%)を役員から徴収しないと、給与として課税されます。役員社宅を検討する際は、税理士などの専門家に相談するのが賢明でしょう。
一般的な費用負担の内訳
家賃以外にも、住居にはさまざまな費用がかかります。誰が何を負担するのか、あらかじめ社宅管理規程で明確にしておくことがトラブル防止につながります。
| 費用項目 | 費用の目安 | 一般的な負担者 |
|---|---|---|
| 初期費用(敷金・礼金・仲介手数料など) | 家賃の4~5ヶ月分 | 企業 |
| 引越し代 | 時期や荷物量による | 企業(とくに転勤の場合) |
| 家賃・管理費 | – | 企業・従業員で分担 |
| 更新料 | 家賃の1ヶ月分程度 | 企業 |
| 火災保険料 | 2年間で1.5~2万円程度 | 企業 |
| 水道光熱費・通信費 | – | 従業員 |
| 退去時の原状回復費用 | 故意・過失による損傷分 | 従業員 |
借り上げ社宅制度を導入・運営する流れ
実際に借り上げ社宅制度を導入し、運営していくための手順を解説します。円滑な運用のためには、事前のルール作りと継続的な管理が欠かせません。
導入までの5ステップ
1. 社内での導入決定
まずは住宅支援制度として借り上げ社宅を導入するかを経営層で検討します。目的や対象者、予算などを大まかに決め、取締役会などで正式に決定します。
2.社宅管理規程の作成
トラブルを防ぐため、以下のような項目を盛り込んだルールブックを作成します。
- 対象従業員の範囲(役職、勤続年数など)
- 物件の条件(エリア、家賃上限、間取りなど)
- 家賃の負担割合
- 入居・退去の条件
- 同居人の範囲
3.物件の選定
規程に基づき、賃貸物件を探します。不動産会社に依頼するのが一般的です。従業員のニーズをふまえ、立地や設備などを考慮して選びます。
4.賃貸借契約の締結
物件が決まったら、法人名義で賃貸借契約を結びます。契約内容を精査し、敷金や礼金などの初期費用を支払います。
5.従業員への周知と運用開始
社内イントラネットや説明会などで制度内容を従業員に周知し、利用希望者の募集を開始します。
導入後の主な管理業務
制度の導入後も、継続的な管理業務が発生します。
- 月次業務:
毎月の家賃支払いや、従業員の給与から自己負担分を天引き(給与控除)する処理が必要です。 - 更新業務:
契約更新時期が来たら、入居中の従業員の意向を確認し、更新手続きや更新料の支払いを行います。 - 入退去管理:
新たな入居者の手続きや、退去時の敷金精算、原状回復に関する対応などを行います。 - 年次業務:
不動産の貸主に対して支払った賃料などをまとめた「不動産の使用料等の支払調書」を作成し、税務署へ提出します。
借り上げ社宅制度のよくあるトラブルと対処法
借り上げ社宅制度の運用では、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。ここでは、代表的なトラブルとその対処法を紹介します。事前の規程作りが何よりの対策となるでしょう。
原状回復費用の負担
退去時に最も多いのが、原状回復費用をめぐるトラブルです。経年劣化による損耗は貸主負担ですが、従業員の故意・過失による傷や汚れは借主(企業)の負担となり、企業はそれらを従業員に請求することになります。
【対処法】社宅管理規程に「従業員の故意・過失による損傷の修繕費用は、従業員負担とする」と明記します。また、入居時に室内の写真を撮っておくことも有効です。
同居人の範囲
「同棲相手と一緒に住みたい」「親を呼び寄せたい」といった要望からトラブルに発展することがあります。
【対処法】規程で同居できる人の範囲(例:配偶者および二親等以内の親族)を明確に定めておきます。これにより、個人的な事情による要求を公平に判断できます。
中途退職時の対応
入居後すぐに従業員が退職してしまった場合、企業は空室の家賃を負担し続けることになったり、短期解約による違約金を請求されたりするリスクがあります。
【対処法】賃貸借契約時に、短期解約の違約金に関する条項を確認しておきましょう。また、規程に「入居後〇年未満で自己都合退職した場合、違約金の一部を従業員が負担する場合がある」といった規定を設けることも一案です。
借り上げ社宅に関するQ&A
ここでは、借り上げ社宅に関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 自分で探した物件を借り上げ社宅にできますか?
A.企業によって異なります。「従業員選択型」の制度を導入している企業であれば、従業員が希望の物件を探し、会社に法人契約してもらうことが可能です。ただし、家賃上限などの社内規程を満たす必要があります。
Q. 同棲は認められますか?
A.これも企業の社宅管理規程によります。近年では多様なライフスタイルに配慮し、婚約者や事実婚のパートナーとの同居を認める企業も増えていますが、規程で「配偶者のみ」と定められている場合もあります。事前に会社の担当部署に確認しましょう。
Q. 大企業でないと導入は難しいですか?
A.いいえ、そんなことはありません。1戸から契約できるため、中小企業でも導入は十分可能です。社有社宅のように大規模な初期投資が不要で、管理の手間も少ないため、むしろ中小企業に適した制度といえるかもしれません。
Q. 退職したらすぐに引っ越さないといけませんか?
A.原則として、退職日までに退去する必要があります。ただし、賃貸借契約の解約予告期間(通常1ヶ月前)があるため、退職が決まったら速やかに会社に報告し、退去日を調整する必要があります。引継ぎ期間などを考慮して、退職後数週間程度の猶予を設けている企業もあります。
借り上げ社宅制度の仕組みやメリットを知ろう
借り上げ社宅制度とは、企業が借りた賃貸物件を従業員に貸し出す制度を指します。相場よりも安い家賃で住居を借りられることや、物件を探す手間が省けることなどから、従業員に人気の福利厚生制度であり、採用活動におけるアピールポイントとなります。また、企業にとっても従業員にとっても、税制面でのメリットが大きいことも魅力です。
一方で、契約や支払いなどの手続きが必要であったり、空き部屋になっても家賃が発生したりといったデメリットも存在します。借り上げ社宅制度の導入は、借り上げ社宅制度のメリットとデメリットの両方をよく理解したうえで検討しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
月額変更届とは?随時改定で標準報酬月額が変更されるタイミングは?
健康保険や厚生年金保険の保険料は、給与に応じて区分した標準報酬月額によって決まります。標準報酬月額の決定方法には、資格取得時決定、定時決定、随時改定の3つがありますが、なかでも忘れ…
詳しくみる生命保険への加入は必要?社会保険をはじめとする社会保障制度との違いも解説!
日本では、9割近い世帯が生命保険に加入しているといわれています。テレビでも、生命保険のCMを見ない日はありません。 これほど普及している生命保険ですが、本当に加入する必要があるので…
詳しくみる社会保険の加入条件とは?手続きやパートの場合も解説
2022年10月から社会保険の適用拡大の条件に変更があり、対象企業の範囲が拡大されています。また、育児休業中の社会保険料免除が開始日と終了日の翌日が同月であっても14日以上の育休取…
詳しくみる厚生年金における加給年金とは?もらえる条件や振替加算についても解説!
厚生年金保険加入者が年金を受給できることになったときに、条件により年金額が加算されることを知っていますか?年金に加算される額のことを「加給年金」「振替加算」といいます。これらは家族…
詳しくみる扶養とは?所得税と社会保険の観点から解説!
所得税の扶養控除や社会保険の扶養など、「扶養」という言葉をよく聞くと思います。そもそも「扶養」という言葉は、所得税でも社会保険でも同じ意味で使われているのでしょうか? 今回は、「扶…
詳しくみる国民健康保険に扶養はある?加入手続きの注意点も解説
日本は国民皆保険制度を採っているため、全国民に健康保険への加入を義務付けています。退職によって社会保険の資格を喪失した際や、フリーター・アルバイトで親の扶養から外れた場合、自営業の…
詳しくみる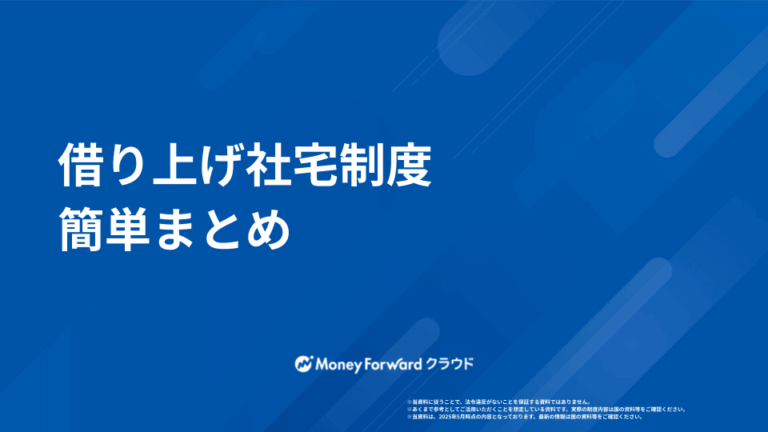

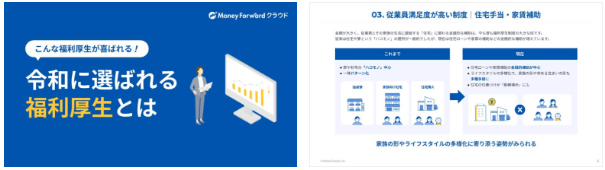
.jpg)
