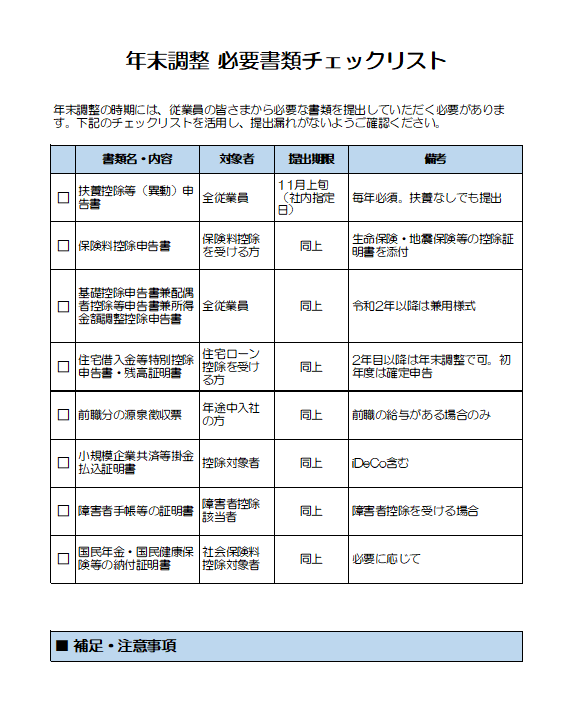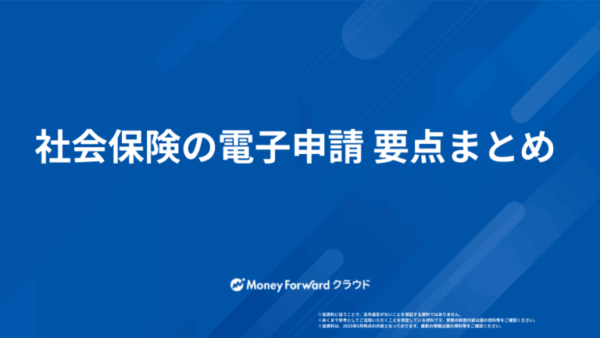- 更新日 : 2025年12月5日
年末調整を自動化するには?国税庁の無料ソフトやアプリでのやり方を解説
毎年、多くの担当者を悩ませる年末調整。膨大な書類の配布や回収、複雑な控除額の計算、度重なる修正依頼など、その業務は多岐にわたり、大きな負担となりがちです。
この記事では、年末調整を自動化するための具体的な方法を解説します。国税庁が提供する無料ソフトの活用法から、Webやスマートフォンを利用したネット申請の手順、さらにはe-Taxとの連携まで、担当者の負担を軽くする方法を理解しましょう。
目次
年末調整の計算の自動化が求められる理由
年末調整業務の自動化は、単に作業が楽になるだけでなく、企業と従業員の双方に大きなメリットをもたらします。
煩雑な手作業の削減
申告書の配布・回収、記載内容のチェック、控除額の検算、給与システムへの入力といった一連の作業は、担当者に大きな時間的、精神的負担をかけます。自動化システムを導入することで、これらの手作業が大幅に減り、担当者は問い合わせ対応や本来注力すべきコア業務に時間を使えるようになります。
法改正への迅速な対応
年末調整に関連する法令は頻繁に改正されます。信頼できるシステムを導入すれば、最新の法令へ自動でアップデート対応するため、担当者が自ら情報を追いかける必要がありません。これにより、法改正の見落としによる申告誤りのリスクを未然に防ぎ、コンプライアンスを強化できます。
計算ミスの防止
システムが控除額などを自動で計算するため、人為的な計算ミスを防ぎ、正確な申告を実現します。担当者は複雑な計算ロジックを都度確認する必要がなくなり、検算や修正対応に費していた時間を大幅に削減できます。
ペーパーレス化の実現
申告書や証明書類を電子データでやり取りすることで、紙代や印刷代、郵送費、保管スペースといった物理的なコストを削減できます。さらに、アクセス制限や暗号化が施されたシステムで情報を管理するため、書類の紛失や盗難といったセキュリティリスクを低減させることが可能です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選
業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。
実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。
社会保険の電子申請 要点まとめ
社会保険の電子申請に関する主要なポイントを、簡潔にまとめた資料です。
電子申請の概要把握や、実務を進める上での確認用資料としてご活用ください。
年末調整の計算を自動化する具体的な方法
年末調整の自動化を実現するには、いくつかの方法があります。企業の規模や状況に合わせて、最適な手段を選ぶことが重要です。ここでは、代表的な3つの方法を紹介します。
1. 年末調整ソフト(給与計算ソフト)の活用
年末調整に特化したソフトウェアや、年末調整機能を含む給与計算ソフトがあります。これらの多くはクラウド型で提供され、従業員からの申告データ収集、計算、進捗管理までを一元的に行えます。導入コストは発生しますが、手厚いサポートや他システムとの連携機能が充実している点が特長です。
2. 国税庁の年末調整控除申告書作成用ソフトウェア
国税庁は、無料で利用できる「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」を提供しています。従業員がこのソフトを使って控除申告書データを作成し、企業に提出することで、担当者はそのデータを給与システムに取り込みます。コストをかけずに電子化を始められる第一歩となります。
- ソフトウェアのダウンロード
国税庁のウェブサイトにあるダウンロードページから、誰でも無料でソフトウェアを入手できます。Windows版、Mac版、そしてスマートフォン版(Android/iOS)が用意されています。ページの案内に従い、お使いのデバイスにインストールすれば準備は完了です。 - マイナポータル連携で控除証明書を自動入力
このソフトや国税庁の年末調整アプリは、マイナポータル経由で取得した控除証明書データを読み込み、申告書に自動反映させることが可能です。これにより、従業員の手入力の手間とミスを減らせます。 - 作成したデータの提出
従業員は作成した電子データをメールなどで勤務先に提出します。企業側は、そのデータを給与計算ソフトなどに取り込むことで、後の計算作業を効率化できます。
3. 国税庁の年末調整計算シート(Excel)
国税庁の公式サイトから無料でダウンロードできるExcelファイルの「年末調整計算シート」です。 給与や控除対象の扶養親族の人数などの情報を入力するだけで、年末調整の税額計算を自動で計算します。入力項目が多いため、手元に全ての申告書や源泉徴収票を準備してから利用しましょう。利用には、Microsoft office Excelがインストールされたパソコンが必要です。
4. Webやスマホアプリを利用した申告
多くの年末調整システムは、Webブラウザや専用のスマートフォンアプリを通じて従業員が申告情報を入力できる仕組みを備えています。これにより、従業員は場所や時間を選ばず、手軽に申告作業を完了できます。特に若い世代の従業員にとっては直感的で分かりやすい方法です。
Webブラウザからの入力手順
基本的な流れとして、まず企業から案内されたURLにアクセスし、ログインします。その後、画面の案内に従って、扶養家族の情報や保険料の支払額などを入力していきます。生命保険料控除証明書などの書類は、スマートフォンで撮影した画像やPDFデータをアップロードするだけで提出が完了します。これが、年末調整のWeb入力の基本的なやり方です。
スマホアプリでの申請手順
スマートフォンを利用する場合、専用アプリをダウンロードするか、スマホ対応のWebサイトにアクセスします。質問に答えていくだけで申告が完了する対話形式のインターフェースが多く、PC操作が苦手な従業員でも簡単です。スマホでのやり方を社内で周知することで、提出率の向上が期待できます。
ネット申請で準備するもの
従業員が個人でネット申請を行うには、マイナンバーカードや保険会社から送られてくる控除証明書データ(電子データ)などが必要です。特にマイナポータルと連携することで、各種証明書データを一括で取得し、自動入力できるため大変便利です。この利便性を従業員に伝えることが、自動化推進の助けとなります。
e-Tax(eLTAX)と連携すればさらなる効率化が可能に
年末調整の自動化をさらに高いレベルで実現するためには、e-Tax(eLTAX)との連携が欠かせません。これにより、データの収集から行政への提出まで、一貫したデジタル化が可能になります。
企業は、従業員から集めた年末調整の電子データを給与システムに取り込み、年税額を計算します。その後、源泉徴収票や給与支払報告書といった法定調書を作成し、e-Tax(eLTAX)を利用して税務署や各市区町村へ電子申告します。これにより、印刷・郵送の手間とコストを無くすことができます。
年末調整の還付金の計算方法
年末調整で還付金がなぜ発生するのか、その計算方法を理解しましょう。還付金とは、1年間で給与から天引きされた源泉徴収税額の合計が、年末に確定した本来納めるべき税額(年調年税額)よりも多かった場合に、その差額が返金されるお金のことです。
計算は以下の6ステップで進められます 。
- 年間の総支給額を確定する
1月1日から12月31日までに支払われた給与や賞与の合計額(税金や社会保険料が引かれる前の金額)を算出します。 - 給与所得を算出する
年間の総支給額から「給与所得控除額」を差し引きます。給与所得控除は、会社員にとっての経費のようなもので、年収に応じて控除額が法律で定められています 。 - 課税所得金額を算出する
給与所得から、さらに各種「所得控除」の合計額を差し引きます 。所得控除には、全員が対象の「基礎控除」のほか、「社会保険料控除」「生命保険料控除」「扶養控除」など、個人の状況に応じた控除があります。 - 算出所得税額を決定する
課税所得金額に、所得税の税率を掛けて「算出所得税額」を計算します 。所得税は、課税所得金額が大きくなるほど税率も高くなる累進課税が採用されています。 - 年調年税額を確定する
算出所得税額から「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」などを差し引いて、その年に最終的に納めるべき所得税額である「年調年税額」を確定させます。 - 過不足額(還付金)を精算する
確定した「年調年税額」と、1年間で給与から天引きされた「源泉徴収税額」の合計額を比較します 。源泉徴収税額の方が多ければ、その差額が「還付金」として戻ってきます。逆に少なければ「追徴金」として追加で徴収されます。
令和7年(2025年分)の年末調整の変更点
2025年に行う年末調整(令和7年分)では、主に以下の点が還付金額に影響する可能性があるため注意が必要です。
定額減税の終了
2024年(令和6年分)に実施された1人あたり4万円(所得税3万円、住民税1万円)の定額減税は、2025年分の年末調整には適用されません。
扶養控除等の見直しと「年収の壁」の変更
いわゆる「年収の壁」への対策として、扶養控除や配偶者控除の適用要件が正式に見直されました。これにより控除の対象となる年収の上限が引き上げられています。
- 扶養の「103万円の壁」が実質「123万円の壁」に
これまで、パート収入などが年収103万円を超えると所得税の扶養から外れていましたが、この上限が実質的に年収123万円に引き上げられました。これは、給与所得控除の最低額が55万円から65万円に、基礎控除が48万円から58万円にそれぞれ引き上げられたためです。 - 19歳以上23歳未満の扶養親族に対応する「特定親族特別控除」の創設
19歳以上23歳未満の扶養親族(学生である必要はない)がいる世帯を対象に、「特定親族特別控除」が新たに設けられました。これにより、扶養する子供の年収が123万円を超えても、150万円以下であれば63万円の所得控除が受けられるなど、収入に応じて段階的な控除が適用されます。
これらの改正により、これまで扶養の対象外だった方が対象になったり、控除額が変動したりする可能性があります。ご自身の家族の収入状況を改めて確認し、年末調整に臨むことが重要です。
年末調整の計算の自動化に失敗しないための注意点
年末調整の自動化は多くのメリットをもたらしますが、システムの導入を成功させるためには、いくつかの注意点があります。事前の準備を怠ると、かえって業務が混乱する可能性もあります。
自社の規模や課題に合ったシステムを選ぶ
年末調整システムは、機能や価格帯が様々です。従業員数が少ない企業であればシンプルな機能のもので十分ですが、複雑な給与体系を持つ大企業の場合は、より高機能なシステムが必要になります。自社の規模やニーズを明確にし、複数のシステムを比較検討することが重要です。
導入・運用コストと費用対効果を見極める
システムの導入には、初期費用や月額利用料が発生します。自動化によって削減できる人件費や印刷コストと比較し、費用対効果を慎重に見極める必要があります。無料トライアル期間などを活用して、実際の使い勝手を確認した上で、本格導入を決定すると良いでしょう。
従業員への周知とサポート体制を整える
新しいシステムを導入する際は、従業員への事前説明が不可欠です。操作マニュアルの配布や説明会の開催など、従業員がスムーズに利用開始できるようなサポート体制を整えましょう。特にデジタルツールに不慣れな従業員への配慮を忘れないことが、円滑な移行のポイントです。
年末調整など効率化・自動化成功した事例
年末調整の計算を自動化することで、業務効率化や属人化の解消に成功した企業の事例を紹介します。ここでは「マネーフォワード クラウド」を導入した2社の取り組みを見ていきましょう。
30%超の業務効率化に成功(オリオンビール株式会社)
オリオンビール株式会社では、給与計算を2名体制で行い、源泉徴収票のマイナンバーを手書きで転記するなど、煩雑な手作業が課題となっていました。特に年末調整は従業員の記入が難しく、人事担当者が代理記入を行うケースも多く、本来業務を圧迫していました。
そこで「マネーフォワード クラウド 給与・年末調整」を導入。年末調整がアンケート形式で分かりやすくなり、従業員自身がスムーズに入力できるようになりました。その結果、代理記入が不要になり、書類回収やチェック作業を前倒しで進められるなど、年末調整の計算を自動化したことで30%超の業務効率化を実現しました。
参照:クラウドによるサービス連携で脱・手作業 30%超の業務効率化に成功|オリオンビール株式会社様の導入事例|株式会社マネーフォワード
年末調整1,000人分をほぼ未経験の2名で完了(フレッシュ物流株式会社)
フレッシュ物流株式会社では、従業員1,000名弱の年末調整を従来は5人で3日間かけて書類配布し、データ入力は1名が手作業で行っていました。業務が属人化し、ベテラン退職後の引き継ぎが困難になるリスクも抱えていました。
クラウド型の年末調整システムを導入した結果、ほぼ未経験の担当者2名だけで1,000人分の年末調整を完了。年末調整の計算を自動化することで、残業時間も大幅に削減し、業務のブラックボックス化を解消できました。持続可能な体制づくりに成功した事例といえます。
参照:年末調整1,000人分をほぼ未経験の2名で完了 残業も減りました|フレッシュ物流株式会社様の導入事例|株式会社マネーフォワード
最適なシステムで年末調整の自動化を実現しましょう
年末調整の自動化は、もはや一部の企業だけのものではなく、あらゆる規模の企業にとって現実的な業務改善策です。紙に頼った従来の方法から脱却し、デジタルツールを活用することで、担当者の負担は劇的に軽くなり、計算ミスといったヒューマンエラーも防止できます。
国税庁の無料ソフトから始める小規模な電子化、Webやスマホアプリを活用した全社的な効率化、そしてe-Tax(eLTAX)連携による完全ペーパーレス化まで、その選択肢は多岐にわたります。2025年の年末調整こそ、自社に最適な自動化の方法を見つけ出し、業務の正確性と生産性を飛躍的に向上させる絶好の機会です。この記事で紹介した情報を参考に、人事労務のDXに向けた第一歩を踏み出してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
源泉徴収票の再発行は会社以外でもできる?可能なケースや手順など解説
源泉徴収票が必要なのに手元になく再発行を検討する際、会社への連絡が難しい場合や退職済みの場合、「会社以外(役所や税務署)で再発行できないか?」と考える方は少なくありません。 結論か…
詳しくみる源泉徴収税額表の税区分「甲乙丙」とは?所得税の違いや年末調整の影響を解説
年末調整では、会社が従業員に毎月支払う給与から源泉徴収してきた所得税などを、年末に再計算して過不足を精算します。このときの源泉徴収額を決める基準となるのが、国税庁の「給与所得の源泉…
詳しくみる【早見表】生命保険料控除はいくらまで書く?新旧制度の違いや注意点を紹介
生命保険料控除とは、年末調整や確定申告の際に、その年の税額を計算するにあたり、生命保険料を差し引いて計算する仕組みです。生命保険料控除の上限金額は、旧制度は所得税10万円、住民税7…
詳しくみる【一覧】年末調整の書類保管期間は何年?紙・電子の違い、紛失リスクを解説
年末調整で扱う申告書や源泉徴収簿といった書類の保管期間は、所得税法により原則7年間と定められています。そのため、税額計算の根拠となるこれらの法定調書は、法律にのっとり適切に管理しな…
詳しくみる年末調整は自分でできる?できない?
年末調整は基本的に会社が実施してくれるため、意識されない方も多いのではないでしょうか。確定申告とは異なり、会社員が年末調整で行わなければならないケースは多くはありません。では、年末…
詳しくみる妻の生命保険料は年末調整で控除できる?条件を解説!
妻の生命保険料は年末調整で控除できるのでしょうか。通常、納税者本人が加入する生命保険は年末調整で控除可能です。一方、妻の分の生命保険は、保険料を誰が支払ったかによって控除の可否が異…
詳しくみる