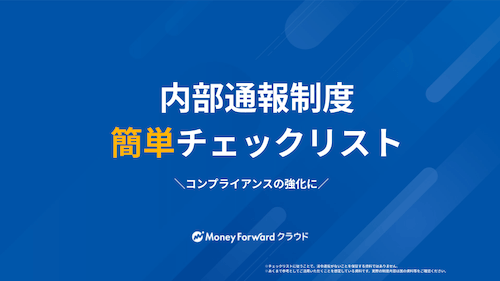- 更新日 : 2025年4月30日
コンプライアンスとは?具体的な意味や使い方・違反事例などをわかりやすく解説
コンプライアンスとは、「法令遵守」という意味がある言葉です。しかし現在では、法令を遵守することはもとより、企業倫理や社会規範を尊重する、といった意味合いがある言葉です。
企業の不祥事の増加や、インターネットの普及、グローバル化などに伴い、企業がコンプライアンスを重視する姿勢が強まっています。
この記事では、コンプライアンスの言葉の使い方(例文)や、コンプライアンスの違反事例などを、わかりやすく解説します。
目次
コンプライアンスとは
コンプライアンスとは、元の「法令遵守」という意味から派生し、現在では「企業倫理や社会規範に従うこと」という広い意味で使われている言葉です。
コンプライアンスに反したことから社会的信用を失い、倒産に追い込まれることもあるため、企業にとって非常に重要な観点です。
コンプライアンスの意味
コンプライアンスに明確な定義はないものの、語源は「compliance(従う・命令に応じる)」からきています。
コンプライアンスという言葉は、元々はアメリカ産業界で「法令遵守」の意味で使われていました。しかし、最近の日本では法令だけでなく就業規則や企業倫理、社会規範などを含むものとして認識されています。
2000年代以降、食品偽装問題やリコール隠しなどが大きく報道されて社会問題となりました。それにより、法令だけでなく社会規範やモラルまでを含めた広義のコンプライアンスを遵守することが企業に対して求められるようになりました。
現在では、顧客データ流出や不正会計、ハラスメント問題などを規制する社内規範を表す言葉としても使われています。
医療現場におけるコンプライアンスとは
医療現場におけるコンプライアンスも、基本的には法令や社会規範を遵守するという意味合いがありますが、人の生命や健康に直接関わるという重要な特性から、医療現場におけるコンプライアンスの内容はより広範かつ厳格です。
医療業界は、医師法や医療法、薬機法、個人情報保護法など、数多くの法律の規制を受けており、まさに「法律の縛りが強い業界」といえます。これらの法令遵守は当然のこととして、さらに各医療機関が定める院内規程(医療安全管理指針、院内感染対策指針、倫理規程など)や、各学会が策定する診療ガイドライン、医師や看護師といった専門職としての高い職業倫理規範(日本医師会が定める医師の職業倫理指針など)も遵守すべき対象となります。
医療現場における、具体的なコンプライアンスの重要な要素は以下の通りです。
- インフォームド・コンセントの徹底
- 患者のプライバシー保護(守秘義務の遵守)
- 医療安全の確保(医療事故防止策の実施)
- 個人情報の適正な管理(特に診療記録などの要配慮個人情報(個人情報保護法2条3項))
- 院内感染対策の徹底
- 職業倫理の遵守
これらを遵守することが、患者からの信頼を得て、質の高い安全な医療を提供することにもつながります。
コンプライアンスの使い方
コンプライアンスという言葉は、下記のような文脈で使われます。
- この企業は、コンプライアンスを徹底するための研修を定期的に実施しています。
- コンプライアンスに違反した場合は、会社の就業規則に基づく解雇や契約解除、損害賠償を含む処分が課される場合があります。
- 新しいコンプライアンスガイドラインが来月発表される予定です。
- 社員一人ひとりがコンプライアンスの大切さを理解し、日々の業務に反映させることが求められています。
- コンプライアンス違反の報告は、内部告発制度を通じて行われることが多いです。
- 企業の成長とともに、コンプライアンスの複雑さも増しているため、適切なコンプライアンス教育が不可欠です。
- 弊社のコンプライアンスに関する考え方として、弊社の一人ひとりが高い倫理観をもち、社会からの期待・要請に応えることで実践されます。
- 取引先のA社でコンプラ違反があったそうですよ。
コンプライアンスという言葉が「遵守する」といった意味を含みます。
そのため、「コンプライアンスを遵守する」といった使い方は、重ね言葉になるので誤りという考え方もあります。しかし実際にはよく使われている表現なので、問題ないとの見方が多いです。
コンプライアンスに関連する用語
ここでは、コンプライアンスに似た意味をもつ用語や、コンプライアンスが使われるような文脈で使用される用語について、わかりやすく解説します。
コーポレートガバナンスとは
コンプライアンスもコーポレートガバナンスも、共に目的は企業の公正で健全な経営を保つことです。
コンプライアンスが企業内外の社会規範や倫理観に「従う」ことを意味するのに対し、コーポレートガバナンスは企業がそれらコンプライアンスを遵守するよう、自ら監視役を付けて外部から「統制」することを指します。
コーポレートガバナンスは、「会社は経営者のものではなく、株主やステークホルダー(利害関係者)のもの」という理念に基づいており、アメリカを中心とした諸外国が取り組み、国際的な重要度も高まっています。日本でも2021年3月1日に施行された改正会社法により、上場会社での社外取締役の設置が義務化されるなど、コーポレートガバナンスの強化がより重要視されてきています。
内部統制とは
内部統制とは、コンプライアンスを含む社内規範を守るため、会社内部の業務適正化など、社内ルールを作り、それを遵守させる仕組みのことをいいます。
金融庁によると、内部統制には以下の4つの目的が設定されています。
- 業務の有効性及び効率性
- 財務報告の信頼性
- 事業活動に関わる法令などの遵守
- 資産の保全
例えば、外部への情報漏洩を防ぐために、USBフラッシュメモリを社外へ持ち出すことを禁止する社内ルールを作り、厳守させるのも内部統制の1つです。
参考:「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」の公表について|金融庁
企業倫理・社会規範とは
企業倫理はビジネス活動に関連する道徳的価値や原則を中心に据え、社会規範は広く社会全体の行動や態度の期待を表す言葉です。
企業倫理
企業倫理は、ビジネス活動の中で企業が遵守すべき道徳的価値や原則を指す概念です。
企業が利益を追求する過程で、法的要件を超えた倫理的責任を果たすための行動規範や判断の基準を提供します。具体的には、公正な取引、顧客のプライバシーの尊重、従業員の権利の保護、環境保護への取り組みなどが含まれます。
社会規範
社会規範は、社会の一員としての人々の行動や態度を規定する、書かれていない「ルール」や「期待」を指します。
例えば「お年寄りや体の不自由な方がいたら、席を譲る」といった考え方は、社会規範の1つでしょう。
社会規範は、文化、伝統、教育、宗教などの多様な要因に基づいて形成され、個人が社会の一員として受け入れられるための行動や態度を示すガイドラインとして機能します。社会規範は、明示的な法律や規則とは異なり、遵守しなかった場合に法的な制裁が伴うわけではありません。しかし、社会規範を逸脱した行動をとると、社会的に大きな影響を与える恐れがあります。
アドヒアランスとは
アドヒアランス(adherence)は、医療分野における用語で、患者の治療計画や指示への従順性や遵守度を指す言葉です。「くっつく」や「接着する」という意味を持ちます。
医療分野で使われるコンプライアンスとアドヒアランスは、どちらも医療分野における患者の治療計画や指示への従順性や遵守度を指す用語ですが、そのニュアンスや意味に違いがあります。
コンプライアンスは、その文字通り「従う」や「服従する」という意味合いが強く、患者が医師の指示や治療計画にどれだけ正確に従っているかを中心に考える概念です。
一方、アドヒアランスは患者と医療従事者の相互理解を基にしている関係です。具体的には、患者自身が治療計画や治療目標に納得し、それに対するコミットメントを持って取り組んでいることを意味します。
コンプライアンスが重視される背景
企業には社会的責任(Corporate Social Responsibility = CSR)が求められ、CSRを果たすためにもコンプライアンスが重視されています。
利益を追求するだけでなく、自らの営利活動が社会に与える影響に責任をもつためにも、企業にはコンプライアンス遵守が必要なのです。
また、コンプライアンスの遵守は、企業にとって自己防衛手段でもあります。というのも、昨今見られる次のような社会的背景があるためです。
- 企業の不祥事はSNSによって広く知れ渡りやすく、その情報がインターネット上に残り続けること
- 2006年に「公益通報者保護法」が施行され、内部告発者が保護されるようになったこと
企業内部のことであっても、コンプライアンス違反に対して「今までもそうだったから」「みんなやっているから」という言い訳は、もはや通用しません。
コンプライアンス違反を起こした企業は厳しい非難を受け、重大な事案になれば社会的な制裁を受けて取引先を失ったり、株価が下落したりするなどして、倒産に至ることもあるのです。
このような事態を未然に防ぐためにも、社会の基準に合わせて社内ルールを作り、コンプライアンスを遵守することがいっそう求められるようになっています。
コンプライアンス違反となる事例
ここでは、コンプライアンス違反となる代表的な事例を5つ紹介します。
データの持ち出しや情報漏洩
多くの企業に考えられるリスクの1つとして、データの持ち出しや情報漏洩があります。
実際に、近年は顧客情報などの漏洩事件がよく問題になっています。日本年金機構では、2015年に125万件もの個人情報が流出する事故が起こりました。
直接的な原因は、標準型メールで送信されてきた添付ファイルを職員が開封してしまったことにありますが、さらに、このようなサイバー攻撃に対し、個人情報の保管場所やパスワード設定などのセキュリティ措置に関する内部規律が、徹底されていなかったことが問題だったと報告されています。また、同年には日本郵政のメール誤送信による情報漏洩事件も発生しました。
昨今はリモートワークの普及で、パソコンやデータなどを社外に持ち出して作業をする機会が増えています。その分、情報漏洩のリスクも増加するため、今まで以上に、内部規範の見直しが必要かもしれません。
ハラスメント
2019年6月の労働施策総合推進法改正により、職場のハラスメント対策が義務化されました。
それまでは、ハラスメントに対する許容範囲が人によって異なり、ハラスメント対策を進めづらい状況でした。そこで、法改正で厚生労働省が具体的な基準を示し、社内対策を義務化しました。これにより、性別や立場を利用したハラスメントなどが社員の尊厳や人格を傷つける行為である認識が広まりました。
また、ハラスメント対策を怠ることは、企業にとって重大なコンプライアンス違反となりました。
超過勤務
不適切な超過勤務やサービス残業もまた、コンプライアンス違反とみなされます。近年は過重労働が命を奪いかねない問題として取り締まられるようにもなりました。
景品表示法違反
景品表示法では、顧客の勧誘方法として大企業がその資本力を利用して商品やサービスに豪華景品を付けたり、過大な、または虚偽の広告を打ったりすることが禁止されています。
不正会計や不正利用
株価を維持するための虚偽申告や脱税のための所得隠し、社内備品の私的利用など、不正会計や不正利用の問題は企業規模に関係なく発生し得る問題です。
近年では、新型コロナウイルス感染拡大による業績不振に対する支援策であった持続化給付金の不正受給が相次ぎました。多くの事業者が企業倫理に反し、コンプライアンスに違反した結果だともいえるでしょう。
コンプライアンス違反が起きる理由
コンプライアンス違反は、単一の原因ではなく、複数の要因が絡み合って発生することが多いです。コンプライアンス違反が起きる主な理由としては、具体的に以下のようなものがあります。
社員などの知識・意識の不足
社員一人ひとりが、関連する法規範や社内規範などの内部ルール、倫理規範、社会規範の内容を十分に理解していなかったり、コンプライアンスの重要性に対する認識が低かったりする場合には、社員がうっかりコンプライアンス違反を犯してしまうことがあります。
社員の「これくらいなら大丈夫だろう」「他の人もやっているから」といった安易な考えが、重大な違反につながるケースも少なくありません。特に、新しい法律の施行や社会情勢の変化に対応できていない場合に起こりやすいです。
過度なプレッシャーやノルマ
過度な業績目標や達成困難なノルマが設定されている場合、社員は目標達成を優先するあまり、不正な手段に手を染めてしまうことがあります。
「業績目標達成・ノルマ達成は会社のためになる」として社員がその行為を自分の中で正当化してしまうと、不正な手段をとることに躊躇がなくなることが多いからです。
具体例としては、売上目標達成のために架空計上を行ったり、納期を守るために品質検査を省略したりするケースがあります。
短期的な成果を求めるプレッシャーが、長期的な視点でのコンプライアンス意識を低下させる要因となります。
不十分な内部統制・監視体制
コンプライアンスを遵守させるための内部統制や監視体制、チェック体制が整備されていないと、コンプライアンス違反が起こりやすくなります。
会社内部の業務適正化など、社内ルールを作り、それを遵守させる仕組みである内部統制などのチェック体制が不十分な場合、社員がコンプライアンスに違反することは分かっていても、心理的にためらうことなく違反行為に及んでしまう恐れがあります。
具体的には、社員のコンプライアンス違反に対するモニタリング体制を整備していない組織内では、社員は「ばれないだろう」と考えてしまう可能性が高いです。
コンプライアンス違反によるリスク
企業がコンプライアンス違反を犯した場合、法的、経済的、社会的な側面から深刻なダメージを負うリスクに直面します。単なるイメージダウンにとどまらず、事業の存続そのものを脅かす可能性もあります。
法的責任を追及されるリスク
コンプライアンス違反の内容に応じて、法律に基づく罰金、高額な課徴金、業務停止命令、許認可の取り消しといった行政処分を受けるリスクを負うことになります。
また、役員や社員個人が刑事責任を問われ、逮捕・起訴されたり、被害者から損害賠償請求訴訟を起こされたりするケースもあります。
法的・行政的な処分を受けると、多大な時間と費用がかかるだけでなく、業務停止命令や許認可の取り消しなどは通常の事業運営をも困難にし、事業の存続そのものが脅かされます。
経済的な損失を負うリスク
上記の法的処分などが新聞やテレビなどのメディアに報道されることで、株価下落による企業価値が毀損したり、再発防止策に導入コストがかかったりなど、直接的・間接的に甚大な経済的損失が企業に発生します。
場合によっては、資金繰りが悪化し、倒産に至るリスクもあります。違反によって失われる利益は、不正によって得た利益をはるかに上回ることがほとんどです。
ブランドイメージを低下させるリスク
コンプライアンス違反が明らかになると、顧客、取引先、株主、地域社会など、ステークホルダーからのブランドに対する信用を大きく損ないます。一度失った信用を回復することは非常に困難であり、製品・サービスの不買、取引停止、株価の下落などを招き、企業のブランドイメージに長期的なダメージを与えます。優秀な人材の流出や採用難にもつながる可能性があります。
コンプライアンスを遵守するメリット
コンプライアンスを遵守することは、リスクを回避するという側面に加えて、企業に多くのメリットをもたらします。法令や社会規範を尊重する姿勢は、企業の持続的な成長と発展の基盤にとってなくてはならないものです。
すなわち、企業がコンプライアンスを重視し、実践することは、社会からの信頼を得て、企業価値を高めるための重要な経営戦略ともいえるのです。
企業価値・社会的信用の向上
コンプライアンスを遵守し、公正で透明性の高い経営を行っている企業は、顧客、取引先、投資家、地域社会などからの信頼を得やすくなります。
信頼を得ることによって長期的な取引関係の構築や、資金調達においても有利に働きます。
加えて、コンプライアンスを遵守している企業として評価されることは、ブランドイメージの向上につながります。
社員のモチベーション向上と人材確保
公正な労働環境が整備され、ハラスメントがなく、法令が遵守されている職場は、社員にとって安心して働ける場所であることが多いです。
またそのような、コンプライアンス意識の高い企業文化のある職場では、社員のエンゲージメントや定着率が高いことも少なくありません。
社会的に信頼されている企業であることは、優秀な人材を採用する上でも大きなアドバンテージとなります。
業務効率の改善と生産性の向上
コンプライアンス遵守のためのルールや業務プロセスを整備する過程で、業務の無駄が見直されたり、責任の所在が明確になったりすることがあります。これにより、業務の標準化が進み、効率化や生産性の向上につながる場合があります。
また、不正やミスが減ることによって、対応に費やす時間やコストの削減も可能です。
コンプライアンスを遵守する3つの方法
企業はコンプライアンスを遵守するため、法令だけでなく、企業倫理や社会規範に従うことが強く求められています。そのためには次のような対策を行う必要があります。
マニュアルを作成する
コンプライアンス遵守のためには、社会基準に合わせたマニュアルの作成が何よりも重要です。マニュアルには、企業のルールとそれに取り組むべき方針、万が一不祥事が起こった際の対応方法や改善策などを記載します。
決まった書式はありませんが、多くの企業に共通する構成要素は下記の3点です。
- 基本理念の確認
- 行動規範
- 行動基準
マニュアル作成の際には、自社の業務に関する法律の知識も必要な場合があります。弁護士など外部の専門家を交えて作成することも検討しましょう。
現場の社員が使いやすい具体的な内容とし、時代錯誤や見落としを避けるため、定期的にマニュアルを見直すことも大切です。
コンプライアンス研修を行う
作成したマニュアルは社内に周知・徹底させましょう。研修を行い、コンプライアンスに対する意識を社内で統一しておくことも重要です。
研修後にはアンケートやテストを実施すれば、各社員の理解度を確認できます。四半期ごとに研修を行う企業が多いようですが、研修の頻度や内容は、社員の理解度に応じて調整しましょう。
コンプライアンス相談窓口を設ける
社内にコンプライアンス統括部門を設けても、一部門のチェックだけでは見逃す可能性があります。社員一人ひとりがコンプライアンスチェックを行い、違反の恐れがある場合には匿名で報告できる相談窓口を設けましょう。企業の不祥事を未然に防げる可能性が高まります。
社内のコミュニケーションのルートを周知させ、報告者を保護する仕組みを構築することで、コンプライアンス違反の認知・是正へつなげる効果が期待できます。
相談窓口は、マニュアルが現場にそぐわない場合に気軽に意見を言える場所としても有効です。
コンプライアンスを強化するための企業事例
ここでは、コンプライアンスを強化するための企業事例として、マネ―フォワードグループの取り組み例をいくつか紹介します。
※以下は記事執筆日時点の内容です。最新情報、およびより詳しく知りたい方は「コンプライアンスに関する基本的な考え方」をご覧ください。
コンプライアンス体制の整備
代表取締役社長が、当社グループにおけるコンプライアンス実践に関して統括し、取締役会の決議により、当社グループのコンプライアンス推進に係る活動を統括する責任者として、CCO(Chief Compliance Officer / 最高コンプライアンス責任者)を任命しています。
代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を四半期に1回開催しており、CCOからコンプライアンス実践の徹底に向けた各種取組みに関して実施状況等の報告を行います。
また、日常業務においてコンプライアンスの観点から留意が必要な事項や法令等の動向等についても報告・協議を行います。
コンプライアンス教育の実施
国内の当社グループ全役職員に対して、入社時にCCOを講師として下記のコンプライアンスオリエンを、e-ラーニング(オンラインテキスト研修及び理解度テスト)にて実施しています。
- 「マネーフォワードグループ コンプライアンス・マニュアル」に関する研修
- インサイダー取引防止・インサイダー情報管理に関する研修
- ハラスメント防止に関する研修
- 知的財産に関する研修
加えて、日常業務で直面する法令や社内規程等に関する研修として、特定のテーマの各種コンプライアンス研修(オンライン研修、オンデマンド研修)も随時実施しており、一部のテーマについては管理職向けの研修を用意するなど、より実践的な教育施策も実施しています。
内部通報制度の制定
グループ全社に適用される「グループ内部通報規程」を制定しています。
具体的には、当社グループ役職員が、当社及びグループ会社内での法令違反行為、コンプライアンス違反行為、ハラスメント行為などの行為について、通報を行えるような受付窓口を設けています。
内部通報窓口は、当社内に設置している2つの窓口(ハラスメント相談窓口とコンプライアンス相談窓口)に加えて、常勤社外監査役及び外部弁護士も窓口として設置しています。メール、チャットツールなどの手段で、匿名で通報することができ、通報の事実とその内容については、内部通報対応に従事する関係者により秘密が厳守されます。
コンプライアンスは社内全体で取り組む重要課題
企業に課せられた社会的責任を果たし、信頼度を高めるためにも、企業にとってコンプライアンスの遵守は重要な課題です。コンプライアンスを軽視した結果として違反が発覚すれば、外部からの厳しい批判を受け、社会的な信用を落とすだけでなく、経営危機に陥る恐れもあります。
コンプライアンスは経営陣のみならず、社員一人ひとりがその重要性を理解し、マニュアルを作成するなどして会社全体で取り組む必要があるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
民法177条とは?第三者の範囲や物権変動の対抗要件についてわかりやすく解説
民法177条とは、第三者に対して不動産の権利を主張するためには登記が必要であることを定める条文です。不動産を取得したときや喪失したとき、あるいは権利を変更したときは、都度登記手続を実施し、第三者に権利を主張できるようにしておかなくてはいけま…
詳しくみる著作者人格権とは?含まれる権利や契約時の注意点を紹介
著作者人格権とは、楽曲や絵画、プログラムなど、ある作品を作った方に認められる権利です。取引に際して、お金を払って譲り受けた成果物でも著作者人格権を無視できることにはなりません。 実務においても注視する必要があるこの著作者人格権とはいったいど…
詳しくみる道路交通法とは?事業者が知っておきたい規制や改正をわかりやすく解説
道路交通法とは、交通ルール等をまとめた法律のことです。無秩序に道路を使用すると人を死傷させてしまうこともありますので、法律で共通のルールを設けているのです。 従業員による運転が事故に繋がることもありますので、道路交通法については企業において…
詳しくみる企業結合規制とは?独占禁止法における定義や審査や届出基準、事例をわかりやすく解説
独占禁止法における企業結合規制とは、企業結合により、企業同士が事業活動を共同して行う関係になり、業界内の競争が制限されることを避けるためのものです。M&A(吸収&合併)の際に、適用される場合があります。本記事では、企業結合ガイドライ…
詳しくみるプライバシーとは?個人情報保護法に基づきながら解説
仕事でも日常生活でもインターネットが欠かせない現代社会において、プライバシーとその保護について知っておくことは大切です。「プライバシー」と「個人情報」の違いや、2022年4月に改正される個人情報保護法について、しっかり把握しておきましょう。…
詳しくみる民法とは?基本原則や改正内容などを簡単にわかりやすく解説
民法とは、個人や法人といった人間の行動に対して適用される法律です。民法により私人の権利が保護され、経済活動を円滑に進めることが可能となります。 本記事では、民法の基本的な事項を見ていきます。事業者が押さえておくべき民法の概要や、2020年に…
詳しくみる