- 更新日 : 2025年11月13日
慰労金とは?具体例や退職金との違い、税金や相場を解説
慰労金とは役員や従業員の労をねぎらうために支給するお金です。同じ趣旨のものとして退職金が知られていますが、こちらは退職金に関する規定に基づき支給され、慰労金とは異なります。この記事では慰労金の具体例を紹介した上で、特に注意が必要な役員退職慰労金の相場や支給手続き等を解説しますので、実務を進める上で参考にしてください。
目次
慰労金とは?
慰労金(いろうきん)とは、労をねぎらうために支給されるお金のことです。同様に長年の労をねぎらう意味合いを持つ退職金との違いについて、以下で解説します。
慰労金と退職金との違い
慰労金では、役員の退任時に支給する役員退職慰労金がよく知られています。その他にも退職金規定で退職金の支給が定められていないパート従業員が退職する際に一時金を支給するパート慰労金などがあります。このうち、役員退職慰労金は、株主総会決議等を経て支給額等を決定しなければならないため、会社の独断で支給できない性質のものです。
一方、退職金は就業規則において会社の退職給付制度として規定するのが一般的で、役員ではなく一般の従業員の退職にあたって支給される点が慰労金とは異なります。また計算方法や支給額を会社が決定できる点でも、役員退職慰労金と異なります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
エンゲージメント向上につながる福利厚生16選
多くの企業で優秀な人材の確保と定着が課題となっており、福利厚生の見直しを図るケースが増えてきています。
本資料では、福利厚生の基礎知識に加え、従業員のエンゲージメント向上に役立つユニークな福利厚生を紹介します。
令和に選ばれる福利厚生とは
本資料では、令和に選ばれている福利厚生制度とその理由を解説しております。
今1番選ばれている福利厚生制度が知りたいという方は必見です!
福利厚生 就業規則 記載例(一般的な就業規則付き)
福利厚生に関する就業規則の記載例資料です。 本資料には、一般的な就業規則も付属しております。
ダウンロード後、貴社の就業規則作成や見直しの参考としてご活用ください。
従業員の見えない不満や本音を可視化し、従業員エンゲージメントを向上させる方法
従業員エンゲージメントを向上させるためには、従業員の状態把握が重要です。
本資料では、状態把握におけるサーベイの重要性をご紹介いたします。
慰労金の具体例
慰労金にはいくつかの種類があります。代表的なものを以下で紹介します。
退職慰労金
退職慰労金とは、一般的には役員退職慰労金と同じ意味になります。この他、退職金が支給されない従業員の退職時に支給されるものもあります。代表的なものが後ほど紹介するパート慰労金です。
役員退職慰労金
役員の退任時に支給される慰労金です。詳細については後ほど解説します。
特別慰労金
厚生労働省による「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」に基づき交付された慰労金など、特別に支給する慰労金のことです。医療従事者、医療機関の職員、介護サービス事業者等が感染症対応の最前線で業務に従事していたことに対し、最大20万円の慰労金を給付しました。
パート慰労金
パート慰労金は、退職金が規定されていないパート従業員の退職時に、長年にわたっての勤務をねぎらうために支給する一定額の慰労金のことです。
慰労金の税金は?課税・非課税?
慰労金に課税されるか否かは、所得税法等の規定(非課税所得に関する規定)によります。慰労金は基本的には課税対象となりますが、先述の新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金など、その慰労金の支給の性質によっては非課税となる場合もあります。
所得税法等で定める非課税所得については、以下のリンクの通りです。
慰労金の相場は?
慰労金の中で支給額の調査結果が公表されているのは、役員退職慰労金です。ここでは役員退職慰労金(役員退職金)の相場について、エヌエヌ生命保険株式会社の「中小企業の退職金に関する調査」の結果を踏まえて解説します。
この調査は、全国の中小企業の役員等約10,000名へのアンケート形式で実施したものです。2020年の調査結果のうち、役員の職位ごとの平均支給額は以下の通りです。
社長:2,476万円
取締役:1,685万円
監査役:1,150万円
参考:役員退職金の相場・簡単シミュレーション・社長の功績倍率データ|エヌエヌ生命保険株式会社
役員退職慰労金の計算方法
役員退職慰労金は一般的には功績倍率法と呼ばれる方法で計算し、計算式は以下の通りです。
役員退職慰労金=退職時の報酬月額×役員在任年数×功績倍率
このうち、功績倍率については役員の職位毎に定められるもので、法律等で明確に定められていませんが、同業種・同規模の類似法人の功績倍率の平均値を上限とすることが一般的です。この功績倍率が役員退職慰労金の相場の重要な要素になっているとも言えるでしょう。
功績倍率の平均値については以下の通りです。
代表取締役(創業者):3.0~3.4
代表取締役:2.4~3.2
専務取締役:2.2~2.7
常務取締役:2.0~2.6
取締役:1.2~2.0
監査役:1.0~1.6
なお、急な業績悪化や病気等により報酬減額があった場合など、功績倍率法では妥当な慰労金の額を算定できない場合もあります。そのような場合には、1年あたり平均額法と呼ばれる方法で算定します。
役員退職慰労金=同規模・同業種の役員退職金1年あたり平均額×役員在任年数
※役員退職金1年あたり平均額=役員退職金÷勤続年数
また、特別な功績があった役員に対しては功労加算金を支給することもあります。一般的には役員退職慰労金の30%の額を上乗せ支給します。
参考:役員退職慰労金とは?計算方法と功労加算・税金面の注意点や支給手続きを解説 | 給与計算ソフト マネーフォワード クラウド (moneyforward.com)
慰労金を支給するメリット・デメリット
慰労金の支給について、会社側のメリットとデメリットを解説します。
慰労金を支給するメリット
役員退職慰労金については、税務上損金算入が可能で、法人税の負担を減らせるのもメリットです。また、役員の退任時以外の慰労金の支給では、退職金支給でその労に報いることができないパート従業員等に対して謝意を表明できることもメリットと言えるでしょう。
慰労金を支給するデメリット
慰労金の中でも役員退職慰労金は高額になることが一般的です。したがって、経営状況や財務基盤が厳しい企業にとっては大きな負担になることはデメリットと言えます。
また、役員退職慰労金は一般的には株主総会決議を経て支給するため、滞りなく決議されるように進めるための調整が負担になります。万一総会で否決されるようなことがあると、企業内部の混乱につながることになるためです。
慰労金を支給する際の手続き
慰労金の中でも役員退職慰労金については、支給手続きが会社法に規定されているため注意が必要です。
取締役(役員)の報酬等について、会社法第361条で定款に定めるか、または株主総会の決議を経ることが求められています。役員退職慰労金を定款に定めることはまれで、一般的には株主総会の決議により定める形を取ります。
ただ、株主総会では支給金額までは決定せず、支給方法や時期などを含めて決定を取締役会に一任することが一般的です。この場合、株主が決議の可否を判断するために支給基準を示す必要があり、取締役会への一任はその基準に基づき行う形を取ります。
支給に関する基準は役員退職金規程など、正式な規程として明文化されていることが望ましいですが、基準として機能する限りは慣行として確立されているものでも問題ないとされています。
また、取締役会への一任のために役員退職慰労金の支給基準を株主に示すためには、株主総会招集通知とともに送付する参考書類に記載しなければなりません。なお、参考書類への記載に代えて、支給基準を本社などに備え置いて株主が閲覧できるようにすること等、適切な措置を取ることも可能とされています。
以上の手続を通じ、株主総会の決議を経ることで、先に述べた税務上のメリットである役員退職慰労金の損金算入が可能になります。
慰労金を支給する際の注意点
先述の通り、役員退職慰労金は法人税の計算上、損金に算入することができるため、会社にとって節税効果をもたらします。この損金算入にあたっては、形式的基準、実質的基準、金額基準の3つの要件を満たす必要があります。これらの要件を満たしていない場合、税務調査で否認される可能性があるため注意が必要です。
形式的基準
役員退職慰労金は会社法により定款で定めるか、または株主総会の決議を経る必要があります。株主総会の決議を経ることなく、事業主の独断で慰労金の支給額を決定した場合には、仮に金額が適正であっても、形式的基準を満たさないために税務調査で否認される可能性があります。
実質的基準
役員退職慰労金を受け取っても、引き続き経営上の主要な地位に就いている場合、役員退職慰労金としての支給が認められません。
なお、役員退職慰労金を受け取った後、役員としての地位や職務内容が大きく変わる分掌変更が行われた場合は、実質的に退職したものと同様と考えられ、役員退職慰労金が認められます。
具体的には以下の場合などが該当します。
- 常勤役員から非常勤役員になる(実質的に経営上の主要な地位にある場合を除く)
- 取締役から監査役になる(実質的に経営上の主要な地位にある場合を除く)
- 役員報酬の額が概ね50%以上減少
金額基準
役員退職慰労金は、役員としての業務従事期間、業種や規模が同じ法人における支給額などを考慮し、妥当と判断される額の支給が認められます。これらの基準から考えて、役員退職慰労金が不相当に高額と判断された場合、高額となった部分については損金算入が認められないため、注意が必要です。
役員退職慰労金については、以下のリンクも参考にしてください。
参考:役員退職慰労金とは?計算方法と功労加算・税金面の注意点や支給手続きを解説
慰労金を正しく支給して労に報いよう
慰労金は役員や従業員の労に報いるために支給するものです。慰労金を支給される役員や従業員だけでなく、会社にとっても節税効果といったメリットがあります。一方、役員退職慰労金は支給手続きが法律で厳密に規定されているため、正しい手続きを踏まなければメリットを享受できないことになりかねません。
この記事で紹介した手続きや注意点などに特に注意して、支給する側、される側双方に良い形で慰労金を支給して、役員や従業員の労に報いましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
試用期間中の社員が能力不足の場合、延長は可能?手続きや注意点を徹底解説
試用期間中の社員のパフォーマンスが期待に満たない場合「能力不足」を理由に期間の延長を検討する人事担当者も多いでしょう。この延長は法的に可能ですが、企業が自由に行えるものではなく、適…
詳しくみる【テンプレ&例文あり】部下の不始末による始末書の書き方は?書き方や注意点を解説
部下を抱えていると、自分だけでなく、部下の始末書作成にも関わることがあるでしょう。本記事では、責任の所在、事実の正確な記載、具体的な再発防止策など、作成するうえで押さえるポイントを…
詳しくみる日雇い派遣とは?禁止されている理由や単発バイトとの違い、例外で許可されるケースを解説
日雇い派遣とは、「派遣期間が30日以内」の仕事を指します。平成24年の派遣法改正で原則禁止となった働き方ですが、一部の条件を満たす人や業務であれば労働が可能です。 本記事では日雇い…
詳しくみる労働条件通知書を変更する場合はどうするべき?変更できる条件や方法を紹介
労働条件通知書を不利益変更する場合は、対象の従業員全員から同意をもらう必要があります。同意なしの変更は原則として認められません。 また「労働条件を変更する場合に満たすべき条件は他に…
詳しくみる継続雇用制度と再雇用との違いとは?選ぶメリット・デメリットを解説
継続雇用制度は、定年を迎えた従業員が希望すれば65歳まで働き続けられるようにする制度です。「高年齢者雇用安定法」に基づき、企業に導入が義務付けられています。少子高齢化が進む中、意欲…
詳しくみる経歴詐称とは?具体例や罰則、企業の対応方法を解説
経歴詐称とは、学歴、職歴、犯罪歴などの経歴を隠したり、虚偽の申告をしたりする行為のことです。経歴詐称が発覚すると企業にとっては大きなリスクになるため、企業の対応が重要になります。本…
詳しくみる

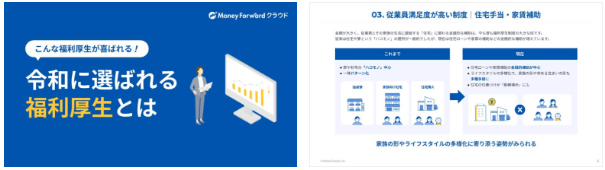
.jpg)
