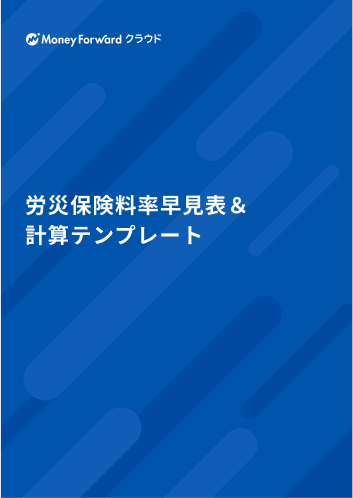- 更新日 : 2025年11月13日
令和7年度の労災保険料率は?金額の計算方法もシミュレーションつきで解説
労災保険料率は、労災保険料の計算に用いられる料率です。
労災事故が起こりやすい危険な業種ほど労災保険料率が高く設定され、危険が少ない安全な業種には低い労災保険料率が設定されています。多くの事業では、労災保険料と雇用保険料をあわせた労働保険料を年度更新と呼ばれる保険料の申告・納付手続きにより納付するのが一般的です。
本記事では、労災保険料率の詳細と計算方法、納付方法について徹底解説します。
労災保険料率は、労災保険料の計算に用いられる料率です。
労災事故が起こりやすい危険な業種ほど労災保険料率が高く設定され、危険が少ない安全な業種には低い労災保険料率が設定されています。多くの事業では、労災保険料と雇用保険料をあわせた労働保険料を年度更新と呼ばれる保険料の申告・納付手続きにより納付するのが一般的です。
本記事では、労災保険料率の詳細と計算方法、納付方法について徹底解説します。
労災保険料率早見表&計算テンプレート | 給与計算ソフト「マネーフォワード クラウド給与」
目次
労災保険料率とは
労災保険料率とは、労災保険料の計算に用いられる料率で、労災保険の給付財源となる保険料を決定する基準です。
そもそも労災保険とは
労災保険とは、業務災害や通勤災害に被災した労働者を対象に必要な給付を行う、労働者を使用する企業が必ず加入しなければならない社会保険制度です。
労災保険は、業務中や通勤中にした怪我だけではなく、白血病や肺がん、難聴、潜水病などの仕事によって発症する病気、脳出血やくも膜下出血、脳梗塞、心筋梗塞、狭心症などの長時間労働によって発症する病気、仕事による精神的な負担から発症する精神疾患などにも対応しています。
業務災害については、労働基準法でも使用者に災害補償を義務付けています。しかし、企業の災害補償の金額は多額となることが多いため、労災保険の給付を受けることで、企業は保険給付の範囲内で労働基準法の業務災害における災害補償の責任を免れることが可能です。
ただし、労災保険の休業補償給付は休業4日目から行われるため、企業には休業3日目までの休業補償を行う必要があることに注意が必要です。
労災保険について、詳しくは以下の記事で説明しています。是非参考にしてください。
労災保険料とは
労災保険料は、労災保険の給付を行うための財源となる保険料です。労働災害や通勤災害に遭ってしまった労働者に対する給付のために徴収され、保険料に従業員の負担はなく、全額事業主が負担します。
企業が労災保険料を正しく計算するには、自社の業種に適用される料率を確認することが重要です。
下記の記事では、労働保険料について具体的に解説しているため、あわせてご覧ください。
労災保険料と労働保険料の違い
労災保険料は、業務災害に対する補償にあてる給付を受けるために、事業主が全額負担する保険料です。労災保険は業務中や通勤中の事故や業務に起因する疾病が対象となり、労災保険料は業種ごとのリスクに応じた料率で計算されます。
一方、労災保険料と雇用保険料をあわせたものを労働保険料といいます。雇用保険料は、労働者が失業した際の給付や育児休業の際の給付にあてられるものです。労働保険料のうち雇用保険料は労働者と事業主がそれぞれ一定割合を負担します。
上記のように、労災保険料は業務災害補償を目的とし事業主が全額負担、雇用保険料は事業主と労働者がそれぞれ負担します。労働保険料のうち労災保険料は全額事業主負担であるのに対し、雇用保険料は労働者も分担する点が大きな違いです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
労災対応がよくわかるガイド
前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。
一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。
‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。
年度更新の手続きガイドブック
年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。
本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
令和7年度の労災保険料率
令和7年度の労災保険料率は、令和6年度と変更はありません。労災保険料率は3年ごとに見直されますが、令和6年に改正されたばかりのため、次回の見直しまで現行の料率が適用されます。
労災保険料率は事業の種類別に区分され、業種ごとに細かく設定されています。同じ事業でも業務内容が異なれば料率も異なるため注意が必要です。具体的な料率は以下のとおりです。
| 分類 | 事業の種類 | 労災保険率 |
|---|---|---|
| 製造業(一部抜粋) | 食品製造業 | 5.5/1,000 |
| 建設業(一部抜粋) | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 34/1,000 |
| 卸・小売・飲食・宿泊 | 全般 | 3/1,000 |
| その他 | ネットショップやコールセンターなど | 3/1,000 |
参考:労災保険率表|厚生労働省
労災保険率は、業務の危険度が高い業種ほど高く設定されています。同じ業種でも具体的な業務内容や役割によって料率が異なるため、注意が必要です。
労災保険料の計算方法
労災保険料は、「全従業員の年度内の賃金総額 × 労災保険率」で計算されます。賃金総額とは、労働者に支払った賃金を合計した金額です。
給料や賞与、手当など、労働の対価として支払われるものはすべて賃金に該当します。現金での給付以外に、通勤に使用する定期券といった現物で支給するものも賃金の総額に含まれるため注意しましょう。
一般的に就業規則や賃金規則で労働者に対して支給することが規定されているものすべてが賃金の総額に含まれますが、退職金や見舞金、労働基準法に基づく休業補償などは性質上賃金の総額に含める必要はありません。
労災保険料は、先述した労災保険料率表のうち、該当する業種の保険料率に、賃金の総額を乗じて計算します。保険料の負担割合は社会保険のように従業員との折半ではなく、全額事業主が負担します。
労災保険料の計算例・シミュレーション
労災保険料の具体的な計算例は以下のとおりです。
建設業
建設業の労災保険率は、事業内容が建築、土木、解体など多岐にわたることから、作業の危険度に応じて細かく分類されており、料率も最小0.6%から最大3.4%までと、非常に幅広くなっています。
一例として、建設業の中で最も高い料率である3.4%が適用される、水力発電施設で計算してみましょう。この事業所の年間賃金総額が1億円だった場合、納付すべき労災保険料は以下の通り算出されます。
100,000,000円 × 3.4% = 3,400,000円
したがって、この事業所が納付すべき確定労災保険料の額は、3,400,000円となります。
舗装工事業
舗装工事業は建設事業の一つであり、労災保険料率は0.9%です。 建設事業の中では、比較的料率の低い分類です。仮に、年度内の賃金総額が2億円の事業所の場合、労災保険料は、賃金総額に労災保険料率の0.9%を乗じて以下のように計算されます。
200,000,000円 × 0.9%= 1,800,000円
したがって、この場合の確定労災保険料は1,800,000円です。
コンクリート製造業
コンクリート製造業は製造業の一つであり、労災保険料率は1.3%です。製造業の中では、料率が高めであり、労働災害の多い業種であることがわかります。コンクリート製造業を営む事業所で、年間の賃金総額が1億8千万円の場合は、賃金総額1億8千万円に労災保険料率1.3%を乗じて保険料が計算されます。
180,000,000円 × 1.3% = 2,340,000円
したがって、この事業所が納める確定労災保険料は2,340,000円です。
ビルメンテナンス業
ビルメンテナンス業の労災保険料率は0.6%です。例えば年間の賃金総額が1億円である場合、賃金総額1億円に、労災保険料率0.6%を乗じて算出されます。
100,000,000円 × 0.6% = 600,000円
したがって、この事業所で納める確定労災保険料の金額は600,000円です。
卸売業
卸売業は、労災保険料率の業種区分において小売業や飲食、宿泊業と同じ0.3%の料率です。 年間の賃金総額が5千万円の事業所を例にすると、労災保険料は賃金総額5千万円に労災保険料率0.3%を乗じて算出します。計算式は以下の通りです。
50,000,000円 × 0.3% = 150,000円
したがって、この事業所で納める確定労災保険料の金額は150,000円となります。
不動産業
不動産業の労災保険料率は0.25%であり、保険業や金融業と並んで最低ラインの料率となっています。仮に、事業所の年間の賃金総額が3千万円の場合、賃金総額3千万円に労災保険料率0.25%を乗じて、以下のように算出されます。
30,000,000円 × 0.25% = 75,000円
したがって、この事業所で納める確定労災保険料の金額は75,000円です。
| 業種 | 賃金の総額 | 労災保険料 | |
|---|---|---|---|
| 例① | 舗装工事業 | 2億円 | 200,000,000×9/1000=180万円 |
| 例② | コンクリート製造業 | 1億8千万円 | 180,000,000×13/1000=234万円 |
| 例③ | ビルメンテナンス業 | 1億円 | 100,000,000×5.5/1000=55万円 |
| 例④ | 卸売業 | 5千万円 | 50,000,000×3/1000=15万円 |
| 例⑤ | 不動産業 | 3千万円 | 30,000,000×2.5/1000=7万5千円 |
建設業の場合、数次の請負によって事業が行われることが常態のため、工事全体の賃金総額を把握することが困難なケースもあるでしょう。
上記のような場合には、特例が認められています。建設業で正確な賃金総額の算出が困難な場合には、請負金額(消費税を除く)に所定の労務比率をかけて賃金総額を算定するのが一般的です。
例えば、令和7年度における舗装工事業の労務比率は17%です。したがって、賃金総額の算出が困難な場合には「請負金額(消費税を除く)×17%」で計算した概算の賃金総額に労災保険料率の0.9%を掛けることで労災保険料を計算できます。
労働保険料の年度更新とは
労働保険料の年度更新とは、前年度の労災保険と雇用保険の確定保険料を申告・納付し、新年度の概算保険料を申告・納付する手続きです。
労働保険でいう「年度」は、4月1日から翌年3月31日で区切られ、年度が替わる際は、具体的に以下の手続きを行うことになります。
- 前年度(前年4月1日から当年3月31日)に実際に支払われた賃金を元に、「確定保険料」を計算
- 当年度(当年4月1日から翌年3月31日)までに支払われる賃金の概算から、概算保険料を計算
※一般的に、賃金の概算額は、前年度に支払われた賃金総額と同額とする - 前年度に支払った概算保険料と、1.の確定保険料の差額を精算
※前年の概算保険料が多ければ還付となり納付保険料に充当が可能、確定保険料が多ければ追加で納付が必要 - 2.(当年度の概算保険料)と3.(前年度と当年度の保険料差額)の合計額を納付する
厚生労働省の年度更新申告書計算支援ツール
厚生労働省が提供する「年度更新申告書計算支援ツール」は、労働保険の年度更新手続きを支援するために作られた、Excel形式の計算ツールです。このツールを活用することで、労動保険料の計算作業が大幅に効率化されます。
このツールは厚生労働省のウェブサイトからダウンロードでき、以下の流れで使用します。まず「算定基礎賃金集計表」に月ごとの雇用保険適用社数と賃金額を入力します。その際、日雇労働被保険者とそれ以外に分けて入力しなければなりません。
次に、「申告書記入イメージ」に、確定保険料と概算保険料の料率・申告済概算保険料額・延納回数を入力します。記入すべき数値は、労働保険料の申告期間前に労働局から送られる「労働保険料の申告書」で確認してください。
以上の手順に沿ってツールの入力を終えると、自動的に支払うべき労働保険料が計算される仕組みです。
年度更新申告書計算支援ツールは、計算結果が申告書の様式通りに表示されるため、数字をそのまま申告書と納付書に転記するだけで、労働保険料の申告と納付が完了します。
手計算によるミスを防げるため、業務効率化にもつながるツールです。
労働保険料の納付期間は6月1日から7月10日まで
労働保険料の納付期間は毎年6月1日から7月10日までです。開始日と終了日が土日祝に当たる場合は後ろ倒しとなるため、令和7年度の納付期間は6月2日から7月10日までとなります。
事業主は、期間内に当年度の労働保険料を計算し、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」を所轄の労働基準監督署や労働局に提出し、国へ納付する必要があります。労働保険料のうち、労災保険料は事業主が全額負担し、従業員の給与から天引きすることは認められていません。
納付を怠ると延滞金が発生する可能性があるため、期限内の手続きが重要です。
労働保険料の納付方法
労働保険料の納付には、現金納付・口座振替・電子納付・労働保険事務組合への委託の方法があります。
現金納付とは、労働基準監督署や労働局、銀行などに申告書を提出し、現金で納める方法です。元請事業主が提出する「一括有期事業報告書」は銀行での取り扱い不可のため、注意が必要です。
口座振替は、指定の銀行口座から自動引き落としで納付する方法を指します。利用には「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」の提出が必要です。
電子納付の場合、インターネットバンキングやATMを利用して納付できます。e-Govのシステムを利用すれば、前年度の情報を取り込んで手続きを簡略化できることがメリットです。
労働保険事務組合への委託は、厚生労働大臣の認可を受けた団体が、労働保険の手続きを事業主に代わって行う方法です。概算保険料の申告・納付や労災保険の特別加入申請などを代行しますが、入会金や手数料が必要な場合があります。とくに中小企業にとっては、事務負担を軽減できる点がメリットです。
納付期限を過ぎると延滞金が発生する
労働保険料を納期限までに納付しない場合、本来の保険料に加えて延滞金を支払う必要があります。
延滞金は法定納期限の翌日から発生し、未納期間に応じて年14.6%(最初の2ヶ月は軽減措置あり)が加算されます。上記は、期限内に納付した事業主との公平性を保つための措置です。
さらに、滞納が続くと財産を差し押さえて強制的に徴収される「強制処分」の対象となるため、期限を守ることが重要です。
労災保険料に関する注意点
労災保険料を適切に納付するためには、納付期限の厳守や計算ミスの防止が重要です。
納付が遅れると延滞金が発生し、場合によっては督促を受けることもあります。また、保険料の算出には賃金総額や業種ごとの保険料率が関係するため、正確な確認が必要です。以下では、各注意点について解説します。
労災保険料は3年に1度改定される
労災保険料率は、業種ごとの過去3年間の災害発生状況をもとに、原則3年ごとに改定されます。
直近では令和6年度に改定され、業種平均の労災保険料率が4.5/1000から4.4/1000へ引き下げられました。特別加入保険料率や一部建設業の労務費率も変更されています。
上記により、事業所が負担する労災保険料が変動するため、最新の保険料率を確認し、適切に対応することが重要です。
複数事業を展開する場合は事業ごとの保険率で計算する
労災保険料の料率は一定の場所において一定の組織のもとに活動をする事業単位で決定されるため、複数の事業を展開する場合は、それぞれの事業で労災保険を成立させ、保険料を計算して申告・納付する必要があります。
つまり、会社全体で1つの労災保険が適用されるわけではなく、原則として営業所や本社・支社などで労災保険は個別に適用されるということです。また、1つの適用事業内において、経理や人事といった複数業種の業務をしている場合、主たる業務の保険料率が適用されます。
出向社員と派遣社員で取り扱いが異なる
出向社員と派遣社員では、適用される労災保険が異なります。
出向社員の場合、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事する者であるため、出向先企業の労災保険が適用されます。
一方、派遣社員は派遣契約が派遣先ではなく派遣元との雇用関係に基づき、派遣元の労災保険が適用されるため、両者を混同しないように注意が必要です。
パート・アルバイトの賃金も対象になる
労災保険は、事業主に雇用されて、労働に対する賃金が支払われている「労働者」の全員に適用されます。雇用形態や働き方は問われないため、常勤の正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトも対象です。そのため、労災保険料の計算をする際は、パートタイマーやアルバイトも含め、労働者に支払われる給与や賞与額を全て「賃金総額」に含める必要があります。
役員報酬は原則として賃金総額に含まれない
労災保険は労働者を保護する制度であることから、会社の経営を担う役員は、原則として労働者に該当せず、対象外となります。そのため、役員に支払われる報酬は賃金とはみなされず、労災保険料算定の基礎となる賃金総額には含まれません。ただし、役員であっても、労働者としての職務を兼ねる「兼務役員」の場合、労働者としての職務に対して支払われる賃金部分については、賃金総額に含める必要があります。
労災保険料率について理解を深め、正しく労災保険料の計算を行いましょう
労災保険は労働者保護の観点から、労災事故が起こった際に保険給付を行うことを目的として設けられた公的保険制度です。労働災害補償保険法に基づき、仕事中や通勤中にケガをした労働者、業務が発症の原因となる疾病にかかった労働者などに必要な給付を行います。労災保険にかかる労災保険料の全額は事業主が負担しなければなりません。
労災保険料は、労災保険料率を用いて計算されます。業種別に定められている労災保険料率と年度の賃金総額をかけあわせた金額が、確定労災保険料の金額です。正しく計算して正確な労災保険料の納付に努めましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
離職票の発行条件は?流れや日数、もらえない・やっぱり欲しい場合の対処法も解説
退職後の手続きで使う離職票。失業保険(基本手当)の受給に必要な書類ですが、自分の場合は発行されるのか、退職したのにいつまで経っても届かない、といった不安はありませんか。特に、失業保…
詳しくみる高額療養費(高額医療費支給制度)とは?社会保険の観点から仕組みを解説!
「高額療養費制度」とは、高額な医療費負担を軽減するための制度で、医療機関で支払った自己負担額のうち限度額を超えた額が手続きによって還付されたり、事前申請によって支払わずに済んだりし…
詳しくみる遺族年金とは?遺族厚生年金の要件や対象者などを解説
遺族年金とは、国民年金または厚生年金の被保険者が亡くなった際に被保険者によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。国民年金の被保険者が亡くなった場合は「遺族基礎…
詳しくみる育児休業給付金とは?育休中の社会保険料についても解説!
育児休業給付金は育児休暇を取得している際に収入を補填してくれる大切な制度です。そこでこの記事では育児休業給付金の支給条件や支給期間などについて分かりやすく解説しました。また、社会保…
詳しくみる介護保険法とは?わかりやすく解説!保険料や介護サービスを受けるまでの流れ
介護保険法とは、介護を必要とする人への保険給付について定めた法律です。介護保険の対象者には第1号被保険者と第2号被保険者があり、保険料の計算方法や納付方法、利用できるサービスが異な…
詳しくみる自己都合退職の失業保険はいつから・いくらもらえる?最新のルールを解説
自己都合退職でも失業保険を受給できます。自己都合退職は会社都合退職に比べて、最終的に受け取れる金額の総額や、必要な雇用保険加入期間(被保険者期間)などの点で差がある点が特長です。そ…
詳しくみる