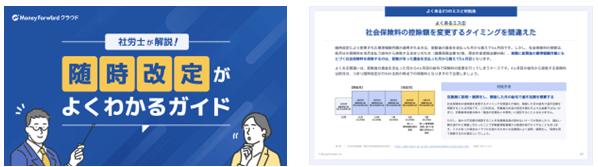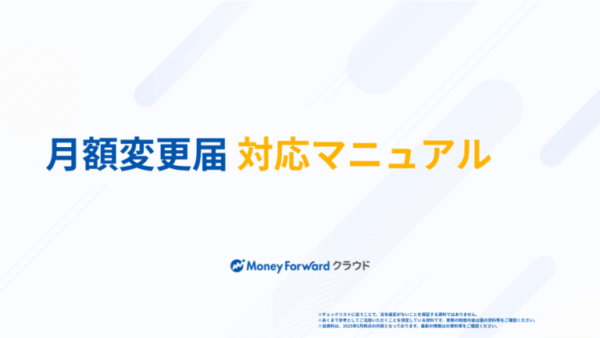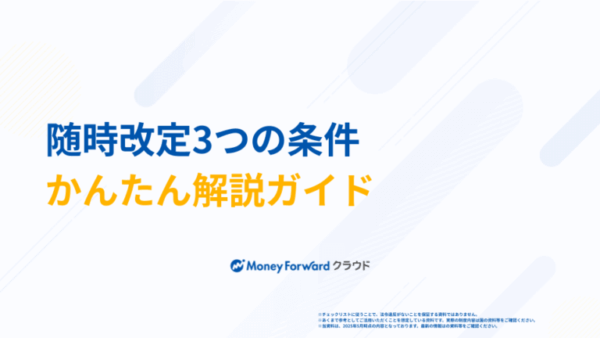- 更新日 : 2025年12月24日
算定基礎届と月額変更届との違いは?対象者や提出方法を詳しく解説
算定基礎届と月額変更届は、企業の社会保険手続きにおいて重要な書類です。従業員の標準報酬月額を決定するために提出が必要な手続きであり、提出方法や提出先に関して注意すべきポイントがあります。
本記事では、算定基礎届と月額変更届との違いや提出方法を詳しく解説します。
目次
算定基礎届(定時決定)は標準報酬月額を決定するために重要な書類
算定基礎届の正式名称は「被保険者報酬月額算定基礎届」です。算定基礎届は毎年1回、従業員の標準報酬月額を見直すために提出する必要があります。
標準報酬月額は、従業員が受け取る報酬をもとに決定される額のことです。これをもとに、健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料などの社会保険料が算出されます。
厚生労働大臣は届出内容にもとづき、毎年1回標準報酬月額を決定する仕組みです。このことを「定時決定」といいます。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月まで、各月に適用されます。
社会保険手続きで重要な役割を果たすため、期日を守って提出しましょう。
算定基礎届について、以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。
算定基礎届の提出が必要なケースと不要なケース
算定基礎届は、7月1日現在のすべての被保険者に提出が求められます。対象となるのは、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマー、育児・介護休業中の従業員も含まれます。
また、傷病により休職している場合でも、社会保険に加入している従業員は対象です。しかし、下記のいずれかに該当する場合は、算定基礎届の提出が不要となります。
- 6月1日以降に資格を取得した従業員
- 6月30日以前に退職した従業員
- 7月改定の月額変更届を提出する場合
- 8月または9月に随時改定が予定されている場合に申出を行った従業員
算定基礎届を提出しないケース・不要なケースを正しく把握し、適切な手続きを行いましょう。
算定基礎届の提出先・提出方法
算定基礎届は、毎年7月1日から7月10日までの間に提出する必要があります。ここでは、提出方法を詳しく解説します。
届出用紙で提出する場合
算定基礎届を「届出用紙」で提出する場合は、必要な書類を整え、算定基礎届送付時に同封されている返信用封筒で事務センターへ郵送します。管轄の年金事務所に直接持参することも可能です。
提出する書類は、下記のとおりです。
- 被保険者報酬月額算定基礎届
- 被保険者報酬月額変更届(該当者がいる場合)
70歳以上の被用者がいる場合や報酬に変更があった場合は、提出する
事前に必要書類を確認し、正確に記入して提出期限内に提出を完了させましょう。
電子申請で提出する場合
電子申請で算定基礎届を提出する場合、CSVファイル形式で届出データを作成し、オンラインで提出します。電子申請すれば、迅速に手続きできるため、手間を省けます。
下記のCSVファイルを用意し、日本年金機構が提供する「電子申請(届書作成プログラム)」を使ってデータを作成する流れです。
- 被保険者報酬月額算定基礎届
- 被保険者報酬月額変更届(該当者がいる場合
提出先は、日本年金機構のオンラインシステムであるe-Govを利用します。電子申請に関する詳細や不明点がある場合は、日本年金機構のホームページやe-Govの総合窓口で確認できます。
電子媒体で提出する場合
電子媒体を使用して提出する場合は、届書作成プログラムで作成したデータを、CDまたはDVDに保存して提出します。提出時には、事業所名、提出元ID、媒体通番を油性ペンで記入する必要があります。
必要な提出物は、下記のとおりです。
- 作成したCDまたはDVD
- 電子媒体届書総括票(紙の届書)
- 被保険者報酬月額変更届(該当者がいる場合)
電子媒体を使用した提出方法について不明点がある方は、日本年金機構のホームページに記載されているガイドラインを確認し、適切に準備を整えましょう。事前に「届書作成プログラム」を使用して、正確なデータ作成を行う必要があります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
随時改定がよくわかるガイド
月額変更届の手続き(随時改定)は、一定の要件を満たす従業員を対象にその都度対応が必要になります。
この資料では、随時改定の基本ルールと手続き方法に加え、よくあるミスの対処方法についても解説します。
月額変更届 対応マニュアル
従業員の報酬が変動した際、「月額変更届」の提出が必要となる場合があります。
本資料は、「月額変更届」に関する対応マニュアルです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きの実務にお役立てください。
随時改定3つの条件 かんたん解説ガイド
社会保険料の標準報酬月額を見直す「随時改定」は、実務上、正確な理解が求められます。
本資料は、「随時改定」の対象となる「3つの条件」について、かんたんに解説したガイドです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きにおける実務の参考としてご活用ください。
月額変更届(随時改定)とは?
月額変更届(随時改定)は、従業員の給与が大きく変動した際に、「標準報酬月額」を変更するための届出です。
通常、社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額は、毎年4月から6月の給与をもとに決定され、9月から適用されます。しかし、昇給や降給、手当の増減などにより給与が大きく変動した場合は、次の定時決定を待たずに随時改定(月額変更届)を提出することで、実態に合った保険料に変更できます。
参考:
関連記事
月額変更届の提出が必要なケース
月額変更届を提出する必要があるのは、次の3つの条件をすべて満たす場合です。
- 昇給または降給などにより、固定的賃金に変動があったこと
- 固定的賃金の変動月から3ヶ月間に支給された報酬の平均額にもとづき、標準報酬月額を算定した場合に2等級以上の変動があったこと
- 3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であること
これらの条件が揃ったら月額変更届を提出して、標準報酬月額を更新し、適切な社会保険料を算出する手続きを行います。
関連記事
月額変更届の対象にならないケース
月額変更届(随時改定)の対象にならないケースは、下記のとおりです。
- 休職中の固定的賃金の変動
- 3ヶ月の平均給与額の変動が非固定的賃金によるもの
休職中に給与体系が変わっても、その期間は通常の勤務ではないため、随時改定の対象外となります。ただし、例外として休職中も給与が減額されることなく支給されている場合は、随時改定の対象となる場合があります。
また昇給や降給があっても、その変動が残業手当や交通費など、非固定的賃金の変動によるものであれば、月額変更届の対象にはなりません。
これらのケースでは、標準報酬月額の変更はする必要がないため、注意しましょう。
月額変更届の手続き方法
月額変更届は、管轄の年金事務所や事務センターに提出します。健康保険が協会けんぽ以外の組合健保や共済組合の場合は、各組合への提出も必要です。
提出方法は、下記のとおりです。
- 窓口
- 郵送
- 電子申請※一部法人では義務化
資本金1億円超の法人や投資法人などは、電子申請が義務化されているため、オンライン手続きが必須です。対象法人以外でも、電子申請は、スムーズに手続きを進められるため、時間を短縮できるメリットがあるため、積極的に利用するとよいでしょう。
算定基礎届と月額変更届の違い
算定基礎届と月額変更届は、いずれも社会保険料を確定するために必要な届出書類です。しかし、提出タイミングや対象者に違いがあります。
算定基礎届は毎年1回、4月から6月に支払われた報酬にもとづいて、翌年8月まで適用される標準報酬月額を決定する手続きです。
一方、月額変更届は昇給や降給、手当の増減など給与の固定的な部分に大きな変動があった場合に提出し、即時に標準報酬月額を変更します。月額変更届による見直しを「随時改定」といいます。
手続きのタイミングの違いは、下記のとおりです。
- 算定基礎届:7月に提出し、標準報酬月額を9月分から適用する
- 月額変更届:給与の変更があったタイミングで提出、変更後の報酬が発生した月から4ヶ月目の保険料に反映される
算定基礎届は毎年7月1日から7月10日までの時期に提出するのに対し、月額変更届は給与が変動したタイミングで随時提出します。
また、月額変更届は該当する従業員がいる場合、その都度提出が求められます。
算定基礎届と月額変更届どちらの標準報酬月額が優先される?
算定基礎届と月額変更届がそれぞれ異なる標準報酬月額を決定する際に、どちらが優先されるかは随時改定のタイミングによって異なります。
具体的には、7月・8月・9月に該当する従業員がいる場合は、その期間に随時改定で決定された標準報酬月額が優先されます。算定基礎届が提出されたあとでも、新たに決定された標準報酬月額が適用される仕組みです。
算定基礎届が提出されたあとに報酬の変更があった場合は、月額変更届を提出しましょう。反映された標準報酬月額を適用させることが大切です。
タイミングを見極めて適切に手続きを行い、社会保険料の算定に誤りがないように注意しましょう。
参考:日本年金機構|算定基礎届と月額変更届(7月・8月・9月改定分)では、どちらの標準報酬月額が優先されますか
関連記事
算定基礎届と月額変更届は同時に提出できる?
算定基礎届と月額変更届は、同時に提出可能です。実際、これらは提出タイミングや内容に応じて、同時または先に提出することが推奨されています。
とくに7月の月額変更届は、6月の給与支払い後、速やかに提出することが求められます。この場合、月額変更届は算定基礎届と同時、または先に提出しましょう。この時期は遅れて月額変更届が提出されるケースや、提出漏れが発生しやすいので注意が必要です。
両者を同時に提出すれば、社会保険料の算定が正確に行われ、手続きがスムーズに進みます。なお、電子媒体(CD等)や電子申請で提出する場合は、それぞれのファイルを別々に作成し、提出しましょう。
参考:
関東ITソフトウェア健康保険組合|令和6年度算定基礎届等の提出方法について
算定基礎届の記入方法
算定基礎届は、従業員の社会保険料を決定するために必要な書類です。正確に記入することが求められるため、提出前に各項目を確認しておきましょう。
算定基礎届は以下のような書類です。
引用:被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者算定基礎届|日本年金機構
ここでは、算定基礎届の記入方法を詳しく解説します。
支払基礎日数
算定基礎届の⑩「日数」の欄には、4月から6月に支払われた報酬にもとづく支払基礎日数を記入します。この日数は、その月に実際に給与が支払われた対象日数を指します。
時給制・日給制の場合は、有給休暇も含む実際の出勤日数が支払基礎日数です。月給制・週給制では、出勤日数に関係なく、暦日数が使用されます。ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則にもとづいて欠勤分を差し引いた日数を記入します。
月給制の場合の例は、下記のとおりです。
【給与末日締、当月末日支払のケース】
| 月 | 暦日 | 支払基礎日数 |
|---|---|---|
| 4月 | 4月1日~30日 | 30日 |
| 5月 | 5月1日~31日 | 31日 |
| 6月 | 6月1日~30日 | 30日 |
【給与25日締、当月末日支払のケース】
| 月 | 暦日 | 支払基礎日数 |
|---|---|---|
| 4月 | 3月26日~4月25日 | 31日 |
| 5月 | 4月26日~5月25日 | 30日 |
| 6月 | 5月26日~6月25日 | 31日 |
参考:日本年金機構|算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)
支払基礎日数は、給与計算の締切日と支払日の関係によって異なるため、注意しましょう。
通貨と現物支給額
通貨と現物支給額の記入方法は、下記のとおりです。
- ⑪「通貨」欄:現金で支給された基本給や手当など、金銭で支払われた報酬を記入
- ⑫「現物」欄:現金以外で支給された報酬(食事や住宅など)を記入
参考:日本年金機構|健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 (記入例)
現物支給は、原則として時価に換算して記入します。ただし、食事や住宅など特定の支給品に関しては、日本年金機構が示す「全国現物給与価額一覧表」を参考にして記入しましょう。
通貨と現物支給額は合算し、⑬「合計」欄にその月の合計額を記入します。正確に合算して記入することで、社会保険料の算出に必要なデータが整います。
総計額
⑭の「総計」欄には、算定対象月におけるすべての通貨と現物の合計額を記入します。算定対象月とは、支払基礎日数が17日以上の月を指します。
たとえば、5月の支払基礎日数が15日だった場合、その月は算定対象月に含まれません。そのため、4月と6月の報酬を合算して記入します。
参考:
日本年金機構|算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)
日本年金機構|健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 (記入例)
平均額
⑮の「平均額」欄には、総計額を算定対象月数で割った金額を記入しましょう。たとえば、算定対象月が2ヶ月(例:4月と6月)であれば、合計を2で割ります。
もし17日未満の月が2ヶ月あった場合は、残りの1ヶ月(17日以上の月)のみの報酬をもとに算出します。この場合、17日未満の月は計算に含めません。小数点以下は切り捨てて記入します。
最終的に記入した平均額をもとに、従業員の標準報酬月額が決定され、そのあと社会保険料の算出に使用される流れです。
正確な計算を行い、記入ミスを防ぎましょう。
参考:
日本年金機構|算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)
日本年金機構|健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 (記入例)
算定基礎届を提出しなかったらどうなる?
算定基礎届は、提出期限を守って提出しなければなりません。期限内に提出しないと、年金事務所から催告状が届く場合があるため、注意しましょう。
そのあとも提出しないままでいると、法律にもとづき、6ヶ月以下の懲役または50万円の罰金が科される可能性があります。長期間提出を怠ってしまうと、年金事務所が立ち入り調査を行い、事業所や従業員に不利益をもたらす恐れがあります。
もし未提出が発覚した際は、速やかに算定基礎届を提出しましょう。
月額変更届の記入方法
月額変更届の記入項目は、下記のとおりです。
| 記入項目 | 説明 |
|---|---|
| 被保険者情報 | 整理番号・氏名・生年月日 |
| 改定年月 | 給与変動後4ヶ月目を記入 |
| 従前の標準報酬月額 | 変更前の金額を記入 |
| 昇(降)給の内容 | 変更のあった月・増減の区分を記載 |
| 給与支給月 | 給与変動後の3ヶ月間を記載 |
| 給与計算の基礎日数 | 17日以上の支払いがあったことを証明 |
参考:日本年金機構|健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届(記入例)
たとえば4月に昇給し、給与が5月に支払われた場合、改定年月は8月となります。このタイミングで、月額変更届を提出し、適正な標準報酬月額の変更を行う必要があります。
随時改定が反映されるタイミング
従業員の給与が変動し、一定の要件を満たす場合は、随時改定によって標準報酬月額が変更されます。給与変動後、固定的賃金が支払われた月から起算して、4ヶ月目に変更されます。
社会保険料は、随時改定が反映された月の翌月に納付されるのが一般的です。しかし、給与が翌月払いの場合、実際に差し引かれるのは、変動後の給与が支払われた月を含めて5ヶ月目です。
企業の給与体系により、反映されるタイミングが異なるため、正確に把握しておきましょう。
月額変更届を提出しなかったらどうなる?
月額変更届を提出しない場合、厚生年金保険法には罰則が定められています。6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
しかし、提出には具体的な期限が定められていません。少し手続きが遅れても、すぐに提出すれば罰則が適用されることは少ないでしょう。
ただし、未提出のままでいると、年金事務所から指摘され、あらためて提出を求められる場合があります。企業のリスクを減らすためにも、給与の固定賃金変更があった際は速やかに手続きを行い、提出漏れを防ぎましょう。
算定基礎届と月額変更届を理解して適切に提出しよう
算定基礎届と月額変更届は、どちらも社会保険料の算定に必要な書類です。企業は、違いや提出方法を理解し、給与の変動に応じて適切に手続きを行いましょう。
どちらの届出も正確に記入し、適切に提出することが、社会保険料の適正な算出と企業の法令遵守につながります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
新卒で雇用保険被保険者証は受け取れる?発行条件や必要なタイミングを解説
新卒の入社手続きで「雇用保険被保険者証」という言葉を初めて聞く方も多いでしょう。雇用保険の加入を証明する大切な書類の1つで、転職時や教育給付金の申請手続きを行う際に、提出を求められ…
詳しくみる企業年金は3種類!厚生年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金の違いと特徴を解説
退職時または60歳以降に受け取ることができる給付に企業年金があります。企業年金は、3階建ての年金の3階部分(1階部分の「基礎年金」、2階部分の「被用者年金」)を担っている年金制度で…
詳しくみる社会保険の同日得喪手続き
「同日得喪」という言葉は、あまり聞きなれないと思いますが、「どうじつとくそう」と読みます。 漢字から連想される通り、社会保険の資格取得と資格喪失を「同日」に行う手続きです。 今回は…
詳しくみる【テンプレ付】育児休業とは?育児休暇との違い、取得可能な期間を解説
育児休業は、1歳未満の子どもを育てるために取得することができる休業です。育児・介護休業法に定められており、女性労働者だけではなく、男性労働者にも育児休業の取得が推奨されています。 …
詳しくみる厚生年金保険料の計算方法
所得税や雇用保険料ほか、給料からはさまざまな税金や保険料が天引きされていることと思います。 そのなかのひとつ、厚生年金保険料の計算方法をご存じですか? 保険料は、毎月の給料とボーナ…
詳しくみる厚生年金保険料が急に上がったのはなぜ?理由や確認方法を解説
厚生年金や健康保険などの社会保険料は、会社勤めや公務員の場合、給与から天引きされるのが一般的です。そのため、給与明細を見て保険料が上がったのを知り驚く方も多いでしょう。保険料が上が…
詳しくみる