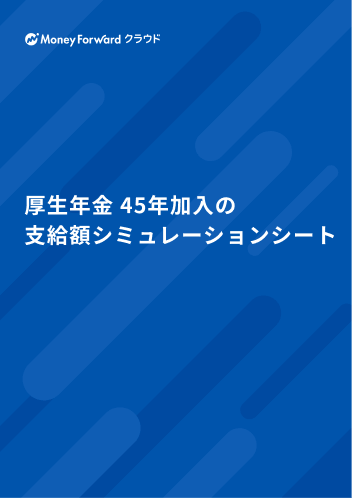- 更新日 : 2025年10月31日
厚生年金に45年加入により受給できる金額が増える?44年特例について
現行制度では、厚生年金は原則65歳以上で受給することができます。しかし、厚生年金制度の改正に伴う経過措置として、一部の被保険者は60歳から受給することが可能です。さらに、厚生年金に44年以上加入した被保険者は、長期加入者特例によって受給額が増額されます。この記事では、厚生年金における44年特例についてご紹介します。
目次
厚生年金とは?
厚生年金とは、会社員や公務員など企業や組織に雇用されている被用者が加入する公的年金です。同じく公的年金に分類される国民年金は、個人事業主や自営業者、学生や無職の方が加入します。
日本の年金制度は「2階建て構造」になっているため、厚生年金の加入者は同時に国民年金の被保険者です。国民年金の加入者を「第1号被保険者」、厚生年金の加入者を「第2号被保険者」、第2号被保険者に扶養されている配偶者を「第3号被保険者」といいます。
なお、日本は全国民が何らかの年金制度に加入する「国民皆年金制度」を敷いているため、20歳以上60歳未満の全国民は国民年金に加入しなければなりません。一方、被用者年金である厚生年金は、厚生年金適用事業所に勤めている70歳未満の方が加入します。例えば20歳未満で就職した場合、国民年金には未加入で厚生年金にのみ加入という状態になるため注意しましょう。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
|---|---|---|---|
| 主な加入者 |
|
|
|
| 加入する年金制度 | 国民年金 | 国民年金と厚生年金 | 国民年金 |
| 加入期間(原則) | 20歳以上60歳未満 | 厚生年金適用事業所に就職してから退職もしくは70歳に到達するまで | 20歳以上60歳未満 |
参考:た行 第1号被保険者|日本年金機構
参考:た行 第2号被保険者|日本年金機構
参考:た行 第3号被保険者|日本年金機構
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
厚生年金における44年特例(長期加入者特例)とは?
国民年金は20歳以上60歳未満の全国民が加入する公的年金制度です。満期は40年となります。一方、厚生年金は適用事業所に就職した段階で加入し、退職による脱退もしくは70歳で資格を喪失するまで保険料を納付しなければなりません。例えば、義務教育を終えた16歳で就職し60歳の定年まで働いた場合は、44年間保険料を納付することになります。44年以上厚生年金をかけた被保険者は「長期加入者の特例」いわゆる「44年特例」を受けることが可能です。
44年特定について紹介する前に、年金受給開始年齢についておさらいしましょう。現行制度では、原則65歳から年金を受給することが可能です。以前は60歳から受給可能でしたが、昭和60年の法律改正に伴い65歳に引き上げられました。その際、年金受給開始年齢を段階的に引き上げるために導入されたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。特別支給の老齢厚生年金とは65歳未満の被保険者が受給できる年金で、下記の要件を満たす必要があります。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること
なお、特別支給の老齢厚生年金は保険料納付時の収入に比例する「報酬比例部分」と被保険者期間によって決まる「定額部分」に分けられます。生年月日と性別に応じて、それぞれ受給開始年齢が異なるため気をつけましょう。

44年特例とは、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受け取っている被保険者が、定額部分の受給開始年齢到達前に退職などによって被保険者でなくなった場合、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れる制度です。44年特例を受けるためには下記の要件を満たす必要があります。
- 厚生年金の被保険者期間が44年以上
- 厚生年金の被保険者でなくなった
- 報酬比例部分の受給資格を満たしている
厚生年金を44年以上かけている場合でも、被用者として働いている間、すなわち厚生年金被保険者の間は44年特例を受けられないので気をつけましょう。
引用:特別支給の老齢厚生年金|日本年金機構
参考:44年以上厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者が、退職などで被保険者でなくなったとき|日本年金機構
44年特例の受給金額はいくら増える?計算式を紹介
44年特例で受け取れる年金は、特別支給の老齢厚生年金における定額部分と説明しました。それでは実際にいくら受給金額が増えるのか、計算式を交えて紹介します。まず、令和4年4月からの定額部分の計算式は下記のとおりです。
被保険者期間の月数は生年月日に応じて上限が決まっています。44年間厚生年金をかけていても528月が上限となるわけではないので気をつけましょう。
例えば、昭和21年4月2日以降に生まれた方は480月が上限となり、定額単価は1.0なので、定額部分は77万8,080円となります。これは、老齢基礎年金の満額とほぼ同額です。
なお、報酬比例部分には上限がないため、加入した被保険者期間に応じて年金額が計算されます。
44年特例の注意点
44年特例の概要、受給要件、受給金額について紹介しました。ここからは、加給年金との関係性や44年特例を受けるための手続きなどについて解説します。
加給年金額も受け取ることができる?
加給年金とは、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方に、老齢厚生年金の受給開始年齢到達時点で生計を維持している配偶者や子がいる場合に加算される年金です。加給年金には年齢制限があり、該当しなくなった場合は加算が終了します。加えて、離婚や死亡によって生計維持関係が解消された場合も加算が終了するので覚えておきましょう。加給年金額と年齢制限については下記のとおりです。
| 対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 223,800円(※) | 65歳未満の配偶者 |
| 1人目・2人目の子 | 各223,800円 | 18歳到達年度の末日までの子 (1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子) |
| 3人目以降の子 | 各74,600円 | 18歳到達年度の末日までの子 (1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子) |
※年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,100円から165,100円が特別加算されます。
加給年金の受給資格は、厚生年金を20年以上かけていた方が65歳到達した時点、または定額部分支給開始年齢に到達した時点と定められています。44年特例で定額部分を受給できる方も該当するため、加給年金額も上乗せ受給可能です。なお、加給年金額加算のためには届け出が必要なので、該当する方は忘れずに届け出しましょう。
44年特例を受けるためには手続きは必要?
44年特例を受けるための特別な手続きは不要です。退職などによって厚生年金を脱退する場合、勤務先を通して「被保険者資格喪失届」を日本年金機構に提出します。被保険者資格喪失届を受領した日本年金機構は44年特例に関する手続きも合わせて行うため、加入者自らが手続きする必要はありません。ただし、生計を維持している子や配偶者がおり加給年金を受け取るためには「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を提出しなければならないため気をつけましょう。
44年特例の対象者が死亡してしまったら?
年金受給の権利を有する方が亡くなった場合、年金を受給する権利を喪失します。これは、特別支給の老齢厚生年金ならびに44年特例の対象者であっても同様です。ただし、死亡した年金加入者と同一生計の遺族は、未支給年金や遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。
未支給年金は、年金を受け取る前に亡くなった場合や、年金を受け取る権利があったものの請求しないうちに亡くなった場合、遺族に支給される給付です。さらに、一定の条件を満たした場合は、遺族厚生年金も受給できます。なお、未支給年金を受け取る場合は「受給権者死亡届(報告書)」を、遺族厚生年金を受給する場合は「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」を日本年金機構に提出しなければなりません。日本年金機構にマイナンバーを登録している方は、原則として年金受給権者死亡届(報告書)の提出を省略できます。
参考:遺族に支払われる年金|日本年金機構
参考:年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構
制度の概要を理解し老後の人生設計を考えよう
厚生年金の「長期加入者の特例」いわゆる「44年特例」について紹介しました。44年特例とは、厚生年金を44年以上かけていた長期加入者が受けることができる特例です。被保険者期間が44年以上ある方は、退職等で厚生年金を脱退した場合、最高77万8,080円もの上乗せ給付を受けることができます。特別支給の老齢厚生年金として支給される報酬比例部分に加えて、老齢基礎年金とほぼ同額の定額部分を受け取ることができるため、該当者は65歳を待たずに同等水準の年金給付を受給することが可能です。当記事を参考に44年特例の概要を理解し、働き方など老後の人生設計を今一度検討してみましょう。
よくある質問
厚生年金の44年特例とはなんですか?
正式には「長期加入者の特例」といい、厚生年金を44年以上かけていた長期加入者が受けることができる年金の上乗せ受給が可能な特例です。詳しくはこちらをご覧ください。
44年特例により受給額はいくら増えますか?
44年特例によって支給される定額部分は被保険者期間の月数に応じて決まり、昭和21年4月2日以降に生まれた方の480月が上限で77万8,080円上乗せされます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
算定基礎届の電子申請のやり方は?いつからできる?GビズIDでの手続きも徹底解説
算定基礎届の電子申請とは、GビズIDとe-Govを利用することで、事業所のパソコンからオンラインで手続きを完結させる方法です。2020年4月から特定法人で義務化された背景もあり、算…
詳しくみる週20時間で社会保険加入になる?条件やシミュレーション、手順など解説
「パートのシフトを週20時間以内に抑えるべきか?」「社会保険料はいくらか?」 2024年10月の法改正で51人以上の企業まで適用が拡大され、2025年以降は全企業への導入も議論され…
詳しくみる雇用保険とは?加入条件と申請方法について
失業した際に支給される失業手当(基本手当)は、雇用保険制度に基づいて給付されるものです。雇用保険は、労働者の生活の安定や再就職の支援を目的とした公的保険制度であり、失業時だけでなく…
詳しくみる国保計算を基本から理解するための3つのポイント
職場で社会保険に加入していない人や生活保護を受給していない人であれば加入が義務付けられている国民健康保険(以下、国保)。 ここではこの国保の保険料計算(以下、国保計算)の基本と、保…
詳しくみる労災保険の保険料は全額事業主負担?計算方法や休業補償の負担割合も解説!
健康保険や厚生年金保険などの社会保険は、原則として労使折半という形式で、事業主と労働者がそれぞれ保険料を負担します。一方、労働者の業務災害や通勤災害による怪我や病気に対して給付を行…
詳しくみる社会保険料(国民年金保険料)控除証明書とは?発行日や使用ケース
国民年金に加入している方には、毎年10月下旬から11月上旬、または翌年の2月上旬の2回、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届きます。この証明書は確定申告や年末調整の際に必要な…
詳しくみる