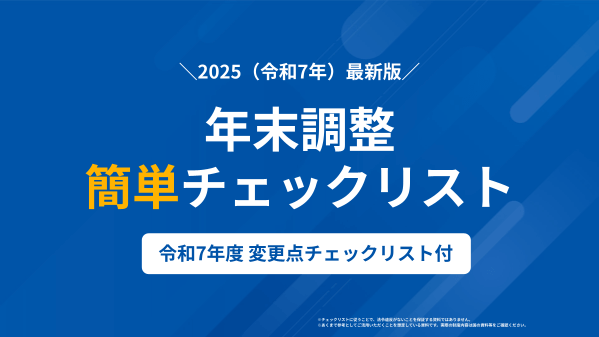- 更新日 : 2025年11月4日
【チェックリスト付】年末調整のダブルチェックとは?やり方やミスを防ぐ方法
年末調整の正確性を高めるには、担当者一人だけでなく、別の人による「ダブルチェック」がとても効果的です。このひと手間を加えることで、所得税の計算ミスや、後から税金を追加で支払うといったトラブルを未然に防げます。
人事や経理の担当者の方は、年末の忙しい時期に山のような書類を前に「扶養家族の申告が間違っていないか」「保険料の計算は合っているか」など、ヒューマンエラーへの不安を感じていないでしょうか。
この記事では、年末調整で起こりがちなミスを防ぐための、効果的なダブルチェックのやり方から、万が一間違えてしまったときの対処法まで、わかりやすく解説します。
目次
年末調整のダブルチェックはなぜ必要?
年末調整のダブルチェックは、計算ミスや申告漏れを防いで、正しい所得税額を計算するために欠かせない作業です。担当者一人の確認だけでは、どうしても見落としや「こうだろう」という思い込みによるヒューマンエラーにつながります。それが、後々の追徴課税や延滞税といったペナルティにつながってしまうかもしれません。
二人以上の目で確認することで、ぐっと客観性が増し、間違いを見つけやすくなります。これは、会社が法律を守り、税務調査のリスクを減らすだけでなく、従業員からの信頼を守ることにもつながる大切なひと手間なのです。
ダブルチェックで防げる代表的なミス
ダブルチェック体制をきちんと作っておけば、年末調整でよくある多くのミスを防ぐことができます。例えば、従業員から提出された申告書の記入漏れや添付書類の不足、担当者が給与システムへ入力する際の金額の打ち間違いなどです。
例えば、扶養控除申告書における扶養親族の所得要件の見落としや、保険料控除申告書に記載された金額と証明書の金額の相違などは、典型的なヒューマンエラーといえるでしょう。これらのミスは、担当者一人だけの確認では気づきにくい場合も少なくありません。
チェックを怠った場合のリスクとは
もしダブルチェックをせず、間違いに気づかないまま手続きを進めてしまうと、会社と従業員の双方にさまざまなリスクが生じます。
こうした事態を避けるためにも、手間を惜しまずにしっかりとしたチェック体制を作ることが、最終的には会社全体を守ることにつながります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
年末調整で従業員がやりがちな8つの間違い
年末調整で従業員の方々がやりがちな8つのミスをとりあげ、正しい対応方法についてまとめました。
年末調整業務をスムーズに完了させるための、従業員向けの配布資料としてもご活用いただけます。
扶養控除等申告書 取り扱いガイド
扶養控除等申告書は、毎月の源泉徴収事務や年末調整の計算をするうえで必要不可欠な書類です。
扶養控除等申告書の基礎知識や具体的な記入方法、よくあるトラブルと対処方法などをわかりやすくまとめたおすすめのガイドです。
年末調整業務を効率化するための5つのポイント
「毎年年末調整のシーズンは残業が多くなりがち…」、そんな人事労務担当者の方に向けて年末調整業務をスムーズに行うためのポイントをまとめました。
スケジュールや従業員向け資料を作成する際の参考にしてください。
年末調整のWeb化、業務効率化だけじゃない3つのメリット
年末調整のWeb化=業務効率化のイメージが強いかもしれませんが、実際には労務担当者にしかわからない「もやもや」を解消できるメリットがあります。
この資料ではWeb化により業務がどう変わり、何がラクになるのかを解説します。
年末調整で発生しやすい間違いの具体例
年末調整のミスは、特定の誰かの責任というより、複雑なルールや忙しいスケジュールの中で起こりがちです。特に間違いやすいポイントを、書類や作業ごとに見ていきましょう。
「扶養控除等(異動)申告書」の不備
扶養控除等(異動)申告書は、控除額を決定する基礎となるため、特に慎重な確認が必要です。
① 扶養親族の所得要件の勘違い
一番多い間違いが、扶養に入れる家族の所得要件です。特にパートなど収入のある配偶者を対象とする「配偶者控除」の収入上限が、2025年分の所得から103万円から123万円に変更となりました。つまり、配偶者の給与収入が123万円(年間所得58万円以下)までであれば、扶養者は配偶者控除を受けられ、配偶者本人にも原則として所得税はかからなくなります。
② 親や子供など、扶養親族の増減申告漏れ
年の途中で扶養親族の状況が変わったにもかかわらず、申告書に反映されていないケースです。
③ 年齢区分と控除額の確認漏れ
扶養控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無で変わります。
- 19歳~23歳未満の子供(特定扶養親族):
控除額は63万円です。生年月日をしっかり確認しましょう。 - 70歳以上の親(老人扶養親族):
- 同居している場合:控除額 58万円
- 同居していない場合:控除額 48万円
同居の有無で控除額が10万円も変わるため、住所の確認も重要です。
④ 夫婦で同じ子供を扶養に入れてしまう
共働きの夫婦が、お互いに同じ子供を扶養親族として申告してしまうケースです。扶養に入れるのは、どちらか一人だけです。
参照:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
参照:各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)|国税庁
「保険料控除申告書」や「住宅ローン控除」の確認漏れ
証明書の添付が必要な手続きは、書類の現物と申告書の数字を見比べる地道な作業が欠かせません。
- 保険料の証明書と申告額が違う
生命保険や地震保険の控除には、保険会社から送られてくる「控除証明書」が必要です。申告書に書かれた金額と証明書の金額が一致しているか、必ず確認しましょう。 - 住宅ローン控除の計算ミス
2年目以降の住宅ローン控除は年末調整でできますが、金融機関の「年末残高等証明書」が必要です。申告された控除額が、証明書の残高にもとづいて正しく計算されているか、会社側でも確かめておくと安心です。
給与システムへの入力・計算ミス
申告書の内容が完璧でも、それを処理する会社側でミスが起こることもあります。
- 単純な打ち間違い(転記ミス)
申告書の数字を給与システムへ手入力する際に起こるミスです。扶養家族の人数や保険料の金額など、一桁間違うだけで税額は大きく変わってしまいます。 - 中途入社した人の前職分を合算し忘れる
年の途中で入社した社員がいる場合、前の会社の源泉徴収票をもらい、その給与額などを合算して年末調整をします。この作業を忘れると、正しい税額計算ができません。
紙やExcelで行うダブルチェックの進め方
紙の申告書やExcelシートを使って年末調整を行う場合、人の目に頼る作業が多くなるため、手順を明確にルール化することがミスの防止につながります。
STEP1:チェックリストの作成
まず、誰がチェックしても同じ品質を保てるように、標準化されたチェックリストを作成します。これまでのミス事例などを参考に、自社の状況に合わせて具体的な項目に落とし込むのがポイントです。
- 従業員情報:
氏名、住所に変更はないか。マイナンバーは正しく登録されているか。 - 扶養控除申告書:
扶養親族の所得要件は満たしているか。重複扶養はないか。年齢区分(19歳~23歳未満など)は正しいか。 - 保険料控除申告書:
証明書はすべて添付されているか。申告額と証明額は一致しているか。 - 住宅ローン控除:
残高証明書は添付されているか。 - 転記・計算:
申告書の各控除額がExcelシートへ正しく転記されているか。計算式は正しいか。
STEP2:一次チェック(担当者自身による確認)
次に、年末調整の主担当者が、作成したチェックリストに沿って一通りの確認作業を行います。申告書と証明書を一つひとつ突き合わせ、記入漏れや計算ミス、添付書類の不備などを洗い出します。ここで見つかった不備は、修正したり従業員へ差し戻して確認を依頼したりします。
STEP3:二次チェック(別の担当者による確認)
主担当者とは別の担当者が、同じチェックリストを使って再度すべての項目を確認します。一次チェックで見落とした点や、担当者の思い込みによる誤りを、異なる視点から発見することがダブルチェックの目的です。より客観的な視点で確認しましょう。
STEP4:修正・フィードバック
チェックの過程でミスが見つかった場合、それを単に修正して終わりにするのではなく、「なぜこのミスが起きたのか」を分析し、来年に活かすことが重要です。 例えば、特定の項目で従業員の記入ミスが多発しているなら、翌年は申告書の配布時にわかりやすい記入例を添付するなどの改善につなげましょう。
システムを活用した年末調整のダブルチェックの進め方
年末調整のクラウドサービスなどを活用すると、人とシステムの役割分担により、チェック作業の精度と効率を向上させることができます。手作業で起こりがちな転記ミスや計算ミスを、根本から防げるのが最大のメリットです。
STEP1:従業員による情報入力と証明書のアップロード
まず、従業員本人がスマートフォンやPCから、システムに直接情報を入力します。保険料の控除証明書なども、紙で回収する代わりに写真データをアップロードしてもらう形が一般的です。この時点で、紙からシステムへの転記作業そのものが不要になります。
STEP2:システムによる自動一次チェック
従業員が入力した情報は、システムが自動で一次チェックを行います。人の目では見落としがちな矛盾点やルール違反を検知します。
- 上限額チェック: 入力された保険料の控除額が、法律上の上限を超えている場合に警告を出す。
- 整合性チェック: 扶養親族の生年月日から、控除の種類(特定扶養など)を自動で判定し、間違いがあれば知らせる。
- 添付漏れチェック: 保険料の金額が入力されているのに、証明書のデータがアップロードされていない場合にエラーを出す。
- 前年比較チェック: 前年まで扶養に入っていた親族が申告されていないなど、大きな変更点があった場合に注意を促す。
STEP3:担当者による二次チェック
システムによる一次チェックが終わった後、担当者が内容を確認します。このとき、ゼロからすべてを確認する必要はありません。システムがアラートを出した箇所や、特に注意が必要な従業員に絞って重点的に確認すればよいため、作業時間を大幅に短縮できます。
STEP4:システム上での修正依頼と確定
もし不備が見つかった場合は、システム上で従業員に直接差し戻し、修正を依頼します。修正が完了し、担当者が最終的な承認を行えば、そのデータをもとに年税額が自動で計算され、年末調整の確認作業が完了します。
ダブルチェックとトリプルチェックの違いは?
チェック体制には、二人で確認するダブルチェックの他に、三人で確認するトリプルチェックもあります。それぞれの特徴を知り、自社に合った方法を選びましょう。
ダブルチェックとは?
ダブルチェックは、一人の作業者(一次チェック者)が行った業務内容を、別の担当者(二次チェック者)が確認する手法です。二人体制で確認することで、一人作業に比べてミスの発見率が飛躍的に高まります。
- 少ない人数でできるので、コストを抑えやすい。
- 一人より客観的で、品質が上がる。
- 二次チェック者も見落としの可能性は残る。
- お互いを信頼しすぎると、確認が甘くなることも。
トリプルチェックとは?
トリプルチェックは、ダブルチェックにさらにもう1人、3人目の確認者(三次チェック者)を加える手法です。特に、ミスが許されない極めて重要な業務や、巨額の金銭が関わる処理などで採用されます。
- 多角的な視点で確認するため、ミスの見逃しを極限まで減らせる。
- より高い正確性と信頼性が求められる業務に対応できる。
- 3人分の工数がかかるため、時間と人件費のコストが増大する。
- 業務のスピードが低下する可能性がある。
年末調整業務において、全ての従業員に対してトリプルチェックを行うのは非効率的かもしれませんが、例えば役員や、住宅ローン控除・扶養親族の変動など、計算が複雑な従業員に限定してトリプルチェックを実施するといった、メリハリのある運用は有効です。
年末調整の間違いに気づいたらどうなる?
どれだけ入念にチェックしても、後から間違いが発覚することはありえます。気づいたタイミングによって対処法が異なりますので、適切な手続きを取りましょう。
1月末(書類提出前)までに気づいた場合
会社が税務署などに書類を提出する前であれば、社内で対応できます。この期間内であれば、会社側で年末調整の再計算が可能です。正しい税額を算出し直し、給与システム上のデータを修正します。1月の給与支給時に、前年12月分の差額を精算(追加徴収または還付)し、従業員には修正後の正しい源泉徴収票を発行します。
源泉徴収票を渡した後~確定申告期間中に気づいた場合
従業員に源泉徴収票を渡してしまった後は、会社で年末調整をやり直すことはできません。この場合、会社は修正した正しい源泉徴収票を再発行し、従業員に渡します。そして、従業員本人が確定申告をして、税金の調整をする必要があります。
会社の担当者は、従業員がスムーズに確定申告できるよう、サポートすることが大切です。
確定申告後に気づいた場合(修正申告・更正の請求)
確定申告の期間(通常は翌年3月15日まで)も過ぎてから間違いに気づいた場合も、従業員本人が手続きをします。
会社のミスが原因で過年度に遡る場合
もし、会社の計算ミスなどが原因で、過去の年度(過年度)の年末調整に誤りがあったことが判明した場合、会社は速やかに対応しなくてはなりません。
まず、影響を受ける従業員に事情を説明し、謝罪します。そのうえで、正しい源泉徴収票を再発行し、不足額を従業員から徴収のうえ納付する必要があります。現年度のように従業員の確定申告では対応できないため注意が必要です。。また、税務署から指摘を受ける前に、会社側から自主的に修正内容を報告することが、信頼を損なわないための重要な対応といえるでしょう。
人とシステムのダブルチェック年末調整のミスを防ぐ
年末調整のミスを防ぐには、チェックリストを活用した人の目と、システムの自動チェックを組み合わせた仕組みづくりがよいでしょう。
この記事で解説した扶養控除の変更点などのポイントをおさえ、システムで単純な計算ミスをなくすことで、担当者はより重要な確認作業に集中できます。
自社に合ったダブルチェック体制の構築や見直しを行い、年末調整のミスを防ぎながら効率化を行いましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
年末調整における扶養控除とは?扶養親族の条件や控除額、必要な手続きまで解説!
毎年の年末調整時に、「扶養する」「扶養控除」という言葉をよく耳にしませんか。「扶養」には「養う」という意味があります。例えば、ある会社員に大学生の子どもがいて、その子どもの生活費を…
詳しくみる中途採用された場合の年末調整を解説!必要な書類など
年の途中で中途採用により会社が変わった場合、転職した先で年末調整を行います。その際、前職を退職したときに受け取った源泉徴収票が必要です。ここでは、中途採用された人が年末調整を受ける…
詳しくみる源泉徴収票に印鑑は必要?社印やシャチハタなどの決まりはある?
企業が給与の支払いをした者に対して発行する「源泉徴収票」は、押印がないのが一般的です。社印がなくても法的には問題はありません。ただし、銀行への住宅ローン申請では社印のある源泉徴収票…
詳しくみる年末調整でのふるさと納税の取扱い
ふるさと納税は自治体への寄付金となります。寄付金は年末調整では処理できませんので、控除を行うためには会社のやってくれる年末調整の他に自分で確定申告をすることが必要です。 ここではふ…
詳しくみる【一覧】年末調整の書類保管期間は何年?紙・電子の違い、紛失リスクを解説
年末調整で扱う申告書や源泉徴収簿といった書類の保管期間は、所得税法により原則7年間と定められています。そのため、税額計算の根拠となるこれらの法定調書は、法律にのっとり適切に管理しな…
詳しくみる学資保険は生命保険料控除の対象になる?年末調整における書類の書き方
年末調整では、保険料控除などの所得控除を受けて節税するのが一般的です。一方、将来の教育費用に備えて学資保険を契約している方も多いことでしょう。では、学資保険は控除対象として税控除を…
詳しくみる