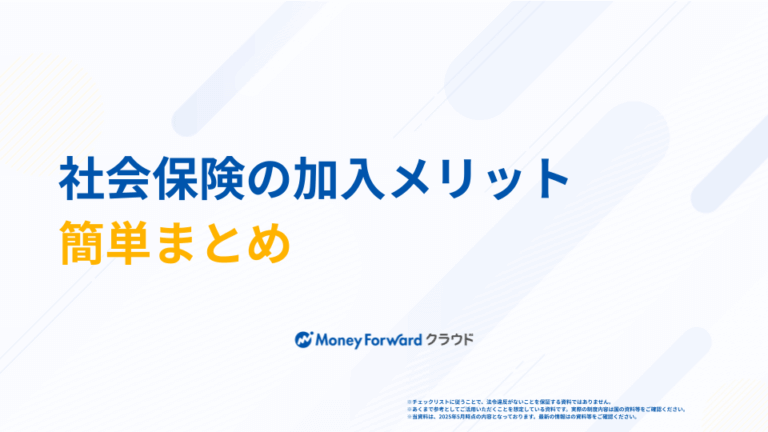- 更新日 : 2025年8月26日
社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入におけるメリット
社会保険に加入していることで保障される内容やメリットについての説明をします。
目次
社会保険の加入義務
社会保険への加入義務がある事業所は、以下のとおりです。
強制適用事業所
事業所が次のいずれかに該当する場合は、社会保険の強制適用事業所になります。
1.一定の事業を行い、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所
この「5人」とは、適用除外規定により被保険者にならない従業員も、常時使用される場合にはカウントされます。
※一定の事業:製造業、鉱業、電気ガス業、運送業、貨物積卸し業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介斡旋業、集金案内広告業、清掃業、土木建築業、教育研究調査業、医療事業、通信報道業、社会福祉事業(以上16事業)
2.常時従業員を使用する国・地方公共団体又は法人の事業所
(従業員が事業主1名だけの場合も含む)
3.船員法の船員として、船舶所有者の使用者が乗り組む船舶
任意適用事業所
強制適用事業所に該当しない事業所の場合、事業主が厚生労働大臣の認可を受けることで、適用事業所となることができます。この場合は、事業所の使用者は従業員(被保険者に該当する者のみ)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請する必要があります。
一括適用事業所
2つ以上の適用事業所の事業主が同じ場合は、厚生労働大臣の承認を受けることで2つ以上の事業所を1つの適用事業所扱いにすることができ、これを一括適用事業所といいます。
この手続きにより、本来は事業所単位で行う社会保険の諸手続きを、一括で処理することができます。
適用除外
以下のいずれかに該当する場合は、適用事業所であっても社会保険の被保険者手続きをすることができません。
1.船員保険被保険者(健康保険適用除外)
2.後期高齢者医療の被保険者
3.国民健康保険組合の事業所に使用される者(健康保険適用除外)
4.日々雇い入れられる人
ただし1ヶ月を超えて継続雇用されることが決定した場合は、1ヶ月を超えた日から被保険者となります。
5.2ヶ月以内の期間を定めて使用される人で雇われる労働者
ただし、所定の期間を超えて引き続き使用される場合は、所定の期間を超えた日から被保険者扱いとなります。。
6.4ヶ月以内の期間で雇われる季節的業務の労働者
ただし、雇用初日から換算して4ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者扱いとなります。
7.臨時的事業で雇われる労働者
ただし、継続して6ヶ月を超えて使用される場合は、当初から被保険者扱いとなります。
8.所在地が一定でない事業所に使用される人
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
入社や退職に伴う社会保険の手続きは多岐にわたり、ミスが許されません。特に厚生年金や健康保険は従業員の将来の給付や医療に直結するため、正確な処理が求められます。
手続きの不備でトラブルになる前に、本資料で社会保険・労働保険の正しい手順や必要書類を確認しておきませんか?
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険加入条件 簡単図解 ミニブック
パートやアルバイトの社会保険加入条件を、最新の法令に基づいて正しく判断できていますか?要件の確認漏れは、未加入によるトラブルや遡及徴収のリスクにつながりかねません。
本資料では、複雑な加入条件を視覚的にわかりやすく図解しています。自社の現状チェックや従業員への説明にご活用ください。
社会保険の健康保険加入におけるメリット
健康保険へ加入した場合のメリットは以下のとおりです。
1.健康保険料の半額は会社負担である
国民健康保険の場合は、全額自己負担であるため個人負担が少ないというメリットがあります。
2.生活保障のための傷病手当金、出産手当金制度がある
国民健康保険の場合は上記の手当の支給はありません。
3.扶養制度があるため、世帯における保険料額を抑えることができる
国民健康保険では扶養という概念がないため、家族全員が被保険者として加入する必要があります。
厚生年金加入におけるメリット(国民年金のみの場合は年金が少額となり、配偶者も保険料の納付が必要)
厚生年金へ加入した場合のメリットは以下のとおりです。
1.扶養制度があるため、世帯において保険料額を抑えることができる
夫婦がともに国民年金のみに加入した場合は、それぞれ保険料を支払う必要がありますが、夫が厚生年金、妻がその扶養に入っている場合は、夫は厚生年金の第2号被保険者、妻は国民年金の第3号被保険者となり、妻の保険料額は0円となります。
2.老齢年金額が上乗せされる
老齢厚生年金は、国民年金の老齢基礎年金に上乗して支給されるので、国民年金のみの加入者に比べ給付額が増えます。
3.障害年金の等級数が多い
国民年金における障害基礎年金の対象は、障害等級1・2級のみですが、障害厚生年金の場合は、3級の場合に一時金が支給されます。
4.遺族年金の支給対象が広く、手厚い保障制度が設けられている
国民年金における遺族基礎年金は、要件を満たす配偶者もしくは子のみに支給されますが、遺族厚生年金は要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母が受け取ることができます。
また、子のない配偶者は遺族基礎年金の受給はできませんが、厚生年金に加入し、一定の要件を満たすと遺族基礎年金も併せて受けることができます。
このように、厚生年金は国民年金に比べ補償の範囲が広いのがメリットです。
まとめ
社会保険に加入していることで、扶養家族がいる場合には世帯での保険料額を抑えることができ、さらには傷病手当金や出産手当金などが支給されるといったメリットがあります。
社会保険は報酬に比例して保険料も高くなりますが、加入して健康保険料や厚生年金保険料を支払っておけば、いざという時により高い保障を受けられるといったメリットがあります。
ただし、加入すべき期間に加入せず、保険料の支払期間が短くなった場合は、将来の年金給付額も減額されるので注意が必要です。
関連記事:
社会保険の厚生年金とは
健康保険の傷病手当金とは
社会保険の出産育児一時金とは
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
年金手帳とは?廃止済み! 厚生年金と国民年金で変わること
2022年3月まで、厚生年金や国民年金に加入すると「年金手帳」が交付されていました。 厚生年金手帳・国民年金手帳のような区別はなく、どちらも共通の手帳です。年金関連情報の管理に必ず…
詳しくみる介護保険被保険者証とはいつ使う?申請手続きや有効期限について解説
介護保険被保険者証とは、介護保険の被保険者資格を証明するものです。65歳以上の第1号被保険者には全員に送付されますが、40歳以上65歳未満の第2号被保険者には、一定の条件のもとで発…
詳しくみる引越し時のマイナ保険証の住所変更はどうする?手続きの流れや必要書類を解説
マイナ保険証とは、「マイナンバーカードの健康保険証利用」の略称です。マイナンバーカードを事前に登録することで、健康保険証として病院受付で利用できます。 政府はマイナ保険証への移行を…
詳しくみる社会保険料の負担割合とは?計算方法や注意点を解説!
給与から控除する健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの保険料は、従業員が全額自己負担するのではなく、労使双方が負担して納付します。負担割合は、社会保険の種類や業種によって異なります…
詳しくみる介護保険サービスを受けるための手続き
介護保険は、要介護状態になった場合に介護サービスを受けることができる制度ですが、被保険者になる年齢は第1号被保険者と第2号被保険者では異なります。 今回は、介護保険サービスを受ける…
詳しくみる社会保険の加入義務とは?対象者の条件やパート・アルバイトの適用範囲拡大についても解説!
社会保険は、けがや病気、出産、老後、障害、死亡といった生活に支障をきたすさまざまなリスクに備え、生活の安定を図ることを目的とした公的な保険制度です。ただし、その仕組みは複雑であり、…
詳しくみる