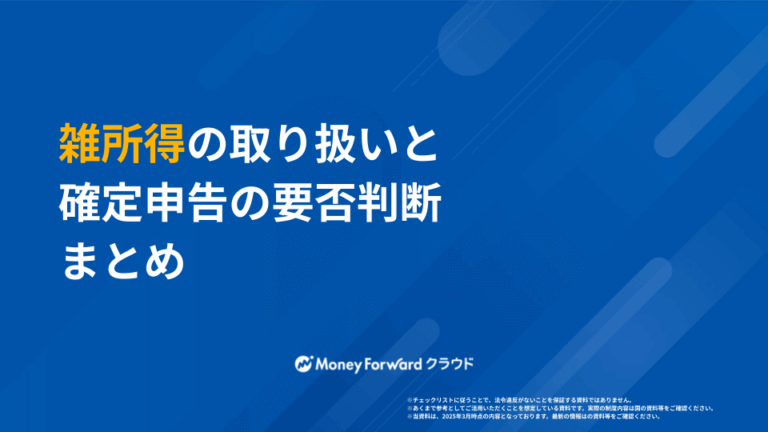- 更新日 : 2025年11月6日
年末調整で雑所得は処理できるか?
給与以外に雑所得がある場合、年末調整で処理することはできるのでしょうか。
年末調整とは、基本的には会社で支払われる給与をもとに、生命保険料など必要経費を控除する計算を、会社が代わりに行ってくれるものです。そのため、会社の給与以外の雑所得は年末調整での処理はできません。
今回は雑所得の処理について解説します。
雑所得とは
まず所得には、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得がありますが、これ以外の所得はすべて雑所得になります。
つまり、雑所得は、所得の性質がよくわからない所得を全て含めているものになります。具体例としては、公的年金での受取やアフィリエイトからの収入などがあります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
年末調整で従業員がやりがちな8つの間違い
年末調整で従業員の方々がやりがちな8つのミスをとりあげ、正しい対応方法についてまとめました。
年末調整業務をスムーズに完了させるための、従業員向けの配布資料としてもご活用いただけます。
扶養控除等申告書 取り扱いガイド
扶養控除等申告書は、毎月の源泉徴収事務や年末調整の計算をするうえで必要不可欠な書類です。
扶養控除等申告書の基礎知識や具体的な記入方法、よくあるトラブルと対処方法などをわかりやすくまとめたおすすめのガイドです。
年末調整業務を効率化するための5つのポイント
「毎年年末調整のシーズンは残業が多くなりがち…」、そんな人事労務担当者の方に向けて年末調整業務をスムーズに行うためのポイントをまとめました。
スケジュールや従業員向け資料を作成する際の参考にしてください。
年末調整のWeb化、業務効率化だけじゃない3つのメリット
年末調整のWeb化=業務効率化のイメージが強いかもしれませんが、実際には労務担当者にしかわからない「もやもや」を解消できるメリットがあります。
この資料ではWeb化により業務がどう変わり、何がラクになるのかを解説します。
年末調整と雑所得
年末調整は、会社員等が自ら確定申告しなくてもいいように、会社で定型的な所得控除をしてもらえる便利な制度です。その趣旨から、雑所得のような定型的でない所得については年末調整で処理することはできません。
確定申告と雑所得
雑所得は年末調整では処理できないことから、原則として確定申告することになります。ただし、雑所得が20万円以下の場合には確定申告は不要になります。
ここで注意が必要なのは、サラリーマンでも医療費控除を受ける場合や会社からの給与以外に所得があるなど、確定申告をしなけなければいけないなら、雑所得が仮に20万円以内であったとしても確定申告で雑所得について申告をしなければいけません。20万円以内について確定申告を不要としているのは、少額の所得について確定申告を求めると納税者の負担が大きいからです。
ほかの理由で確定申告をするのであれば、原則どおり確定申告が必要になるということです。
したがって、生命保険料控除を年末調整で申告するのを忘れたので、確定申告するような場合にも、雑所得があれば申告しなければなりません。
住民税の申告と雑所得
所得税では、給与とは別の所得が20万円までであれば、確定申告は不要ですが、住民税にはそのような規定がないため、給与所得と合わせて住民税の申告が必要です。
雑所得の計算方法
(1)公的年金を受給している場合
「公的年金受給額 − 公的年金等控除額」により計算されますが、以下の速算表により簡単に計算されます。
例えば、70歳で400万円年金を受け取ると、「400万円 × 75% − 37万5,000円 =262万5,000円」になります。
■速算表
【65歳未満】
| 公的年金等の収入金額 | 掛率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 700,001 円から 1,299,999 円まで | 1 | 70 万円 |
| 1,300,000 円から 4,099,999 円まで | 0.75 | 37 万 5,000 円 |
| 4,100,000 円から 7,699,999 円まで | 0.85 | 78 万 5,000 円 |
| 7,700,000 円以上 | 0.95 | 155 万 5,000 円 |
【65歳以上】
| 公的年金等の収入金額 | 掛率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,200,001 円から 3,299,999 円まで | 1 | 120 万円 |
| 3,300,000 円から 4,099,999 円まで | 0.75 | 37 万 5,000 円 |
| 4,100,000 円から 7,699,999 円まで | 0.85 | 78 万 5,000 円 |
| 7,700,000 円以上 | 0.95 | 155 万 5,000 円 |
(2)公的年金以外の雑所得がある場合
「総収入金額 − 必要経費」により計算されます。例えば、アフィリエイトで収入が50万円あり、通信費やパソコン購入費などの必要経費が25万円あったとすれば、「50万円 − 25万円 = 25万円」が所得になります。
(3)特例措置
雑所得は、他の所得と合算される総合課税になります。しかし、先物取引、オプション取引、外国為替証拠金取引(FX)などの収益は、先物取引に係る雑所得等の特例の対象になっており、総合課税ではなく申告分離課税になっています。
申告分離課税というのは、ほかの所得と合算せずに、当該所得に税率を掛けて税額を計算する方法です。税率は、所得税が15%、地方税が5%になっています。
なお、店頭取引と市場取引との間の損益通算は可能なので、複数の金融取引がある場合には、チェックしてみるとよいでしょう。また、損益通算をした結果がマイナスとなれば、3年間の繰越控除が認められているので、次年度以降収益が発生した場合には、繰り越した損失を収益から控除することができます。
まとめ
以上、雑所得について解説してきました。最近は、ネットで収益を得ている人も増えてきているので、税務当局も目を光らせているようです。
年末調整では雑所得は申告できませんので、確定申告の時期になったら、1年を振り返り、申告すべき収益を得ていないかきちっとチェックし、申告漏れがないよう注意しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
扶養控除とは?対象となる要件や控除額、メリット・デメリットを解説
扶養控除(ふようこうじょ)とは、納税者に養っている親族がいる場合に、所得税や住民税の負担を軽減できる「所得控除」の制度です。 企業の人事労務担当者にとって、扶養控除は年末調整や入社…
詳しくみる【一覧】年末調整の必要書類を回収するには?原本や紛失時の対応も解説
年末調整の書類回収を円滑に進めるには、対象書類と提出期限を従業員へ明確に周知し、計画的に進めることが求められます。そのため、原本が必要な書類とコピーでも良い書類の区別、紛失時の再発…
詳しくみる年末調整で必要な控除証明書とは?発行方法も解説
年末調整は、会社が従業員に支払う毎月の給与から源泉徴収されている額を、年末に精算して過不足を調整する手続きです。手続きをするのは給与所得を支払った会社ですが、従業員自身が記載して会…
詳しくみる続柄の書き方は大丈夫?記載方法の基本をチェックしよう
公的な書類を記入する際、「続柄」の欄を記入することがあります。しかし、誰を基準に書くのかは書類によって異なるため、書き方に迷うこともあるでしょう。 ここでは、住民票の申請、年末調整…
詳しくみる年末調整の書類はボールペンで書く?特定の色や鉛筆ではダメな理由を解説!
年末調整の書類を記入する際、鉛筆でいいのかボールペンを使用するべきか迷う方がいるでしょう。正しくは、ボールペンで記載します。さらに間違いを修正する場合は修正テープではなく、国税庁の…
詳しくみる住宅ローン控除は定額減税に影響がある?税額がすべて控除された場合
住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が所得税等から控除される制度です。定額減税も、年末調整時に年間所得税額との精算を⾏うことは住宅ローン控除と同様です。本記事では…
詳しくみる