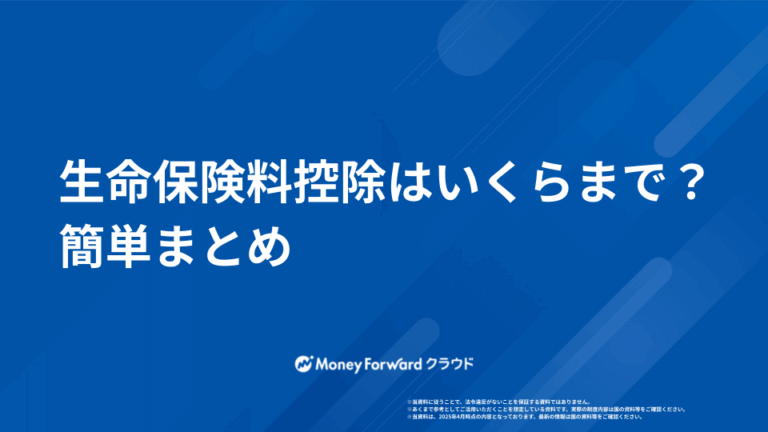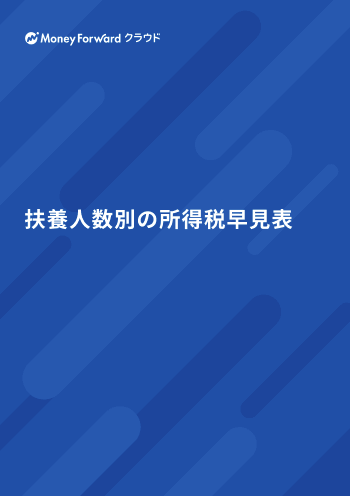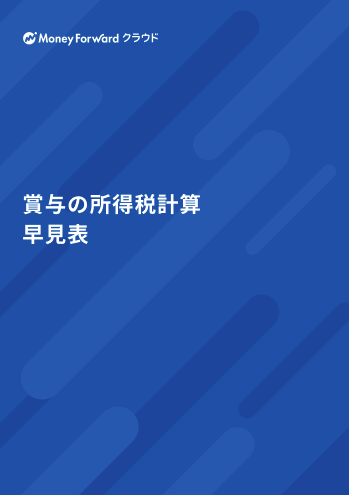- 更新日 : 2025年11月5日
【早見表】生命保険料控除はいくらまで書く?新旧制度の違いや注意点を紹介
生命保険料控除とは、年末調整や確定申告の際に、その年の税額を計算するにあたり、生命保険料を差し引いて計算する仕組みです。生命保険料控除の上限金額は、旧制度は所得税10万円、住民税7万円で、新制度は所得税12万円、住民税7万円と決まっています。上限金額を超えた分は控除されません。
この記事では、効率的かつ正しく生命保険料控除を行うための、基本概念や区分、上限金額や計算方法を解説します。
目次
生命保険料控除とは何か
生命保険料控除とは、所得控除のひとつであり、所得から一定の金額を差し引き、課税対象額としない仕組みです。1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料を、所得から差し引きます。生命保険料控除ができる保険には、生命保険、介護医療保険、個人年金保険の大きく3つの種類があります。
一般生命保険料控除
一般生命保険は、死亡やそのほか一定の事由に起因して、一定額の保険金が支払われる保険です。たとえば、死亡や高度障害に備える終身保険や、教育資金を準備するための学資保険が該当します。また、被保険者が死亡や高度障害状態になったとき、毎月一定額を一定期間受け取れる収入保障保険も一般生命保険です。ただし、保険期間が5年未満の貯蓄保険や、貯蓄共済は対象外です。自身の保険がどういった内容になっているか、あらためて確認しましょう。
生命保険料控除の対象となる生命保険の要件は次のとおりです。
|
介護医療保険料控除
介護医療保険は病気やケガなどに保険金が支払われる保険です。病気やケガの際に医療費を一定金額保障する医療保険や、ガンと診断されたら保障がおりるガン保険が代表的な種類です。また介護保険や就業不能保障特約も介護医療保険に該当します。一般生命保険料控除と同様に、保険期間が5年未満の貯蓄保険や、貯蓄共済は対象外となる点に注意が必要です。
介護保険料控除の対象となる介護保険の要件は次のとおりです。
|
個人年金保険料控除
個人年金保険は、契約時に決めた年齢まで保険料を払い込み、そのかわりに一定期間にわたり年金を受け取れる貯蓄型の保険です。老後資金が公的年金では足りなくなるリスクを、補う目的があります。
個人年金保険料控除を生命保険料控除として申請するには、以下の通り満たさなくてはいけない条件があり、該当するか確認して進めましょう。
|
なお、旧個人年金保険料については生命保険料控除の対象となる保険契約であって、退職年金を除く年金を給付する定めのあるもののうち、新個人年金保険料の要件を満たすものが対象となる点にも注意が必要です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
人事・労務関連の法改正まとめ 2026年版
所得税などの実務と並行して確認しておきたいのが、今後の労働法制の動きです。特に議論が進む労働基準法の改正は、企業の労務管理を大きく変える可能性があります。
最新の法改正情報と実務対応をまとめた本資料で、いつ、何が変わるのかを今のうちに把握しておきましょう。
扶養人数別の所得税早見表
所得税額は給与額や扶養親族の人数によって細かく変動します。毎月の給与計算で、正しい税額を算出できているか不安になることはありませんか?
計算ミスは給与の修正対応など無駄な業務を生んでしまいます。給与額と扶養人数を照らし合わせるだけで税額がわかる本資料を、計算時の確認用としてお使いください。
賞与の所得税計算早見表
年数回しかない賞与計算は、毎月の給与計算に比べて手続きを間違いやすい業務です。特に所得税は前月の給与額を基準にするなど特殊な算出が必要なため、計算ミスが起こりかねません。
複雑な計算や表の確認作業を効率化できる本資料で、ミスのない正確な賞与計算を行いましょう。検算用としても便利です。
生命保険料控除の旧制度と新制度の違い
生命保険料控除制度は、平成22年に税制改正されました。そのため、2011年12月31日以前に締結した保険契約は旧制度とし、2012年1月1日以降に締結した保険契約は新制度として扱います。ただし、契約日が2011年12月31日以前の契約でも、2012年1月1日以降に、更新や特約途中付加などで契約内容が更新されたものは、以後の保険料が新制度の適用です。
旧制度と新制度では控除区分と控除できる限度金額が異なります。それぞれの違いを、以下に解説していきます。
控除区分が異なる
2012年から生命保険料控除制度が改正された際に、新制度では介護医療保険料控除が新設されたため、控除区分が異なります。
| 旧制度 〜2011年12月31日 | 新制度 2012年1月1日〜 | |
|---|---|---|
| 控除区分 | 生命保険料控除 個人年金保険料控除 | 生命保険料控除 介護医療保険料控除 個人年金保険料控除 |
旧制度は、2011年12月31日までに締結された契約が対象です。ただし、主契約や特約更新を行っていたり、各控除区分に該当する特約中途付加を行っていたりする場合は、新制度の税区分の扱いです。
新制度では、介護医療保険料控除が新たに追加されました。これは、2012年1月1日以降に締結された契約が対象です。
適用限度額が異なる
旧制度と新制度では、生命保険料控除の限度額と計算方法が異なります。旧制度は所得税10万円、住民税7万円の控除だったのに対し、新制度は所得税12万円、住民税7万円に変更されています。
| 旧制度 | 新制度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | |
| 一般生命保険料控除 | 50,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 28,000円 |
| 介護医療保険料控除 | ― | ― | 40,000円 | 28,000円 |
| 個人年金保険料控除 | 50,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 28,000円 |
| 合計 | 100,000円 | 70,000円 | 120,000円 | 70,000円※ |
※新制度の住民税の所得控除限度額は、各28,000円ですが、合計金額は70,000円が限度額です。
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、新旧の制度にまたがる契約がある方は、それぞれの制度で金額を計算します。各控除の適用限度額は、所得税で40,000円、住民税で28,000円です。新旧制度あわせて制度全体の適用額は、所得税で120,000円、住民税で70,000円になります。
参考:新制度での控除額はどうなるの?(公営財団法人 生命保険文化センター)
所得税の計算方法
所得税の計算方法は、以下の表に当てはめることで計算ができます。
【新制度の所得税の生命保険料控除】
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
【旧制度の所得税の生命保険料控除】
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
たとえば、新制度の生命保険料控除の対象に該当する保険料を年間50,000円支払った場合、控除額は以下の金額になります。
住民税の計算方法
住民税の生命保険料控除額を計算する場合、以下の表に当てはめて計算ができます。
【新制度の住民税の生命保険料控除】
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
| 32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
【旧制度の所得税の生命保険料控除】
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等✕1/2+7,500円 |
| 40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等✕1/4+17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000円 |
たとえば、新制度の生命保険料控除の対象に該当する保険料を年間50,000円支払った場合、住民税の控除額は以下の金額になります。
生命保険料控除の注意点
生命保険料控除を行う際に注意すべき点について、以下より解説します。
生命保険料控除の対象外になる保険もある
生命保険料控除は、すべての生命保険に適用されるわけではありません。たとえば、保険期間が5年未満の貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、財形貯蓄保険や、財形住宅貯蓄積立保険、団体信用生命保険なども対象外です。対象となる保険契約については国税庁のホームページに要件が掲載されていますので、確認して処理を進めましょう。
転職をしたら処理は転職先で行う
年度の途中で転職をした場合、年末調整は新しい勤務先で行います。新しい勤務先で年末調整を行う際は、転職する前の企業が発行する源泉徴収票の提出が必要です。退職の際に発行してもらい、すみやかに転職先企業に提出を求めましょう。また、年内に再就職をしなかった場合、その年は確定申告が必要です。確定申告を行う際も、離職する前の企業が発行する源泉徴収票を見ながら行いますので、手元に用意しておきましょう。
生命保険料控除の処理方法
生命保険料控除は、会社員であれば年末調整で行い、個人や年度の途中で退職した方は、確定申告で処理を行います。それぞれ手順を、以下に記載します。
年末調整の処理方法
会社員の場合、生命保険料控除の申請は、会社が年末調整の際に行います。加入している保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」を取得し、保険料控除等申告書に添付して提出してもらいましょう。
【手順1】
保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」を取得します。紙で郵送される場合と、保険会社のホームページからデータで証明書をダウンロードできる場合も多いです。
【手順2】
生命保険料控除証明書の記載内容にもとづいて、勤務先が指定する保険料控除申告書に、内容を記載します。記入例は国税庁のホームページに記載がありますので、参考にしましょう。なお、生命保険料控除は限度金額を超えた分は控除されませんので、注意が必要です。
【手順3】
勤務先へ保険料控除申告書と生命保険料控除証明書を提出します。確認を行う担当者は、チェックの際に上限金額を超えている分は内容を確認しなくてもよく、その分業務の手間を減らせます。
なお、給与天引きで保険料を支払っており、企業が控除対象金額の一覧を受け取っている場合、従業員は証明書の添付が不要です。また、給与の年間収入が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外となるため、確定申告での申請が必要です。
確定申告の処理方法
自営業者や年度の途中で退職した人は、確定申告で控除申請を行います。翌年2月16日から3月15日の確定申告期間において、証明書を添付し控除を受けましょう。また、e-Taxで確定申告をする場合は、証明書の添付は省略可能です。
【手順1】
保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」を取得します。紙で郵送される場合と、保険会社のホームページからデータで証明書をダウンロードできる場合もあります。
【手順2】
確定申告書類に、生命保険料控除証明書の内容を記載します。e-Taxで申請を行う場合は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から行います。システムの案内に従って必要事項を入力するだけですが、e-Taxを利用するためには、以下の準備が必要です。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォン、もしくはICカードリーダー
- 利用者識別番号
生命保険料控除のよくある疑問
生命保険料控除のチェックを行う際によくある疑問について、以下より解説します。
生命保険料控除の申告を忘れた
生命保険料控除は、会社員や公務員であれば、年末調整で手続きを行います。申告を忘れたことに気づいたタイミングが勤務先における期限内であれば、すみやかに申し出てもらい必要な資料の提出を求めましょう。年末調整に間に合わなかった場合は、従業員に確定申告を案内します。
確定申告は、翌年の2月16日〜3月15日が受付期間です(土日祝は日にちが前後します)。ただし、生命保険料控除のように税金の払い戻しを受ける還付申告だけなら、生命保険料を支払った年の翌年1月1日から5年間のうちに、税務署に申告が可能です。
控除証明書を紛失した
生命保険料控除証明書を紛失した場合、加入会社に依頼して再発行の手続きを行いましょう。ただし、保険会社によっては生命保険料控除証明書のデータがホームページからダウンロードできます。可能な保険会社かを確認し、期限内に取得するよう案内しましょう。
控除証明書が届かない
生命保険料控除証明書は、各社時期は多少前後しますが、10月中旬ごろに契約住所に発送されます。控除証明書が届かない場合は、保険会社にすみやかに連絡し、発送状況を確認しましょう。保険会社によっては生命保険料控除証明書のデータを、ホームページからダウンロードできる会社も増えています。申請期限が迫っている方は、データダウンロードができないかも、あわせて確認できると安心です。
生命保険料控除は制度を理解し適正な処理を行う
生命保険料控除は、1年間の払い込み保険料を所得から差し引く制度です。生命保険料控除は加入時期により、旧制度と新制度にわかれます。税区分や限度額が異なるので、制度を理解し、適正な処理を行いましょう。また、生命保険料控除証明書が届かないといったトラブルは、早急に保険会社に確認を取ることで、対応できます。正しく制度を理解し、適正な時期に処理を行いましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
給与支払報告書の提出先はどこ?総括表・個人別明細書の書き方や提出期限なども解説
企業の経理や労務を担当する中で、「給与支払報告書は、どこに提出すればいいのだろう」と疑問に感じた経験はありませんか。従業員の住民税額を決定する根拠となる大切な書類のため、提出先や書…
詳しくみるミス防止チェック付!源泉徴収票は自分で作成できる?発行方法や令和7年12月改正を解説
年末調整は、毎月の給与から天引きされた所得税の過不足を調整するための大切な手続きです。年末調整後には、企業は従業員に対して「源泉徴収票」を交付しますが、その作成を外部に委託している…
詳しくみる給与所得者の基礎控除申告書の収入金額がわからない時は?副業・年金の扱いも解説
年末調整の時期、手元に配られた「給与所得者の基礎控除申告書」を見て、「まだ12月の給料やボーナスが支払われていないのに、どのように年収を書けばいいの?」と疑問に思う方もいるでしょう…
詳しくみる源泉徴収票はいつどこでもらう?もらえない時の対応方法も解説!
毎年の年末調整の時期や退職するときなどに会社からもらう源泉徴収票ですが、会社員が正しく税金を納める上でとても重要な書類です。 今回は、源泉徴収票に関して、どこでもらうのか、どのタイ…
詳しくみる年末調整で地震保険料控除を受けるには?
2007年から、年末調整において地震保険料が控除されるようになりました。 ここでは、年末調整で地震保険料控除を受けるために必要な書類、計算方法、保険料控除及び配偶者特別控除申告書の…
詳しくみる新卒が年末調整を行うには?必要書類やアルバイト収入の扱いを解説
新卒社員の年末調整は、学生時代のアルバイト収入や前職の有無によって手続きが変わり、複雑に感じる人も多いのではないでしょうか。とくに「扶養控除申告書」の記入や、複数の源泉徴収票をどう…
詳しくみる