- 更新日 : 2025年11月19日
業務委託の給与明細は必要?テンプレートで支払明細書の書き方も解説
業務委託では、給与明細や源泉徴収票の発行義務はありませんが、報酬の内訳を明確にする「支払明細書」の発行は行いましょう。
支払明細書を発行すれば、給与の詳細を明らかにできるため、支払いに関するトラブルを防げます。
本記事では、業務委託契約における基本的なルールや支払明細書の書き方などを詳しく解説します。
あわせて、すぐに支払明細書が作成できるテンプレートまで紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
業務委託では給与明細や源泉徴収票が不要
業務委託契約においては、給与明細や源泉徴収票の発行義務はありません。
給与明細や源泉徴収票の発行は、労働基準法で定められた義務ですが、業務委託契約はこの枠組みに該当しないためです。
具体的には、業務委託で支払われるものは「報酬」であり「給与」ではありません。
給与は、雇用契約に基づいて支払われるものであり、源泉徴収の対象となりますが、報酬は原則として源泉徴収の対象外です。
また、業務委託は、会社と個人事業主や法人の間で結ばれる対等な関係のため、会社が従業員に対して行うような、給与明細の発行や社会保険の手続きを行う必要がないからです。
とはいえ、報酬支払いの証明をするために、「支払明細書」や「発注書」の発行は行いましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
給与明細電子化マニュアル
こちらは「給与明細電子化マニュアル」の資料です。給与明細の電子化をご検討中、または導入を進めている企業様向けの資料となります。
情報収集や実務の参考資料として、ぜひご活用ください。
給与明細(自動計算できる計算式入り)
こちらは「給与明細(自動計算できる計算式入り)」の資料です。給与計算を自動で行うための計算式が設定されています。
日々の給与計算業務の参考資料として、ぜひご活用ください。
給与計算 端数処理ガイドブック
給与計算において端数処理へのルール理解が曖昧だと、計算結果のミスに気づけないことがあります。
本資料では、端数処理の基本ルールをわかりやすくまとめ、実務で参照できるよう具体的な計算例も掲載しています。
給与計算がよくわかるガイド
人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。
複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。
そもそも業務委託とは
業務委託とは、業務の一部または全体を外部の個人や企業に依頼する契約形態を指し、雇用契約とは異なり、依頼者と受託者の間に「雇用関係」が生じません。
報酬は契約に基づいて支払われ、作業内容や納期などの条件は、契約書で明確に定められるのが一般的です。
たとえば、Webデザインやライティング業務など、多くの分野で業務委託が活用されています。
業務委託での契約形態では、受託者が「個人事業主」として業務を遂行することが多く、自由度の高い働き方が可能です。
一方で、雇用契約と異なり労働基準法の適用外となるため、給与明細や福利厚生は対象外です。
次項で、「業務委託契約」と「雇用契約」の違いについて詳しく解説します。
業務委託契約と雇用契約の違い
業務委託契約と雇用契約の主な違いは、「労働時間の拘束」や「雇用主の指揮命令」にあります。
雇用契約では、従業員が雇用主の指揮命令下で働き、労働基準法が適用されるため残業手当や有給休暇などの保障があります。
一方、業務委託契約では、受託者は契約内容に従い独立した立場で業務を遂行するため、作業時間や方法について自由度が高い反面、労働基準法は適用されません。
また、雇用契約では給与明細や源泉徴収票が発行されますが、業務委託では発行されません。
代わりに、支払明細書や請求書を活用するのが一般的です。
このように、雇用契約と業務委託契約は、法的な取り扱いが大きく異なります。
業務委託の報酬は確定申告で給与所得に該当しない
業務委託契約で支払われる報酬は、確定申告において「給与所得」ではなく「事業所得」または「雑所得」として扱われます。
給与所得とは、会社員やアルバイトが受け取る給与や手当を指します。
一方、業務委託の報酬は、独立した立場で業務を行う受託者が受け取るため、給与所得に該当しません。
そのため、受託者は自ら確定申告を行い、所得税や住民税などを納税する必要があります。
報酬が一定額を超える場合は、支払者が所得税を源泉徴収し、差し引いた額を受託者に支払うケースもあります。
この場合は、受託者は支払調書を基に確定申告を行い、所得税の不足分や過払い分の調整が必要です。
業務委託では給与明細の代わりに支払明細書を発行
業務委託では、雇用契約とは異なり、給与明細ではなく支払明細書を発行することが一般的です。
給与明細は雇用契約で働く従業員に対して発行されるものであり、雇用主が給与の内訳を明示するためのものです。
一方、業務委託契約では受託者が「個人事業主」として働くため、給与ではなく報酬が支払われます。
そのため、報酬の内訳を記載した支払明細書が必要です。
次項で、支払明細書とは何か、さらに請求書や領収書との違いについて詳しく解説します。
支払明細書とは
支払明細書とは、支払われた金額の内訳を明記した書類のことです。
業務委託においては、委託元が委託先に支払った報酬の内訳として、どの業務にいくら支払われたのかを具体的に記載した書類です。
支払明細書には、一般的に下記の内容を記載します。
| 記載項目 | 詳細 |
|---|---|
| 支払先 | 報酬を受け取る個人または法人の名称 |
| 支払日 | 報酬が支払われた日付 |
| 支払金額 | 支払われた総額 |
| 内訳 | 業務内容ごとの報酬額 |
| 備考 | その他記載が必要な事項 |
支払明細書は受託者にとって、収入の証明や税務申告の際に必要な重要な書類です。
委託元の企業や会社は、委託先の個人や法人に対して、トラブルを防ぐためにも必ず支払明細書を発行しましょう。
支払明細書と請求書や領収書との違い
支払明細書、請求書、領収書の違いは、下記の通りです。
| 項目 | 役割 |
|---|---|
| 支払明細書 | 委託元が委託先に支払った報酬の内訳を明記した書類 |
| 請求書 | 委託先が委託元に対して、報酬の支払いを求める際に発行する書類 |
| 領収書 | 委託先への支払いが完了したことを証明するために発行する書類 |
上記のように、それぞれ異なる目的で作成されます。
業務委託の支払明細書を発行するメリット
支払明細書を発行すれば、発注者と受託者の双方に下記のようなメリットがあります。
- 取引内容の認識齟齬が防げる
- 税務申告をスムーズに行える
- 信頼関係を構築できる
支払明細書を発行すれば、双方が金銭の流れを明確に把握でき、報酬の誤りやトラブルを未然に防げます。
その結果、お互いに信頼関係を築けて、長期的な取引にも繋がります。
受託者が確定申告を行う際には、支払明細書が証拠書類として役立ち、発注者側も経費の記録として活用できるのもメリットです。
業務委託の給与明細に使える無料テンプレート
マネーフォワード クラウドでは、業務委託の支払明細書に使えるテンプレートをご用意しております。無料でダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。
業務委託の支払明細書の書き方
業務委託の支払明細書に記載するべき項目について、下記に分けて解説します。
- 書類名
- 送付先の会社名
- 発行した日付
- 発行元の情報
- 残高の情報
- 取引内容
それぞれどのように記載するのか詳しく解説します。
書類名
支払明細書の書類名は、「支払明細書」と明記しましょう。
その他に、「業務委託費支払明細書」や「報酬支払明細書」などの名称を用いる場合もあります。
また、請求書を兼ねたい場合は、「請求書兼支払明細書」と明記し、支払期日を忘れずに記載しましょう。
送付先の会社名
支払明細書を受け取る相手の会社名を正式名称で記載します。
法人の場合は「株式会社」や「合同会社」を省略せず記載し、あわせて部署名や担当者の氏名も記載しましょう。
ただし、会社名と氏名を両方記載する際は、「御中」と「様」が重複しないように注意してください。
個人の場合は、氏名や屋号を記載します。
送付先名が間違っていると、取引先との信頼関係に影響を与える可能性があるため、十分に確認する必要があります。
発行した日付
支払明細書を作成した日付を記載します。
発行した日付を記載すれば、いつの取引の支払明細書であるかを管理しやすくなります。
発行元の情報
発行者の名称、住所、連絡先を記載します。
法人の場合は会社名と所在地、個人事業主の場合は事業主名と事務所の所在地を明記しましょう。
あわせて、担当者名や連絡先(電話番号やメールアドレス)を記載すると、不備があった場合の問い合わせ対応がスムーズになります。
残高の情報
取引日・支払日に数ヶ月のズレがある場合は、支払前の残高、今回の支払額、支払後の残高などを支払明細書に記載する必要があります。
支払を受け取る側が、現在の支払い状況を正確に把握できるようにするための項目のため、記載に誤りがないようにしましょう。
取引内容
取引内容は、明確に記載しましょう。
具体的に記載するべき内容は、下記の通りです。
| 記載内容 | 詳細 |
|---|---|
| 業務内容 | どのような業務をしたのかを記載 |
| 納品日 | 納品した日やサービスを提供した日を記載 |
| 単価 | 業務ごとの単価を記載 |
| 数量 | 個数や本数など納品した数量を記載 |
| 報酬金額 | 数量と単価を掛け合わせた金額を記載 |
業務内容はできる限り具体的に記載しましょう。
たとえば、「デザイン業務」など漠然とした表現ではなく、「ロゴデザイン作成」「ウェブサイトデザイン」など、具体的な業務内容を記載すれば、誤解を防げます。
業務内容が複数の場合は、項目ごとに分けて記載するとわかりやすくなります。
合わせて、消費税の有無も忘れずに明記しましょう。
業務委託の支払明細書を発行しないとどうなる?
業務委託の支払明細書を発行しない場合、法的義務はないものの、取引の透明性や信頼関係に影響を及ぼす可能性があります。
業務委託は雇用契約とは異なり、給与明細の発行が法律で義務付けられていません。
そのため、明細書を発行しないこと自体は違法ではありませんが、さまざまなリスクが考えられます。
たとえば、取引内容を確認できないため、報酬額や支払期日に関する認識の相違によって、トラブルが発生する可能性があります。
また、支払者側も記録が曖昧になるため、後日税務調査などで正確な支払い実績を提示できない可能性もあるでしょう。
これらを防ぐため、支払明細書を発行することは双方にとってメリットがあります。
取引内容の認識齟齬や、報酬に関するトラブルを未然に防ぐためにも、業務委託の支払明細書を発行するのがおすすめです。
業務委託の給与明細は不要!代わりに支払明細書で透明性を確保しよう!
本記事では、業務委託には給与明細が不要である理由や、支払明細書の書き方などを解説しました。
業務委託では給与明細の発行義務はありませんが、報酬内容を明確にするために支払明細書の発行を行いましょう。
支払明細書を発行すれば、取引内容を明確にでき、報酬に関するトラブルを防げます。
また、受託者にとっては確定申告の際に重要な証拠書類となり、発注者側も正確な記録を残せます。
本記事を参考に、正しい支払明細書を作成し、トラブルのない取引を目指しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
三重県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
三重県で事業を運営する企業にとって、給与計算は日々の業務の中でも重要かつ煩雑な作業の一つです。正確な給与計算を行うためには専門的な知識と時間が必要であり、多くの企業が外部の給与計算…
詳しくみる【テンプレ付】給与規程(賃金規程)とは?作成時の規則と手順を解説
労働者が事業主と労働契約を締結する際、最も重視する労働条件として賃金があります。その事業所で根拠となるのが給与規程(賃金規程)ですが、そもそも作成は法的に義務づけられているのでしょ…
詳しくみる頑張った手当とは?特別手当の一種!ボーナスとの違いや相場、ユニークな名称の事例も
「従業員の頑張りを正当に評価し、組織の活性化につなげたい。」そう考える経営者や人事担当者の皆様にとって、「頑張った手当」は非常に魅力的な選択肢の一つです。 この記事では、頑張った手…
詳しくみる所得税徴収高計算書の記入方式
給与や報酬を支払う事業者にとって、源泉徴収業務は避けて通れない重要な税務手続きです。しかし、いざ「所得税徴収高計算書」を目の前にすると、どの欄に何を記入すればよいのか迷ってしまう方…
詳しくみる福利厚生で社宅を運用する際のトラブル4選!法人の課題と解決策を解説
福利厚生として社宅の導入を検討しているものの「トラブルが起こりそうで不安」「トラブルにうまく対処する方法は?」といった不安や疑問を感じている方も多いでしょう。 そこで今回は、法人の…
詳しくみる実質賃金とは?名目賃金との違いやマイナスになる原因をわかりやすく解説
実質賃金とは、単なる給与額面ではなく、労働者の購買力を正確に示す重要な指標です。近年、日本では実質賃金の低下が問題となっており、多くの企業や労働者に影響を与えています。 本記事では…
詳しくみる
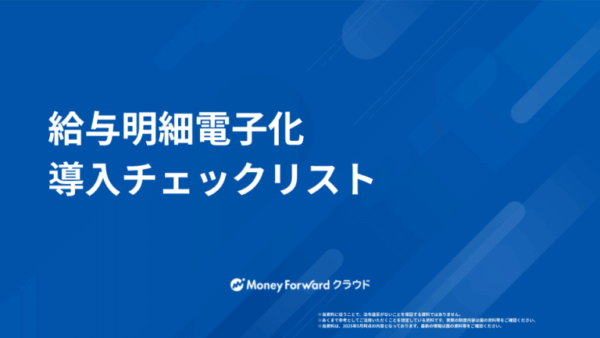
.png)

