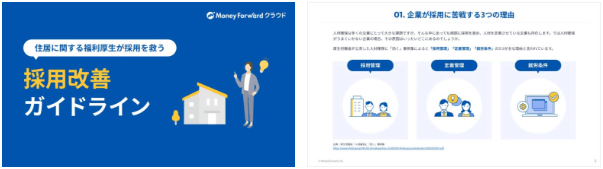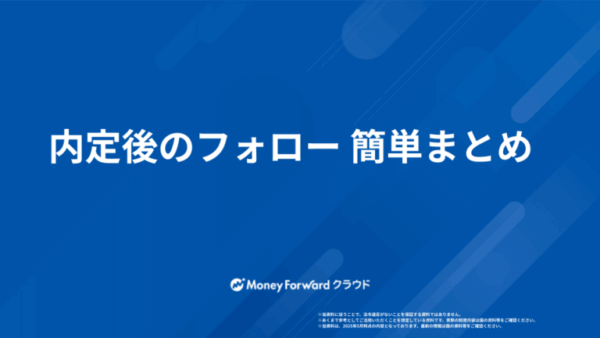- 更新日 : 2025年10月31日
新卒採用計画の立て方は?計画書の無料テンプレートつき
新卒採用は企業の未来を左右する重要な活動です。一方で、効果的な採用計画の立て方に悩む企業も少なくありません。
本記事では、新卒採用計画の立て方や必要な準備、計画書の作成方法について詳しく解説します。さらに、すぐに活用できる無料テンプレートもご紹介しましょう。
目次
新卒採用計画とは?
新卒採用計画は、企業が新卒者を採用するための戦略的な計画です。事業目標に沿って必要な人材を確保し、効果的な採用活動を行うための指針となります。採用目標、スケジュール、予算、選考プロセスなどを包括的に定め、計画的な採用活動を可能にします。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
住居に関する福利厚生が採用を救う 採用改善ガイドライン
人材確保は多くの企業にとって大きな課題ですが、そんな中にあっても順調に採用を進め、人材を定着させている企業も存在します。では人材確保がうまくいかない企業の場合、その原因はいったいどこにあるのでしょうか。
3つの原因と、それを解決する福利厚生の具体的な内容まで、採用に役立つ情報を集めた資料をご用意しました。
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
内定後のフォロー 簡単まとめ
内定者へのフォローアップは、採用活動における重要なプロセスです。 本資料は「内定後のフォロー」について、簡単におまとめした資料です。
ぜひダウンロードいただき、貴社の取り組みの参考としてご活用ください。
試用期間での本採用見送りにおける、法的リスクと適切な対応
試用期間中や終了時に、企業は従業員を自由に退職させることができるわけではありません。
本資料では、試用期間の基本的な概念と本採用見送りに伴う法的リスク、適切な対応について詳しく解説します。
新卒採用計画に必要な準備は?
新卒採用計画に必要な準備には、採用目標と求人要件の設定、採用予算の策定、選考プロセスの設計が含まれます。
また、採用担当者の教育や選考基準の明確化も重要です。これらの準備を通じて、効果的な採用活動を実現します。
採用目標と求人要件の設定
事業計画に基づいて、量的目標(採用人数)と質的目標(求める人物像)を設定します。これらの目標は、企業の成長戦略や人材ニーズ、部門ごとの採用ニーズを把握し、具体的な採用人数や職種を決定します。
採用予算の設定
採用活動に必要な予算を算出します。例えば、広告費、イベント参加費、選考にかかる経費など、想定される費用を洗い出し、適切な予算配分を考えます。
選考プロセスの設計
エントリーから内定までの選考ステップにおける各段階での評価基準や面接方法を決定し、効率的かつ公平な選考プロセスを構築します。
採用担当者の教育
採用担当者に対して、選考基準や面接技術に関する教育を実施し、一貫した評価と効果的な選考を行うためのスキルを養成します。
選考基準の明確化
応募者を評価する際の基準を明確にします。学歴、スキル、人物像など、具体的な評価項目と基準を設定し、公平な選考を実現します。
新卒採用計画の立て方・手順は?
新卒採用計画の立て方・手順は、まず採用スケジュールを策定し、効果的な採用チャネルを選定します。次に、魅力的な求人広告や会社説明資料を作成し、インターンシッププログラムの実施計画を立てましょう。これらの手順を通じて、体系的な採用活動を展開します。
採用スケジュールの策定
採用活動の全体スケジュールを策定します。具体的には、説明会、エントリー期間、選考期間、内定出しのタイミングなど、重要なマイルストーンを設定しましょう。
採用チャネルの選定
効果的な採用チャネルを選定します。就職サイト、大学の就職課、合同説明会など、多様な採用チャネルの中から最適なものを選びましょう。
求人広告や資料の作成
魅力的な求人広告や会社説明資料を作成します。自社の強みや特徴、求める人物像を明確に伝える内容を心がけましょう。
インターンの実施
インターンシッププログラムを企画・実施します。学生に実際の業務を体験してもらい、相互理解を深める機会を設けます。
新卒採用計画書の作り方は?
新卒採用計画書の作り方は、基本情報、採用方針、スケジュール、選考プロセス、予算計画など、必要な項目を網羅的に記載します。
各項目を具体的かつ明確に記述し、実行可能な計画書を作成することが重要です。リスク管理や実施体制も忘れずに含めましょう。
基本情報
会社名、作成日、作成者など、計画書の基本情報を記載します。
採用方針
新卒採用の目的や方針、求める人物像を明確に記載します。
採用スケジュール
採用活動の全体スケジュールを時系列で記載します。
採用手法
利用する採用チャネルや広報手段を具体的に列挙します。
選考プロセス
エントリーから内定までの選考ステップと評価基準を詳細に記載します。
インターンシッププログラム
インターンシップの実施計画や内容を記載します。
内定者フォロー
内定から入社までのフォロー計画を記載します。
予算計画
採用活動に関わる予算の詳細を記載します。
リスク管理
想定されるリスクとその対策を記載します。
実施体制
採用活動の実施体制や役割分担を明記します。
新卒採用計画書の無料テンプレート
新卒採用計画書作成に役立つ無料テンプレートが以下のURLからダウンロードできます
ワード形式:https://biz.moneyforward.com/payroll/templates/4131/
エクセル形式:https://biz.moneyforward.com/payroll/templates/4126/
上記のテンプレートを活用することで、効率的に採用計画書を作成できます。必要に応じて、自社の要件に合わせてカスタマイズしてご利用ください。
新卒採用計画書を作成する時のポイントは?
新卒採用計画書作成時のポイントは、目標設定の現実性、求める人物像の具体的な定義、スケジュールの実現可能性です。過去の実績や市場動向を考慮し、達成可能な目標を立てましょう。また、明確な選考基準と余裕のあるスケジュール設定が質の高い採用活動につながります。
目標設定の現実性
採用目標は、過去の実績や市場動向を考慮し、現実的な数値を設定します。達成可能な目標を立てることで、効果的な採用活動が可能になります。
具体的な定義
求める人物像や選考基準を具体的に定義します。抽象的な表現を避け、明確な基準を設けることで、一貫性のある選考が可能になります。
スケジュールの現実性
採用活動のスケジュールは、社内リソースや市場動向を考慮し、現実的な計画を立てます。余裕を持ったスケジュール設定が、質の高い採用活動につながります。
新卒採用計画書を作成する時のポイントは?
新卒採用計画書作成時のポイントは、目標設定の現実性、求める人物像の具体的な定義、スケジュールの実現可能性です。過去の実績や市場動向を考慮し、達成可能な目標を立てましょう。また、明確な選考基準と余裕のあるスケジュール設定が質の高い採用活動につながります。
目標設定の現実性
採用目標は、過去の実績や市場動向を考慮し、現実的な数値を設定します。達成可能な目標を立てることで、効果的な採用活動が可能になります。
具体的な定義
求める人物像や選考基準を具体的に定義します。抽象的な表現を避け、明確な基準を設けることで、一貫性のある選考が可能になります。
スケジュールの現実性
採用活動のスケジュールは、社内リソースや市場動向を考慮し、現実的な計画を立てます。余裕を持ったスケジュール設定が、質の高い採用活動につながります。
新卒採用後のオンボーディング計画のポイント
採用活動が成功しても、その後のオンボーディングが不十分であれば、新入社員が力を発揮する前に離職してしまうリスクがあります。計画的かつ丁寧なオンボーディングを設計することで、早期戦力化と定着率向上を両立できます。
入社初日からの動きを具体化して不安を払拭する
新入社員は、入社直後に業務だけでなく人間関係や社内ルール、評価制度など、多くの不安を抱えがちです。こうした不安を軽減し、スムーズなスタートを切ってもらうためには、初日からの動きを明確に計画し、本人に事前に共有しておくことが効果的です。
たとえば、初日のスケジュールとして、会社説明、各部門の紹介、設備案内、必要書類の提出、IT環境のセットアップなどを組み込みます。午後にはメンターとの初回面談やチームの顔合わせの時間を設けることで、「自分がこの職場の一員になる」という実感を持ってもらえます。見通しの立つスケジュールと丁寧なサポートによって、不安を和らげることができます。
中長期のオンボーディング計画を立てて段階的に慣れてもらう
オンボーディングは1日や1週間で完了するものではなく、入社から数か月をかけて段階的に進める必要があります。1か月、3か月、6か月といったタイミングで業務内容や育成方法を変化させながら、継続的にサポートする仕組みを設けましょう。
たとえば、最初の1か月は「業務理解」と「社内関係構築」に重点を置き、OJTと並行して部門横断的な交流の場を設けます。3か月目には「目標設定」と「中間評価」を実施し、自分の成長実感と今後の期待値をすり合わせます。6か月目には「定着と自走」のフェーズとして、自律的に業務を推進できる状態に近づけていきます。こうしたステップを事前に設計しておくことで、育成の軸がぶれずに進行できます。
メンターやOJT担当者との連携を強化してサポート体制を整える
新入社員の育成において、メンターやOJT担当者の存在は非常に重要です。誰に相談すればよいのかが明確であるだけで、新入社員は心理的安全性を感じ、安心して仕事に取り組めるようになります。
そのためには、メンターやOJT担当者に対しても、事前に育成方針や接し方の研修を行い、役割と期待を明確に伝えることが求められます。また、メンター自身が孤立しないよう、人事担当者が定期的に状況確認を行い、困りごとを聞く機会を設けると効果的です。新入社員と育成担当者の双方にとって負担の少ない、バランスの取れた体制を構築することが肝要です。
フィードバックと振り返りの機会を設けて成長を促進する
オンボーディング期間中は、新入社員本人が自分の成長を実感できるようにすることが、モチベーション維持に直結します。そのため、定期的な1on1ミーティングやフィードバック面談を通じて、進捗の確認と評価を行う仕組みを整えましょう。
たとえば、週1回の1on1では、業務の理解度、悩み、不安点などをヒアリングし、必要に応じて軌道修正を行います。また、月次での自己評価や上司からのコメントを記録することで、振り返りの材料とし、継続的な改善意識を育てることができます。このような仕組みがあることで、新入社員は「見守られている」という安心感を得られ、主体的に成長へ向かう姿勢が育ちます。
新卒採用に効果的なブランディング戦略とは?
新卒採用市場では企業間の競争が激化しており、自社の魅力を効果的に伝える「採用ブランディング」の重要性が高まっています。求職者との価値観の一致を図ることで、質の高いマッチングと早期離職防止を実現できます。
自社の採用ターゲットを明確に定義する
ブランディング戦略を立てる第一歩は、「誰に向けてアピールするのか」を明確にすることです。自社が求める人物像を定義し、その人物像に合致する学生に響く情報発信を行う必要があります。たとえば、「自ら考え行動する人材」や「社会課題に関心がある人材」など、行動特性や価値観の観点から採用ターゲットを設定することで、メッセージの一貫性が生まれます。
さらに、大学の属性(文理・専攻・地域など)や、インターン経験の有無、情報収集の傾向なども分析材料とすることで、より具体的なターゲット像を描くことができます。これにより、効果的なメディア選定やコンテンツ設計が可能となります。
自社の魅力を言語化し、差別化ポイントを明確にする
採用ブランディングにおいては、自社の特徴や強みを求職者に伝わる形で言語化することが不可欠です。業種や規模、制度面だけでなく、働く人の雰囲気や価値観、キャリアステップといった「ソフト面の魅力」を打ち出すことが、差別化につながります。
たとえば、「20代でリーダーを任される文化」や「地域密着型で社会貢献性が高い仕事」「失敗を歓迎するチャレンジ風土」など、他社では得られない体験を具体的に示すことで、求職者の共感を得ることができます。また、社員インタビューや1日の業務紹介を通じて、リアルな情報を伝える工夫も有効です。
発信チャネルを選定し、一貫した情報を提供する
採用ブランディングは、発信内容だけでなく、その届け方も重要なポイントです。ナビサイトや自社採用サイト、SNS、オンライン説明会など、多様なチャネルを活用しつつ、発信するメッセージを統一することが求められます。
たとえば、自社採用サイトでは理念やキャリア制度を深く紹介し、Instagramでは社内イベントの様子をビジュアルで伝えるなど、媒体の特性を活かしながらも「一貫性のあるトーン」を意識することが重要です。どのチャネルから接点を持ったとしても、企業としての印象がブレないことが、ブランド構築において信頼感を高める鍵となります。
社員を巻き込み、ブランドの内面化を促進する
採用ブランディングは人事部門だけで完結するものではありません。実際に働く社員の言動や姿勢が、企業ブランドの体現者として重要な役割を果たします。そのため、社員が企業理念や求める人物像を理解し、自分の言葉で語れるようにする働きかけが必要です。
たとえば、リクルーター制度や座談会の登壇者に対して事前の研修を実施し、伝えるべきメッセージを共有することが効果的です。また、社員がブランディングに主体的に関わることで、社内の一体感やエンゲージメントの向上にもつながります。企業文化の“発信力”は、社員一人ひとりの行動に根ざしてこそ、説得力を持って伝わるものです。
新卒採用においてデータ分析はどのように活用できる?
感覚や経験に頼った採用から脱却し、より効果的で再現性のある採用活動を行うためには、データ分析の導入が不可欠です。採用プロセス全体を可視化し、意思決定の質を高める取り組みが、競争力のある人材確保につながります。
採用プロセス全体を数値化して現状を把握する
まず着手すべきは、採用活動における各プロセスを数値で把握することです。エントリー数、書類通過率、面接通過率、内定承諾率、入社後の定着率など、学生が会社を知ってから入社するまでのプロセスである採用ファネルに沿ってKPIを設定し、定期的にモニタリングを行うことで、ボトルネックを特定できます。
たとえば、書類選考の通過率が著しく低い場合には、募集要項と実際の応募者のマッチ度にギャップがある可能性があります。また、面接での辞退が多い場合には、面接官の対応や企業説明の質を見直す必要があるかもしれません。このように、数値で可視化することで、属人的な判断から脱し、客観的な課題把握が可能になります。
過去の採用データを分析して傾向を把握する
過去の採用データを蓄積・分析することで、自社にマッチする人材の傾向や、効果的な採用手法を明らかにできます。たとえば、どの学校・地域・媒体からの応募者が内定・定着しやすいのかを分析することで、今後のターゲティングに活かせます。
また、入社後の評価や離職理由と、選考時の評価項目との相関を分析すれば、将来的な活躍度合いを予測する「予測的採用(Predictive Hiring)」の精度も高まります。これにより、見極めの基準を洗練させ、採用のミスマッチを減らすことが可能です。
採用チャネルごとの効果を比較して戦略を最適化する
求人媒体、人材紹介、リファラル採用、SNS経由など、多様化する採用チャネルの中で、どこに注力すべきかは企業によって異なります。各チャネルの応募者数、通過率、採用単価、定着率などを比較・分析することで、費用対効果の高いチャネルにリソースを集中する判断ができます。
たとえば、ナビサイトからの応募は多くても通過率が低い一方で、リファラル採用は母集団が小さくても採用後の定着率が高いといった傾向が見られる場合、次年度の採用戦略に大きなヒントとなります。このような分析結果に基づいたチャネル設計が、採用効率を格段に高めます。
採用プロセスをデジタル化・自動化する方法
近年、採用業務の効率化と質の向上を目的として、採用プロセスのデジタル化・自動化が急速に進んでいます。人事担当者の負担軽減にとどまらず、候補者体験の向上や採用活動の高度化にもつながる取り組みです。
採用管理システム(ATS)を活用して情報を一元化する
採用業務では、応募者情報の管理、書類選考、面接スケジュールの調整、進捗管理など、さまざまな作業が発生します。これらをメールやスプレッドシートで管理していると、情報の重複や抜け漏れが起こりやすく、対応の遅れにつながります。そうした課題を解消するのが、採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)です。
ATSを導入することで、応募者の情報を一元管理し、選考の各ステップを視覚的に把握できます。評価や面接結果の記録も蓄積され、チーム内での情報共有が容易になるため、選考判断のスピードと質が向上します。また、複数のチャネルからの応募も自動で集約されるため、担当者の作業負担が大幅に軽減されます。
面接調整や連絡業務を自動化して手間を削減する
採用担当者にとって、面接日程の調整や候補者との連絡は、想像以上に時間を要する業務のひとつです。この業務においても、自動化ツールを活用することで大幅な効率化が図れます。
たとえば、GoogleカレンダーやOutlookと連携する面接スケジューラーを導入すれば、空き日程を候補者が選べる仕組みを自動で提供できます。これにより、担当者が都度メールを往復する必要がなくなり、ミスも減少します。また、書類選考結果の自動通知や面接リマインダーの自動送信など、繰り返しの多い連絡業務もシステム化することで、抜け漏れを防ぎながら対応のスピードを維持できます。
オンライン選考ツールで距離や時間の制約を解消する
選考の初期段階においては、Web面接ツールや録画面接、オンライン適性検査の活用が一般化しています。これらのツールを導入することで、遠方在住の候補者や在職中の応募者に対しても、柔軟な対応が可能となります。
録画面接を活用すれば、応募者が都合の良い時間に面接動画を撮影・提出し、企業側は複数人で非同期に確認することができます。これにより、面接官のスケジュール調整の負担が減り、短期間で多くの候補者を公平に比較することが可能となります。また、適性検査をデジタル化することで、性格傾向や業務適応度を数値的に把握しやすくなり、選考の客観性を高められます。
優良な人材を確保するなら効果的なプロセス設計が必要
新卒採用計画は、企業の将来を左右する重要な戦略です。綿密な準備と現実的な目標設定、効果的なプロセス設計が成功の鍵となります。定期的な見直しと改善を行い、変化する採用市場に柔軟に対応することで、優秀な人材の確保と企業の持続的な成長につながります。
本記事で紹介した手順やポイントを参考に、自社に最適な採用計画を立てましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
年末年始手当の取り扱いとは?適用されないケースや導入のポイントを解説
年末年始に出勤する社員に対して支給する年末年始手当は、感謝の意味を込めたインセンティブとして多くの企業で導入されています。しかし、取り扱いを誤ると「賞与扱いになるのか?」「割増賃金…
詳しくみるOJTとは?意味やOFF-JTとの違い、研修のやり方や成功のコツを解説
従業員を育成するための代表的な教育手法の一つにOJTがあります。今回は、このOJTについて見ていくとともに、OJTと似たような言葉である「OFF-JT」との違いは何か、OJT研修の…
詳しくみるコンセンサスとは?意味やビジネスにおける重要性、使い方を解説
ビジネスにおける「コンセンサス(合意形成)」とは、全員が納得して行動に移すために欠かせないプロセスです。社内会議で意見が割れてしまい、なかなか結論が出ないときこそ、コンセンサスが重…
詳しくみるキャリアセンターとは?採用活動の際に利用するメリットや手順などを解説!
キャリアセンターとは、大学や専門学校に設置される部署で、学生の就職支援を行う窓口です。 企業にとっては、新卒の学生へアプローチするための窓口となります。しかし、どのように関係を築け…
詳しくみる従業員エンゲージメントとは?高める方法を知って、離職率低下と生産性向上を実現しよう
「従業員エンゲージメント」という言葉をご存知ですか?これは、従業員が企業の目指す方向性を理解し、自発的に貢献しようとする意欲のことです。エンゲージメントの向上は、多くの企業が抱える…
詳しくみる心理的安全性が高い職場とは?メリット・特徴・作り方をわかりやすく解説
職場で安心して発言できる雰囲気は、業務効率やチームの成果に大きな影響を与えます。そこで注目されているのが「心理的安全性」です。これは、発言や提案が否定されたり評価に響いたりすること…
詳しくみる