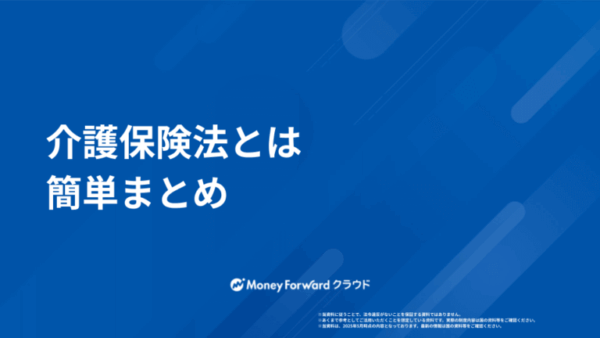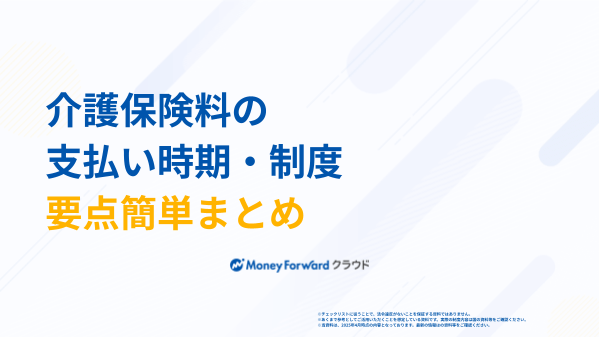- 更新日 : 2025年11月19日
介護保険被保険者証とはいつ使う?申請手続きや有効期限について解説
介護保険被保険者証とは、介護保険の被保険者資格を証明するものです。65歳以上の第1号被保険者には全員に送付されますが、40歳以上65歳未満の第2号被保険者には、一定の条件のもとで発行されます。
本記事では、介護保険被保険者証について、使用する場面や有効期限、転居時の手続き、紛失した場合の再発行方法などについて紹介します。
目次
介護保険被保険者証とは
介護保険被保険者証とは、介護保険の被保険者であることの証明書です。要介護認定や要支援認定を申請するとき、介護保険制度のサービスを受けるときなどに使用します。
介護保険被保険者証の記載事項
介護保険被保険者証には、被保険者の氏名・住所・生年月日のほか、被保険者番号・要介護状態の区分(要介護1など)・要介護認定日・要介護認定有効期限・1ヶ月の支給限度基準額・サービスの種類ごとの支給限度基準額・保険料を滞納した場合の給付制限についての事項などが書かれています。
介護保険被保険者証

健康保険証との違い
健康保険証(健康保険被保険者証)は、健康保険組合や全国健康保険協会、国民健康保険など、医療保険の被保険者であることの証明書で、病気やけがなどで保険診療を受けるときに、医療機関に提示するものです。
介護保険被保険者証は、介護保険の被保険者であることを証明するもので、要介護認定申請・要支援認定申請をするときや介護サービスを受けるときなどに利用します。
2024年12月2日より、健康保険被保険者証はマイナンバーカードに移行されますが、介護保険被保険者証は、2024年9月現在、マイナンバーカードとの結合について具体的な予定はありません。
しかし将来的には、介護保険被保険者証もマイナンバーカードと一体化される可能性があるといわれています。
後期高齢者医療保険証との違い
後期高齢者医療保険証とは、後期高齢者医療保険の被保険者であることの証明書です。
後期高齢者医療保険とは、75歳以上(一定の障害が認定された場合は65歳以上)の人が加入する医療保険です。健康保険や国民健康保険などに加入していた人は、75歳になると後期高齢者医療保険の被保険者となります。
後期高齢者医療保険証を医療機関の窓口に提示することで、保険診療を受けられます。
高齢受給者証との違い
高齢受給者証とは、高齢受給者(70歳以上75歳未満)の一部負担金割合を示すものです。
70歳以上75歳未満の一部負担金の割合は収入によって異なり、2割の人と3割の人がいます。そのため高齢受給者が保険診療を受けるときは、健康保険被保険者証とともに高齢受給者証も医療機関の窓口に提示する必要があります。
第1号被保険者
介護保険の被保険者は、年齢により、第1号被保険者と第2号被保険者に分けられています。第1号被保険者とは、65歳以上の被保険者です。
第1号被保険者は、理由を問わず、要介護認定や要支援認定を受けたときに、各種の介護サービスが利用できます。
第2号被保険者
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。第2号被保険者の場合、加齢に起因する特定疾病により要介護認定を受けた場合にのみ、介護保険のサービスが利用できます。
特定疾病とは、次の16種類です。
- がん(医師が回復の見込みがないと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護や支援が必要な状態であっても、原因が上記の疾病ではない場合は、介護保険のサービスは利用できません。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐妊娠出産・育児・介護編‐
妊娠出産、育児、介護は多くの労働者にとって大切なライフイベントです。
仕事と家庭生活を両立するうえで重要な役割を担う社会保険・労働保険のうち、妊娠出産、育児、介護で発生する手続きをまとめた実用的なガイドです。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
介護保険法とは かんたん解説ガイド
介護保険法の概要や仕組みについて、わかりやすく解説したガイド資料です。
制度への理解を深めるための学習用資料や、社内研修の参考情報としてご活用ください。
介護保険料の支払い時期・制度 要点簡単まとめ
介護保険料の支払い時期や制度の仕組みについて、要点を簡潔にまとめた資料です。
実務における確認用や、制度理解を深めるための参考資料としてご活用ください。
介護保険被保険者証はいつ使う?
介護保険被保険者証は、要介護認定申請時やケアプラン作成依頼時、介護給付金申請時などに使用します。このようなときは、介護保険被保険者証に記載された介護保険番号や要介護状態などの情報を確認する必要があるためです。
要介護認定の申請
介護保険被保険者証は、要介護認定や要支援認定を申請するときに、必要書類とともに市区町村や地域包括支援センターの窓口に提出します。
なお、第2号被保険者で、まだ介護保険被保険者証を所持していない場合、健康保険被保険者証を提出します。
ケアプランの立案・作成
ケアプラン(介護サービス計画書)の立案や作成をケアマネジャー(介護支援員)に依頼するときも、介護保健被保険者証を使用します。
ケアプランとは、どの介護サービスを利用するかについての計画書です。介護保険被保険者証に記載されている被保険者番号や要介護状態の区分、支給限度基準額などは、ケアプラン作成時に必要な情報です。
介護給付金の支給申請
介護保険では、入浴用いすなどの特定福祉用具を購入したときや、段差の解消・手すりの取り付けなど住宅を改修したときに、費用の一部が支給されます。
このような介護給付金の支給申請時にも、介護保険被保険者証が必要です。
介護保険被保険者証の申請手続きと受け取り方法
介護保険被保険者証は、どのように入手するのでしょうか。65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分けて説明します。
第1号被保険者
65歳に到達し第1号被保険者になると、市区町村から介護保険被保険者証が郵送されます。自分から交付申請をする必要はありません。
受け取った介護保険被保険者証は、介護や支援が必要になるまで紛失しないように保管しておき、要介護認定や要支援認定を申請するときに使用します。
介護保険被保険者証を所持していても、要介護・要支援認定を受けていない場合は介護保険のサービスが利用できないため、注意が必要です。
第2号被保険者
第1号被保険者と異なり、第2号被保険者は、全員が介護保険被保険者証を所持しているわけではありません。
第2号被保険者は、加齢を原因とする16種類の特定疾病により要介護認定または要支援認定を受けた場合にのみ、介護保険被保険者証が交付されます。
介護保険被保険者証の有効期限
医療保険の被保険者証の中には、有効期限が書かれているものもあります。介護保険被保険者証にも、有効期限があるのでしょうか。
要介護認定を受けていない人
介護保険被保険者証自体には、有効期限が設定されていません。そのため要介護認定や要支援認定を受けていない人は、交付された介護保険被保険者証の更新手続きをする必要はありません。
要介護認定を受けている人
介護保険被保険者証そのものには有効期限がありません。ただし、要介護認定や要支援認定には有効期間があります。
要介護認定や要支援認定の有効期間を過ぎてしまうと、介護サービスが利用できなくなります。そのため要介護認定や要支援認定を受けている人は、所定の期間内に更新手続きをしなければなりません。
要介護認定や要支援認定の有効期間は、次のとおりです。
新規・変更:原則として6ヶ月(状態により、3ヶ月~12ヶ月)
更新:原則として12ヶ月(状態により、3ヶ月~24ヶ月)
有効期限が満了する60日前頃に、更新のための書類が自宅に郵送されるため、早めに更新手続きをしましょう。なお、上記の期間に関わらず、期間中に身体の状態が変化したときは、変更申請ができます。
要介護・要支援認定が更新されると、新しい介護保険被保険者証が発行されます。
介護保険被保険者証の再発行手続き
介護保険被保険者証を紛失してしまったときや転居したときは、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
介護保険被保険者証を紛失した場合
介護保険被保険者証を紛失したときは、市区町村の介護保険担当窓口などで再発行手続きができます。本人が窓口まで行けない場合は、家族やケアマネージャーが代行できます。
再発行手続きには、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類が必要です。同一世帯の家族やケアマネージャーなどが手続きをするときは、本人確認書類に加え、委任状を添付します。
再発行手続きをすると、新しい介護保険被保険者証が交付されます。
住所変更した場合
住所を移転したときは、介護保険被保険者証も変更手続きをしなければなりません。転居先が同一市区町村の場合と、同一市区町村でない場合に分けて説明します。
同一市区町村内での転居
同じ市区町村内で転居したときは、市区町村役場の介護保険担当窓口で住所変更手続きをします。転居届を提出するときに、併せて手続きをするとよいでしょう。
同一市区町村外への転居
転出先が同一市区町村外の場合は、転出前と転入後に手続きをする必要があります。
転出前:
転出前の市区町村役場で、介護保険被保険者資格喪失手続きをし、介護保険被保険者証を返却します。このとき「受給資格者証」を渡されます。受給資格者証は転出先の市区町村役場で使用するため、紛失しないようにしましょう。
転入後:
転入先の市区町村役場に、転入から14日以内に「受給資格者証」を提出します。この手続きにより要介護認定が引き継がれるため、転入先の市区町村で改めて要介護認定を受ける必要はありません。手続き後、新しい介護保険被保険者証が交付されます。
介護保険被保険者証は介護サービス利用に必須
介護保険被保険者証は、介護保険の被保険者であることの証明書です。氏名や住所・被保険者番号・要介護度・受給限度額などが記載されていて、要介護認定やケアプラン作成、介護サービスを受けるときなどに使われます。
65歳以上の第1号被保険者には、全員に介護保険被保険者証が交付されます。一方、40歳から64歳までの第2号被保険者は、全員が介護保険被保険者証を交付されるわけではなく、加齢による特定疾病により要介護・要支援状態になったときにのみ交付されます。
住所を変更したときは、介護保険被保険者証についても手続きをする必要があります。紛失したときは再交付申請が可能です。介護保険被保険者証は大切に保管し、必要な介護サービスを円滑に利用しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
生命保険への加入は必要?社会保険をはじめとする社会保障制度との違いも解説!
日本では、9割近い世帯が生命保険に加入しているといわれています。テレビでも、生命保険のCMを見ない日はありません。 これほど普及している生命保険ですが、本当に加入する必要があるので…
詳しくみる社会保険料率(健康保険・厚生年金保険)の確認方法は?保険料額表の見方や計算方法を解説
健康保険料や厚生年金保険料の計算の根拠となる、保険料率の確認方法をご存知でしょうか。保険料率は、お住まいの地域や加入している健康保険組合によって異なり、年度ごとに改定されるため、定…
詳しくみる労災保険の休業補償給付を請求する際に医師の証明は必要?請求時に必要な書類も解説
休業補償給付とは、業務上のケガや病気が原因で休業する場合に、休業日の収入の一部を補填するための給付です。休業補償給付をスムーズに受け取るには、医師の証明が必要かどうかを含め、手続き…
詳しくみる育児休業給付金の計算方法 – いつの給与までが対象になる?
育児休業は、子どもが1歳(一定の条件を満たした場合は2歳まで)取得できます。また、育児休業期間中は通常、給与は無給になりますが、雇用保険から育児休業給付金を受けることができます。 …
詳しくみる医療保険とは?社会保険との違いはある?
「医療保険」や「社会保険」という言葉をよく耳にしますが、その違いについて意識して考えたことがない方は多いのではないでしょうか。 医療保険は保険制度の名称ですが、社会保険は医療保険を…
詳しくみる社会保険における健康保険とは
業務外で病気やけがをしたとき、またはそのために休業してしまったときに頼れる公的な医療保険制度が社会保険制度のひとつである健康保険です。出産時や死亡時にも給付金を受け取れます。 整理…
詳しくみる