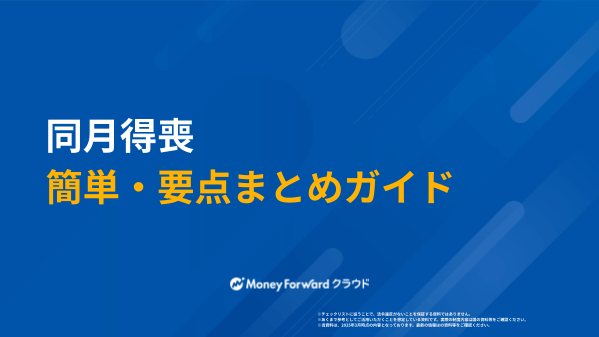- 更新日 : 2025年12月11日
同月得喪における社会保険料を解説!厚生年金や健康保険の保険料はどうなる?
会社は、要件を満たした人を社会保険に加入させます。会社は社員に長く働いてもらいたいのですが、実際は1ヵ月未満など、短期間で退職する人も出てきます。その際に社会保険の同月得喪が生じる場合があります。
今回は、社会保険の同月得喪の定義や概要と、同月得喪が生じた場合に厚生年金や健康保険の保険料がどうなるのかについて解説します。
目次
同月得喪とは
社会保険の同月得喪とは、同月内に社会保険の資格取得日と資格喪失日があることを言います。
ただし、あくまで同じ月内で資格取得日と資格喪失日が発生することが前提です。例えば、退職日が月末である場合は、資格喪失日は翌月1日になってしまうため、同月得喪は成立しないことに注意してください。
同日得喪との違い
「同月得喪」と似たような言葉に「同日得喪」があります。同日得喪とは、60歳以上で退職し、退職後に1日の空白もあけることなく継続して再雇用される場合に雇用関係が一度中断したとして資格喪失と資格取得を行う手続きです。
同月得喪は同月内での資格取得・喪失の手続きですが、同日得喪は同日での資格喪失・取得という違いがあります。
同月得喪が発生するケース
同月得喪が発生するケースとして、例えば、12月1日に入社し社会保険の資格を取得したけれども、12月20日に退職し資格を喪失した場合が挙げられます。この場合、被保険者資格を取得した月に資格を喪失していますので、同月得喪が生じていることになります。
これが、例えば、上記と同じ12月1日に社会保険の資格を取得し、12月31日に退職して資格を喪失した場合には、入社日、退職日は同じ12月ですが、資格取得日、資格喪失日で見ますと、月をまたぐ形になるため同月得喪にはならないのです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
同月得喪が生じた場合の厚生年金保険料
厚生年金保険の資格取得月と同月に資格喪失した際、すなわち、同月得喪が生じた場合は厚生年金保険料の納付が必要になります。
厚生年金保険料の被保険者負担分は退職の際の給与から控除され、会社が被保険者負担分と会社負担分を併せた厚生年金保険料を翌月末までに日本年金機構に納付することとなります。
ただし、同月得喪が生じた場合でも、月末時点で別の年金の被保険者になっていた場合には例外があります。
厚生年金保険料について資格喪失者が同月内に別の年金の被保険者となったとき
同月得喪が生じた人が、同じ月に厚生年金保険の資格、もしくは第2号被保険者を除く国民年金の資格取得があった場合はどのように処理するのでしょうか?
先に厚生年金保険の資格を喪失した会社では、その人が同月末までに別の年金の被保険者になるかどうかがわからないため、資格を喪失した会社の分の厚生年金保険料を徴収します。
その後、その人に、同じ月に厚生年金保険の資格、もしくは第2号被保険者を除く国民年金の資格取得があった場合、その制度に合わせた保険料を納付します。
この場合、年金事務所の手続きを経て先に喪失した会社に厚生年金保険料が還付されますので、本人負担分は会社から被保険者に還付されることになるのです。
これは、保険料の二重払いをしないようにするためです。
同月得喪が生じた場合の健康保険料
健康保険料に関しては、厚生年金保険料と違って同月得喪の場合でもその月の健康保険料の納付が必要になります。健康保険料の納付が必要になるというところが厚生年金保険料と異なりますので注意してください。
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書の無料テンプレート
以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。
同月得喪について再確認しておきましょう
社会保険の同月得喪が生じる場合のケースと同月得喪が生じた場合の厚生年金保険料、健康保険料の取り扱いについて見てきました。あまり取り扱うことがないと思われるケースですので、知らない方もいるかもしれません。
同じような場合にどのように対応すればよいのか、また、該当するケースが生じた場合に社員に正確な説明ができるように再度確認しておきましょう。
よくある質問
同月得喪とはなんですか?
同月得喪とは、同月内に社会保険の資格取得日(入社日)と資格喪失日(退職日の翌日)があることを言います。ただし、資格喪失日は退職日の翌日となってしまうため、退職日が月末の場合は同月得喪は成立しません。詳しくはこちらをご覧ください。
同月得喪と同日得喪の違いについて教えてください。
同月得喪は同じ月内で資格取得・喪失が生じる手続きですが、同日得喪は60歳以上で退職し、退職後に1日の空白もあけることなく継続して再雇用する際に資格喪失・取得を同日に行う手続きのことを言います。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
住宅手当は社会保険料に含まれる?社宅と比べてどちらが安いか解説【無料テンプレートつき】
住宅手当は、従業員が支払う家賃等を補助する制度です。手当は社会保険料を計算する際に含まれる場合と含まれない場合があります。また、住宅手当と似た制度に社宅がありますが、両者はどのよう…
詳しくみる労災保険の時効は2年?5年?申請期限と延長ができるケースを解説
労災保険の申請には期限があります。申請が遅れると、受け取れるはずの給付金が受け取れなくなることもあります。この記事では、労災保険の時効について、具体的な期限や起算日の数え方、時…
詳しくみる社会保険の事業主負担率はいくら?計算式と注意点をわかりやすく解説
企業の経営者や担当者にとって、社会保険料の事業主負担は避けて通れない重要なコストです。「社会保険の事業主負担率は何パーセント?」「給与40万円の従業員だと、会社の負担はいくらになる…
詳しくみる扶養手当不支給証明書とは?書き方や記入例、提出先、注意点を解説
扶養手当不支給証明書は、扶養手当制度を設けている企業が、従業員に対して扶養手当を支給していないことを証明する社内書類です。共働き世帯では、配偶者の一方が手当を受給している場合、もう…
詳しくみるパート・アルバイトの社会保険
一定の要件を満たせば、パート・アルバイトであっても、社会保険に加入することはできます。しかし、会社によって対応はまちまちで、なかには正社員でなければ社会保険の手続きをしてもらえない…
詳しくみる高額療養費(高額医療費支給制度)とは?社会保険の観点から仕組みを解説!
「高額療養費制度」とは、高額な医療費負担を軽減するための制度で、医療機関で支払った自己負担額のうち限度額を超えた額が手続きによって還付されたり、事前申請によって支払わずに済んだりし…
詳しくみる