- 更新日 : 2025年11月6日
12月入社の人の年末調整は必要?
12月入社の従業員の年末調整は、給料が当月支給で12月に給料支払いがある場合、ほかの社員と同じように行う必要があります。給料が翌月支給で12月に給料支払いがない場合は、年末調整は行いません。代わりに12月入社従業員に対して確定申告が必要なことを伝え、スムーズに手続できるよう援助することが求められます。
12月入社の人の年末調整は必要?
毎年12月に従業員に給料を支払う際は、年末調整を行わなければなりません。当然、その年に入社した社員についても4月入社の新入社員か、ほかの月に入社した中途採用の社員かを問わず、年末調整の対象とする必要があります。しかし、12月入社の社員については給与支給のタイミングとの関係で、以下のように対応が異なります。
12月の給与が翌月支給の場合
給料は、支払いをもって金額が確定します。12月に働いた分であっても支払いがされなければ、所得税を払わなければならない給与所得は発生していないことになります。1月に支払われる12月分給与は12月が属する年ではなく、1月の属する年の給与所得として年末調整を行うことになります。
12月入社の社員には、12月に働いた分の給料が支払われます。しかし、翌月払いとしている会社では、12月分の給与は来年の1月に支払うことになり、12月に給料は支払われません。このケースでは12月入社の社員は年末調整の対象にはなりません。
したがって給与を翌月支給としている会社において12月入社の社員に給与所得は発生せず、年末調整の対象にも該当しないことになります。12月入社の社員には、自身で確定申告をして所得税の精算をしてもらいます。
12月の給与が当月支給の場合
給与を翌月支給としている会社では、12月入社の社員の年末調整は対象外として取り扱われますが、給与を当月支給としている会社では、12月入社の社員の年末調整は対象となります。
給与支給が当月中に行われる会社では、12月分の給与は12月中に支払われ、12月入社の社員に対しても12月に働いた分の給与が12月に支払われます。そのため、その会社でその年に年末調整をすべき給与所得が発生し、年末調整を行う必要が生じるのです。
12月入社の社員の年末調整をするためには、迅速に必要な書類の提出を受けることが大切です。基礎控除等申告書や扶養控除等申告書、生命保険料控除申告書といった年末調整の書類を、速やかに記入のうえ提出してもらう必要があります。また前職の源泉徴収票の提出を受け、記載内容を加味して年末調整を行うことも忘れないようにしなければなりません。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
送付状テンプレ集 36選パック-時候の挨拶×12か月分(上旬・中旬・下旬)
こちらは「送付状テンプレ集 36選パック」です。 12か月分の上旬・中旬・下旬、それぞれの時期に対応した時候の挨拶が含まれています。
季節や時期に応じた送付状を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。
電子契約にも使える!誓約書ひな形まとめ
誓約書のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。資料内から任意のひな形をダウンロードいただけます。
実際の用途に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
人事・労務担当者向け Excel関数集 56選まとめブック
人事・労務担当者が知っておきたい便利なExcel関数を56選ギュッとまとめました。
40P以上のお得な1冊で、Excel関数の公式はもちろん、人事・労務担当者向けに使い方の例やサンプルファイルも掲載。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。お手元における保存版としてや、従業員への印刷・配布用、学習用としてもご活用いただけます。
12月入社で年末調整ができない場合は確定申告で対応
給与を翌月支給としている会社では、12月入社の社員は年末調整の対象外となります。転職での12月入社で以前に雇用されていたとしても、前職の会社で年末調整を行ってもらうことはできません。このようなケースでは、転職前の会社でも転職後の会社でも年末調整の対象者となることはできないため、所得税の精算には確定申告が必要です。その旨を案内し、スムーズに確定申告ができるようサポートすることが大切です。
確定申告について従業員に案内することが望ましい内容は次の通りです。
| 確定申告の実施時期 | 毎年2月16日から3月15日まで (3月15日が土曜日・日曜日の場合は月曜日まで) |
| 申告場所 | 1.住所を所轄する税務署 2.特設会場が設けられる場合もあり 3.郵送・インターネットでの申告も可 |
| 必要書類 | 各種控除申告書や証明書類、前職の源泉徴収票など |
確実な所得税徴収を目的に、毎月の給料からは多めに源泉徴収されています。年末調整を会社で受けられない転職者は確定申告をしない限り、多く徴収された所得税を取り戻すことはできません。12月入社の社員が不利益を被らないために、きちんと確定申告を行うよう援助することが必要です。
12月入社の人の年末調整は給与の支給方法によって違う
12月入社の社員の年末調整は、給与の支給方法にとって異なります。給与を翌月支給としている会社では12月入社の従業員は対象外となり、年末調整は行われません。当月支給としている会社では年末調整を行う必要があります。
年末調整を行わない場合、12月入社の社員は自分自身で確定申告しなければ多く徴収されている所得税を取り戻すことはできません。会社には12月入社の従業員が不利益を被らないため、確定申告について援助することが求められます。
よくある質問
12月入社の社員は年末調整の対象になりますか?
12月入社の社員は給与が当月支給の会社では年末調整の対象となりますが、翌月支給の会社では年末調整の対象となりません。詳しくはこちらをご覧ください。
12月入社の社員で年末調整できない場合は、どうしたらよいのでしょうか?
社員自身が確定申告を行い、会社には情報提供やサポートが求められます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
12月支給の賞与で年末調整を処理する場合の方法と注意点
年末調整は、1年の最後の給与支払となる12月給与で行われることが一般的ですが、12月支給の賞与で行われる場合もあります。年末調整のやり方自体は、賞与でも給与でもあまり変わりませんが…
詳しくみる【2026年最新】源泉徴収票の見方とチェックすべき項目を解説!
年末になると、会社から発行される源泉徴収票。その中身を理解しているかと聞かれたら、自信がない方が多いと思います。 サラリーマンの大半は、自分自身で税金の計算を行う場面がほとんどない…
詳しくみる遺族年金に年末調整は必要?
受け取った遺族年金による年金収入は非課税であるため、年末調整は原則不要です。また、扶養に入るためには年間所得が一定額以下である必要がありますが、税法上、遺族年金はこの所得に含まれま…
詳しくみる年末調整の収入金額とは?所得金額との違いや計算方法を解説!
年末調整の時期になると、会社から申告書類が配布され記入して提出します。 申告書には収入金額の記入欄がありますが、「収入金額」「総支給額」のどちらを記入するかで悩んだことはありません…
詳しくみる支払調書の発行が必要な事例と書き方とは?受け取る側の注意点とは
源泉徴収票は知っていても、支払調書という書類はあまり馴染みがないという方は多いのではないでしょうか。支払調書は法人又は個人事業主が、一定の場合には税務署への提出が必要となる法定書類…
詳しくみる年末調整での社会保険料控除を解説!控除対象や計算方法を紹介
会社の担当者は、年末調整が終了した際、源泉徴収票を作成します。その源泉徴収票にある社会保険料控除の金額は、会社が従業員に給与を支払う際に控除した社会保険料だけではありません。 今回…
詳しくみる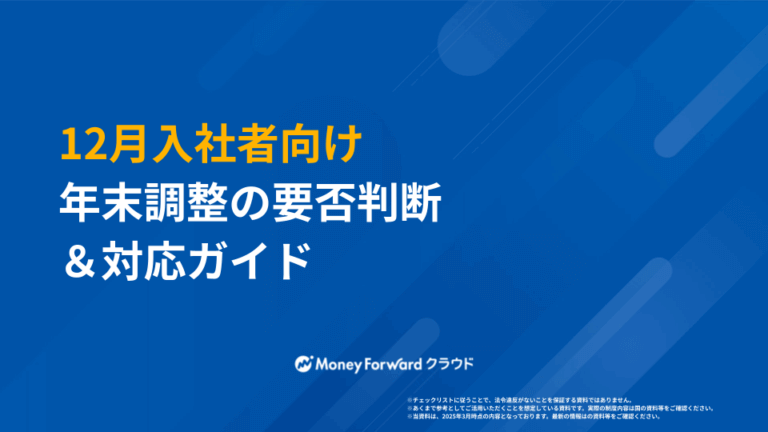
.png)


