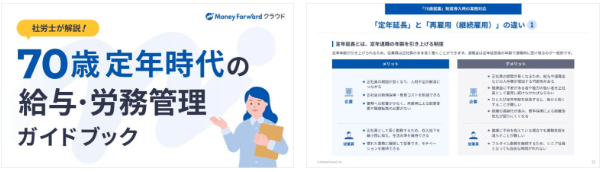- 更新日 : 2024年12月27日
改正高年齢者雇用安定法(2021年4月施行)とは?改正ポイントを徹底解説!
少子高齢化が進む中、働く意欲がある人が年齢にかかわらず活躍できる社会を実現すべく、2021年4月に高年齢者雇用安定法が改正されました。企業は定年の引き上げや70歳までの就業確保措置など、さまざまな努力義務を果たす必要があります。
高年齢者雇用安定法はどのように変わったのでしょうか。高年齢者雇用安定法改正の背景や、ポイントについて解説します。
目次
改正高年齢者雇用安定法(2021年4月1日施行)とは?
高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)は、高年齢者(55歳以上)の雇用機会を守るために制定された法律です。定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、高年齢者の雇用や再就職の促進、その他高年齢者に対する就業機会の確保について定められています。
これまでの高年齢者雇用安定法との違い
今回の改正の大きなポイントは、65歳から70歳までの就業機会が確保されたことです。当該労働者を60歳まで雇用していた事業主は、以下のいずれかの措置を講じることが努力義務となります。
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度や勤務延長制度など)
- 70歳までの継続的に業務委託を締結する制度の導入
- 70歳までに事業主が自ら実施する社会貢献事業もしくは事業主が委託、出資等をする団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入
詳細については後ほど詳しく説明しますが、働ける年齢が65歳から70歳に引き上げられることが最大のポイントといえます。
高年齢者雇用安定法改正の背景
なぜ高年齢者雇用安定法が改正されることになったのでしょうか。その背景にあるのは、「少子高齢化」と「一億総活躍時代」という2つのキーワードです。
労働者人口が減少する中で経済成長を続けていくためには、高齢者の方の活躍が必要不可欠です。高年齢者にとっても、元気で働く意欲があるのにも関わらず、定年で働けなくなってしまうのは本意ではないでしょう。特に安倍政権下では、日本国民の誰もが活躍できる「一億総活躍社会の実現」をスローガンとし、高齢者の就業促進に力を入れてきました。
「働く意欲がある人は、年齢に関わらず能力を十分に発揮してほしい」「高年齢者の方にもどんどん活躍してほしい」という考えから、高年齢者雇用安定法が改正されたのです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
70歳定年時代の給与・労務管理ガイドブック
高年齢者雇用安定法の改正で「70歳まで働く時代」が到来しています。
本資料では70歳就業制度導入時の実務対応をはじめ、定年延長・再雇用で給与を見直す際のポイント、健康管理・安全衛生管理で配慮すべきことをまとめました。
シニア社員の給与を見直すときにやってはいけない5つのこと
少子高齢化による人口減少が社会問題となっている今、60歳以上の雇用が企業の課題となっています。
本資料ではシニア社員を取り巻く環境変化を説明するとともに、定年延長や再雇用で給与を見直す際の注意点をまとめました。
同一労働同一賃金 対応マニュアル
働き方改革の推進により、正規社員と非正規社員の待遇差解消を目的とする「同一労働同一賃金」への対応が企業に求められています。
本資料では適切な対応方法を示しながら、非正規社員の給与見直しの手順を解説します。
改正高年齢者雇用安定法のポイントは?
高年齢者雇用安定法の改正について簡単に説明しましたが、具体的には何が変わったのでしょうか。また、企業はどのように対応すべきなのでしょうか。ここからは、改正高年齢者雇用安定法の内容を見ていきましょう。
ポイントは、大きく分けて「高年齢者就業確保措置」「70歳までの継続雇用制度」「創業支援等措置」の3点です。
高年齢者就業確保措置
高年齢者就業確保措置は、「定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主」もしくは「65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主」が、業者に対して行わなければならない措置です。高年齢者就業確保措置に関しては「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の第10条の2に記載されています。
参考:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律|e-Gov法令検索
対象となる事業主は、以下のいずれかの措置を講じることが努力義務として課せられます。
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度
- 70歳までの継続的に業務委託を締結する制度の導入
- 70歳までに事業主が自ら実施する社会貢献事業もしくは事業主が委託、出資等をする団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入
上記の1.~3.が、高年齢者就業確保措置にあたります。
従来の高年齢雇用措置では定年引き上げ、継続雇用制度ともに65歳までが対象でしたが、今回の改正で70歳までに引き上げられました。企業においては定年制度そのものをなくすか、定年年齢を70歳にする、もしくは定年年齢を現状のままにして、それを過ぎたら70歳まで再雇用や勤務延長で雇い続け、雇用機会を設けるようにするとよいでしょう。
- 70歳までの定年引き上げ
企業の対応としてまず考えられるのが、定年年齢の引き上げです。定年を70歳まで引き上げる場合は、就業規則に定年年齢について記載されていればそれを変更し、全従業員一律で70歳まで雇い続ける必要があります。給与や退職金、役職定年などの社内制度も見直す必要があるでしょう。
- 定年制の廃止
定年という制度そのものを撤廃することで、改正高年齢者雇用安定法に対応することもできます。定年制度がある場合は就業規則を変更し、社内制度を見直す必要があるでしょう。定年制を廃止すれば、働ける間は70歳であろうと80歳であろうと、いつまでも働いてもらうことができます。逆に言えば、従業員が自ら退職の意思を示さない限り、雇用契約を一方的に終了することはできません。当該従業員の健康や安全に配慮し、高年齢者でも働ける環境を整備する必要があるでしょう。
70歳までの継続雇用制度
定年の引き上げや定年制の廃止を行わない場合は、継続雇用制度を選択するという方法もあります。例えば、定年年齢が65歳で、当該従業員が65歳以降も働く意思がある場合は、再雇用制度や就業延長制度などを使って雇用の継続に努めましょう。また、事業主自身が継続して雇用することも、グループ会社や子会社、関連会社といった特殊関係事業主が雇用することもできます。
創業支援等措置
今回の改正では、高年齢者に対する創業支援措置も新たに盛り込まれました。具体的には、前述の「④70歳まで継続的に業務委託を締結する制度の導入」です。従業員として雇用契約を結んで働くのではなく、高齢の元従業員がフリーランス・自営業者という立場になり、業務委託契約を結んで働けるようにするための措置です。労働者にとっては勤務時間に縛られない、副業ができる、体力に合わせて無理なく仕事ができるというメリットがあり、事業者側には繁忙期など、必要に応じて業務を委託できるというメリットがあります。
また、「⑤70歳までに事業主が自ら実施する社会貢献事業もしくは事業主が委託、出資等をする団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入」も創業支援措置に含まれます。「社会貢献事業」は「不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業」とされていますが、どのような事業が社会貢献事業に該当するかは事業主の判断に任されています。
改正高年齢者雇用安定法における努力義務とは?
改正高年齢者雇用安定法では、上記のような措置を講じることを努力義務として事業主に課しています。この「努力義務」とは、何でしょうか。守らない場合、ペナルティなどはあるのでしょうか。ここからは、改正高年齢者雇用安定法における努力義務について考えていきます。
努力義務と義務の違いは?
「義務」は「必ず行わなければならないこと」を指す言葉です。法律で「義務」と書かれている場合は「法的義務」を指します。法的義務は、法令あるいは当事者の法律行為(契約など)に基づいて生じ、不履行の場合には国家権力等によって履行が強制され、違反した場合は制裁されることもあります。例えば、道路交通法では信号に従って通行しなければならないという義務が定められていて、それを守らないと反則金や罰金、懲役刑などの刑罰あるいは行政罰が科せられます。
努力義務とは強制力を伴わず、その名のとおり当事者の努力を促すことを指します。義務の場合、法律の条文には「~しなければならない」と書かれますが、努力義務の場合は「~するよう努めなければならない」と書かれるケースが多いです。
努力義務違反による罰則は?
努力義務には強制力がないため違反しても罰則はありませんが、守らなくても構わないということではありません。努力義務を怠ると、監督官庁(ハローワーク等)から指導・助言を受けることがあります。
改正高年齢者雇用安定法による企業への影響は?
改正高年齢者雇用安定法によって、企業はさまざまな影響を受けると考えられます。定年年齢を引き上げると従業員が増えるため、人件費が増加します。そして、高年齢者の能力を活かしつつ業績を伸ばせるよう、さらなる企業努力が求められます。人材配置についても、これまでの経験や知見が活かせるように、健康面や安全面を考慮しながら決めるとよいでしょう。
高年齢者が働きやすい職場環境の整備も求められます。椅子などを用意して立ち仕事を軽減する、移動の手間を省けるよう資材や機材を配置するといった物理的な環境整備のほか、休憩時間や就業時間などの就業規則も必要に応じて見直したほうがよいでしょう。
改正高年齢者雇用安定法に関連する助成金は?
国は単に高年齢者雇用安定法を改正して、事業主に努力義務を課すだけではありません。事業主が環境を整備して、高年齢者の雇用が確保できるよう助成制度を用意しています。厚生労働省が所管する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では「65歳超雇用推進助成金」として、3種類の助成コースを設けています。
65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引き上げなどの高年齢雇用措置を講じている事業主を助成するコースです。受給要件は以下の3点です。
- 労働協約または就業規則により一定の新しい制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届け出た事業主であること
- 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し経費を支出したこと
- 高年齢者雇用推進者の選任および所定の高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること
対象被保険者数と定年などを引き上げる年数によって受給金額が異なり、最大160万円(対象被保険者が10人以上で70歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を行った事業主の場合)の助成金を受け取ることができます。
参考:65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)令和3年4月以降申請分|独立行政法人高齢・障害者・求職者雇用支援機構
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年齢未満の有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して支払われる助成金です。
受給要件は以下の2点です。
- 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画(以下「無期雇用転換計画」とする)を作成し、高齢・障害者・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
- 1.の無期雇用転換計画に基づき、当該無期雇用転換計画期間内に、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
支給額は対象労働者1人あたり48万円(中小企業事業主以外は38万円)、生産性を向上させた事業主に対しては1人あたり60万円(中小企業事業主以外は48万円)が助成されます。
参考:65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)|独立行政法人高齢・障害者・求職者雇用支援機構
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用促進を図るために賃金や人事処遇、労働時間、健康管理など雇用管理制度の整備にかかる措置を実施した事業主を助成する制度です。
受給要件は以下の2点です。
- 高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入)」を内容とする「雇用管理整備計画」を作成し、高齢・障害者・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
- 1.の雇用管理整備計画に基づき、当該雇用管理整備計画の実施期間内に「雇用管理整備措置」を実施し、措置の実施状況を明らかにする書類を整備していること。また、雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備し、支給対象被保険者が1人以上いること
支給対象経費に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額が支給されます。なお、生産性要件を満たしている場合は、支給対象経費に75%(中小企業事業主以外は60%)を乗じた額が支給されます。
参考:65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)|独立行政法人高齢・障害者・求職者雇用支援機構
自社の状況に合わせて高年齢者雇用安定法への対応を行いましょう!
高年齢者雇用安定法が改正されたことで、企業は70歳までの定年の引き上げや定年制の廃止、70歳までの継続雇用制度、創業支援措置などを講じ、高年齢者の雇用を維持する努力義務が生じます。これによって、就業規則や社内制度、組織体制などを見直す必要があるかもしれません。
一億総活躍時代の今、高年齢者の経験や知見をいかに活用できるかが業績アップのカギとなりそうです。これを機会に高年齢者雇用安定法にしっかり対応し、高年齢者の方も働きやすい環境を整えましょう。
よくある質問
高年齢者雇用安定法はどのような点が改正されましたか?
70歳までの定年引き上げ、定年制の廃止、70歳までの継続雇用制度など、高年齢者が働きやすい措置を講じることが努力義務となりました。詳しくはこちらをご覧ください。
高年齢者雇用安定法を守らないとどうなりますか?
努力義務なので刑罰などはありませんが、監督官庁(ハローワーク等)から指導・助言を受けることがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
兼業とは?副業との違いやメリット・デメリット、注意点を解説!
兼業とは、本業と同等の他の仕事を掛け持ちすることです。兼業の働き方は、企業などに雇用されるものや、起業して事業主として働くものなど様々です。本記事では、兼業とは何かや副業との違い、…
詳しくみる【2025年最新】勤怠管理の法律で守るべき義務・労働基準法の改正点まとめ
企業は従業員を雇用する際に、労働基準法にしたがって正確な勤怠管理を行う義務があります。 しかし、近年は働き方改革による法改正にともない、勤怠管理のあり方も変化しています。 そのため…
詳しくみる【無料テンプレート付】残業届とは?目的やルールも解説!
長時間労働を削減するために、残業届の導入を検討している企業も多いのではないでしょうか。残業を申請制にすることで残業を行うハードルが上がり、不要な残業を予防できます。残業申請制はただ…
詳しくみる労務担当者必見!作成した就業規則の届出義務とは?
就業規則の作成・届出義務とは? 原則として常時10人以上の労働者を使用している事業場では、会社の規則を明文化した就業規則の作成および管轄の労働基準監督署への届出が必要となります。 …
詳しくみる出張中の残業に残業代は出ない?移動時間や休日の扱いについて解説!
出張中に所定時間外の労働を行った場合、残業代が支給されるにはいくつかの条件があり、出張に伴う移動時間も労働時間にはカウントされません。労働者としては、出張中でも残業をしたら残業代を…
詳しくみるアニバーサリー休暇とは?メリット・デメリットや導入事例について解説
「社員のモチベーションを上げたい」「働きやすい職場環境を作りたい」 上記のような課題を抱える企業におすすめなのが、アニバーサリー休暇です。 従業員が誕生日や結婚記念日などの特別な日…
詳しくみる