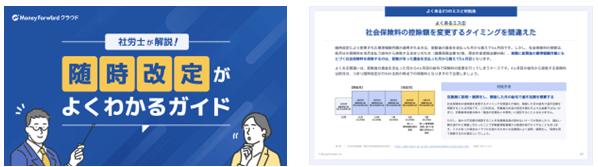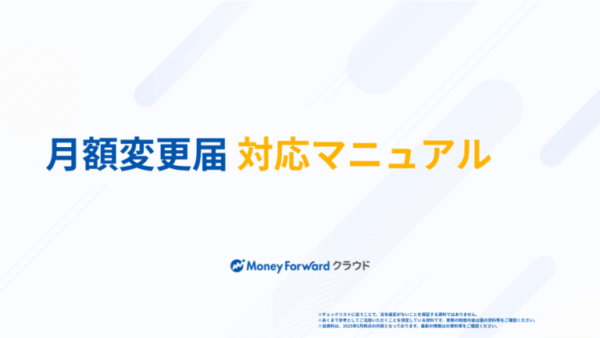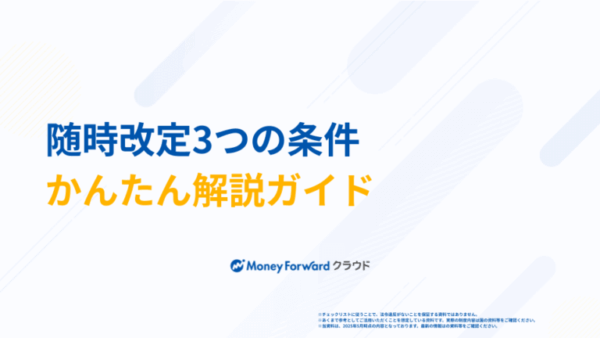- 更新日 : 2025年11月15日
社会保険の月額変更届(随時改定)を忘れたらどうなる?罰則や遡及適用について解説
月額変更届(随時改定)は、従業員の給与に大きな変動があった際に必要です。しかし、もし提出を忘れてしまうと、社会保険料の過不足が発生し、罰則やトラブルの原因になる可能性があります。
本記事では、月額変更届を出し忘れた際の影響や罰則、遡及適用について解説します。
目次
月額変更届(随時改定)とは?
月額変更届とは、従業員の給与に大きな変動があった際に、社会保険料の基礎となる「標準報酬月額」を変更するために提出する書類です。この手続きのことを「随時改定」といいます。
正式名称は「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」です。
社会保険料は、標準報酬月額の等級に応じて決定されています。給与の変動によって、この等級が2等級以上変動した場合は、一定の条件を満たせば随時改定が必要です。
正しく届け出ることで、保険料の過不足を防ぎ、従業員の社会保険記録を正確に保てます。
以下の記事では、月額変更届について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
月額変更届の提出基準
月額変更届(随時改定)は、次の3つの条件をすべて満たした場合に提出が義務付けられています。
- 昇給または降給などにより、固定的賃金に変動があったこと
- 固定的賃金の変動月から3ヶ月間に支給された報酬の平均額にもとづき、標準報酬月額を算定した場合に2等級以上の変動があったこと
- 3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であること
これら3つをすべて満たすことで、月額変更届の提出が求められ、社会保険料の調整が行われます。
以下の記事では、随時改定を行う条件について詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。
提出期限と手続きの流れ
月額変更届は、随時改定が必要となったタイミングで、速やかに提出することが求められています。
提出先は、事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センターです。どちらに提出しても構いませんが、事務センターに提出する方が処理時間は一般的に短くなります。また、健康保険が協会けんぽ以外(組合健保・共済組合など)の場合は、所属する組合にも提出が必要となります。
提出方法は、窓口での提出、郵送、または電子申請から選択可能です。なお、資本金1億円超の法人や投資法人などの一部企業は、法令により電子申請が義務化されているため、オンラインでの手続きが必須です。
提出が遅れると、新しい標準報酬月額の適用が遅れ、保険料の過払いや未払いが発生するリスクがあります。そのため、給与に変動があった際は、条件を満たしているかを早急に確認し、スムーズに手続きを進めましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
随時改定がよくわかるガイド
月額変更届の手続き(随時改定)は、一定の要件を満たす従業員を対象にその都度対応が必要になります。
この資料では、随時改定の基本ルールと手続き方法に加え、よくあるミスの対処方法についても解説します。
月額変更届 対応マニュアル
従業員の報酬が変動した際、「月額変更届」の提出が必要となる場合があります。
本資料は、「月額変更届」に関する対応マニュアルです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きの実務にお役立てください。
随時改定3つの条件 かんたん解説ガイド
社会保険料の標準報酬月額を見直す「随時改定」は、実務上、正確な理解が求められます。
本資料は、「随時改定」の対象となる「3つの条件」について、かんたんに解説したガイドです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きにおける実務の参考としてご活用ください。
月額変更届を出し忘れた場合の罰則・影響
月額変更届(随時改定)の提出を忘れてしまうと、保険料の過不足だけでなく、年金事務所からの指摘や従業員とのトラブルなどのリスクがあります。
ここでは、月額変更届を出し忘れた場合の罰則・影響を解説します。
社会保険料の未収や過払いが発生する可能性
月額変更届を提出しないまま放置すると、標準報酬月額が正しく変更されず、本来支払うべき社会保険料と実際に徴収された保険料に差が生じます。その結果、下記のような問題が発生するおそれがあります。
- 事業主・従業員ともに、本来納めるべき社会保険料を支払っていない状態になる
- 会社が年金事務所から指摘を受け、未払い分を追加徴収されるリスクがある
- 未納期間が長期にわたると、最大で過去2年間遡って徴収される可能性がある
- 事業主と従業員が、本来支払わなくてもよい社会保険料を負担してしまう
- 従業員にとっては手取り給与の減少につながるため、不満が生じる可能性がある
- 過去分の保険料を精算する手続きが必要となり、事務負担が増える
提出忘れは金銭的・業務的な負担を招くため、早期に気づき、適切に対応することが大切です。
以下の記事では、社会保険についてわかりやすく解説していますので、あわせて参考にしてください。
年金事務所から指摘・調査される可能性
年金事務所(日本年金機構)は、社会保険の適切な運用を監督する役割をもっています。月額変更届の提出がなされていないと、下記のような対応をとられることがあります。
| 対応 | 詳細 |
|---|---|
| 行政調査のリスク | ・年金事務所の職員が事業所へ立ち入り調査を行うことがある ・調査の結果、未納の社会保険料が判明した場合、過去2年分を遡って徴収される ・企業側の対応が不十分だと、監督官庁からの指導や是正勧告を受ける可能性がある |
| 修正届出の要求 | ・過去の給与変動を確認し、未提出の月額変更届を提出し直す必要がある ・追加徴収された社会保険料は、事業主と従業員の双方が負担する ・従業員とのトラブルにつながる可能性がある |
こうした指摘が繰り返されると、企業の信頼性にも影響を与えかねません。そのため、日頃から正確な手続きを心がける必要があります。
従業員とのトラブルにつながるリスク
月額変更届の提出忘れは、企業だけでなく、従業員にも直接的な影響を及ぼします。場合によっては、企業と従業員との間でトラブルに発展してしまうため、注意が必要です。
企業があとから月額変更届を提出し、遡及適用されると、従業員の給与から追加で社会保険料が徴収されます。「なぜ今になって多く引かれるのか」と従業員が納得できず、企業への不信感が生じるでしょう。
また、社会保険料の未納期間があると、従業員の将来の年金受給額に影響が出る可能性があります。
従業員の生活に関わる重要な制度なため、正確な保険料計算と手続きが求められるでしょう。このようなリスクを避けるためには、日頃から給与の変動に注意を払い、必要な手続きを怠らないことが企業の責任です。
法令違反として罰則を受ける可能性
月額変更届を提出しないことは、法的にも問題になる場合があるため、注意が必要です。健康保険法第48条および厚生年金保険法第100条では、事業主に対し、正確な報酬月額の届出が義務付けられています。
もし意図的に届出を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。悪質と判断されたら、社会保険適用事業所の資格を取り消される場合もあるため、注意しましょう。
ただし、単なる提出忘れや軽微なミスについては、早期に修正手続きを行うことで大きな問題には発展しないケースが大半です。とはいえ、法令にもとづく義務である以上、手続きには常に注意を払い、正確かつ迅速な対応を心がけることが大切です。
月額変更届を出し忘れた場合、遡及適用はできる?
月額変更届の提出を忘れた場合でも、条件を満たせば過去に遡って標準報酬月額を修正する「遡及適用」が認められるケースがあります。健康保険法および厚生年金保険法にもとづき、原則として最大で過去2年分まで遡及適用が可能です。
一方で、2年以上前の給与変更については、基本的に遡及適用はできません。
なお、提出が大幅に遅れた場合には、「遅延理由書」の提出を求められる場合があります。企業に故意や悪意がなければ、必要な書類を整えたうえで適切に手続きを進めれば、遡及が認められるケースが大半です。
適用が認められたら、未払いの社会保険料があると追加徴収が発生し、従業員への精算対応が必要となります。反対に、過払いがあった場合は、翌月以降の保険料に充当するか、還付手続きを行います。
ただし、遡及手続きは煩雑になりがちです。トラブルや事務負担を避けるためにも、気づいた時点ですぐに手続きをはじめましょう。
月額変更届を出し忘れた場合の対応
月額変更届を出し忘れた場合、放置せずに早急な対応が求められます。
ここでは、提出忘れに気づいた際にとるべき具体的な対応について解説します。
速やかに年金事務所に連絡する
月額変更届の提出を忘れていたことに気づいたら、まずは管轄の年金事務所に速やかに連絡しましょう。提出が遅れたこと自体に罰則が課されるケースは少ないため、慌てる必要はありません
しかし、対応を後回しにするのは避けましょう。連絡の前に、下記の情報を整理しておくとスムーズです。
- 対象となる従業員の情報:氏名・被保険者番号・変更があった給与額など
- 変更の理由と発生日:昇給・降給などの経緯とタイミング
- 提出するべき書類の確認:遅延理由書が必要かどうかも含めて確認
これらの情報を用意したうえで年金事務所に相談し、指示にしたがって手続きを進めましょう。対応が早いほど、手続きや精算もスムーズに進みます。
必要な添付書類を揃える
月額変更届の提出が遅れたら、通常の提出書類に加えて追加書類が必要となるケースがあります。主な必要書類は、下記のとおりです。
| 必要書類 | 詳細 |
|---|---|
| 月額変更届 | 必須書類、標準報酬月額の変更内容を正確に記入 |
| 遅延理由書(必要な場合) | 提出が長期間遅れた場合(通常6ヶ月以上)に求められる 遅延の理由・遅延した期間・適用される従業員の情報を記載する |
| 適用理由の説明書(任意) | 遡及適用を求める場合は、理由や背景を明記した書類を添えるとよい |
書類に不備があると、再提出や追加資料の提出を求められ、手続きに時間がかかってしまいます。事前に年金事務所と確認をとりながら、漏れなく書類を準備しましょう。
従業員に説明する
月額変更届の出し忘れによって、社会保険料に過不足が生じた場合、従業員の給与に影響が出ることがあります。トラブルを防ぐためには、丁寧な説明と誠実な対応が必要です。
とくに、標準報酬月額が上がるケースでは、社会保険料の追加徴収が発生するため、従業員に納得してもらうことが大切です。給与変更の影響を受ける従業員に対して、手続きの遅れがあったこと、追加で社会保険料の支払いが発生する可能性があることを説明しましょう。
精算方法は従業員と相談し、以下のような選択肢を提示します。
- 翌月の給与で一括控除する
- 数ヶ月に分割して控除する
- 賞与から調整する
なお、従業員の同意なしに給与から追加控除を行うことは法律で認められていません。必ず同意を得たうえで、書面に記録を残しましょう。
また、標準報酬月額が下がるケースでは、過払い分の社会保険料の取り扱いについて、還付や充当の方法を検討する必要があります。保険料の修正は、所得税や年末調整にも影響を及ぼす可能性があるため、必要に応じて税務担当者とも連携しましょう。
従業員との信頼関係を損なわないためにも、事前に丁寧な説明を行い、従業員の負担を最小限に抑える形で対応することがポイントです。
月額変更届の手続きミスを防ぐ方法
月額変更届は、手続きが煩雑であるため、提出漏れや誤記入などのミスが起こりがちです。
ここでは、手続きミスを防ぐ方法を解説します。
社内の給与管理体制を見直す
月額変更届の手続きミスを防ぐには、まず社内の給与管理体制を見直しましょう。
とくに、下記の点を意識して改善を図ることが大切です。
- 給与変更のチェックリストを作成する
- 社内の担当者の役割を明確にする
- 手続きのスケジュール管理を徹底する
これらを徹底することで、手続きの漏れや遅れを未然に防ぎ、適切なタイミングで月額変更届を提出できる体制を整えられます。結果として、従業員との信頼関係の維持や、事務負担の軽減にもつながるでしょう。
給与システムやクラウドツールを活用する
手作業による管理は、ヒューマンエラーが発生しやすい課題があります。そのため、給与計算システムや、クラウド型の労務管理ツールの導入が効果的です。
給与計算システムには、「自動チェック機能」が搭載されているものもあり、提出忘れを未然に防げます。また、クラウド型の労務管理ツールでは、データが一元管理されるため、担当者間での情報共有もスムーズになります。
リマインダー機能を活用すれば、提出期限前にアラートを受け取れるため、提出漏れを防止できるでしょう。これらのシステムやツールをうまく活用すれば、業務の効率化だけでなく、月額変更届のミスを大幅に減らすことが可能です。
定期的な教育とWチェック体制を構築する
労務担当者や経理担当者の知識不足によるミスを防ぐためには、定期的な研修や勉強会を実施することが大切です。とくに、標準報酬月額の変更基準や、届出が必要なタイミングを正しく理解しておけば、ミスの発生を大きく減らせます。
また、ダブルチェック体制の構築も効果的です。月額変更届を提出する前に、別の担当者が書類を確認するようにすれば、記入漏れや誤記載を早期に発見し、修正が可能になります。
さらに、社会保険労務士(社労士)との連携を強化するのもおすすめです。社内で判断に迷う際に、社労士に相談すれば正確な対応ができるだけでなく、制度改正などの最新情報も入手しやすくなります。
このような体制を継続的に整えておくことで、担当者のスキル向上だけでなく、社内全体の労務管理の質を高められるでしょう。
月額変更届の提出漏れを防ぎ、適切な手続きを行おう
月額変更届の提出ミスは、企業と従業員の双方に不利益をもたらす可能性があります。日頃から給与管理体制の整備やツールの活用、教育体制の強化を行い、ミスを未然に防ぐことが大切です。
正確でスムーズな手続きを行い、企業の信頼と従業員の安心につなげましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
給付制限期間中のアルバイトは20時間以上働いても問題ない?注意点を解説
給付制限期間中に20時間以上アルバイトをすると雇用保険の加入条件を満たしてしまい、失業手当(失業給付)を受け取れなくなる可能性があります。 しかし、条件次第では失業手当を受け取りつ…
詳しくみる厚生年金保険料が引かれすぎ?計算方法を解説!
会社員に支払われる給与と賞与からは、所得税(源泉徴収税)などが差し引かれています。厚生年金保険料も控除されているものの1つで、給与からは標準報酬月額に厚生年金保険料率をかけた金額、…
詳しくみる社会保険料の対象者は誰?パートの加入条件から計算方法までわかりやすく解説
社会保険は、私たちの生活を支える重要な制度ですが、どのような人が社会保険料の対象になるのかは働き方によって異なります。正社員はもちろん、パートやアルバイトで働く方にとって、自分が加…
詳しくみる労災保険の給付期間や申請期限は?休業補償などの種類別に解説!
労災保険の給付には療養補償給付や休業補償給付、葬祭料などがあります。それぞれいつまで補償が受けられるのかに加え、申請可能な期限を確認しておきましょう。うつ病が労災認定されるまでには…
詳しくみる離職票の発行条件は?流れや日数、もらえない・やっぱり欲しい場合の対処法も解説
退職後の手続きで使う離職票。失業保険(基本手当)の受給に必要な書類ですが、自分の場合は発行されるのか、退職したのにいつまで経っても届かない、といった不安はありませんか。特に、失業保…
詳しくみる年金は何種類ある?厚生年金などの公的年金と私的年金の違い
一口に年金といっても、その種類はたくさんあります。国の制度である厚生年金などの公的年金だけでなく私的年金もあり、仕組みも複雑です。 本稿では年金の種類とともに、厚生年金などの公的年…
詳しくみる