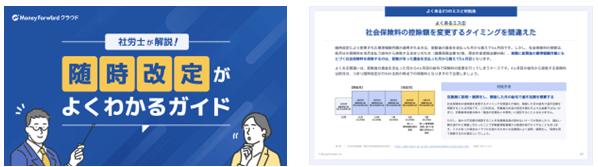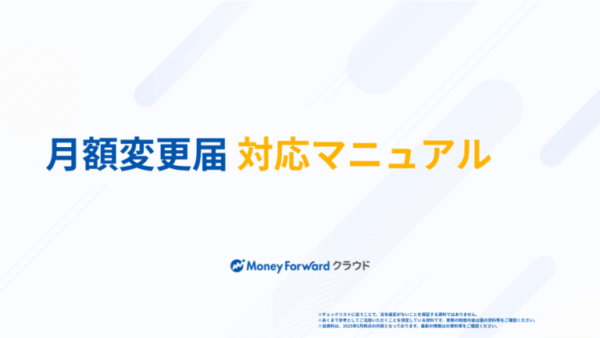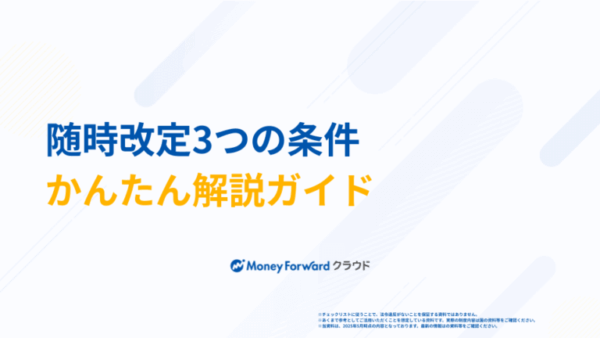- 更新日 : 2025年11月6日
社会保険の随時改定はいつから反映される?タイミングや手続き方法を解説
社会保険料を決定する際に用いられる「標準報酬月額」は、基本的には年1回の定時決定によって見直されます。しかし、昇給や降給などで給与が大きく変動した場合には、「随時改定」という手続きが必要です。
本記事では、随時改定がいつから反映されるのか、そのタイミングや条件、手続き方法を解説します。
目次
随時改定とは?
随時改定とは、毎年4〜6月に行われる「定時決定」を待たずに、従業員の給与に大きな変動があった際に、社会保険料の算定基準となる標準報酬月額を変更する制度です。
標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金の保険料を算出するための基準となる金額です。個々の給与額を一定の範囲ごとに「等級」に分類し、その等級に応じて決定されます。
昇給・降給・各種手当の増減など、給与が大きく変動したまま放置すると、保険料が実態と合わなくなってしまいます。そのため、適正な保険料を反映させるために、随時改定が行われる仕組みです。
この手続きには、月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)の提出が必要です。企業の人事・総務担当者には、正しい理解と速やかな対応が求められます。
参考:
関連記事
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
随時改定がよくわかるガイド
月額変更届の手続き(随時改定)は、一定の要件を満たす従業員を対象にその都度対応が必要になります。
この資料では、随時改定の基本ルールと手続き方法に加え、よくあるミスの対処方法についても解説します。
月額変更届 対応マニュアル
従業員の報酬が変動した際、「月額変更届」の提出が必要となる場合があります。
本資料は、「月額変更届」に関する対応マニュアルです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きの実務にお役立てください。
随時改定3つの条件 かんたん解説ガイド
社会保険料の標準報酬月額を見直す「随時改定」は、実務上、正確な理解が求められます。
本資料は、「随時改定」の対象となる「3つの条件」について、かんたんに解説したガイドです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きにおける実務の参考としてご活用ください。
随時改定の条件
随時改定は、単に給与が変わっただけで必要になるものではありません。ここでは、随時改定の対象となる3つの条件について解説します。
1.従業員の固定的賃金に変動がある
1つ目の条件は、昇給や降格などにより、固定的賃金に変動があることです。固定的賃金とは、毎月あらかじめ決まった金額や支給率で支払われる給与や手当のことで、具体的なものは下記のとおりです。
- 基本給の昇給・降給
- 役職手当、家族手当、通勤手当などの変更、廃止
- 日給や時間給の単価変更
- 歩合給や請負給の支給単価・支給率の変更
- 割増賃金率や時間単価の変更による時間外手当の変動
これらに該当する変動があれば、随時改定の対象となる可能性があります。ただし、残業代やインセンティブなど、月ごとの労働時間や成果に応じて変動する「非固定的賃金」は、要件に含まれません。
2.3ヶ月間連続して支払基礎日数が17日以上ある
2つ目の条件は、固定的賃金の変動があった月を含む3ヶ月間、各月の「支払基礎日数」が一定以上あることです。支払基礎日数とは、給与計算の対象となる日数を指し、給与形態により数え方が異なります。
給与の支払いが月末締翌月末日払いの場合、1月の昇給分が含まれる給与が支払われるのは2月28日となります。そのため、変動月は2月としてカウントされ、2月・3月・4月の支払基礎日数が連続して17日以上あるか、確認が必要です。
なお、短時間労働者が「特定適用事業所」に勤務している場合は、支払基礎日数が11日以上であればこの条件を満たします。
3.標準報酬月額に2等級以上の差が生じている
3つ目の条件は、賃金変動後3ヶ月間の給与の平均額にもとづく標準報酬月額と、変更前の標準報酬月額との間に「2等級以上の差」が生じていることです。
社会保険料は、全国健康保険協会が定める「保険料額表」に記載された等級にもとづき、計算されます。
たとえば、昇給によって標準報酬月額が28等級から30等級へ変動した場合は、2等級の差が生じるため随時改定の対象です。
| 変更前 | 平均月額 | 変更後 | 対象有無 |
|---|---|---|---|
| 28等級(410,000円) | 440,000円 | 30等級 | 随時改定の対象 |
| 28等級(410,000円) | 420,000円 | 29等級 | 対象外 |
2等級未満の変動では改定は行われないため、要件を満たしているか確認する必要があります。
参考:
関連記事
随時改定の対象にならないケース
下記のような場合には、3つの条件を満たしていたとしても、随時改定の対象外となる可能性があります。
- 休職中に固定的賃金の変動があった場合
- 非固定的賃金による変動のみの場合
休職期間中に昇給などがあった場合でも、その間は通常勤務がないため、随時改定の対象外です。ただし、休職中も給与が満額支給されているようなケースでは、例外的に対象となる場合があります。
また固定的賃金が上がったとしても、残業手当(非固定的賃金)が大幅に減り、結果的に標準報酬月額が2等級下がった場合などは、随時改定の対象にはなりません。
このように、変更の原因が非固定的賃金であるかも、随時改定の判断において重要なポイントです。
随時改定が反映されるタイミング
従業員の給与に大きな変動があり、随時改定の3つの条件をすべて満たした場合、標準報酬月額が変更されます。変更の反映タイミングは、固定的賃金が変動した月の給与が実際に支払われた月を起点として4ヶ月目からです。
以下で、多くの会社で採用されている、給与が翌月払いのケースについて具体的に解説します。
給与が翌月払いの場合【具体例】
給与が翌月払いの会社では、賃金が変動した月の翌月からカウントを開始し、4ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用されます。
たとえば、5月に昇給があって昇給分が反映された給与が6月に支払われた場合は、その月を起点としてカウントをはじめ、4ヶ月目にあたる9月から標準報酬月額が変更されます。社会保険料の納付はその翌月となるため、10月支給分の給与から新しい保険料が控除される流れです。
給与が翌月払いであることを見落とすと、反映タイミングを誤る可能性があるため、給与支払いのタイミングを正しく把握したうえで手続きを行いましょう。
変更後の標準報酬月額の適用期間
随時改定によって変更された標準報酬月額は、一定の期間そのまま適用されます。原則として、下記の期間が適用期間です。
- 1~6月に随時改定があった場合:その年の8月まで適用
- 7~12月に随時改定があった場合:翌年の8月まで適用
ただし、例外として下記のような場合には、適用期間が変更される可能性があります。
- 新たに随時改定に該当した場合
- 産前産後休業や育児休業の終了による改定が行われた場合
このようなケースでは、新しい報酬月額があらためて適用されるため、変更時期を正確に確認し、給与計算に反映する必要があります。
随時改定の手続き方法
従業員が随時改定の要件を満たした場合、事業者は速やかに手続きを行う義務があります。手続きは「月額変更届」の提出によって行われ、記載方法や提出方法に注意が必要です。
ここでは、随時改定の手続き方法を詳しく解説します。
月額変更届の作成
随時改定を行う際には、月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)を提出する必要があります。この届出は、変更された給与額にもとづき、標準報酬月額を再設定するための重要な書類です。
月額変更届は、年金事務所や、日本年金機構のサイトからダウンロードできます。
なお、年間平均による算定を希望する場合には、追加で申立書や被保険者の同意書などの添付書類が必要です。必要な様式は、日本年金機構のサイトで確認しましょう。
関連記事
月額変更届の記載方法
月額変更届の記入項目は、下記のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 被保険者情報 | 整理番号・氏名・生年月日 |
| 改定年月 | 給与変動後4ヶ月目を記入 |
| 従前の標準報酬月額 | 変更前の金額を記入 |
| 昇(降)給の内容 | 変更のあった月・増減の区分を記載 |
| 給与支給月 | 給与変動後の3ヶ月間を記載 |
| 給与計算の基礎日数 | 17日以上の支払いがあったことを証明 |
出典:日本年金機構|健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届(記入例)
記入漏れや誤記があると手続きに遅れが生じるため、日本年金機構の記入例を参考にしながら、正確に記載しましょう。
必要書類を提出
月額変更届の記入が完了したら、所轄の年金事務所または事務センターに提出します。健康保険が協会けんぽ以外の組合健保・共済組合に加入している場合は、その組合にも提出が必要です。
提出方法は、下記の3通りあります。
- 窓口での提出
- 郵送による提出
- 電子申請(e-Govポータルを利用)
ただし、資本金1億円超の法人や投資法人、相互会社などの一部法人は電子申請が義務化されています。そのため、該当する場合はオンラインでの手続きが必須です。
迅速かつ正確な提出が、保険料の適正な計算と反映につながるため、事前に準備を整えておきましょう。
随時改定の手続きを忘れた場合の影響
随時改定の届出を行わない場合、厚生年金保険法等により6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。ただし、月額変更届には明確な提出期限が定められておらず、少しの遅れでただちに罰則が適用されることは稀です。
とはいえ、手続きが遅れたまま放置すると年金事務所からの指摘や催告が入ることもあり、最終的には届出が必要になります。過去に遡って保険料の計算・徴収を行う必要が出てくる場合もあるため、早めの対応が求められるでしょう。
提出漏れや訂正が必要な場合の対応
随時改定の提出漏れや誤りに気づいた場合は、速やかに管轄の年金事務所や健康保険組合に相談しましょう。提出が遅れていても、原則としては遡って正しい標準報酬月額が適用され、過不足がある場合は差額分の徴収・精算が必要になります。
未提出の状態が長く続くと、罰則の対象や年金事務所からの調査対象となるリスクも高まります。固定的賃金に変更があった際は、速やかに随時改定の要否を確認し、漏れのない手続きを心がけましょう。
社会保険の随時改定を行う際の注意点
随時改定は、標準報酬月額の正しい算定のために必要な手続きです。しかし、ミスや遅れがあると従業員や企業に影響を与える可能性があります。
ここでは、随時改定を行う際の注意点について解説します。
早めに月額変更届を提出する
随時改定の要件を満たした場合は、なるべく早く月額変更届を提出しましょう。届出が遅れると、標準報酬月額の反映が遅れ、給与から控除する社会保険料を誤ったり、納付すべき社会保険料と給与から控除した社会保険料を照合する手間が増えたりします。
標準報酬月額の変更は、給与変動後3ヶ月間の平均報酬額をもとに決定され、4ヶ月目から適用されます。スムーズに適用するためには、変動のあったタイミングで速やかに対応できるよう、あらかじめ準備を整えておきましょう。
従業員に通知は迅速に行う
随時改定により標準報酬月額が変更されると、それに応じて社会保険料も変動します。定時決定とは異なり、予期しない時期に手取り額が変動するため、従業員に対して事前の説明と速やかな通知が求められます。
保険料が増加する場合、手取りの減少による不満や混乱を避けるためにも、影響を丁寧に説明することが大切です。決定通知が届いたら速やかに対象者へ伝え、必要に応じて相談窓口を設けるなどの配慮も必要です。
変更後の保険料率の適用月を確認する
随時改定が適用されたあと、保険料がいつから変更されるのかを正しく確認することが大切です。
たとえば、4月に昇給して5月から新しい給与が支払われた場合は、標準報酬月額の変更は8月から適用され、9月支給の給与から新しい保険料が控除されます。
給与計算のミスは、従業員からの信頼を損なう可能性もあるため、注意が必要です。給与担当者は、反映タイミングを把握し、正確に給与明細に反映させることが求められます。
残業代が変動しても随時改定の対象ではない
随時改定は、基本給や各種手当などの固定的賃金の変動があった場合にのみ適用されます。残業代や歩合給などの非固定的賃金の増減は対象外です。
ただし、固定的賃金の変動後に残業時間が増えると、3ヶ月の給与平均が高くなり、結果として標準報酬月額の等級が想定よりも上がる可能性があります。そのため、随時改定を行う際には、変動後3ヶ月間の支給総額もあわせて確認しましょう。
随時改定の反映タイミングを把握し、スムーズに手続きを進めよう
社会保険の随時改定は、従業員の給与変動に応じて適切な保険料を算出するために欠かせない制度です。
随時改定が適用されると、固定的賃金の変動後の給与が支払われた月から数えて4ヶ月目に新しい標準報酬月額が反映されます。新しい保険料の控除は、その翌月の給与から開始されるため、実際に従業員の給与に反映されるのは5ヶ月目です。
届出の遅れは、過不足の精算や罰則のリスクを招くため、要件に該当する場合は速やかに手続きを行いましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
厚生年金保険料が引かれすぎ?計算方法を解説!
会社員に支払われる給与と賞与からは、所得税(源泉徴収税)などが差し引かれています。厚生年金保険料も控除されているものの1つで、給与からは標準報酬月額に厚生年金保険料率をかけた金額、…
詳しくみる会社が倒産したら失業保険はいくらもらえる?計算方法と注意点
会社が倒産した場合の失業保険は、自己都合で会社を辞めた場合よりも手厚くなっています。 所定給付日数は多く、給付制限を受けずに受給できます。被保険者期間も12カ月から6カ月に短縮され…
詳しくみる雇用保険資格喪失届の郵送方法は?添付書類や返信用封筒、提出期限などを徹底解説
従業員の退職に伴い発生する「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出は、事業者の重要な義務です。多忙な中で、手続きを郵送で済ませたいと考える人事・労務担当者の方も多いでしょう。 本記事で…
詳しくみる健康保険の被扶養者の要件について
日本に在住する人であれば、短期滞在者を除いて国籍にも性別にも年齢にも関係なく、どの人に対しても加入が義務付けられているのが健康保険です。 この健康保険により、病気や負傷、出産や亡く…
詳しくみる入社時の社会保険加入手続き|必要書類から期限、中途採用やパートの対応まで解説
新入社員の入社に伴う社会保険の手続きは、期限が定められており、必要書類も多岐にわたるため、複雑に感じられるかもしれません。 この記事では、入社時の社会保険手続きについて、基本的な流…
詳しくみる特定疾病とは?介護保険の観点から解説!
介護保険の制度は65歳以上の高齢者を対象としたものですが、16の特定疾病に罹患した場合には40歳以上65歳未満でも公的介護保険サービスを受けられます。また、上記に該当しない場合でも…
詳しくみる