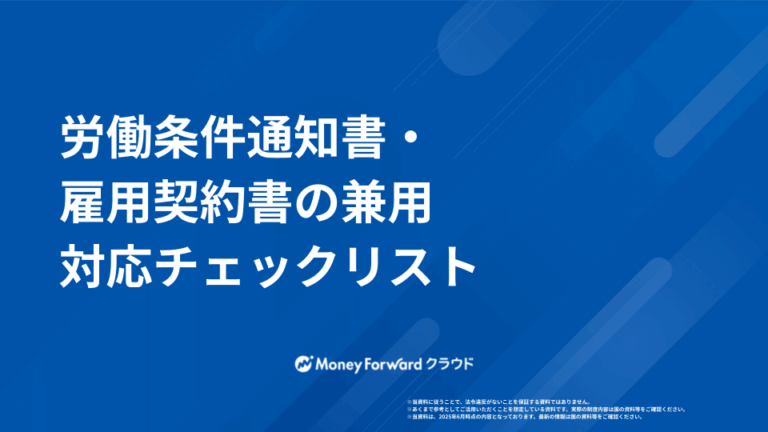- 更新日 : 2025年11月25日
【テンプレ付】雇用契約書と労働条件通知書がないのは違法?違いや兼用方法も解説
企業が従業員を雇い入れる際、「雇用契約書」と「労働条件通知書」という2つの書類があります。これらは労働条件を明確にする点で共通していますが、法律上の義務や役割は異なります。
労働条件通知書は法律で交付が義務付けられた「通知」であり、雇用契約書は双方合意の証となる「契約」です。また、労働条件通知書兼雇用契約書として兼用して契約を行う場合もあります。
本記事では、両者の違いから、兼用の方法、記載しなくてはならない項目、法改正のポイントまでをわかりやすく解説します。
この記事で人気のテンプレート(無料ダウンロード)
目次
雇用契約書と労働条件通知書がないのは違法?
雇用契約書と労働条件通知書は、どちらも労働条件を明示する書類ですが、雇用契約書は、法律で作成が義務付けられていないのに対し、労働条件通知書は、労働基準法で企業から労働者への交付が義務付けられています。
ですので、労働条件通知書を交付しない状態は、労働基準法違反にあたります。 労働基準法第15条において、企業は労働者(従業員)を雇い入れる際、必ず労働条件を明示・交付しなければならないと定められているためです。もしこの義務を怠った場合、同法第120条にもとづき、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
一方で、雇用契約書の「作成」自体は、法律で義務付けられていません。 法律では、口頭での合意でも労働契約は成立します。そのため、雇用契約書がないこと自体が即座に違法となるわけではありません。 しかし、口約束だけでは合意内容の客観的な証拠が残らないため、後のトラブルに発展するリスクを抱えることになります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド5選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
入社・退職・異動の手続きガイドブック
書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。
最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめた人気のガイドですす。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。
人事・労務テンプレート集28種類! ‐採用・入社・退職編‐
人事・労務の業務で日常的に使用する、採用・入社・退職に関わる書類のテンプレートを28種類ご用意しました。
Word/Excelの2つのファイル形式でダウンロードできますので、自社で使いやすい形にカスタマイズしてご活用ください。
入社前後の手続きがすべてわかる!労務の実務 完全マニュアル
従業員を雇入れる際には、雇用契約書の締結や従業員情報の収集、社会保険の資格取得届の提出など数多くの手続きが発生します。
本資料では、入社時に必要となる労務手続き全般を1冊にわかりやすくまとめました!
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?
労働条件通知書は交付が義務付けられていますが、雇用契約書は任意です。
雇用契約書は、労働契約法や民法にもとづく「労働契約(雇用契約)」の内容について、企業と労働者の双方が合意したことを証明する書類です。雇用契約書の作成自体は法律で義務付けられていません。しかし、労働条件などについて後でトラブルにならないように、雇用契約書を取り交わすケースが多いです。
一方、労働条件通知書は労働基準法およびパートタイム労働法、労働派遣法を根拠法とするもので、書面交付(メールやFAX含む)が義務付けられています。こちらは、事業主から労働者に対して一方的に交付されます。
この2つの書類に記載する事項はいくつか共通しているので、両方の書類を兼ねた「労働条件通知書兼雇用契約書」を作成し、取り交わす企業もあります。
雇用契約書と労働条件通知書の主な違いを以下の表にまとめます。
| 項目 | 雇用契約書 | 労働条件通知書 |
|---|---|---|
| 書類の性質 | 労使間の「契約書」 | 企業から労働者への「通知書」 |
| 作成の義務 | 法的には義務なし | 法律で作成・交付が義務 |
| 根拠法規 | 民法、労働契約法など | 労働基準法 |
| 署名・押印 | 労使双方(合意の証拠) | 企業側のみ(労働者側は不要) |
| 違反時の罰則 | 特になし(ただしトラブルの元) | あり(30万円以下の罰金) |
雇用契約書と労働契約書との違いは?
実務上、「雇用契約書」と「労働契約書」は、ほぼ同じ意味の書類として使われています。 厳密には、民法では「雇用契約」、労働契約法では「労働契約」という言葉が使われますが、従業員を雇い入れて労働の対価として賃金を支払うという本質は同じです。本記事でも、これらは同義のものとして扱います。
参考:
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律|e-Gov法令検索
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律|e-Gov法令検索
労働契約法|e-Gov法令検索
民法|e-Gov法令検索
雇用契約書と労働条件通知書は兼用できる?
労働条件通知書と雇用契約書は、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として1枚にまとめることもできます。
労働条件通知書と雇用契約書を兼用するメリットは、手続きの簡素化と管理の効率化です。 もし別々に作成すると、書類が2種類になり、交付漏れや管理が煩雑になる恐れがあります。1枚にまとめることで、法律上の「通知義務」を果たしつつ、同時に「契約合意の証拠」も残せます。
「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として兼用した書類を取り交わすタイミングは、労働者(従業員)を雇い入れる際、遅くとも労働契約が開始される(入社)までに行います。
兼用する際の必須要件
「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として兼用する場合、以下の2点を必ず満たす必要があります。
- 労働基準法で定められた明示事項がすべて記載されていること。
- 労使双方(企業側と労働者側)の署名または記名押印欄があること。
この要件を満たした書類を2部作成(または1部作成してコピー)し、双方が署名・押印のうえ、1部ずつ保管します。
労働条件通知書で必ず明示すべき項目は?(2024年4月改正対応)
労働条件通知書(兼用する場合も含む)には、必ず記載しなければならない「絶対的明示事項」と、社内で定めがある場合に記載が必要な「相対的明示事項」があります。
法律で定められた「絶対的明示事項」
絶対的明示事項は、雇用形態にかかわらず、すべての労働者に対して必ず明示しなければなりません。
- 労働契約期間
期間の定めがない(無期雇用)か、ある(有期雇用)か、更新の有無も記載します。 - (有期契約の場合)契約更新の基準
労働契約に期間が定められている場合、労働契約の更新方法や基準について記載します。 - 就業の場所と従事すべき業務の内容
労働者が就業する場所や、仕事の内容について記載します。 - 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇など
労働時間について記載します。有給休暇などの扱いについても、ここに記載します。
交替制勤務の場合は、就業時転換に関する事項も必要です。 - 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期
基本給、諸手当、計算方法(時給、月給など)、締切日、支払日。 - 退職に関すること(解雇の事由を含む)
定年制の有無や自己都合による退職の届出時期、解雇の事由、その手続について記載します。
【2024年4月改正】追加された明示事項
2024年(令和6年)4月1日の労働基準法施行規則改正により、絶対的明示事項に以下の内容が追加されました。
- 就業場所・業務内容の「変更の範囲」の明示
将来的に転勤や配置転換の可能性がある場合、その範囲(例:「会社の定めるすべての事業所」「会社の指示するすべての業務」など)を明示する必要があります。 - (有期契約の場合)更新上限の有無と内容
有期労働契約で更新上限(例:「通算契約期間5年まで」「更新回数3回まで」)を設ける場合、その内容を明記しなければなりません。 - (有期契約の場合)無期転換申込権に関する事項
同一企業での通算契約期間が5年を超える有期契約労働者には「無期転換申込権」が発生します。この権利が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込める旨(申込権)と、無期転換後の労働条件を明示する必要があります。
定めがある場合に明示すべき「相対的明示事項」
相対的明示事項は、会社に定めがある場合に明示が必要です。
- 昇給に関すること
- 退職手当(退職金)に関すること
- 賞与(ボーナス)などに関すること
- 食費、作業用品などの負担に関すること
- 安全衛生に関すること
- 職業訓練に関すること
- 災害補償などに関すること
- 表彰や制裁に関すること
- 休職に関すること
パート・アルバイトや有期雇用労働者への明示事項は?
正社員以外の、いわゆるパートタイム労働者やアルバイト、契約社員(有期雇用労働者)を雇い入れる場合は、以下の4項目についても明示しなければなりません。
- 昇給の有無
- 退職手当(退職金)の有無
- 賞与(ボーナス)の有無
- 相談窓口
これらは、正社員との待遇差(同一労働同一賃金)に関するトラブルを防ぐ目的で定められています。たとえ昇給や賞与なしであっても、「無し」と記載しなければなりません。
労働条件通知書 兼 雇用契約書を作成・交付する際の注意点
労働条件通知書は、契約更新の際も必要です。仮に契約内容が同じであっても、交付しなくてはなりません。したがって、労働条件通知書兼雇用契約書を取り交わした場合も、契約更新時に改めて取り交わす必要があります。
労働条件通知書兼雇用契約書を作成する際は、労働条件通知書を作成する際と同様に、以下のことに注意しましょう。
- 適切な方法によって明示されているか
- 明示する書面の項目に不足はないか
- 有期雇用の場合は、更新の有無や更新の判断基準が明記されているか
- パートやアルバイト、有期雇用労働者の場合は、追加で必要な4項目が明示されているか
労働条件の明示はメールでも可能
労働条件の明示は、原則として「書面」の交付が必要です。 ただし、労働者本人が希望した場合には、FAXや電子メール、Slack・Chatworkなどのビジネスチャット、LINE、SMS、個人のマイページへの掲示といった電磁的方法(電子交付)も認められています。
- 労働者本人が電子交付を希望していること。(希望しない人に強制はできません)
- 交付するファイル形式が、労働者側で容易に出力・保存できるものであること。(例:PDFファイル)
- 本人のみが閲覧できる方法であること。(例:本人専用のメールアドレス、マイページなど)
電子交付を希望した労働者に対しても、「希望した」ことを確認するために、希望する交付方法(「メール(アドレス:xxxx@…)」など)を書面で提出してもらうことが推奨されています。
署名・押印の取り扱い
「労働条件通知書」としては、労働者側の署名・押印は不要です。 しかし、「雇用契約書」として兼用し、双方の合意を明確にするためには、労働者本人の署名(または記名押印)をもらう運用が確実です。
電子契約サービスを利用して電子署名を行う方法もありますが、電子交付(PDFをメールで送るだけ)の場合は、労働者に内容を確認のうえ、同意する旨を返信してもらう、あるいは印刷して署名したものを返送してもらうといった対応が考えられます。
交付が遅れた場合の対処法
従業員の入社から時間が経ってしまい、労働条件通知書の交付をし忘れていたことに気づいた場合、法律違反の状態であることに変わりはないため、気づいた時点ですぐに対応しなければなりません。
- 速やかに書類を作成:現在の労働条件(または入社時の条件)を明記した労働条件通知書(兼 雇用契約書)を作成します。
- 従業員への説明と交付:交付が遅れたことを率直に謝罪し、書類の内容を丁寧に説明します。
- 署名・押印の取得:内容に認識齟齬がないことを確認してもらったうえで、署名・押印をもらい、企業も控えを保管します。
もし従業員が内容に異議を唱えたり、署名を拒否したりした場合は、その理由をヒアリングし、認識のすり合わせ(話し合い)が必要です。
【無料】雇入通知書・労働条件通知書のテンプレート
以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。
労働条件通知書と雇用契約書の役割を理解しトラブルを防ごう
企業が従業員を雇い入れる際、労働条件通知書を交付しない状態は労働基準法違反となります。これは法律で定められた企業の義務です。一方で、雇用契約書の作成は任意ですが、労使間の合意を明確にし、「言った、言わない」のトラブルを防ぐために作成するのが賢明です。
実務上、これら2つの書類は「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として1枚にまとめる(兼用する)ことができます。兼用することで、法律上の「通知義務」を果たし、同時に「契約合意の証拠」も残せます。
兼用する際は、2024年4月改正で追加された項目(就業場所の変更範囲、有期契約の更新上限など)を含め、法律で定められた記載事項を漏れなく明記し、適切に交付・管理しましょう。
雇用契約書については、以下の記事で詳しく解説しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
アルバイトにも就業規則は必要?テンプレートやもらってない場合の対処法も紹介
「アルバイトだけど、就業規則って関係あるの?」「もし会社とトラブルになったら…」初めてアルバイトをする方や、これまであまり意識してこなかった方も、就業規則について疑問や不安を感じる…
詳しくみる就職氷河期とは?いつのこと?現在の年齢や支援プログラムについて解説!
就職氷河期とは、バブル崩壊後の、新卒採用が特に厳しかった1993年〜2005年頃のことで、当時大学などを卒業した世代を就職氷河期世代と呼びます。本記事では、就職氷河期世代の年齢や特…
詳しくみるダイバーシティ&インクルージョンとは?事例や効果的な導入ポイント
現代社会は、多様性が尊重される時代です。世の中の生活環境や消費者のニーズ、働き方などに対する価値観が多様化しており、多様性に順応できない企業は淘汰されるリスクが高まります。 そのこ…
詳しくみる【記入例付き】労働条件通知書の書き方は?厚生労働省のテンプレートや注意点を解説
労働条件通知書の作成と交付は、企業が従業員を雇用する際に法律で定められた重要な義務です。書類に不備があると、後になって従業員との間で認識の齟齬が生まれ、深刻な労使トラブルに発展する…
詳しくみる【テンプレ付】退職勧奨とは?円滑な進め方や、企業が気を付けたい3つの注意点
「退職勧奨はどのように行うのだろう」「退職勧奨されたらどうすればよいのか知りたい」 このように悩む方もいるのではないでしょうか。 退職は会社、従業員と双方にとって一大事であるため、…
詳しくみる【テンプレート付き】始末書の書き方は?遅刻・紛失・交通事故など状況別の例文まとめ
始末書とは、仕事上の問題(ミス、トラブル、アクシデントなど)の発生から解決までの経緯にまつわる報告書です。始末書は、謝罪や反省の気持ちを表す点では反省文と似ており、事の経緯を記録す…
詳しくみる