- 更新日 : 2025年11月18日
育児休業給付金の計算方法 – いつの給与までが対象になる?
育児休業は、子どもが1歳(一定の条件を満たした場合は2歳まで)取得できます。また、育児休業期間中は通常、給与は無給になりますが、雇用保険から育児休業給付金を受けることができます。
今回は、育児休業給付金とは何かを再確認し、育児・介護休業法の改正による育児休業給付金の影響、支給額の計算方法や手続きについて見ていきます。
目次
育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、雇用保険に加入している被保険者が育児休業を取得して給与が一定以上支払われなくなった場合に、雇用保険から給付される給付金のことです。
育児休業給付金には、出生時の育児休業期間を対象に支給される「出生時育児休業給付金」と育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
給与計算の「確認作業」を効率化する5つのポイント
給与計算の確認作業をゼロにすることはできませんが、いくつかの工夫により効率化は可能です。
この資料では、給与計算の確認でよくあるお悩みと効率化のポイント、マネーフォワード クラウド給与を導入した場合の活用例をまとめました。
給与規程(ワード)
こちらは、給与規程のひな形(テンプレート)です。 ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。
規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。
給与計算 端数処理ガイドブック
給与計算において端数処理へのルール理解が曖昧だと、計算結果のミスに気づけないことがあります。
本資料では、端数処理の基本ルールをわかりやすくまとめ、実務で参照できるよう具体的な計算例も掲載しています。
給与計算がよくわかるガイド
人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。
複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。
育児・介護休業法の改正ポイントおさらい
2022年4月から育児・介護休業法の改正が段階的に施行されています。今回の改正は特に男性の育児休業制度が大きく見直されています。
育児・介護休業法の改正についてのポイントは、下記のようになります。
- 雇用環境整備や個別の周知・意向確認の措置の義務化
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
- 「産後パパ育休」制度の開始
- 育児休業の分割取得
- 育児休業給付に関する規定整備
- 育児休業の取得状況を公表するよう企業に義務付け
- 育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大
- 子の看護休暇の見直し(対象及び取得事由の拡大、除外規定の一部撤廃、改称
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
- 育児・介護のためのテレワーク導入(努力義務)
- 介護休暇の取得要件の緩和
- 介護離職防止のための雇用環境整備
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認
- 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
詳しい内容はこちらでご確認ください。
育児休業給付金の計算方法
ここからは、育児休業給付金と出生時育児休業給付金の計算方法について見ていきます。出生時育児休業給付金、育児休業給付金は、ともに休業した日についての給付金ですので、休業開始日から休業終了日までの分が支給対象になります。
出生時育児休業給付金の計算方法
出生時育児休業給付金の支給額は、原則として、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限は28日)×67%」です。
※休業開始時賃金日額は、申請の際に提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」で、育児休業を開始する前6カ月間の賃金を180で割った金額です。
※休業開始時賃金日額の上限額は15,190円(ただし令和5年7月31日まで)です。
出生時育児休業給付金の上限額は、15,190円×28日×67%=284,964円になります。
※出生時育児休業期間に会社から賃金が支払われた場合は、支払われた賃金の額により支給額が変わります。
- 休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%以下の場合
休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67% - 休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%超から80%未満の場合
休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額 - 休業開始時賃金日額×休業期間の日数の80%以上の場合
出生時育児休業給付金は支給されません。
例えば、休業開始時賃金日額が9,000円で14日間の出生時育児休業を取得した場合で育児休業を開始した場合、賃金が全く支払われていなければ、支給額=9,000円×14日×67%=84,420円になります。
育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1カ月)について、原則として、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%(育児休業開始日から181日目以降は50%)」です。
※休業開始時賃金日額は、申請の際に提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」で、育児休業を開始する前6カ月間の賃金を180で割った金額です。
※支給日数は原則30日間です。ただし、休業終了日を含む休業期間の日数は休業終了日までの日数になります。
※休業開始時賃金日額の上限額は15,190円、下限額は2,657円(それぞれ令和5年7月31日まで)です。
支給日数が30日の場合、支給上限額と支給下限額は次のようになります。
(給付率67%) 支給上限額 305,319円 支給下限額 53,405円
(給付率50%) 支給上限額 227,850円 支給下限額 39,855円
※育児休業期間に会社から賃金が支払われた場合は、支払われた賃金の額により支給額が変わります。
- 休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%以下の場合
休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67% - 休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%超から80%未満の場合
休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額 - 休業開始時賃金日額×休業期間の日数の80%以上の場合
育児休業給付金は支給されません。
例えば、休業開始時賃金日額が9,000円(賃金月額が270,000円)で育児休業を開始した場合、賃金が全く支払われていなければ、以下になります。
- 育児休業開始日から180日目までで休業日数が30日の場合の計算
支給額=9,000円×30日×67%=180,900円 - 育児休業開始日から181日目以降で休業日数が30日の場合の計算
支給額=9,000円×30日×50%=135,000円
育児休業給付金を受け取るための手続き – 企業と従業員
ここからは、出生時育児休業給付金、育児休業給付金を受け取るための手続きについて解説します。
出生時育児休業給付金の手続き
【必要書類】
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書など、出生時育児休業を開始した日と終了した日、賃金額、支払い状況がわかるもの
- 払渡希望金融機関指定届
- 母子健康手帳、医師の診断書など、出産予定日ならびに出産日を確認できる、いずれかのもの(コピー可)
- 受給予定の従業員が会社に出生時育児休業の申し出を行います。
- 従業員が必要な書類を会社に提出します。
- 会社が必要な書類をそろえて管轄のハローワークに提出します。
- 審査が承認されたら出生時育児休業給付金が支払われます。
育児休業給付金の手続き
【必要書類】
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳、出勤簿、タイムカードなど、育児休業を開始した日と終了した日、賃金額、支払い状況がわかるもの
- 払渡希望金融機関指定届
- 母子健康手帳など、育児の事実、出産予定日ならびに出産日を確認できるもの(コピー可)
- 受給予定の従業員が会社に出生時育児休業の申し出を行います。
- 従業員が必要な書類を会社に提出します。
- 会社が必要な書類をそろえて管轄のハローワークに提出します。
- 審査が承認されたら育児休業給付金が支払われます。
その後は、1〜2カ月に1回、支給申請手続きを行います。
【育児休業給付金はいつまでもらえるか】
原則は、子どもが1歳になる日の前日まで支給されます。
しかし、一定の要件を満たした場合には、最長で1歳6カ月または2歳になる日の前日まで受けられる場合があります。
育児休業申出書のテンプレート(無料)
以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。
出生後休業支援給付金とは【2025創設】
出生後休業支援給付金とは、労働者が対象期間※において育児のために一定期間の休業を取得した場合に、雇用保険から支給される給付金です。これは2022年10月に施行された「産後パパ育休(出生時育児休業)」の活用促進を目的に設けられた制度であり、男性の育児参加を経済的に後押しするための新たな支援策として注目を集めています。
給付対象
給付の対象となるのは、雇用保険の被保険者であり、次の条件を満たした労働者です。
- 出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得していること
- 被保険者の配偶者が通算14日以上の育児休業を取得していること(配偶者が自営業者など、配偶者の育児休業を要件としない場合を除く)
なお、この給付金は通常の「育児休業給付金」とは別枠で支給されるもので、併用も可能です。ただし、「育児休業給付金」は1歳までの育児休業に対する制度であるのに対し、「出生後休業支援給付金」は出生直後の育児を目的とする短期間の休業支援という点で位置づけが異なります。
- 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日 」までの期間
- 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 」までの期間
支給額
支給額は、休業開始時の賃金日額に支給対象日数(最大28日)と13%を乗じた金額となります。これは育児休業給付金とは別に支給され、両制度を併用することで、実質的に手取り賃金相当の収入が確保される設計となっています。これにより、出産後すぐに育児に関わりたいと考える労働者のニーズに応えることができ、企業側も多様な働き方を支援する体制を整えるうえで重要な制度といえるでしょう。
企業の人事担当者にとっても、従業員からの相談や取得希望に柔軟に対応するためには、この制度の概要や申請手続き、他制度との関係性を正しく理解しておくことが欠かせません。
出生後休業支援給付金を受け取るための手続き
ここからは、出生後休業支援給付金を受け取るための手続きについて解説します。
必要書類
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業取得状況申出書
- 勤怠記録または出勤簿
- 賃金台帳の写し(必要に応じて)
- その他、ハローワークから求められた補足資料
従業員
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードの写しなど)
- 出生証明書類(出生届の写しや母子健康手帳の該当ページの写しなど)
- 金融機関口座情報(給付金振込先)
- その他、個別に必要とされる資料
手続きの流れ
- 育児休業の意向を会社へ申し出る
子の出生予定日が確定した段階で、従業員は会社に対して出生後の育児休業取得の意思を申し出ます。休業の予定期間や分割取得の有無をあらかじめ伝えておくことが望ましいです。 - 休業期間とスケジュールの社内調整
人事担当者は、部署内での業務調整を行いながら、休業取得に向けたスケジュールを整備します。必要に応じて、社内ルールやガイドラインに従った書類提出を求めます。 - 必要書類の準備と確認
従業員と会社がそれぞれの書類を整えます。作成ミスや記載漏れがないよう、相互に確認しながら進めることが重要です。 - ハローワークへの申請書類提出
会社が取りまとめた書類一式を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。提出期限は、被保険者の育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までとされています。 - 審査および給付金の支給
ハローワークによる審査が行われ、要件を満たしていると認定された場合、指定された銀行口座に給付金が振り込まれます。支給までの期間は通常1~2か月程度です。
出生後休業支援給付金と他の育児関連制度との違い
出生後休業支援給付金は、特に出産直後の時期に焦点を当てた制度です。「育児休業給付金」や「産後パパ育休」と混同されがちなので、違いについて整理します。
育児休業給付金との違い
育児休業給付金は、原則として子どもが1歳になるまでの間に取得した育児休業を対象とした制度です。これは父母どちらも対象であり、長期的な育児休業を想定した設計となっています。対して、出生後休業支援給付金は、子の出生日または出産予定日のうち早い日から8週間以内というごく限られた期間に取得する休業を対象にしています。
産後パパ育休との位置づけ
出生後休業支援給付金の根拠となっているのが、いわゆる「産後パパ育休(出生時育児休業)」です。この制度は、令和4年10月に施行された改正育児・介護休業法に基づいており、父親が出産直後の時期に柔軟に育休を取れるようにすることを目的としています。
この制度では、従来の育児休業とは別に最大4週間の休業が取得可能で、2回まで分割取得できるのが特徴です。出生後休業支援給付金は、この制度を取得した際に、賃金が支払われていない場合に支給される金銭的支援となります。
出生後休業支援給付金と育児休業給付金は併用できる?
出生後休業支援給付金と育児休業給付金は併用が可能ですが、取得する休業の期間と内容によっては、申請書類の準備や提出時期が複雑になることがあります。
育児・介護休業法の改正を確認して正しく給付金を受給しましょう
育児休業給付金は、法改正により、育児休業給付金の他にも出生時育児休業給付金を受け取ることができるようになりました。
支給要件や必要書類を確認して、正しく出生時育児休業給付金や育児休業給付金を受けられるように手続きを行っていきましょう。
よくある質問
育児休業給付金とは何か教えてください
育児休業給付金とは、雇用保険に加入している労働者が支給要件を満たした場合に雇用保険から給付される給付金のことです。育児休業給付金には、「出生時育児休業給付金」と「育児休業給付金」があります。詳しくはこちらをご覧ください。
育児休業給付金の計算方法について概要を解説してください
出生時育児休業給付金は、原則、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限28日)×67%」です。育児休業給付金は、原則、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%(181日目以降は50%)」です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
特別支給の老齢厚生年金とは?受給要件と金額・手続きを解説
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金加入歴が1年以上あり、昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前に生まれた人に支給される年金です。受給開始年齢は生年月日や性別によって定め…
詳しくみる副業すると社会保険料が増える?社会保険加入時に注意すべきポイントを解説!
働き方改革が推進され、多様な働き方の一つとして副業・兼業のダブルワークを認める企業が増えています。「自身の能力を一つの企業にとらわれず幅広く発揮したい」という想いから前向きに検討し…
詳しくみる職業訓練に合格するためのジョブ・カードの書き方とは?採用担当者の視点を踏まえた作成手順を徹底解説
Pointジョブカードとは? ジョブカードは、訓練選考と再就職成功を左右します。 訓練動機と就職目的を明確化 経験は行動と成果で記載 面談を意識した記述が重要 Q&A Q.…
詳しくみる雇用保険被保険者転勤届の書き方は?提出先や添付書類も解説
従業員の支店間異動(転勤)などが発生した際、「雇用保険被保険者転勤届」の手続きが必要になることがあります。この届出は、従業員が同じ会社(同一事業主)の異なる事業所へ移る際に、雇用保…
詳しくみる労働保険料率の内訳
労働保険料は、労災保険料と雇用保険料で構成されており、各保険料における事業主と労働者の負担割合はそれぞれ異なっています。ここでは、労災保険と雇用保険のおさらいをしながら、労働保険料…
詳しくみる介護休暇は年5日まで?給与は無給?条件や対象家族、介護休業との違いも解説
家族の介護が必要になったとき、仕事を休んで対応するための制度が「介護休暇」です。この制度では年に5日まで取得できますが、「給与は無給?」「対象家族に制限は?」「介護休業とは何が違う…
詳しくみる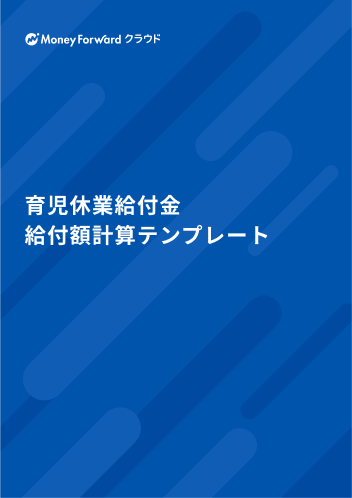

-e1762740828456.png)

