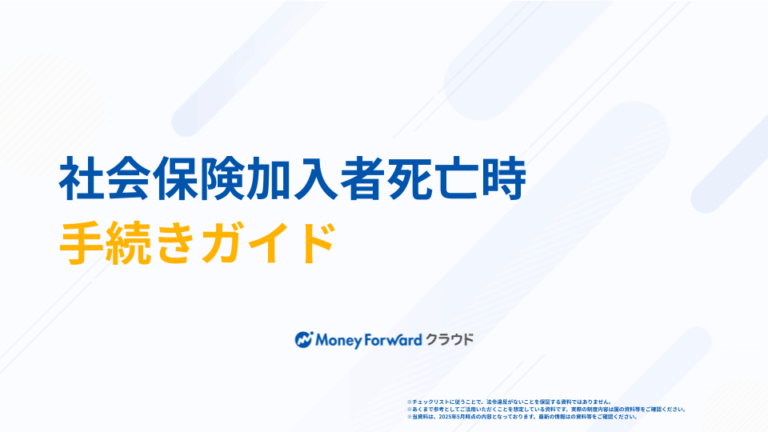- 更新日 : 2025年11月19日
社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入者の死亡時の手続きは?一時金はもらえる?
被保険者が死亡した場合は、各保険者に届け出る必要があります。社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入者が死亡した場合は健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届、国民健康保険加入者が死亡した場合は国民健康保険資格喪失届、後期高齢者医療保険加入者が死亡した場合は後期高齢者医療障害認定申請書及資格取得(変更・喪失)届で手続きを行います。
目次
社会保険に加入している人が死亡した場合の手続きは?
社会保険に加入している従業員が死亡した場合は、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失の手続きが必要です。所定の方法で資格喪失の届出書を提出します。被保険者資格を喪失した際は、健康保険証も返還しなければなりません。被扶養者分を含め、交付されていた健康保険証を返してもらい、返還します。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出
健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届は、社会保険に加入していた人が退職や死亡などで被保険者資格を喪失する際の届出に用いる書類です。提出方法は以下の通りです。
提出書類
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届
提出期限
・死亡日の翌日から5日以内
提出方法
・電子申請・郵送・窓口持参のいずれか
・提出媒体はCDやDVDでも可
提出先
・郵送の場合は事務センター、窓口持参の場合は事業所の所在地を管轄する年金事務所
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
国民健康保険に加入している人が死亡した場合の手続きは?
死亡した従業員が社会保険ではなく国民健康保険に加入していた場合は、会社が保険者に対して届出を行う必要はありません。国民健康保険被保険者の資格喪失を届け出るのは、世帯主か同一世帯に属する人です。届出の義務がある人が、所定の方法で届け出る必要があります。
国民健康保険資格喪失届を提出
国民健康保険資格喪失届は、国民健康保険に加入していた者が死亡などの理由で被保険者資格を喪失する際の届出に用いる書類です。提出方法は以下の通りです。
提出書類
・国民健康保険資格喪失届(国民健康保険異動届出書)
提出期限
・死亡日から14日以内
提出先
・市町村役場
後期高齢者医療保険に加入している人が死亡したときの手続きは?
死亡した従業員が後期高齢者医療保険加入者であった場合、会社が保険者に対して届出を行う必要はありません。後期高齢者医療保険の資格喪失を届け出るのは、世帯主か同一世帯に属する人です。届出の義務がある人が、所定の方法で届け出る必要があります。
後期高齢者医療障害認定申請書及資格取得(変更・喪失)届書を提出
後期高齢者医療障害認定申請書及資格取得(変更・喪失)届書は、後期高齢者医療保険に加入する場合や資格を喪失する場合の届出に用いる書類です。加入者の死亡時に、以下の方法で提出します。
提出書類
・後期高齢者医療障害認定申請書及資格取得(変更・喪失)届書
提出期限
・死亡日から14日以内
提出先
・市町村役場
年金や死亡一時金はいくらもらえる?
各医療保険は加入者の死亡に対して一時金の給付を行っています。健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険から、以下のように死亡一時金が支払われます。
健康保険の場合
・埋葬料として、一律の金額が支払われる。
・協会けんぽの場合は5万円
国民健康保険
・葬祭費として、市区町村別に定められた金額が支払われる。
・5~7万円
後期高齢者医療保険
・葬祭費として、市区町村別に定められた金額が支払われる。
・3~5万円
また、要件を満たす遺族に対しては厚生年金から遺族厚生年金、国民年金から遺族基礎年金が支払われます。
社会保険加入者の死亡時は速やかに健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届を提出しよう
社会保険の加入者が死亡した場合は、会社が健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届を提出して手続きを行う必要があります。電子申請・郵送・窓口持参のいずれかの方法で、郵送の場合は事務センター、窓口持参の場合は所轄の年金事務所に提出します。死亡者が国民健康保険に加入していた場合や、後期高齢者医療保険加入者であった場合は、会社が届出を行う必要はありません。世帯主か同一世帯に属する人が、それぞれ定められた方法で死亡の手続きを行います。
被保険者が死亡した場合の健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届の提出期限は、死亡日の翌日から5日以内です。遅れないよう、速やかに提出しましょう。
よくある質問
社会保険に加入している人が死亡した場合の手続きは?
会社が、死亡日の翌日から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出して手続きを行います。詳しくはこちらをご覧ください。
国民健康保険に加入している人が死亡した場合手続きは?
世帯主か同一世帯に属する人が、国民健康保険資格喪失届を死亡日から14日以内に提出して手続きを行います。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労働災害(労災)とは?種類や対策について解説!
企業の人事担当者にとって、労働災害の発生は避けられない課題の一つです。予期せぬ事故はいつでも発生する可能性があり、その際には迅速かつ適切な対応が求められます。本記事では、労働災害に…
詳しくみる健康保険組合とは
日本で健康保険と呼ばれているのは、健康保険法に基づく雇用者を対象とした医療保険です。この被用者医療保険事業を国に代わって行っているのが、健康保険組合です。 つまり、健康保険組合は被…
詳しくみる労働保険の一般拠出金とは
労働保険では、2007年4月1日から「一般拠出金」についての申告および納付を行うことになっています。この「一般拠出金」は、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づいたものです…
詳しくみる押さえておくべき社会保険(健康保険)と国民健康保険の違い
自分で起業するという計画を立てたときには、不安もあるでしょうが、ワクワク感も大きいですよね。今は勤めていらっしゃる会社の健康保険に加入されているものと思いますが、退職後の健康保険を…
詳しくみる社会保険料率・社会保険料額の決定方法
社会保険料率の水準は、物価や賃金水準をふまえ、財政のなかで給付と負担を調整できるよう、計画して決められていました。しかし、現在では急激な少子高齢化が進み、社会補償と負担する社会保険…
詳しくみる労働保険料とは? 計算方法から申告・納付に必要な手続きまで解説!
毎年7月に申告と納付をする労働保険料は、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を合計したものです。給付を受ける際は各保険とも個別に支給されますが、保険料の納付は合算して取り扱われ…
詳しくみる