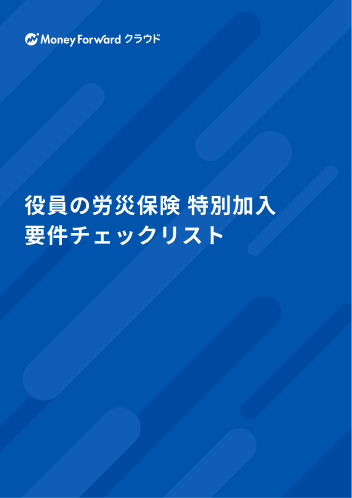- 更新日 : 2025年11月13日
役員は労災保険の適応外?特別加入についても解説!
労災保険は、労働者のための保険制度であることから、事業主や役員は対象外になっています。基本的に事業主・役員は労災保険へ加入することも、給付を受けることもできません。しかし労働者と同じように働くことが多い中小企業主は、労災保険に特別加入することができます。役員も中小企業主とともに労災保険に特別加入することが可能です。
目次
役員は労災保険の適応外?
労働者が、通勤中や仕事中にケガをした場合には労災保険から必要な補償が受けられます。労働者の仕事に原因があるケガや病気に対して補償を行うのが、労災保険です。
では、労働者ではなく役員が病気やケガをした場合、労災保険はどのように取り扱われるのでしょうか?労災保険の対象者や、役員に対する補償について考えてみましょう。
そもそも労災保険とは
労災保険とは「労働者災害補償保険」の略で、労働者を対象にした保険制度です。労働者の労働災害によるケガ、障害、死亡をはじめ、作業や職場環境が原因でかかる病気、働き過ぎによる精神疾患など、仕事が原因で引き起こされる労働者の病気やケガに対して給付が行われます。通勤中の事故によるケガなども給付対象です。
もともと労災保険は、雇用されている身分であることから立場の弱かった従業員を保護するために設けられた制度です。本来、従業員を雇用する事業主には、労働基準法上の安全配慮義務があります。業務上の事故による傷病等が生じた場合、使用者に過失がなくても被災労働者や遺族に補償義務があります(労働基準法第8章「災害補償」)。
労災保険法は、この労働基準法の災害補償の規定を担保するための法律であり、同じ昭和22年に姉妹法として制定されました。労働基準法は、役員や家族を労働者としていません。そのため労災保険も役員や家族は、保険給付の対象外としています。
役員でも労災保険が適応可能になるケース
基本的に事業主などの役員は、労災保険から給付を受けることはできません。しかし、役員の性質によっては役職名称にかかわらず、労災保険の給付対象になる場合場あります。どのような範囲の役員が労災保険で補償を受けられるかは、労働者性によって判断されます。
労働者性とは、労働者を判断する基準のことです。具体的な判断要素としては、勤務時間・勤務場所の拘束の程度と有無、業務内容・遂行方法に対する指揮命令の有無、仕事の依頼に対する諾否の自由の有無、機械や器具の所有や負担関係、報酬の額・性格、専属性の有無などを総合的に考慮します。
また役員であっても中小事業主とともに労災保険の特別加入をすることによって、労災保険の適応を受けることができます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
労災対応がよくわかるガイド
前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。
一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。
‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。
年度更新の手続きガイドブック
年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。
本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
労災保険の特別加入
労災保険の特別加入とは、労働者以外でも労災保険への加入を特別に認める制度です。労働者ではないものの労働者と同じように労災保険の対象とすることが妥当であると判断された者が、申請手続きを行うことで労災保険に特別加入することができます。中小事業主や一人親方、特定作業従事者、海外派遣者、定められた事業を行う個人事業主が労災保険に特別加入することが認められています。役員は中小事業主とともに労災保険に特別加入することになります。
労災保険の特別加入の対象者
中小事業主は、本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して労災保険に特別加入する必要があります。中小事業主の労災保険の特別加入が認められるのは、以下の企業規模の対象者です。
| 金融業・保険業・不動産業・小売業 | 労働者数50人以下 |
| 卸売業・サービス業 | 労働者数100人以下 |
| そのほかの業種 | 労働者数300人以下 |
対象者は、以下の通りです。
- 事業主(事業主が法人そのほかの団体であるときはその代表者)
- 労働者以外の事業従事者(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人そのほかの団体である場合の代表者以外の役員など)
特別加入申請の手続き
中小事業主などの役員の労災保険特別加入は、次の要件を満たしている場合に認められます。
- 雇用する労働者について保険関係が成立していること
- 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
この2つの要件を満たしていない場合は、中小事業主・役員が労災保険に特別加入することはできません。特別加入申請の手続きは労働保険組合を通じて、以下の方法で行います。
- 提出書類:特別加入申請書(中小事業主等)
- 提出先:所轄の労働基準監督署長を経由の上、労働局長
労災保険の特別加入に関する補償範囲・保険料
労働者が労働災害にあった場合には、重大な過失や故意による相殺分を除いて労災保険から保険給付を受けることができます。これに対して特別加入の中小事業主・役員は、限られた範囲でしか労災保険から補償を受けることはできません。労災保険に特別加入する場合には、補償範囲と保険料について確認しておくことが必要です。
補償範囲
労災保険に特別加入した中小事業主などの役員に対しては、以下のいずれかの場合に該当する仕事中の災害に対して、保険給付が行われます。
- 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に、特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
- 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
- ①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
- 上記の①、②、③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
- 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
- 通勤途上で次の場合
- 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
- 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
- 事業の運営に直接必要な運動競技会そのほかの行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合
通勤災害については、労働者と同じように取り扱われます。また事業主が同一でない2つ以上の事業における業務を要因とする病気に対しても、要件を満たしていれば労働者と同じように保険給付を受けることができます。
保険料
中小事業主の特別加入の保険料は、給付基礎日額をもとに、以下の式で計算されます。
給付基礎日額は特別加入の申請に基づき、労働局長によって決定されます。保険料の計算のほか保険給付の金額算出の基礎となるため、適正な額である必要があります。
役員が労災保険の特別加入をする手続き
事業主などの役員は、家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して行われることが必要です。申請書に特別加入を希望する役員の氏名や給付基礎日額を記入し、労働保険事務組合を通じて加入申請の手続きをします。
役員でも労災保険が適用される場合もあるため、しっかり理解しよう!
労災保険は、労働者を対象とした保険制度で、事業主などの役員は労災保険の対象外とされています。しかし、役員であっても労働者と同じ身分である場合は、労災保険の対象になります。役員が労災保険の対象となるかどうかは、実態で判断され、労働者性が認められれば、労災保険の対象として扱われます。
また、中小事業主は労災保険に特別加入することができ、その場合は役員、その家族も労災保険に特別加入することができます。労災保険に特別加入すると、労災事故にあった場合などに保険給付を受けることができます。労災保険や、労災保険の特別加入について理解し、万が一の場合に備えましょう。
よくある質問
役員は労災保険の適応外ですか?
役員は基本的に労災保険の適応外ですが、労働者性によっては対象となる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
労災保険の特別加入制度とはなんですか?
労災保険で保護することが妥当だと認められる中小企業事業主や一人親方、特定作業従事者、海外派遣者などの労災保険への加入を特別に認める制度です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
労災保険の関連記事
新着記事
役員社宅を賢く経費にする方法は?節税メリットから賃料計算まで徹底解説
Point役員社宅の経費化とは? 役員社宅は、賃料相当額を正しく計算・徴収すれば合法的に経費化でき、大きな節税効果があります。 会社負担の家賃は損金算入可能 賃料相当額の計算が必須…
詳しくみる組織開発とは?人材開発との違いや代表的な手法、成功に導くプロセスを徹底解説
Point組織開発とは、組織全体の関係性と機能を高める取り組み。 組織開発は、人と人の相互作用を改善し、変化に強い組織をつくるプロセスです。 関係性と対話に焦点 個人でなく組織全体…
詳しくみるキャリアパス面談で何を話すべきか?理想の将来を描き自己成長につなげるための完全ガイド
Pointキャリアパス面談とは、将来像を言語化し成長戦略を描く対話です。 キャリアパス面談は、理想の将来と市場価値向上を実現するための戦略設計の場です。 将来像と現状の差を明確化 …
詳しくみるストレスチェック結果の提供同意書とは?取得のタイミングや注意点を徹底解説
Pointストレスチェック結果の提供同意書とは、結果を事業者へ共有するための法定手続きです。 ストレスチェック結果は、本人の明示的同意がなければ会社は取得できません。 事前同意は無…
詳しくみるストレスチェックの方法とは?実施手順から事後措置までの実務を徹底解説
Pointストレスチェック方法とは、労働者の心理的負担を測定し、職場改善につなげる制度。 ストレスチェックは、正しい手順と事後措置まで実施して初めて有効です。 年1回以上の実施が原…
詳しくみるストレスチェック報告書の提出期限や書き方は?労働基準監督署への報告義務と作成手順を解説
Pointストレスチェック報告書とは、実施結果を労働基準監督署へ報告する法定書類です。 ストレスチェック報告書は、常時50名以上の事業場が年1回実施後、遅滞なく提出します。 対象は…
詳しくみる