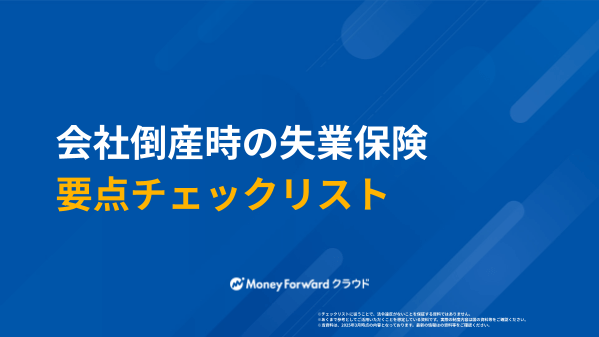- 更新日 : 2025年11月12日
会社が倒産したら失業保険はいくらもらえる?計算方法と注意点
会社が倒産した場合の失業保険は、自己都合で会社を辞めた場合よりも手厚くなっています。
所定給付日数は多く、給付制限を受けずに受給できます。被保険者期間も12カ月から6カ月に短縮され、勤務期間が1年未満でも受給できる場合があります。
この記事では、会社が倒産したらいくら基本手当を受け取れるのか、失業保険の計算方法や受給する際の注意点について解説します。
目次
失業保険とは?
失業保険とは、正式名称は「雇用保険」といい、労働者が失業等の状態になった場合に所定の保険給付等が行われます。
雇用保険は雇用の安定、雇用機会の増大、労働者の生活の安定などを目的に、さまざまな事業を行っています。求職者給付は、雇用保険が行う代表的な保険給付です。失業者の生活を安定させ、就職活動を容易にすることを目的として支給されます。求職者給付のうち、基本手当は失業中の生活保障となるものであり、一般的には失業手当ということもあります。
基本手当の金額は、基本手当日額と所定給付日数によって決定されます。
基本手当日額
基本手当日額は、賃金日額のおよそ50~80%(60~64歳は45~80%)です。賃金が低いほど、率は高くなります。賃金日額は、離職した日の直前の6カ月間に毎月決まって支払われた賃金の合計額を、180で割った金額です。次の上限が定められています。
(2022年8月1日~)
| 年齢 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 30歳未満 | 6,835円 |
| 30歳以上45歳未満 | 7,595円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,355円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,177円 |
所定給付日数
所定給付日数は、基本手当が給付される日数です。離職の理由、失業者の年齢、被保険者であった期間などによって、90~360の日数が定められています。
基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から1年間です。所定給付日数が残っていても、受給期間を過ぎると基本手当は受けられなくなります。
基本手当についての詳細は、以下の記事を参考にしてください。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
人事・労務担当者向け Excel関数集 56選まとめブック
人事・労務担当者が知っておきたい便利なExcel関数を56選ギュッとまとめました。
40P以上のお得な1冊で、Excel関数の公式はもちろん、人事・労務担当者向けに使い方の例やサンプルファイルも掲載。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。お手元における保存版としてや、従業員への印刷・配布用、学習用としてもご活用いただけます。
入社前後の手続きがすべてわかる!労務の実務 完全マニュアル
従業員を雇入れる際には、雇用契約書の締結や従業員情報の収集、社会保険の資格取得届の提出など数多くの手続きが発生します。
本資料では、入社時に必要となる労務手続き全般を1冊にわかりやすくまとめました!
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
会社が倒産したら失業保険はいくらもらえる?
会社が倒産した場合は、特定受給資格者として基本手当を受給します。また勤務していた事業所の閉鎖や移転により、離職した場合も特定受給資格者になります。
倒産の離職によって特定受給資格者となる範囲
- 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続きの申立てまたは手形取引の停止など)に伴い離職した者
- 事業所において大量雇用変動の場合(1カ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者、および当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
- 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む)に伴い離職した者
- 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
特定受給資格者の所定給付日数
| 被保険者であった期間 | ||||||
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||
| 年齢 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30歳以上 35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
| 35歳以上 45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | |||
| 45歳以上 60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
| 60歳以上 65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
特定受給資格者の失業保険受給要件
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること(特定受給資格者でない場合は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あること)
会社が倒産した時の失業保険の手続きについて
会社が倒産した場合でも基本手当受取の手続きは通常と変わりません。以下の流れで手続きします。
1.求職の申込みと受給資格の決定
ハローワークに以下の必要書類を提出して、手続きします。
- 雇用保険被保険者離職票-1、-2
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードがない場合は個人番号確認書類(通知カード、住民票記載事項証明書)と身元確認書類(運転免許証、官公署が発行した身分証明書、健康保険証など)
- 写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚
- 本人名義の預貯金通帳
↓
2.雇用保険説明会への参加
受給資格者証の交付と、基本手当の受取方法や就職活動についての説明を受けます。
↓
3.待期期間
受給資格の決定を受けてから7日間は待期期間になり、基本手当は支給されません。失業の状態が継続している必要があります。
↓
4.1回目の失業認定
4週間に1回、受給資格者証と失業認定申告書を提出します。就職活動の実績や就労状況についての確認を受けます。
↓
5.1回目の基本手当受給
失業が認定された日数分の基本手当が支給されます。
会社が倒産した場合の失業保険の注意点
失業保険ともいわれる雇用保険は、失業した労働者が早期に安定した職業に就けることを目的として給付されます。
会社倒産など、準備する余裕がないまま職業を失った場合には、自己都合で退職した場合と比べて所定給付日数が多く、待期期間もないといった、手厚い給付を受け取ることができます。
ただし多くの人が勘違いしているような、わかりにくい部分もあります。
失業保険は1度受給すると、2回目以降はもらえない?
基本手当受給後に就職し、また失業状態になった場合は、基本手当を受け取れない場合があります。受給者としての資格を有していないことによるもので、被保険者期間が短いことが理由です。
離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あること(特定受給資格者に該当する場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること)
パートも失業保険はもらえる?
パートも雇用保険に加入していれば、被保険者期間などの要件を満たすことで基本手当を受給することができます。
【雇用保険への加入条件】
- 31日以上、雇用されること(雇用見込みも含む)
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
会社が倒産したら速やかに失業保険の手続きをしよう
会社が倒産した場合には、特定受給資格者に該当し、自己都合で退職した場合よりも手厚い内容の基本手当を受けることができます。受給に必要な被保険者期間は1年間のうち6カ月以上と短縮され、さらに給付制限がないため、待期期間終了後すぐに受給できます。
所定給付日数は、90~330日です。1度もらうと2度目は就職して必要な被保険者期間を満たす必要があります。また基本手当は、パートでも受給できます。
受給期間は、1年間(所定給付日数が330日の場合は1年と30日)で、期間を過ぎると所定給付日数が残っていても受給できなくなります。受給期間は離職した日の翌日から数えるため、速やかに手続きしましょう。
よくある質問
会社が倒産したら失業保険はいくらもらえますか?
離職直前6カ月の賃金をもとに計算される基本手当日額の90~330日分を受けることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
失業保険は一度受給すると、2回目以降はもらえませんか?
失業保険を再度もらうためには、新たに受給資格を得る必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労災で医療費が10割負担?払えないときの対応や返金手続きを解説
労災(労働災害)によるけがや病気で病院を受診したにもかかわらず、医療費を全額(10割)請求されることがあります。受診した医療機関が労災指定病院でない医療機関を受診した場合や、必要書…
詳しくみる介護保険料は年齢でどう変わる?40歳から65歳以上をシミュレーション
「40歳になったら、給与の手取りが減った気がする」「65歳になったら年金から何か引かれている」。それは、「介護保険料」ではないでしょうか。介護保険料は、将来の介護に備えるための重要…
詳しくみる失業保険(失業手当)の条件は?金額や期間、再就職手当まで解説
会社を退職した後の生活を支える雇用保険の給付、いわゆる失業保険ですが、いつからいくら振り込まれるのか不安を感じる場面もあるでしょう。 失業保険(失業手当・失業給付金)の受給条件は、…
詳しくみる労災は使わない方がいい?メリット・デメリットを徹底比較
仕事中や通勤途中にケガや病気をしたとき、労災保険を使うかどうか悩む方は非常に多くいます。「会社に迷惑をかけるのではないか」「申請手続きが面倒そう」など、不安や疑問は尽きないものです…
詳しくみる雇用保険における再就職手当とは
失業や休業の場合にはもちろん、労働者が能力開発のため教育を受ける場合にも利用できる雇用保険。一般的には失業保険と言われる、自己による都合や会社側の都合によって離職した際に支給される…
詳しくみる労働保険とは?加入条件や料率の計算、手続き方法、未加入の場合を解説
労働保険は、労災保険と雇用保険を総称するもので、事業主が加入手続きを行います。この保険には、両保険を一括管理する一元適用と、別々に扱う二元適用があり、農林水産業や建設業は二元適用事…
詳しくみる