- 更新日 : 2025年7月10日
裁量労働制における「みなし労働時間」とは?
働き方改革が進む中、多様な労働形態への関心が高まっています。その中でも「裁量労働制」は、専門性の高い業務に従事する労働者にとって、時間に縛られない自由度の高い働き方を実現する制度として注目されています。
しかし、裁量労働制について「定額働かせ放題」といった誤解や、制度の本質を理解しないまま導入されるケースも少なくありません。特に、制度の核心となる「みなし労働時間」については、その意味や適切な設定方法について正しく理解している企業は多くないのが現状です。
みなし労働時間とは、実際の労働時間に関係なく、あらかじめ定められた時間働いたものとみなす仕組みです。しかし、単に割増賃金を節約する目的で短めの時間を設定することは法の趣旨に反し、労働者の権利を侵害することにもつながりかねません。
本記事では、裁量労働制における「みなし労働時間」の正しい理解と適切な運用方法について、法的な根拠から実務上の注意点まで、人事担当者が知っておくべきポイントを詳しく解説します。制度の本来の趣旨を理解し、労使双方にとってメリットのある運用を実現するための知識を身につけましょう。
目次
裁量労働制における「みなし労働時間」の意味
裁量労働制とは、特定の業務に就労した労働者の労働時間について、実際の労働時間にかかわらず一定の労働時間働いたものとみなす制度です。働いたものとみなされる時間のことを「みなし労働時間」といいます。
例えば、みなし労働時間を9時間と定めた場合には、実際の労働時間が8時間や10時間であったとしてもみなし労働時間の9時間働いたものと扱います。なお、8時間を超えるみなし労働時間を設定する場合、1日8時間を超えた部分については、通常の労働時間の原則どおり、時間外割増賃金の支払いが必要になります。
また、裁量労働制の「みなし労働時間」の規定は、労働基準法に定める年少者、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(本人から請求があった場合に限る。以下「妊産婦」という。)には適用されません。年少者および妊産婦については、労働基準法上、時間外労働が禁止されていますが、みなし労働時間を適用する場合、実労働時間ではなくみなし労働時間で労働時間を算定することとなるため、時間外労働の禁止規定の効力が及ばなくなってしまう恐れがあるためです。
なお、妊産婦については本人からの請求があった場合は、裁量労働制を適用せず、実労働時間を算定しなければなりませんが、妊産婦であっても裁量労働制を希望する場合等も考えられますので、適用可否は、当該業務や本人の状況等を判断して慎重に考えるべきでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール
年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。
本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。
労働時間管理の基本ルール【社労士解説】
多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。
労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。
36協定の締結・更新ガイド
時間外労働や休日労働がある企業は、毎年36協定を締結して労働基準監督署に届出をしなければなりません。
本資料では、36協定の役割や違反した場合の罰則、締結・更新の手順などを社労士がわかりやすく解説します。
割増賃金 徹底解説ガイド(時間外労働・休日労働・深夜労働)
割増賃金は、時間外労働や休日労働など種類を分けて計算する必要があります。
本資料では、時間外労働・休日労働・深夜労働の法的なルールを整理し、具体的な計算例を示しながら割増賃金の計算方法を解説します。
裁量労働制における「みなし労働時間」の定め方
裁量労働制における「みなし労働時間」は、そもそも業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者に委ねるべき業務について、個々に実労働時間を算定するのではなく、実態に応じた適切な労働時間働いたものとみなして、実際の時間配分を労働者に委ねるものです。
例えば、これまでの事例から考えて毎日11時間、12時間と働かなければ終わらないような業務について、割増賃金を払いたくないからといって、みなし労働時間を実態より短い8時間や9時間といった時間に定めるようなことは許されません。
東京労働局の説明資料では、次のように記載されています。
「実際のみなし労働時間の決め方については、法令で『このような水準に決めるべき』という規定は盛り込まれていませんが、割増賃金節約だけのために短めのみなし労働時間を定めることは、制度の趣旨に反しています。このため決議する際に、労使委員会の委員は、使用者側から評価制度、賃金制度に関する説明を十分に受けて、対象業務の内容を理解した上、みなし労働時間が適切な水準のものとなるよう決議するように留意してください。」(東京労働局「『企画業務型裁量労働制』の適正な導入のために」より。)
専門業務型裁量労働制の場合も趣旨は同じです。専門業務型・企画業務型それぞれ、労使協定・労使委員会決議でみなし労働時間を定めます。みなし労働時間の決定に労働者の関与を必須のものとすることで、割増賃金節約を目的とするような、制度の濫用を防ぐこととされています。
裁量労働制と他の制度との関係(変形労働時間制等)
裁量労働制の理解のためにここでは、労働時間の柔軟化について様々な他の制度と比較してみたいと思います。
1.労働時間法制の変遷
もともと、労働時間法制は工場などで集団的に働く労働者を念頭に置き、定型的な規制を課すものでした。すなわち1日8時間、1週40時間の労働時間を法定労働時間とし、これを超える労働に対しては割増賃金を支払う、という考え方でした。
しかし、脱工業化・グローバル化の進展の中で、従前の働き方のみでは、多様化する社会に対応できなくなりました。また、日本特有の事情として、長期雇用を前提とする長時間労働の問題があります。業務の繁閑に応じて労働者を採用・解雇するのではなく、長期安定的に雇用を続ける。業務が縮小しても労働者を安易に解雇することはしないが、業務繁忙の時には長時間労働で対応する、という働き方です。これが過重労働を生み、過労死・過労自殺にさえ至っています。
2.労働時間法制の柔軟化
労働者の健康を守り、ワークライフバランスを改善するために、労働時間法制について柔軟化が図られています。柔軟化の方法は二通りあります。
(1)法定労働時間の柔軟化
法定労働時間を1日8時間1週40時間に固定せず、一定の期間内などでトータルしてこの範囲に収まるならば、柔軟に定めることを認めるものです。以下の二通りがあります。これらはあくまで法定労働時間の取り扱いを柔軟化するものであり、定められた期間での実際の労働時間が法定労働時間を超えた場合には、割増賃金が支払われます。
1.変形労働時間制
1週間・1ヶ月・1年など、一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間に収まるなら、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて働かせることができる制度です。
2.フレックスタイム制
1ヶ月(2019年4月以降は3ヶ月)以内の一定の期間の総労働時間を決めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自らの意思で決めて働くことができる制度です。
(2)労働時間算定そのものの柔軟化
労働者の実際の労働時間にかかわらず、一定の労働時間を「働いたものとみなす」制度です。みなし労働時間の中に時間外労働が含まれている場合その分の割増賃金も支払われますが、実際の労働時間がみなし労働時間より多くても少なくても支払われる賃金は変わらないことになります。専門業務型や企画業務型のほか、事業場外労働など、実際の労働時間算定が困難な場合にも認められています。
裁量労働制における使用者の具体的指示の禁止とは
裁量労働制で、実際の労働時間でなく労使で定めた「みなし労働時間」働いたものとする趣旨は、業務の遂行方法も時間の配分も労働者の裁量に任せるべき業務だからです。使用者が始業・終業の時間を指定したり、特定の時間帯の勤務を労働者に命じたりすることは許されません。逆に言えば、そのような使用者の指示が必要な業務ならば裁量労働制の適用対象にはならないものです。裁量労働制の業務の要件については、別記事で詳しく説明しています。
「みなし労働時間」を適切に設定し、運用していきましょう
裁量労働制におけるみなし労働時間の意味は上述の通りであり、対象となる業務は、時間配分や業務遂行の方法を労働者に任せるものに限定されています。昨今、この趣旨を理解せずに「定額働かせ放題」であるかのような誤解がしばしば見られます。裁量労働制は、労使の協議決定により導入されるものですので、使用者・労働者双方が趣旨を理解して適切な運用をするように努めなければなりません。
<参考>
水町勇一郎「労働法第7版」262~264、277~284頁
東京労働局「労働基準法のあらまし」
<関連記事>
みなし残業は労働基準法違反か?法的根拠と注意点を解説
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
年5日の有給休暇の取得義務に罰則はある?ばれないもの?中小企業の対応を解説
2019年4月の労働基準法改正により、企業は年に10日以上有給休暇が付与される従業員に対して、年5日以上の有給休暇を取得させる義務があります。違反すれば罰則の対象となるため、適切な…
詳しくみる就業規則の慶弔休暇規程の記載例・雛形|日数や適用範囲、休日の取り扱いなども解説
従業員のライフイベントに配慮し、安心して働ける環境を整備することは、企業の持続的な成長にもつながります。その中でも慶弔休暇は、従業員の働きやすさを支える福利厚生のひとつとして、エン…
詳しくみる出張とは?各種手当や日帰り・宿泊の判断基準を解説!
普段の就業場所において業務を行うだけでなく、異なった場所に出張する必要性が生じる場合もあります。会社員には馴染みの深い出張ですが、正しく理解できている方は少ないのではないでしょうか…
詳しくみる勤怠管理はなぜ必要?企業が守るべき5つの理由や管理方法を解説
勤怠管理は本当に必要なのかと疑問に思う企業担当者もいるでしょう。しかし、従業員の出退勤を正確に把握することは法律上の義務であり、企業運営の根幹を支える重要な業務です。 働き方改革や…
詳しくみるシフトや勤務変更の進め方とは?拒否できるケースやトラブルを防ぐコツを解説
勤務時間や業務内容、勤務地が変更される「勤務変更」は、企業が柔軟に運営を進めるうえで欠かせない対応です。一方で、こうした変更は従業員の生活や働き方に直結するため、不安や疑問を抱かれ…
詳しくみる出社とは?企業や従業員のメリット・デメリット、リモートの課題を解説
ここ数年の労働環境は、リモートワークの普及により大きく変化しましたが、出社の重要性は依然として高いままです。この記事では、出社の定義、コロナ禍を経てなぜ出社率が再び高まっているのか…
詳しくみる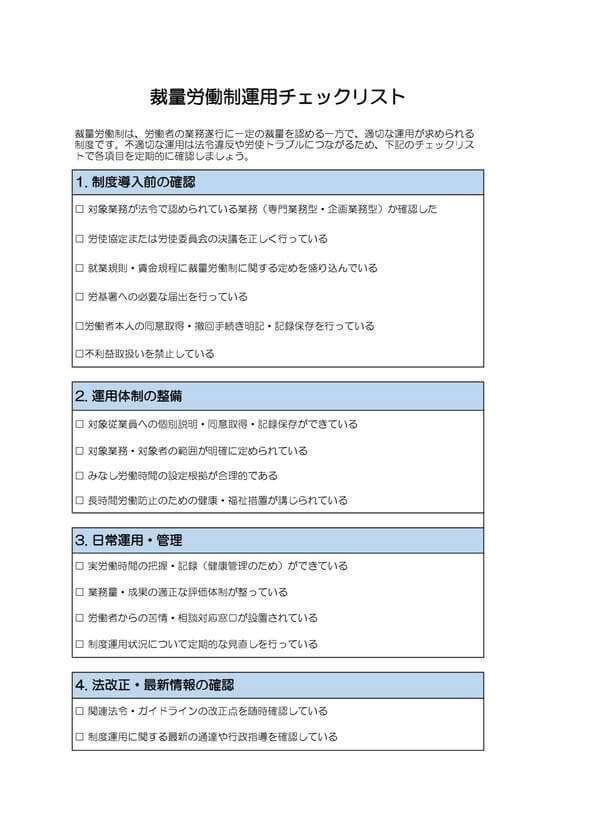



.png)