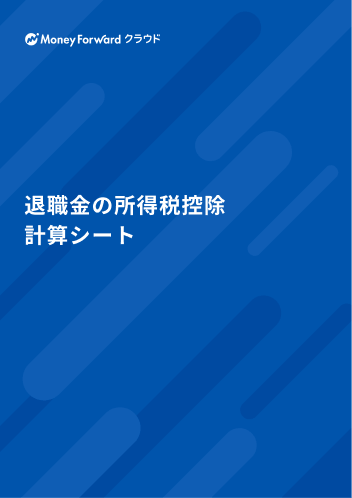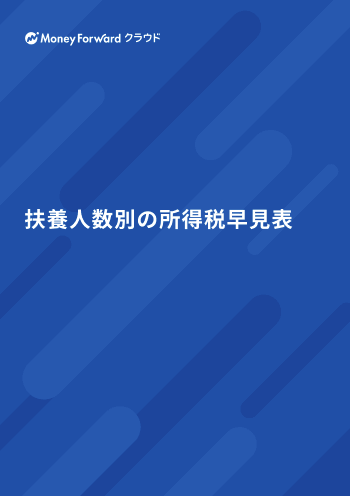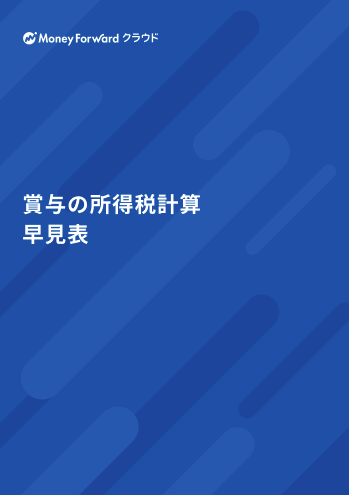- 更新日 : 2025年12月24日
退職所得控除とは?計算方法や退職金にかかる税金、確定申告手続きをわかりやすく解説
退職金にかかる税金の負担を大きく軽減する「退職所得控除」という制度があります。この制度を正しく理解し活用することで、将来受け取る手取り額が大きく変わる可能性があります。
この記事では、退職所得控除の基本的な仕組みから、勤続年数に応じた控除額の計算方法、税額のシミュレーション、iDeCoや5年ルールといった注意点まで、あらゆる疑問に答えます。ご自身の退職金がいくらになり、税金はいくら引かれるのか、この記事でしっかり確認していきましょう。
※実際の税額は個々の条件によって変わるため、最終的には「退職所得の受給に関する申告書」や自治体・税務署の案内で確認してください。
目次
退職所得控除とは
退職所得控除とは、退職金などの「退職所得」から一定額を差し引ける、所得税法上の優遇制度です。この控除により課税対象となる金額が大幅に減少し、結果として所得税や住民税の負担が軽くなります。
税法上、退職時に勤務先から受け取る退職一時金・企業年金・解雇予告手当などは「退職所得」に区分されます。毎月の給与や賞与が「給与所得」として課税されるのに対し、退職所得は長年の勤務に対する功労報酬としての性格を持つ一時的な所得であるため、特別な税制上の配慮が設けられているのです。
参考:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
人事・労務関連の法改正まとめ 2026年版
所得税などの実務と並行して確認しておきたいのが、今後の労働法制の動きです。特に議論が進む労働基準法の改正は、企業の労務管理を大きく変える可能性があります。
最新の法改正情報と実務対応をまとめた本資料で、いつ、何が変わるのかを今のうちに把握しておきましょう。
扶養人数別の所得税早見表
所得税額は給与額や扶養親族の人数によって細かく変動します。毎月の給与計算で、正しい税額を算出できているか不安になることはありませんか?
計算ミスは給与の修正対応など無駄な業務を生んでしまいます。給与額と扶養人数を照らし合わせるだけで税額がわかる本資料を、計算時の確認用としてお使いください。
賞与の所得税計算早見表
年数回しかない賞与計算は、毎月の給与計算に比べて手続きを間違いやすい業務です。特に所得税は前月の給与額を基準にするなど特殊な算出が必要なため、計算ミスが起こりかねません。
複雑な計算や表の確認作業を効率化できる本資料で、ミスのない正確な賞与計算を行いましょう。検算用としても便利です。
退職所得控除額の計算方法
退職所得控除額は、勤続年数によって計算方法が決まります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額の計算式 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数 ※計算結果が80万円未満の場合は80万円 |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 – 20年) |
退職所得控除の計算は「勤続年数が20年以下」か「20年超」かで大きく2つに分かれます。計算する上での重要なポイントは、勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて1年として扱う点です。たとえば、勤続19年6ヶ月の場合は、「20年」として計算します。この端数切り上げの取り扱いは、退職所得控除額を算出する際の法定ルールとして明確に定められています。
- 勤続年数が15年(14年3ヶ月)の場合
20年以下の計算式を適用します。
勤続年数の端数は切り上げるため、15年で計算します。
計算式:40万円 × 15年 = 600万円 - 勤続年数が40年の場合
20年超の計算式を適用します。
計算式:800万円 + 70万円 ×(40年 – 20年)= 2,200万円
退職所得控除額の早見表
ご自身の勤続年数と照らし合わせるだけで、退職所得控除額が一目でわかる早見表です。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 80万円 | 21年 | 870万円 |
| 5年 | 200万円 | 25年 | 1,150万円 |
| 10年 | 400万円 | 30年 | 1,500万円 |
| 15年 | 600万円 | 35年 | 1,850万円 |
| 20年 | 800万円 | 40年 | 2,200万円 |
受け取る退職金の額が退職所得控除額以下であれば、課税所得はゼロとなり、結果的に所得税や住民税は課されません。ただし、同一年中に複数の退職金を受け取る場合や勤続年数が短い者・役員等については、控除額や課税方法が異なるため注意が必要です。これらのケースでは、通常の退職所得控除の計算が適用されない場合もあるため、申告時には源泉徴収票や支給明細をもとに慎重に確認することが重要です。
退職金にかかる税金の計算方法
退職金にかかる所得税の計算は一見複雑に見えますが、3つのステップに分けることで、正確に算出できます。
ステップ1. 課税退職所得金額を求める
最初に、税金の計算対象となる「課税退職所得金額」を求めます。 この金額は、退職金の満額ではなく、所得税法第30条・第31条および所得税法施行令第70条に基づき、以下の計算式で算出されます。これにより、退職金にかかる税負担が大幅に軽くなる仕組みになっています。
- 退職所得控除額を差し引く
まず、ご自身の勤続年数に応じた「退職所得控除額」を退職金の総額から差し引きます。これにより、課税の対象となる金額が大幅に減ります。 - さらに1/2にする
次に、1.で計算した金額を半分(1/2)にすることで、長年の勤続に対する功労を配慮した税制上の優遇措置(所得税法第30条第3項)が適用されます。 - 1,000円未満は切り捨てる
最後に、計算して出た金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます(所得税法施行令第70条第2項)。
- 退職所得控除額を計算
勤続30年は「20年超」の区分なので、
800万円 + 70万円 ×(30年 – 20年)= 1,500万円 - 課税退職所得金額を計算
(2,000万円 – 1,500万円)× 1/2 = 250万円
この250万円が、所得税を計算するための元となる金額です。
ステップ2. 所得税額を算出する
次に、ステップ1で算出した課税退職所得金額をもとに、実際の所得税額を計算します。この算出は、所得税法第89条および所得税法施行令第164条に基づく「超過累進税率」により行われ、国税庁が公表する下記の「所得税の速算表」を用いて計算します。
| 課税退職所得金額(A) | 所得税率(B) | 控除額(C) |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
- ご自身の「課税退職所得金額」が、表のどの区分に当てはまるかを探します。
- その区分の「所得税率」を掛け算します。
- 最後に、同じ区分の「控除額」を引き算します。
- 300万円は、速算表の「195万円超 330万円以下」の区分に該当します。
- この区分の税率は10%、控除額は97,500円です。
- 計算式に当てはめます。
300万円 × 10% – 97,500円 = 202,500円
この202,500円が、基準となる所得税額です。
ステップ3. 最終的な納税額を計算する
最後に、ステップ2で算出した所得税額に、「復興特別所得税」を加えます。この税は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するための特別措置に関する法律(復興財源確保法)附則第104条および所得税法第12条に基づき、基準となる所得税額の2.1%を上乗せして課税する仕組みです。
計算を簡単にするため、以下の式を使います。
- 202,500円 × 102.1% = 206,752.5円
- 1円未満の端数を切り捨てて、最終的な所得税の納税額は 206,752円 となります。
住民税の計算も忘れずに
退職所得には、所得税だけでなく住民税も課税されます。住民税の税率は一律10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)ですが、これは地方税法第34条の2および第321条の5に基づくもので、退職所得に対する住民税は、「退職所得に係る特別徴収」として、支払者(事業主)が退職金の支払時に源泉徴収し、翌月10日までに納入する仕組みとなっています。この制度は総務省の通達(個人住民税の特別徴収制度に関する取扱い)に基づき適用されており、所得税の源泉徴収とは制度が異なります。そのため、納税者本人が別途住民税を納付する必要はありません。
退職金にかかる所得税・住民税の計算シミュレーション
ケース1. 勤続15年、退職金1,500万円の場合
- 退職所得控除額:40万円 × 15年 = 600万円
- 課税退職所得金額:(1,500万円 – 600万円)× 1/2 = 450万円
- 所得税額:450万円 × 20% – 427,500円 = 472,500円
- 納税額(所得税):472,500円 × 102.1% = 482,422円
ケース2. 勤続38年、退職金3,500万円の場合
- 退職所得控除額:800万円 + 70万円 ×(38年 – 20年)= 2,060万円
- 課税退職所得金額:(3,500万円 – 2,060万円)× 1/2 = 720万円
- 所得税額:720万円 × 23% – 636,000円 = 1,020,000円
- 納税額(所得税):1,020,000円 × 102.1% = 1,041,420円
退職所得控除の注意点
退職所得控除を利用する際には、いくつかの注意点があります。特に勤続年数が短い場合やiDeCoを受け取る際など、税負担や手続きが変わるケースがあるため、事前に確認しておくことが重要です。
短期退職で注意すべき「5年ルール」
勤続年数が5年以下の従業員などが受け取る退職金は、税制上の優遇措置が一部適用されません。これは一般に「5年ルール」と呼ばれ、短期勤続者に対して課税上の特例を制限する制度です。
具体的には、課税退職所得金額を計算する際に通常適用される「×1/2」措置(所得税法第30条第3項)が勤続年数5年以下の者に支払われる退職手当等については適用除外とされています(所得税法第30条第4項、所得税法施行令第70条第3項)。このルールは、従来は法人役員や特定役員等に限定されていましたが、2022年1月1日以降の支給分からは一般従業員にも適用対象が拡大されています。
iDeCo(個人型確定拠出年金)を一時金で受け取る場合
iDeCoの老齢給付金を一時金で受け取る場合も、税法上は退職所得として扱われ、退職所得控除の対象となります。これは、所得税法第30条・第31条および確定拠出年金法第32条に基づく取扱いです。また、同一年中に複数の退職金(一時金)を受け取る場合は、所得税法施行令第69条第3項の規定により、これらを合算の上で勤続年数を通算(重複部分は除外)して控除額を計算します。その結果、控除額を使い切ってしまい、2回目以降の受給分が課税対象となる場合があります。そのため、iDeCoの受取時期と退職金の支給時期をずらすなど、受給のタイミングの調整が税負担軽減の有効な対策となります。
退職金の額が退職所得控除額より少ない場合
退職金の額が退職所得控除額を下回る場合、課税退職所得金額は0円となり、所得税および住民税は課されません。これは、所得税法第31条および所得税法施行令第69条に基づく取扱いで、退職所得控除額が実際の退職金額を上回るときは、課税対象が生じない仕組みとなっています。なお、控除しきれなかった金額を他の所得(給与所得・事業所得など)から差し引く(損益通算する)ことはできません(所得税法第69条の趣旨による)。
複数から退職金を受け取る場合
前年以前4年以内に他の会社から退職金を受け取ったことがある場合や、同一年中に複数の会社から退職金を受け取る場合には、勤続年数の重複期間を調整して退職所得控除額を計算する必要があります(所得税法施行令第69条第3項)。この場合、それぞれの退職金を単独で計算するのではなく、通算した勤続年数に基づき控除額を算定するため、通常の計算方法とは異なります。
障害者になったことが退職の原因である場合
退職の原因が障害者になったことによる場合は、通常の計算式で算出した退職所得控除額に100万円が加算されます。これは所得税法施行令第69条第6項に定められており、障害により退職した者の生活上の配慮を目的とした特例です。
退職金を年金形式で受け取る場合
退職金を年金形式で受け取る場合、この退職所得控除は適用されません。年金として定期的に受け取る場合は、税法上「雑所得」に区分され、所得税法第35条・第36条および施行令第83条・第84条に基づき「公的年金等控除」の対象となります。一方、一般的に、一時金で受け取る場合には「退職所得」として扱われ、退職所得控除(所得税法第31条)や1/2課税などの優遇措置が適用されます。そのため、一般的に一時金で受け取る方が税制上有利となるケースが多いものの、老後の生活設計や資金管理の観点から、自身のライフプランに合わせて受取方法を検討することが重要です。
未払賃金立替払制度を利用した場合
企業の倒産により国が未払賃金を立て替える「未払賃金立替払制度」により退職金相当額を受け取った場合も、税法上は退職所得として扱われ、退職所得控除が適用されます。これは賃金の支払の確保等に関する法律第7条・第7条の2に基づく立替払いであっても、所得税法第30条・第31条上、退職手当等の性質を有するものとみなされるためです。
令和7年以降の退職所得控除の改正の見通し
現時点では、政府税制調査会において、退職所得課税制度の見直しが議論されています。制度見直しの背景には、働き方・雇用の移動性を高めるため、長く在籍することに税制上の優遇が偏っているという指摘があります。たとえば、現行制度では、勤続年数が20年超の部分について控除額が増える仕組みとなっており、これが転職を妨げる一因になっているとの指摘があります。
また、2025年(令和7年)税制改正大綱において、勤続期間等の重複排除規定の見直しなどが明記されています(例:前年以上4年以内に他の退職金を受け取った場合の勤続年数重複排除を9年に延長)。
これらの改正は、主に2026年(令和8年)以降に支給となる退職金等に適用される予定です。今後の改正の動向を把握しておくことが重要です。
退職所得控除を受けるための手続き
退職所得控除の適用を受けるためには、「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」を退職金が支払われる前に支払者へ提出することが必須です(所得税法第203条、所得税法施行規則第77条)。
参考:A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)|国税庁
この申告書を提出すれば、勤務先(退職金の支払者)が課税退職所得金額を計算し、源泉徴収(給与天引き)を実施するため、原則として受給者自身が確定申告を行う必要はありません。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないとどうなる?
「退職所得の受給に関する申告書」を提出し忘れると、退職金の支払額に対して一律20.42%(所得税20%+復興特別所得税2.1%)が源泉徴収されます。これは、所得税法第203条および所得税法施行令第322条の2に基づき、申告書未提出時は退職所得控除などの優遇を適用せず、退職金全額を課税対象とみなして源泉徴収する取扱いとなるためです。その結果、実際の税負担よりも多く天引きされる場合があるため、翌歳に確定申告を行って払い過ぎた税金を還付申告する必要があります。スムーズな手続きを行うためにも、退職金支給前に必ず申告書を提出しておくことが重要です(復興財源確保法附則第104条)。
退職金の確定申告が必要になるケース
原則として退職金に関する確定申告は不要ですが、以下のような場合には申告が必要となります。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
(所得税法第203条により、申告書未提出時は一律20.42%で源泉徴収されるため) - 年をまたいで退職金が支払われ、源泉徴収が正しく行われなかった場合
(所得税法第120条・第121条の確定申告義務規定に基づく) - 海外企業などから退職金を受け取り、日本で源泉徴収が行われていない場合
また、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)を受けたい場合には、退職所得に関係なく確定申告を行うことで税金が還付される可能性があります。
退職金を受け取る際には申告書の提出を忘れずに
本記事では、退職所得控除の仕組みから具体的な税金計算、iDeCoや5年ルールなどの注意点などを解説しました。
退職所得控除は、長年の勤労に報いるための税制優遇制度です。この制度を最大限に活用するためには、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に必ず提出することが何よりも重要です。
退職金は、あなたのこれからの人生を支える大切なお金です。この記事を参考に制度を正しく理解し、ご自身の権利をしっかりと活用してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
給与計算の認定試験「給与計算実務能力検定試験」とは?難易度や勉強方法などを解説
給与計算の実務スキルを客観的に証明したいと考えたとき、多くの実務者が目標とするのが「給与計算実務能力検定試験」です。この資格は、給与計算の専門知識と実務能力を社会的な基準で証明する…
詳しくみる住民税の決定通知書はいつ届く?会社と個人の時期や納付書がない理由を解説
住民税の決定通知書や納付書は、徴収方法によって異なりますが、一般的に毎年5月から6月にかけて手元に届きます。 会社員などの「特別徴収」対象者は5月頃に勤務先へ、個人事業主などの「普…
詳しくみる給与計算の時間短縮方法を解説!ツールの選び方も紹介
給与計算は、月末から月初にかけて勤怠集計や控除計算を短期間で正確に処理する必要があり、担当者に大きな負担がかかります。本記事では、そんな煩雑な業務を根本から見直し、時間を短縮する方…
詳しくみる香川県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
香川県でビジネスを展開する企業にとって、給与計算は従業員の満足度と企業の信頼性を左右する重要な業務です。しかし、税務や社会保険の複雑な手続きを自社で管理するのは大きな負担となります…
詳しくみる静岡県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
静岡県内で給与計算代行サービスを依頼したいと考えたとき、「一体いくらぐらいかかるのか」「信頼できる事務所の見つけ方は?」といった疑問が浮かんでくるでしょう。 地域特性や企業規模、業…
詳しくみる福利厚生賃貸とは?住宅系福利厚生制度と他の福利厚生制度を比較しながら解説
採用や人材定着、ブランディングなど、さまざまな部分に影響を与える福利厚生。 今回は福利厚生の基礎知識に加え、住宅系福利厚生制度(住宅手当/社宅制度)と他の福利厚生の比較、福利厚生賃…
詳しくみる