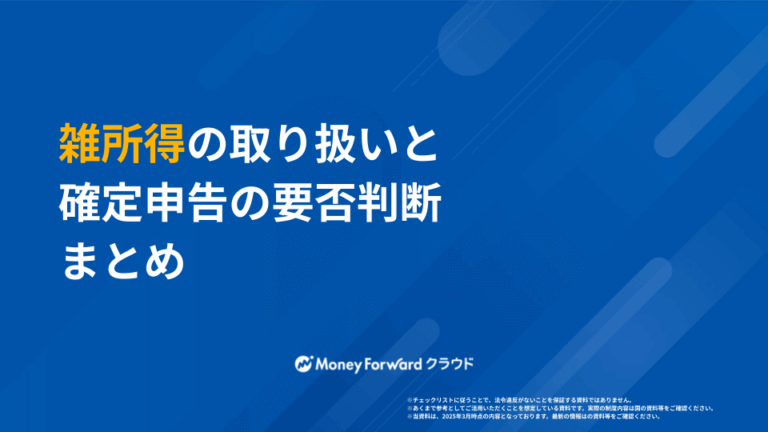- 更新日 : 2025年11月6日
年末調整で雑所得は処理できるか?
給与以外に雑所得がある場合、年末調整で処理することはできるのでしょうか。
年末調整とは、基本的には会社で支払われる給与をもとに、生命保険料など必要経費を控除する計算を、会社が代わりに行ってくれるものです。そのため、会社の給与以外の雑所得は年末調整での処理はできません。
今回は雑所得の処理について解説します。
雑所得とは
まず所得には、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得がありますが、これ以外の所得はすべて雑所得になります。
つまり、雑所得は、所得の性質がよくわからない所得を全て含めているものになります。具体例としては、公的年金での受取やアフィリエイトからの収入などがあります。
年末調整と雑所得
年末調整は、会社員等が自ら確定申告しなくてもいいように、会社で定型的な所得控除をしてもらえる便利な制度です。その趣旨から、雑所得のような定型的でない所得については年末調整で処理することはできません。
確定申告と雑所得
雑所得は年末調整では処理できないことから、原則として確定申告することになります。ただし、雑所得が20万円以下の場合には確定申告は不要になります。
ここで注意が必要なのは、サラリーマンでも医療費控除を受ける場合や会社からの給与以外に所得があるなど、確定申告をしなけなければいけないなら、雑所得が仮に20万円以内であったとしても確定申告で雑所得について申告をしなければいけません。20万円以内について確定申告を不要としているのは、少額の所得について確定申告を求めると納税者の負担が大きいからです。
ほかの理由で確定申告をするのであれば、原則どおり確定申告が必要になるということです。
したがって、生命保険料控除を年末調整で申告するのを忘れたので、確定申告するような場合にも、雑所得があれば申告しなければなりません。
住民税の申告と雑所得
所得税では、給与とは別の所得が20万円までであれば、確定申告は不要ですが、住民税にはそのような規定がないため、給与所得と合わせて住民税の申告が必要です。
雑所得の計算方法
(1)公的年金を受給している場合
「公的年金受給額 − 公的年金等控除額」により計算されますが、以下の速算表により簡単に計算されます。
例えば、70歳で400万円年金を受け取ると、「400万円 × 75% − 37万5,000円 =262万5,000円」になります。
■速算表
【65歳未満】
| 公的年金等の収入金額 | 掛率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 700,001 円から 1,299,999 円まで | 1 | 70 万円 |
| 1,300,000 円から 4,099,999 円まで | 0.75 | 37 万 5,000 円 |
| 4,100,000 円から 7,699,999 円まで | 0.85 | 78 万 5,000 円 |
| 7,700,000 円以上 | 0.95 | 155 万 5,000 円 |
【65歳以上】
| 公的年金等の収入金額 | 掛率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,200,001 円から 3,299,999 円まで | 1 | 120 万円 |
| 3,300,000 円から 4,099,999 円まで | 0.75 | 37 万 5,000 円 |
| 4,100,000 円から 7,699,999 円まで | 0.85 | 78 万 5,000 円 |
| 7,700,000 円以上 | 0.95 | 155 万 5,000 円 |
(2)公的年金以外の雑所得がある場合
「総収入金額 − 必要経費」により計算されます。例えば、アフィリエイトで収入が50万円あり、通信費やパソコン購入費などの必要経費が25万円あったとすれば、「50万円 − 25万円 = 25万円」が所得になります。
(3)特例措置
雑所得は、他の所得と合算される総合課税になります。しかし、先物取引、オプション取引、外国為替証拠金取引(FX)などの収益は、先物取引に係る雑所得等の特例の対象になっており、総合課税ではなく申告分離課税になっています。
申告分離課税というのは、ほかの所得と合算せずに、当該所得に税率を掛けて税額を計算する方法です。税率は、所得税が15%、地方税が5%になっています。
なお、店頭取引と市場取引との間の損益通算は可能なので、複数の金融取引がある場合には、チェックしてみるとよいでしょう。また、損益通算をした結果がマイナスとなれば、3年間の繰越控除が認められているので、次年度以降収益が発生した場合には、繰り越した損失を収益から控除することができます。
まとめ
以上、雑所得について解説してきました。最近は、ネットで収益を得ている人も増えてきているので、税務当局も目を光らせているようです。
年末調整では雑所得は申告できませんので、確定申告の時期になったら、1年を振り返り、申告すべき収益を得ていないかきちっとチェックし、申告漏れがないよう注意しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
なぜ大変?年末調整を効率化するシステム導入から電子化の方法まで解説
毎年多くの時間と手間がかかる年末調整。従業員からの書類回収や度重なる修正依頼に、頭を悩ませている担当者の方も多いのではないでしょうか。この煩雑な業務は、やり方を見直すことで大幅な効率化が可能です。 この記事では、年末調整がなぜ大変なのかとい…
詳しくみる年末調整での保険料控除の書き方をわかりやすく解説!
一定の生命保険料・地震保険料・社会保険料を支払うと、所得税計算で保険料控除の対象になり、給与所得に対する課税金額を低く抑えることができます。会社員の場合は会社が実施する年末調整で申告することにより、定められた方法で計算される金額の控除が受け…
詳しくみる年末調整のときに記載する住所は住民票の住所でよい?
年末調整の書類には、住所を記載する欄が設けられており、提出の際は正しく書かなければなりません。原則として記入する住所は、年末調整の翌年1月1日に住民票をおいている住所です。実際に住んでいる住所と住民票をおいている住所が異なる場合、年末調整の…
詳しくみる社労士が年末調整を行うのは違反?社労士と税理士の業務範囲を解説!
企業の人事労務担当者にとって相談しやすい専門家は、税理士と社労士ではないでしょうか。しかし、社労士と税理士とでは、専門家として行える業務範囲が異なります。 毎年年末に行う重要な業務に年末調整があります。年末調整の業務を依頼するのは、税理士と…
詳しくみる年末調整のRPA活用で何が自動化できる?業務フローやメリットを徹底解説
年末調整は、RPA(Robotic Process Automation)を導入することで、これまで多くの時間を費やしてきた手作業を大幅に効率化できます。これにより、申告書のデータ入力や煩雑なチェック作業が自動化され、担当者の負担軽減とヒュ…
詳しくみる年末調整の障害者控除を受けるには?いくら戻るか、書類の書き方も解説【令和7年・2025年】!
本人、配偶者、親や家族が障害者である場合、「障害者控除」の対象となります。年末調整で申告することで、課税金額を低く抑えて所得税負担を軽減することができます。控除を受けるには年末調整の書類に記入することが必要ですが、障害者が本人か、配偶者、親…
詳しくみる