- 更新日 : 2025年6月23日
マイナンバーと住基ネットの関係って何?
住基ネットの導入。
当時は様々な議論を引き起こしましたが、そのためもあってか結局はあまり普及しませんでした。普及率はいまだ5パーセント前後。今回、新たに導入されるマイナンバー、住基ネットとの関係に迫りたいと思います。
マイナンバーと住基ネット
住基ネットは、正式名称を「住民基本台帳ネットワークシステム」と言います。
氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通で本人確認ができるようにされていました。導入された当時はいろいろな議論が巻き起こったため、参加しない自治体が出てくるなど、大きな話題となりました。
ただマイナンバーと大きく違う点は、行政機関間での情報連携を目指したものではなく、あくまでも自治体の事務における個人情報の効率化を目指していた点です。
一方、マイナンバーは行政機関間での情報連携を目指し、国の各行政機関の合意形成の下、制度が設計されてきました。個人番号カードについても、住民基本台帳カードが普及しなかったことを鑑み、国民の利便性向上のため、さまざまな機能が付与されていく予定です。
具体的には、以下のような機能が挙げられています。
・公的資格確認機能
・公的個人認証機能
・ICチップの民間開放
・地方公共団体による独自利用
・キャッシュカード・クレジットカード機能
・健康保険証としての機能
まだ実現するかどうかは分かっていませんが、仮にすべての機能が搭載されると、カードはこれ1枚だけで大丈夫、ということにもなりそうです。
これだけの機能を盛り込むのは、やはり住民基本台帳カードが使いにくいという評判のためか、普及率がかなり低くとどまったことも原因の一つにあると考えられます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
マイナンバーカードの保険証利用の拡大で発生しやすい5つのトラブル
医療機関等へのオンライン資格確認の導入が原則義務化され、今後マイナ保険証を利用する従業員は増えることが予想されます。
この資料では導入義務化の概要をはじめ、マイナ保険証の利用が進む中で発生しうるトラブルとその対応策について解説します。
マイナポータル 簡単解説ガイド
マイナポータルの概要や利用について、わかりやすくまとめた解説ガイドです。
社内での周知や、マイナポータル活用のための参考資料としてぜひご活用ください。
マイナンバー提出用紙(ワード)
従業員からのマイナンバー収集はスムーズに進んでおりますでしょうか。
本資料は、マイナンバーの提出にご利用いただけるWord形式のテンプレートです。ぜひダウンロードいただき、マイナンバーの収集業務にご活用ください。
住民基本台帳カードから個人番号カードへ
マイナンバー制度の施行に合わせ、住民基本台帳カードが個人番号カードへ引き継がれることになります。来年1月以降、個人番号カードは住民基本台帳カードの機能を引き継ぎ、さらに大きな社会的役割を担うことになります。
住民基本台帳カードは来年1月以降、新規発行を行わない予定です。個人番号カードを取得する際には、お持ちの住民基本台帳カードは廃止・回収されます。なお、個人番号を取得せず、住民基本台帳カードを有効期間まで使い続けることは可能です。今回の個人番号カードでは、電子証明書が標準搭載されるため、e-Tax等にすぐ活用することができます。
住基ネット自体は、マイナンバーが始まった後も継続利用されますが、イメージとしては住基ネットは全国自治体の個人情報管理システム、マイナンバーは住基ネットを含む各行政機関の情報連携システムといった感じです。

(出典:マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります!入門編pdf|内閣府)
住基ネットとマイナンバーの違い
住基ネットの主体は、あくまで自治体だったため、一部の自治体が不参加を表明するなど、住基ネットの導入当初には混乱がありました。今回、マイナンバーの主体は国ですので、各自治体の判断で不参加などを表明することは不可能になっています。
マイナンバーの導入当初は、住民票コードの活用が議論されたこともありましたが、結局は別の制度として行われることになりました。
まとめ
ただ実は、個人番号12桁の数字のうち、個人番号の先頭11桁は住民票コードから生成されます。末尾の1桁は、検査用数字であり、先頭の11桁から計算されます。意外なつながりがありました。
住基ネットは国民総背番号制度のさきがけともいわれていましたので、国の長年にわたる苦労の末、マイナンバー制度にたどり着いたことを表すものといえるかもしれません。
国民総背番号制は、住基ネットの導入の際、大議論が巻き起こり、国民の間には嫌悪感にも似た感情があるかもしれません。ただ確かに国による個人情報の管理が容易となることのデメリットも大きいのですが、行政効率の向上化、手続の簡略化など、メリットになる点も少なくありません。
問題はマイナンバー制度がしっかりと運営されるかどうかです。住基カードの普及率は5%と低調でした。これは様々な理由があると思いますが、国民のプライバシー意識の高さともいえると思います。
国は、しっかりとした情報保護と、その広報によって、マイナンバー制度の信頼性を高め、普及に努めていくことが肝要であると考えます。また、国民は制度が目的を超えて運用されていないかをチェックする役割があります。
マイナンバー制度は、住基ネットの反省を生かしつつ、そこから発展した制度となるようです。住基ネットは普及率こそ低かったですが、大きな問題も起こさず運用されてきました。このことから、今回のマイナンバー事業においても、住民基本台帳が実質的な原本として利用されることとなり、マイナンバーのシステムの「土台」としての役割を果たすこととなります。
住基ネットとは違い、今回のマイナンバーは全国民を対象とするかなり大規模なシステム運用が期待されています。住基ネットとはかなり運用規模が変わってくる可能性も高いと思います。果たしてそのような条件下において、運用が問題なく行われるかどうか注視する必要があるかもしれません。
photo by Christian Schnettelker
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
マイナンバーの医療分野での活用!健康保険証の代わりにも?
マイナンバーではなく個人番号カードに健康保険証(被保険者証)機能を付与することが、現在議論されています。 もし実現すれば医療分野においても活用されることとなり、個人番号カードの利便…
詳しくみるマイナンバーの保管期間に関するまとめ
国税関係帳簿や書類は一定の保管期間が義務付けられています。事業規模や書類の種類にもよりますが、7年の保管期間であれば問題ないと認識されている方が多いことと思います。 ではマイナンバ…
詳しくみる【提出用紙テンプレ付】マイナンバーの「基本方針」とは?考え方とポイント
マイナンバーを適切に取り扱うために必要な安全管理措置。ここではこの安全管理措置のガイドラインとも言うべき「基本方針」について解説します。 「基本方針とは何か」というところから、具体…
詳しくみる知っておきたい「マイナンバー制度」2015年10月から運用開始!
いよいよ、2015年「マイナンバー制度」が日本でもはじまります。実際の運用はもう少し先からとなりますが、10月には全国民にマイナンバーの通知が予定されていることもあり、実質的には2…
詳しくみるマイナ保険証の義務化はいつから?5つの変わることと資格確認書についても解説
「マイナ保険証の義務化っていつから?」「紙の健康保険証は使えなくなるの?」 上記のような疑問をもっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 2025年12月2日からマイナ保険証…
詳しくみるマイナ保険証に同意しないとどうなる?薬剤情報・高額療養費への影響と注意点を解説
2024年12月以降、現行の健康保険証は新規発行が終了しています。今後は、マイナ保険証が基本となる時代へと移行します。 とはいえ、マイナ保険証を使いたくない方や同意しないとどうなる…
詳しくみる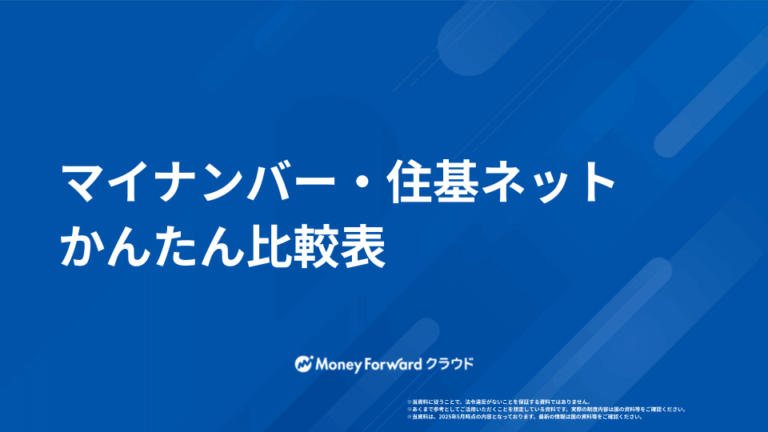

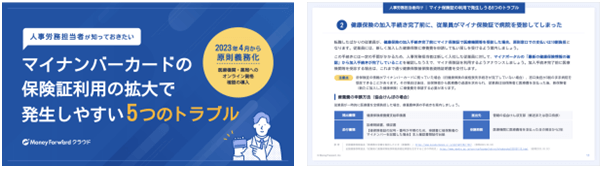
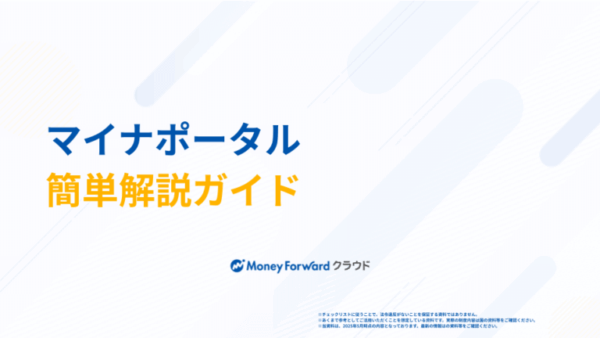
-e1761041825741.png)