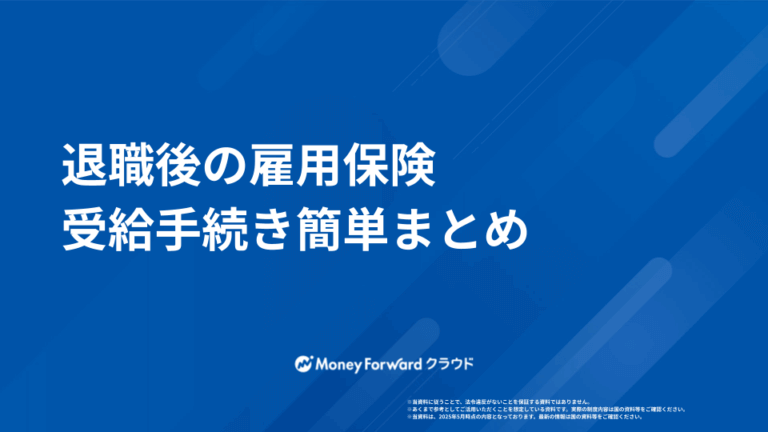- 更新日 : 2025年6月23日
退職後に雇用保険(基本手当)を受給するための手続きは?必要書類も解説!
会社退職後に失業手当(基本手当)を受け取るには、ハローワークで説明会の出席や失業の認定などの手続きが必要です。
ここでは、離職票などの基本手当を申し込む際の必要書類や、手続きの流れを紹介します。また、基本手当がいくらもらえるのか、計算方法を解説しますので、退職後の生活を検討する際の参考にしてください。
目次
退職後に雇用保険(基本手当)を受給する手続きは?
基本手当とは、会社に勤めていた方が離職した際、働く意思と能力があっても就職先が見つからずに働くことができない場合に、雇用保険の制度から支給される最もポピュラーな手当です。失業したときにもらえることから、失業手当などとも呼ばれます。
会社を退職して転職活動をしているときなど、失業中に雇用保険の基本手当を受け取るためには、いくつかの手続きが必要です。基本手当が支払われるまでには一定の期間がかかるため、可能であれば、退職前に手続きの流れや必要書類を確認しておくほうが手続きをスムーズに行えるでしょう。以下に、基本手当を受け取るまでの流れを解説します。
必要な書類を確認する
在職中に確認しておきたいのは、「雇用保険被保険者証」の有無と、「離職証明書」の内容についてです。
雇用保険被保険者証とは、会社が従業員の雇用保険加入手続きを行った際、加入したことを確認する大切な証明書です。入社して会社が雇用保険の資格取得の手続きをした際に発行される書類ですが、退職時まで会社で預かっていることもあります。雇用保険の被保険者番号は転職しても変わることはありません。転職して新しい会社に就職した際には、雇用保険の被保険者番号を会社に伝える必要がありますので、大切にとっておきましょう。
また、退職に際して、会社は雇用保険の資格喪失の手続きと同時に「離職証明書」をハローワークに提出するのが一般的です。この離職証明書には、本人の氏名と住所、退職した事業所の名称や所在地、離職日以前の給与の支払い状況、離職理由などが記載されています。離職理由が正しいものであるか、確認しましょう。
退職後、会社が資格喪失と離職票発行の手続きを同時に行った場合には、会社から雇用保険被保険者離職票(1および2)が渡されます。離職票は、59歳以上の方には必ず発行されますが、59歳未満の方は希望しなければ発行されません。会社退職後すぐに次の転職先が決まっている方は離職票が発行されなくても問題ありませんが、基本手当などの給付を受給する予定の方は、必ず退職前に離職票の発行の希望を会社に伝えるようにしましょう。
雇用保険の資格喪失の手続きは従業員退職後に行うため、離職票など基本手当の申請に必要な書類が後日会社から郵送されてくる場合もあれば、従業員自身が退職後に取りに行く場合もあります。これらの書類が、基本手当の申請に必要となりますので、受け取ったらなくさずに保管しましょう。
ハローワークで求職の申し込みをする
退職後、ハローワークでまず「求職の申し込み」を行います。その際に必要となる書類は、以下の通りです。
【持ち物】
- 個人番号確認書類(いずれか1種類)
- マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
- 「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」
- 運転免許証や写真つきの住民基本台帳カードなど、本人確認ができて、住所や年齢が記載されているもの
- 写真2枚(縦3cm×横2.5cm、3カ月以内に撮影されたもの)
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
参考:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス
受給要件を満たしているかどうかの確認と離職の理由の判定後に、受給資格が決定されます。この際、離職理由に異議がある場合の相談も可能です。その後、受給説明会の日時が通知され、このタイミングで「雇用保険受給資格者のしおり」が配布されます。
雇用保険受給者向け初回説明会へ出席する
通知を受けた雇用保険受給者向けの初回説明会に参加します。持ち物は以下の通りです。
【持ち物】
- 雇用保険受給資格者のしおり(前回ハローワークから配布されたもの)
- 筆記用具
初回説明会に出席して「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。大切な書類ですから紛失しないように注意しましょう。初回説明会の際に最初の「失業認定日」がいつなのかを知らされます。
失業の認定を受ける
基本手当は、失業状態にある方に給付されます。そのため、原則として4週間に1度、指定された日にハローワークへ出向き、失業の認定を受ける必要があります。
【持ち物】
- 雇用保険受給資格者証(雇用保険受給者向けの初回説明会で交付されたもの)
- 失業認定申告書
失業認定を受けるためには求職活動を行わなければなりません。そして、就職に向けての活動状況などを「失業認定申告書」に記入し、ハローワークへ提出します。
基本手当(失業手当)が支給される
原則として、4週間に1度の失業の認定を受けると、通常5営業日で指定の口座に基本手当が振り込まれます。ただし、初回の基本手当を受け取るまでには、待機期間の満了と、給付制限期間を考慮しなければいけません。
待機期間とは、すべての方に適用されるもので、求職の申し込み後、受給資格が決定された日から通算して7日間をいいます。この期間は失業の状態にあることが必要であり、基本手当の支給対象とはなりません。
そして、給付制限期間とは、離職理由によって適用される基本手当が支給されない期間です。自己都合で退職した方は、原則2カ月の給付制限期間があることも覚えておきましょう。給付制限期間は待機期間満了の翌日からカウントされます。つまり、自己都合で退職した方が基本手当の申請を行った場合、基本手当を受け取るまでには少なくとも3カ月ほど待つ必要があるのです。
リストラや倒産など会社都合の退職の場合は、待機期間のみの適用となり、給付制限期間はありません。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。
年度更新の手続きガイドブック
年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。
本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
労災対応がよくわかるガイド
前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。
一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。
雇用保険の受給に必要な書類のポイントは?
会社を離職する際に必要となる「雇用保険被保険者証」「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」のポイントについて解説します。
雇用保険被保険者証

引用:雇用保険被保険者証|ハローワーク インターネットサービス
雇用保険被保険者証は、ハローワークから勤務先を通じて従業員本人に交付される重要な書類であり、事業主が保管するものではなく、従業員本人が保管する書類です。この被保険者証を見れば、従業員自身が雇用保険に加入していることを確認できます。
雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号は、その人専用の番号となっています。ハローワークでの基本手当の手続きには必要ありませんが、新しい会社に入社して、再度雇用保険に加入する際に必要となりますので大切に保管しておきましょう。
雇用保険被保険者離職票-1

引用:雇用保険被保険者離職票|ハローワーク インターネットサービス
基本手当を申請する際に必要となる書類です。会社が「雇用保険被保険者喪失届」をハローワークに提出したあと、または提出と同時に「離職証明書」をハローワークに提出すると、ハローワークが発行し、会社経由で退職者本人に渡されます。雇用保険に加入していた情報が記載されており、マイナンバーや基本手当が支給される際の振込口座の情報を記載するようにもなっています。
マイナンバーは、ハローワークに行ってから窓口で書くようになっていますので、記入せずに持っていくようにしましょう。
雇用保険被保険者離職票-2

引用:雇用保険被保険者離職票|ハローワーク インターネットサービス
おなじく、基本手当の申請に必要となる書類です。労働者の被保険者番号などの情報や事業主の情報、離職日以前の給与の支払い状況など多くのことが記載されています。また、失業保険の開始時期や期間を左右する離職理由も、ここに記載されることとなります。
退職後に支給される雇用保険(基本手当)の金額は?
基本手当として受け取れる1日分の金額(基本手当日額)は、会社から支給されていた離職前の6カ月間の給与を1日当たりで平均した金額のおおよそ45%〜80%です。給与が低い方ほど、給付率が高くなるよう設定されています。
所定給付日数は失業時の年齢や雇用保険に加入していた期間によっても異なりますが、自己都合の退職であれば、基本手当が支給されるのは短くて90日分(3カ月分)、長くても150日(5カ月分)ですので、受け取れる金額をご自身の状況に当てはめながら計算する必要があります。
基本手当として受け取れる金額は、以下の方法で計算します。
基本手当日額とは、離職前6カ月間に支払われた総支給額(各種手当を含む。賞与は除外)を180日で割って求めた賃金日額に、45%〜80%の給付率をかけて求めたものです。
給付率は、賃金日額によって以下のように変動します。
*1:離職時の年齢が60〜64歳の場合は11,120円となります
*2:離職時の年齢が60〜64歳の場合は80〜45%に変更
*3:離職時の年齢が60〜64歳の場合は45%に変更
参考:雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和4年8月1日から~|厚生労働省
さらに、離職時の年齢によって、賃金日額および基本手当日額の上限・下限額が定められています。算出した金額が超えている場合には、上限・下限の金額を用いて計算します。
【賃金日額の上限と下限】
【基本手当日額の上限と下限】
所定給付日数は、雇用保険に加入していた期間に応じて決定されます。たとえば、65歳未満の方で自己都合で退職した場合、雇用保険に加入していた期間が10年未満であれば、基本手当の給付日数は90日となります。なお、会社都合での退職の場合は年齢と雇用保険の加入期間に応じて細かく給付日数が決められており、最低で90日、最長で330日となっています。
【自己都合の退職の場合の給付日数】
では、モデルケースとなるAさんの例で、もらえる基本手当の総額を計算してみましょう。
- Aさん(離職時の年齢28歳)
- 退職理由:自己都合
- 雇用保険の被保険者期間:5年
- 月額の総支給額(手当込み・賞与なし):20万円
- 給付日数:90日
基本手当の総額の計算手順
- 賃金日額:20万円×6カ月÷180日=6,666円(賃金日額の範囲内なのでこのまま使用)
- 給付率:50%~80%
- 基本手当日額:4,887円
6,666円×80%ー0.3{(6,666円ー5,030円)/7,350円}6,666円=4,887円(基本手当日額の範囲内なのでこのまま使用)
計算式(y:基本手当日額 w:賃金日額)
y=0.8×w-0.3{(w‐5030円)/7350円〕w - 基本手当総額:4,887円×90日=43万9,830円
※端数処理の関係で金額が異なることがあります。
Aさんが普通に働いた場合、90日間(3カ月)で会社から支給される給与総額は60万円です。基本手当では、約7割を受給できる計算となります。
基本手当を受け止めるためには、ハローワークできちんと手続きを行おう
失業中に受給できる雇用保険の基本手当は、求職活動中の生活の支えとなるものです。離職理由によっては、申し込みをしてから実際に基本手当が振り込まれるまでには、ある程度待たなくてはいけません。必要となる書類や、ハローワークでの手続きをきちんと行い、受給の認定を受けるようにしましょう。
よくある質問
退職後に雇用保険(基本手当)を受給する手続きは?
退職時に会社から渡された「雇用保険被保険者離職票-1、2」とマイナンバーカードなどの必要書類を持ってハローワークで手続きを行います。手続きには、求職の申し込み、説明会の参加、失業の認定などが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
雇用保険(基本手当)の受給に必要な書類のポイントは?
退職時に会社から受け取った「雇用保険被保険者離職票-1、2」を失くさずにハローワークに提出すること。離職票2には離職理由が記載されているので、間違いがないか確認しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
【記入例付き】通勤災害で使用する様式16号の3の書き方は?提出方法まで解説
通勤中の事故で負傷した場合、通勤災害として労災保険の給付を受けるためには、「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」の提出が必要です。しかし、いざ書類を前にすると、専門用…
詳しくみる退職時に会社側が行う社会保険手続きは?離職票と離職証明書の違いも解説!【テンプレ付き】
従業員が退職する際には、決められた期限までに健康保険や雇用保険の喪失届を提出する必要があります。また、従業員が退職後にハローワークに基本手当など失業時に受け取れる給付を申請すること…
詳しくみる社会保険に加入できる人が増える!平成28年10月施行の制度改正内容を解説
平成28年10月に改正社会保険制度が施行され、加入対象者が拡大されます。ここではこの改正によってどのような基準で加入対象者が拡大されるのか、その目的は何なのかについて解説します。 …
詳しくみる失業保険(失業手当)の条件は?金額や期間、再就職手当まで解説
会社を退職した後の生活を支える雇用保険の給付、いわゆる失業保険ですが、いつからいくら振り込まれるのか不安を感じる場面もあるでしょう。 失業保険(失業手当・失業給付金)の受給条件は、…
詳しくみる関東ITソフトウェア健康保険組合の3つのメリットまとめ
どの経営者にとっても、従業員が安心して働ける環境を作ることは重要な責務です。また、自社の福利厚生を整えることが、従業員の満足度向上や新たな人材の確保に良い影響を与えることは間違いあ…
詳しくみる年金は何種類ある?厚生年金などの公的年金と私的年金の違い
一口に年金といっても、その種類はたくさんあります。国の制度である厚生年金などの公的年金だけでなく私的年金もあり、仕組みも複雑です。 本稿では年金の種類とともに、厚生年金などの公的年…
詳しくみる