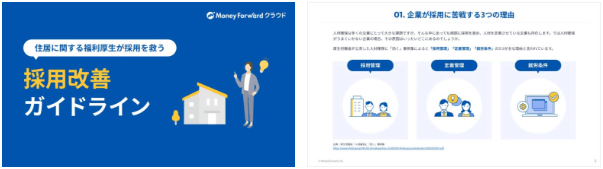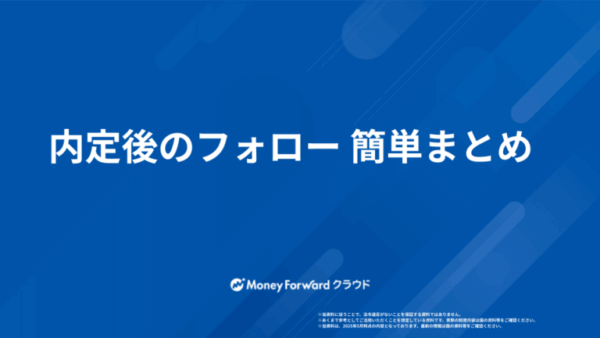- 更新日 : 2025年11月26日
採用で使う適性検査の種類一覧 SPIや玉手箱など主要ツールと選び方をご紹介
企業の採用活動において、候補者の能力や人柄を客観的に判断するために「適性検査」の導入は不可欠です。しかし、適性検査には数多くの種類が存在し、「自社に合うものがわからない」と悩む担当者様も少なくありません。この記事では、中小企業の経営者や採用担当者様に向けて、適性検査の主な種類を一覧で分かりやすく解説します。能力検査と性格検査の違いから、具体的なツールの比較、導入時の選び方、そして採用後の活用方法まで、網羅的にご紹介します。
目次
適性検査の主な種類一覧
適性検査は、候補者が持つさまざまな側面を測定するために、大きく分けて「能力検査」と「性格検査」の2種類で構成されることが一般的です。まずは、それぞれの検査が何を目的とし、どのような内容なのか、基本的な違いを理解しておきましょう。
能力検査
能力検査は、業務を遂行する上で必要となる基礎的な知的能力や思考力を測定するものです。主に、文章の読解力や論理的思考力を測る「言語分野」と、計算能力や図形の読解、推論能力を測る「非言語分野」に分かれています。この検査により、候補者が業務内容を正しく理解し、効率的に処理できるかといったポテンシャルを客観的に判断することができます。学歴や職歴だけでは分からない、地頭の良さや思考の速さ・正確さを可視化する目的で実施されます。
性格検査
性格検査は、候補者の人柄や価値観、行動特性などを把握するために行われます。質問紙法が一般的で、日常の行動や考え方に関する多くの質問に回答してもらうことで、協調性、ストレス耐性、達成意欲、リーダーシップといった多角的な側面を分析します。この結果は、自社の社風やチームにマッチするかどうかを判断する重要な材料となります。また、面接だけでは見抜きにくい内面的な特徴を理解し、入社後のミスマッチを防ぐためにも活用されます。
その他の検査
基本的な能力検査や性格検査のほかに、特定の目的や職種に特化した検査も存在します。例えば、候補者のストレス耐性や精神的な安定性をより深く測定する「ストレス耐性検査」や、特定の職務で高い成果を出す人材に共通する行動特性(コンピテンシー)を評価する「コンピテンシー検査」などがあります。ITエンジニア向けのコーディングテストや、デザイン職向けのポートフォリオ評価なども、広義には適性検査の一環と捉えることができます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
住居に関する福利厚生が採用を救う 採用改善ガイドライン
人材確保は多くの企業にとって大きな課題ですが、そんな中にあっても順調に採用を進め、人材を定着させている企業も存在します。では人材確保がうまくいかない企業の場合、その原因はいったいどこにあるのでしょうか。
3つの原因と、それを解決する福利厚生の具体的な内容まで、採用に役立つ情報を集めた資料をご用意しました。
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
内定後のフォロー 簡単まとめ
内定者へのフォローアップは、採用活動における重要なプロセスです。 本資料は「内定後のフォロー」について、簡単におまとめした資料です。
ぜひダウンロードいただき、貴社の取り組みの参考としてご活用ください。
試用期間での本採用見送りにおける、法的リスクと適切な対応
試用期間中や終了時に、企業は従業員を自由に退職させることができるわけではありません。
本資料では、試用期間の基本的な概念と本採用見送りに伴う法的リスク、適切な対応について詳しく解説します。
代表的な適性検査ツール
世の中には多種多様な適性検査ツールが存在します。ここでは、多くの企業で導入実績があり、知名度の高い代表的なツールをいくつかご紹介します。それぞれに特徴や測定できる領域が異なるため、自社の目的に合わせて比較検討することが重要です。
SPI
リクルートマネジメントソリューションズが提供する、国内で広く利用されている適性検査の一つです。知名度が高く、多くの受検者が対策をしていることでも知られています。内容は基本的な「能力検査」と「性格検査」で構成されており、汎用性が高く、業種や職種を問わず活用できるのが特徴です。受検方法もテストセンターやWebテスティングなど多様で、企業のニーズに合わせて選択できます。個人の資質を多角的に測定し、面接だけでは分からない人柄の理解を深めるのに役立ちます。
玉手箱・GAB
日本エス・エイチ・エル(SHL社)が提供する適性検査で、特に金融業界やコンサルティング業界などで多く採用されています。特徴は、複数の問題形式(計数、言語、図表の読み取り、英語など)が組み合わされており、短時間で多くの問題を処理する能力が求められる点です。GABは総合職向けの適性検査パッケージで、思考力だけでなく、情報処理のスピードと正確性を重視したい場合に適しています。
TAL
従来の適性検査とは一線を画す、ユニークな形式が特徴の検査です。図形の配置問題など、対策がしづらい質問を通じて、候補者の潜在的な人物像やストレス耐性を評価します。特に、対人影響力やコンプライアンス意識など、ビジネスにおける重要な資質を見抜くことを目的としています。他の検査と組み合わせて利用することで、より多角的な人物評価が可能になります。
CUBIC for WEB
株式会社CUBICが提供するこのツールは、採用選考だけでなく、入社後の配置や育成、さらには組織分析まで一気通貫で活用できる点が大きな強みです。個人の特性を詳細に分析するだけでなく、組織全体の傾向を可視化することも可能なため、中小企業の組織開発にも役立ちます。コストパフォーマンスにも優れており、幅広い用途で利用できることから多くの企業に導入されています。
HCi-AS
株式会社ヒューマンキャピタル研究所が提供する、特にストレス耐性やメンタルヘルスの側面に焦点を当てた適性検査です。現代のビジネス環境で重要視される、プレッシャーのかかる状況下での対応力や感情のコントロール能力などを測定します。特に営業職や管理職など、高いストレス耐性が求められる職種の採用や、全社的なメンタルヘルス対策の一環として活用されるケースが増えています。
その他の適性検査ツール
上記以外にも、さまざまな特徴を持つ適性検査ツールがあります。例えば、既存社員のデータを基に自社で活躍する人材モデルを作成し、候補者とのマッチ度を測る「ミキワメ」や、多面的な評価項目で詳細なフィードバックが得られる「eF-1G」、候補者の思考プロセスを可視化する「tanΘ(タンジェント)」など、各社が独自の理論に基づいたツールを開発しています。
適性検査を導入する目的
適性検査は、単に候補者を選別するための手段ではありません。導入することで、採用活動全体に多くのメリットをもたらします。なぜ多くの企業が適性検査を活用しているのか、その主な目的を整理してみましょう。
客観性と公平性の担保
採用面接では、どうしても面接官の主観や経験、その時の印象に評価が左右されがちです。適性検査を導入することで、すべての候補者を同じ基準で測定した客観的なデータを得ることができます。これにより、評価のブレをなくし、公平性の高い選考プロセスを構築することが可能になります。学歴や経歴といった表面的な情報だけでなく、ポテンシャルに基づいた採用判断ができるようになります。
潜在的な特性の把握
短い面接の時間だけで、候補者の内面的な特性や潜在能力をすべて見抜くことは困難です。適性検査を活用すれば、対話だけでは分かりにくいストレス耐性、価値観、潜在的な強みや弱みをデータとして可視化できます。これらの情報は、候補者をより深く理解するための補助線となり、面接時に掘り下げるべき質問を準備するのにも役立ちます。
ミスマッチの防止
早期離職の大きな原因の一つに、企業文化や仕事内容、人間関係とのミスマッチが挙げられます。適性検査によって候補者の性格や価値観を事前に把握し、自社の社風や配属予定のチームとの相性を予測することで、入社後の「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを減らすことができます。結果として、従業員の定着率向上につながり、採用と育成のコスト削減にも貢献します。
採用活動の効率化
特に応募者が多数集まる場合、すべての候補者とじっくり面接を行うのは現実的ではありません。適性検査を選考の初期段階で実施することで、自社が求める能力や特性の基準を満たす候補者を効率的に絞り込むことができます。これにより、採用担当者は有望な候補者とのコミュニケーションに集中できるようになり、採用活動全体の生産性が向上します。
適性検査の選び方
数ある適性検査の中から、自社に最適なツールを選ぶためには、いくつかのステップを踏んで検討することが重要です。ここでは、中小企業が導入で失敗しないための選び方のポイントを5つのステップで解説します。
採用課題と求める人物像を明確にする
最初に行うべきことは、「なぜ適性検査を導入するのか」という目的の明確化です。「早期離職が多い」「特定の部署で活躍できる人材が欲しい」「面接の評価がバラバラ」など、自社が抱える採用課題を洗い出しましょう。その上で、どのような資質や能力を持った人物が必要なのか、具体的な「求める人物像(ペルソナ)」を定義することが、最適なツール選びの第一歩となります。
測定したい項目を決める
採用課題と求める人物像が明確になったら、次にそれを評価するために「何を測定すべきか」を具体的に決めます。例えば、「論理的思考力」を重視するのか、「協調性」や「ストレス耐性」を優先するのかによって、選ぶべきツールは変わってきます。各適性検査ツールがどのような項目を測定できるのかを比較し、自社の優先順位に合ったものを選定しましょう。
受検形式を検討する
適性検査には、候補者が指定の会場に出向く「テストセンター」、自宅などのPCで受検する「Webテスティング」、自社のPCで受検する「インハウスCBT」、紙で回答する「マークシート」など、さまざまな受検形式があります。利便性、コスト、不正防止の観点から、それぞれのメリット・デメリットを比較し、自社の運用体制や候補者の層に合った形式を選びましょう。
費用と手間を比較する
適性検査の料金体系は、1人あたりの従量課金制や年間契約の定額制など、ツールによってさまざまです。単純な単価だけでなく、年間の採用人数や利用頻度を考慮して、トータルコストを試算することが大切です。また、導入時の設定や結果の分析にかかる社内スタッフの手間も重要な比較ポイントです。無料トライアルがあれば積極的に活用し、操作性やサポート体制を確認しましょう。
結果の活用方法を考える
適性検査の結果を、単なる合否判断の材料で終わらせては非常にもったいないです。面接時に候補者の特性を深掘りするための質問材料として使ったり、内定者フォローの参考にしたり、入社後の配属先や育成プランを検討する際のデータとして活用したりと、多岐にわたる活用が可能です。選考から入社後まで、どのように結果を活かしていくかを見据えてツールを選ぶことが重要です。
適性検査の最新トレンドと注意点
適性検査の世界も、テクノロジーの進化や働き方の変化に合わせて日々進化しています。ここでは、2025年9月現在の最新トレンドと、企業が導入・運用する上での注意点について解説します。
AI活用と新しい検査
近年、AI(人工知能)を活用した適性検査が増えています。AIが候補者の回答パターンや速度を分析し、より精度の高い性格診断や潜在能力の予測を行うものです。また、候補者が話す動画をAIが解析して表情や声のトーンから特性を評価するツールや、ゲーム形式で楽しみながら受検できるアセスメントなど、新しい形の検査も登場しており、評価の客観性や多角化が進んでいます。
オンライン受検の不正防止
Webテストが主流になる一方で、替え玉受検や電卓の使用といった不正行為のリスクが課題となっています。この対策として、Webカメラを通じてAIや試験官が受検中の様子を監視する「プロクタリングサービス」を導入する企業が増えています。不正を防止し、検査の公平性を担保するための技術も進化していますが、導入には追加コストがかかる点も考慮が必要です。
応募者体験の向上
煩雑で時間のかかる選考プロセスは、候補者の入社意欲を削いでしまう原因になります。この「候補者体験(Candidate Experience)」を重視する考え方が広まっており、適性検査も例外ではありません。スマートフォンでの受検に最適化されているか、デザインが分かりやすいか、といったUI/UXの観点がツール選びの新たな基準になっています。受検後に本人へ簡単なフィードバックを提供するツールも人気です。
法的留意点
採用選考においては、応募者の基本的人権を尊重し、公正であることが求められます。適性検査の内容が、本来自由であるべき思想・信条や、本人に責任のない家庭環境などを探るような不適切なものであってはなりません。厚生労働省が示す「公正な採用選考の基本」を遵守し、あくまで職務遂行に必要な能力・適性を判断する目的の範囲内で、適切な検査を選択・運用することが重要です。
自社に最適な適性検査の活用
企業の成長は「人」で決まります。数ある適性検査の中から自社の目的や課題に合ったツールを見極めて導入することは、採用の成功率を高めるだけでなく、入社後の人材育成や組織開発においても重要な役割を果たします。本記事で紹介した適性検査の種類一覧や比較ポイントを参考に、まずは自社が「何のために適性検査を行うのか」を明確にすることから始めてみてください。客観的なデータを活用し、より戦略的な人事施策を実現しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
eラーニングとは?最新トレンド、無料から使えるシステム7選を紹介
eラーニングとは、インターネットとパソコンなどのインターネットデバイスを使ったオンライン学習のことです。インターネット環境とデバイスさえあれば受講できるため、資格勉強や研修などに広…
詳しくみるジョブ・クラフティングとは?意味やメリット・デメリット、やり方を解説
従業員の主体性を尊重し、モチベーションを高める新しい働き方として注目されているのが、「ジョブ・クラフティング」です。 単に任された業務をこなすのではなく、自分の強みや適性、価値観に…
詳しくみるモチベーションを上げる方法は?自分・部下・組織のやる気を高める心理学
モチベーションを上げる方法は、精神論ではなく、科学的な根拠や心理学に基づいたアプローチが効果的です。この記事では、自分のモチベーションを上げる方法から、仕事や勉強での実践的なテクニ…
詳しくみるキッズウィークとは?実施の目的や取り組み・メリットなどを解説
少子化対策や働き方改革の観点から、注目を集めているのがキッズウィークです。 本記事では、キッズウィークの概要や実施の目的、実際に制度を導入した自治体および導入を検討している自治体を…
詳しくみる感情労働によるバーンアウト!会社への影響やストレスを溜めない対策を解説
顧客との接客や対話を中心に働く「感情労働」は、自分の感情を隠す分、ストレスを溜め込みやすくなります。高負荷のストレスになれば、バーンアウトにつながる可能性もあるでしょう。 この記事…
詳しくみるQCストーリーの定義と進め方は?現場の課題を確実に解決する手順
「QCストーリーの定義やメリットは?」 「QCストーリーは本当に効果があるのか?」 「問題解決型や課題達成型、自分の抱えている問題には、どの型を使えばいいのか分からない」 上記のよ…
詳しくみる