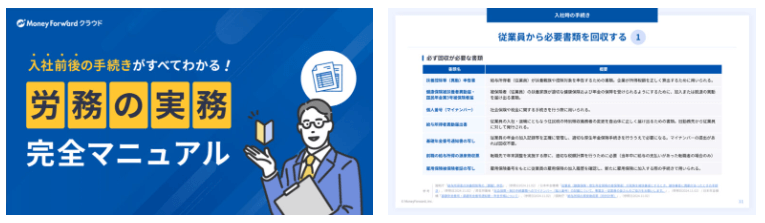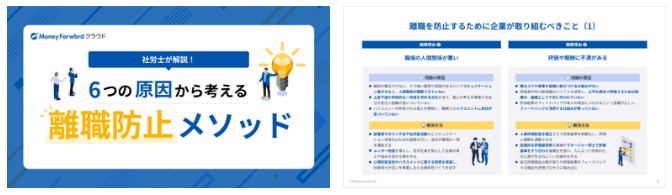- 更新日 : 2025年9月26日
報酬制度の設計方法は?税金の扱いや役員報酬の場合などを解説
報酬制度は、社員のやる気を引き出し、企業の成長を後押しする重要な仕組みです。しかし設計は複雑で、目的や種類、税務の扱いまで幅広い知識が必要です。不公平な制度はモチベーション低下や離職につながるリスクもあります。
この記事では、報酬制度の基本的な考え方から、主な種類、税務上の注意点、そして具体的な設計手順までわかりやすく解説します。
報酬制度とは?
報酬制度とは、社員の貢献に応じてどのような対価を支払うかを定めた、企業全体の仕組みやルールのことです。給与が毎月支払われる基本的な金額を指すのに対し、報酬制度は給与だけでなく、賞与や手当、福利厚生、成長機会の提供なども含めて設計されます。
つまり「いくら支払うか」だけでなく、「どのように報いるか」という方針を示すものであり、制度の在り方によって社員の働きがいや行動の方向性に大きな影響を与えます。
報酬制度を設計する目的
企業が報酬制度を設計・見直しする主な目的は、企業の持続的な成長を実現することにあります。具体的には、以下のような目的が挙げられます。
- 人材の確保と定着:
魅力的な報酬制度は、優秀な人材を採用し、社員の離職を防ぐ上で効果的です。 - 社員のモチベーション向上:
公平で納得感のある制度は、社員のエンゲージメントを高め、生産性の向上につながります。 - 行動の方向づけ:
企業が求めるスキルや成果を明確にし、それに対して報いることで、社員の行動を経営目標の達成へと方向づけます。 - 人件費の適切な管理:
企業の支払い能力に応じて、戦略的かつ計画的に人件費をコントロールします。
報酬制度を構成する主な要素
一般的に、社員へ支払われる報酬は「金銭的報酬」と「非金銭的報酬」に大別されます。報酬制度の設計においては、これらの要素をバランス良く組み合わせることが求められます。
金銭的報酬
金銭で直接支払われる報酬です。従業員の生活の基盤となり、短期的なモチベーションに直結します。
| 報酬 | 概要 |
|---|---|
| 基本給 | 年齢・能力・役割などに基づき、月々支払われる報酬の土台 |
| 諸手当 | 役職手当、通勤手当、残業手当、住宅手当など |
| 賞与(ボーナス) | 会社の業績や個人の評価に応じて、定期的に支払われる |
| インセンティブ | 個人の短期的な目標達成度に応じて、都度支払われる報奨金 |
| 退職金・年金制度 | 退職時に支払われる一時金や、老後のための企業年金 |
非金銭的報酬
金銭以外で提供される価値や機会です。従業員の働きがいや会社への帰属意識(エンゲージメント)を高め、長期的な人材定着に大きな影響を与えます。
| 価値や機会 | 概要 |
|---|---|
| 福利厚生 | 社会保険、健康診断、社員食堂、レクリエーションなど |
| 学習・成長の機会 | 研修制度、資格取得支援、OJT(実務を通じた指導)など |
| キャリア開発の機会 | 昇進・昇格のチャンス、希望する部署への異動制度など |
| 職場環境・働きがい | 良好な人間関係、快適なオフィス、柔軟な働き方(リモートワーク等) |
| 評価・称賛 | 社内表彰制度、上司や同僚からの感謝 |
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
人事・労務担当者向け Excel関数集 56選まとめブック
人事・労務担当者が知っておきたい便利なExcel関数を56選ギュッとまとめました。
40P以上のお得な1冊で、Excel関数の公式はもちろん、人事・労務担当者向けに使い方の例やサンプルファイルも掲載。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。お手元における保存版としてや、従業員への印刷・配布用、学習用としてもご活用いただけます。
入社前後の手続きがすべてわかる!労務の実務 完全マニュアル
従業員を雇入れる際には、雇用契約書の締結や従業員情報の収集、社会保険の資格取得届の提出など数多くの手続きが発生します。
本ガイドでは、入社時に必要となる労務手続き全般を1冊にわかりやすくまとめました。
社労士が解説!6つの原因から考える離職防止メソッド
少子高齢化にともなう労働人口の減少が加速する中、従業員の離職は事業継続に影響がでるほど大きな企業課題となっています。
本ガイドでは、従業員の離職につながる6つの原因と、効果的な離職防止策について解説します。
報酬制度の主な種類と特徴
報酬制度の根幹となる基本給の決定方法には、いくつかの種類があります。どの制度を選択するかによって、社員に送るメッセージや組織文化が大きく変わるため、それぞれの特徴を理解することが重要です。
職能給:能力を評価する
職能給は、社員が持つ職務遂行能力(スキルや知識)に応じて格付けし、報酬を決定する制度です。年齢や勤続年数とともに能力も向上するという考え方がベースにあり、多くの日本企業で採用されてきました。
- メリット:社員の長期的なスキルアップを促し、ゼネラリストの育成に向いています。また、配置転換などにも柔軟に対応しやすいです。
- デメリット:能力と実際の成果が必ずしも一致しない場合があり、成果を上げている若手社員の不満につながる可能性があります。また、年功序列的になりやすく、人件費が高止まりしやすい傾向があります。
職務給:仕事の価値で評価する
職務給は、社員が担当する「職務(ポジション)」の価値や責任の重さに応じて報酬を決定する制度です。「同一労働同一賃金」の考え方に沿っており、欧米企業で主流となっています。
- メリット:職務内容と報酬が明確に結びついているため、公平性・納得感が高いです。専門性の高いスペシャリストの採用・育成に適しています。
- デメリット:職務が変わらない限り、報酬が上がりにくい構造です。また、各職務の価値を正しく評価するための「職務評価」の導入・維持にコストと手間がかかります。
成果給:出した結果で評価する
成果給は、社員が達成した業績や成果(売上、利益など)に基づいて報酬を決定する制度です。個人の成果が報酬に直接反映されるため、とくに営業職などでインセンティブとして導入されることが多いです。
- メリット:社員の成果への意欲を強く刺激し、短期的な業績向上につながりやすいです。
- デメリット:個人の成果を重視するあまり、チームワークが阻害されたり、短期的な視点に陥りやすくなったりする場合があります。また、成果を公平に測定できる指標の設定が難しいという課題もあります。
報酬制度の設計で考慮すべき税金の扱い
報酬制度を設計する上で、役員と従業員とでは税法上の扱いが根本的に異なることを理解しておきましょう。とくに役員報酬を設計する上では、会社のキャッシュフローに大きな影響を与えます。従業員へのインセンティブに関する税金の扱いも確認します。
役員報酬と損金算入のルール
従業員の給与とは異なり、役員報酬は、一定の要件を満たさない限り、会社の損金(経費)として認められません。損金にするためには法律で定められた厳格な要件を満たす必要があります。
これは、役員が自身の報酬を自由に決めることで、会社の利益を不当に操作し、法人税を圧縮することを防ぐためです。
最も基本的な方法は、報酬を毎月の給与(定期同額給与)として支払うことです。この方法では、事業年度が始まってから3ヶ月以内にその年度の月額を決定し、期末まで毎月同額を支払い続けることで、その全額が損金として認められます。
役員報酬を損金として認めさせるには、主に以下の方法があります。
- 毎月決まった給与を支払う(定期同額給与)
「毎月25日に100万円」のように、支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとで、その事業年度中の支給額が常に同額である給与です。金額を改定できるのは、原則として事業年度開始から3ヶ月以内に限られます。経営状況の著しい悪化など、特別な事情がない限り期中の変更は認められません。 - 事前に賞与の届出をする(事前確定届出給与)
役員への賞与(ボーナス)のように、特定の時期にまとまった額を支払う報酬です。支払う時期と金額をあらかじめ税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し届け出る必要があります。 - 会社の業績に連動する(業績連動給与):
会社の利益や株価といった客観的な業績指標に連動して支給額が算定される報酬です。算定方法を有価証券報告書で開示するなど、主に上場企業を対象とした制度であり、多くの中小企業にとっては活用が難しいのが実情です。
役員報酬の月給に加えて賞与を支給する場合
役員へ賞与(ボーナス)を支給し、それを損金にするには、月給とは別に「事前確定届出給与」という極めて厳格な手続きを事前に行わなければなりません。
これは、「いつ、誰に、いくら支給するか」をあらかじめ税務署へ届け出て、その計画通りに支給する方法です。この手続きは柔軟な報酬設計を可能にしますが、届け出た内容と1円でも違う金額を支給した場合、その賞与の全額が損金として認められないというリスクがあります。そのため、計画通りの正確な支払いが絶対条件となります。
従業員のインセンティブと税金
従業員に支払われる賞与やインセンティブは、役員報酬とは異なり、原則として「給与所得」として扱われるため、会社の損金(経費)として扱われます。そのため、通常の給与と同様に所得税および復興特別所得税の源泉徴収の対象となり、社会保険料の算定基礎にも含まれます。
一方で、福利厚生の一環として支給される手当(通勤手当や出張手当など)の中には、法律で定められた要件を満たすことで所得税が課税されない「非課税手当」があります。これらを活用することで、従業員の実質的な手取り額を増やすことが可能です。
- 通勤手当:公共交通機関の場合、月15万円まで非課税
- 出張手当:社会通念上、相当と認められる金額は非課税
- 食事補助:一定の要件(本人が半額以上負担など)を満たせば非課税
関連:所得税のかからない手当とは?給与以外で非課税となる手当の項目一覧
報酬制度を設計する5つのステップ
自社に合った報酬制度を設計するためには、体系的なアプローチが必要です。ここでは、報酬制度の作り方を5つの実践的なステップに分けて解説します。
ステップ1:方針を明確にする
まず、自社の経営理念やビジョンに基づき、「何に報いる会社でありたいか」という報酬制度の基本方針を明確にします。安定を重視するのか、挑戦を促すのか、チームワークを大切にするのかなど、企業文化と連動した方針を定めることが、一貫性のある制度設計の土台となります。
ステップ2:等級制度を設計する
社員を序列化するための「等級制度」を設計します。職能給であれば能力のレベルに応じて、職務給であれば職務の価値に応じて、社員をいくつかの等級に格付けします。各等級に期待される役割や責任を定義した「等級定義書」を作成することで、評価の基準が明確になります。
ステップ3:報酬水準を設定する
自社の報酬が、市場(同業他社や同地域)と比較してどの程度の水準にあるべきかを決定します。報酬調査会社のデータなどを参考に、競争力のある水準を設定することが、人材獲得の観点から重要です。また、自社の支払い能力(人件費予算)とのバランスも考慮する必要があります。
ステップ4:報酬体系の詳細を設計する
基本給、賞与、手当などの各要素を具体的に設計していきます。等級ごとの基本給の金額範囲(給与レンジ)を定めたり、賞与の計算式(業績評価とどう連動させるかなど)を決めたりします。
ステップ5:シミュレーションと導入・周知
新しい報酬制度を導入した場合の人件費総額が、予算内に収まるかなどをシミュレーションします。現行制度からの移行措置(経過措置)も検討が必要です。最終決定後は、社員説明会などを開催し、制度の目的や仕組みを丁寧に説明し、社員の理解と納得を得ることが、円滑な運用の鍵となります。
報酬制度の設計でよくある質問(Q&A)
ここでは、報酬制度の設計において、実務担当者が判断に迷いやすい点についてQ&A形式で解説します。
Q1. 人事評価制度とは、どのように連携させればよいですか?
報酬制度と人事評価制度は、密接に連携させる必要があります。等級制度の昇格・降格は人事評価の結果に基づいて決定され、賞与や昇給額も評価結果に連動するのが一般的です。評価の公平性・透明性が、報酬の納得感を担保する上で不可欠です。
Q2. 非金銭的報酬(福利厚生など)は、どう位置づければよいですか?
非金銭的報酬は、金銭的報酬を補完し、従業員エンゲージメントを高める「トータルリワード(総報酬)」の重要な一要素です。とくに、多様な価値観を持つ現代において、魅力的な福利厚生や働きやすい環境、成長機会の提供は、金銭と同等かそれ以上に、人材の確保・定着に影響を与える可能性があります。
Q3. 制度変更を社員にどう説明すればいいですか?
透明性をもって、丁寧に説明することが最も重要です。「なぜ制度を変えるのか」という背景や目的、「新しい制度で何がどう変わるのか」「社員にとってどのようなメリットがあるのか」を明確に伝えましょう。説明会を開催し、質疑応答の時間を十分に設けるとともに、個別の質問に対応できる窓口を用意することも有効です。
報酬制度とは企業の理念を映す戦略的な仕組み
報酬制度の設計は、単なる給与ルールではなく企業理念や経営方針を表現する重要な制度です。企業が「何を大切にし、どのような人材を評価するのか」という価値観そのものを形にする、経営の根幹をなす戦略的な活動です。
職能給・職務給・成果給といった制度の特徴を理解し、税務上の取り扱いや役員報酬の規制も踏まえた上で設計することが求められます。また、金銭的報酬だけでなく福利厚生や成長機会といった非金銭的報酬も組み合わせることで、人材の定着やエンゲージメント向上につながります。
自社の理念やビジョンを反映した、公平で納得感のある報酬制度を設計・運用することが、社員一人ひとりの成長を促し、組織全体の力を高め、ひいては企業の持続的な成長を実現する原動力となるでしょう。
関連:基本給の決め方と低い場合のデメリットとは?
関連:役員報酬の決め方の注意点と知っておくべき3つの制度
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
【始末書テンプレート付き】パワハラ防止法とは?法改正の内容や対策法を解説!
パワハラ防止法の対策方法を検討する企業が増えています。2022年4月には法改正が行われ、中小企業もパワハラ防止法の対象となりました。パワハラ防止法に違反すると職場環境が悪化するだけでなく、企業名公表といった罰則を受けるリスクも高まります。そ…
詳しくみる退職勧奨を自己都合にされた場合の対処法は?離職票や失業保険も解説
退職勧奨は原則として「会社都合退職」です。しかし、離職票に「自己都合退職」として記載されてしまうケースがあり、その場合は失業保険の給付開始が遅れるなど不利益を受ける可能性があります。 この記事では、退職勧奨で自己都合にされた時の修正方法や会…
詳しくみる体調不良で休めないのはパワハラ?欠勤が多い従業員への対応も解説
体調不良で休めない状況は、パワハラに該当する可能性があります。一方で、欠勤が多い従業員への対応に悩む企業も少なくありません。本記事では、体調不良時の休暇取得とパワハラの関係、そして欠勤が多い従業員への適切な対応方法を解説します。 体調不良で…
詳しくみるリクルーターとは?役割や選定基準、制度の導入方法、企業事例を解説
リクルーターとは、主に現場で業務にあたる社員が採用活動を行う採用活動です。求職者に直接アプローチして面談を実施し、コミュニケーションを取りながら自社の魅力を伝える活動を行います。 本記事ではリクルーターの概要や役割、制度のメリットやデメリッ…
詳しくみるフィードバック面談の効果的な方法は?シートの活用から逆質問への対応まで徹底解説
フィードバック面談は、従業員の成長を支え、組織全体のパフォーマンス向上につなげるために欠かせない取り組みです。しかし、その方法を誤ると、かえって従業員のモチベーションを低下させることにもなりかねません。 この記事では、人事労務の初心者の方で…
詳しくみる人的資本経営の開示項目とは?情報開示の19項目や具体例を解説
人的資本経営の情報開示は、企業の競争力向上のために重要です。 2023年から上場企業等には開示義務が課されており、とくに「7分野19項目」に基づく情報開示が求められています。本記事では、人的資本の具体的な開示項目と内容、事例を紹介します。 …
詳しくみる