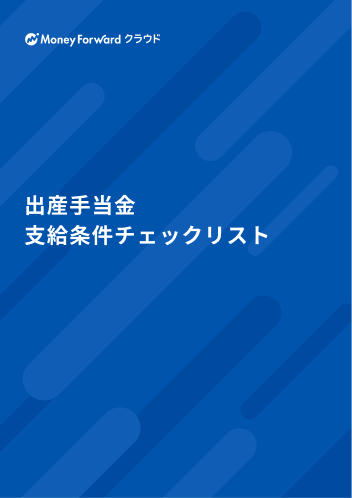- 更新日 : 2025年11月18日
出産手当金がもらえないケースはどんな時?支給条件や受給期間も解説!
出産手当金とは、被保険者が出産のために会社を休み、その期間の給与が支払われていないことを条件に、健康保険からもらえるお金です。したがって、必ずもらえるとは限りません。
本記事では、出産手当金がもらえないケースはどのような時があるのか詳しく解説します。あわせて、支給条件や受給期間も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
目次
出産手当金がもらえないケースはある?
出産手当金は、出産する人が必ずもらえるお金と思っている方が多いのではないでしょうか。しかし、条件によってもらえないケースがあります。そのため、自分は出産手当金がもらえるのかどうかを、事前に確認したほうがよいでしょう。
以下で、出産手当金がもらえないケースを解説します。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐妊娠出産・育児・介護編‐
妊娠出産、育児、介護は多くの労働者にとって大切なライフイベントです。
仕事と家庭生活を両立するうえで重要な役割を担う社会保険・労働保険のうち、妊娠出産、育児、介護で発生する手続きをまとめた実用的なガイドです。
育休中の給料・ボーナス 要点簡単まとめ
育休中の給料・ボーナスについて、スライド形式で要点を簡潔にまとめた分かりやすいガイドです。
従業員への配布用にもご活用いただけますので、ぜひお気軽にダウンロードしてご活用ください。
産後パパ育休制度の創設で、企業が取り組むべき7つのこと
育児・介護休業法の改正により、新たに「産後パパ育休制度(出生時育児休業)」が創設されました。
この資料では、産後パパ育休制度の概要と創設される背景をふまえて、経営者や人事労務担当者が取り組むべき実務のポイントを解説します。
出産手当金がもらえないケース5選
出産手当金がもらえないケースは5つあります。
- 国民健康保険の加入者
- 健康保険の扶養に入っている
- 健康保険の任意継続制度を利用している
- 休業中に給与の支払いが発生している
- 申請までの期間が2年を超えている
以下に1つずつ見ていきましょう。
① 国民健康保険の加入者
国民健康保険の加入者は、出産手当金をもらえません。国民健康保険には、出産手当金の制度がないためです。
もらうための条件として、会社の健康保険に自分が加入(被保険者)している必要があるからです。出産のために、会社を休んでいる方がもらえる対象となるため、国民健康保険の加入者はもらえません。
② 健康保険の扶養に入っている
健康保険の扶養に入っている方は、出産手当金はもらえません。上記のように、会社の健康保険に出産する人自身が加入している必要があります。
健康保険であっても、配偶者の扶養に入っているケースでは、支給の対象外となっているため、出産手当金はもらえません。また出産手当金は、出産をする本人がもらう手当です。加入者である配偶者(夫)は、もらえないため注意しましょう。
③ 健康保険の任意継続制度を利用している
会社を辞めて、健康保険の任意継続制度を利用している方は、出産手当金はもらえません。任意継続制度とは、仕事を辞めても最長2年間は会社の健康保険に続けて加入できる制度です。
ただし任意継続の場合でも、以下の条件をすべて満たした場合は出産手当金をもらえます。
- 退職日までに1年間以上、健康保険に加入していること
- 退職日に働いていないこと
- 退職翌日の時点で、出産手当金を受給しているか受給できる状態にあったこと
④ 休業中に給与の支払いが発生している
出産手当金は、産前産後に休業していて、給与が支払われていない場合にもらえるものです。
たとえば、産前休業に入らず、出産する前まで働いていて、給与をもらっている場合は、その分、手当金がもらえません。また、出勤していなくても会社から給与の支払いがある場合も同様です。
会社からの給与が出産手当金の金額を上回るようであれば、もらえません。出産手当金が給与より少ない場合は、差額分が受け取れます。
そのため、会社から休業中に給与の支払いが発生している場合、出産手当金はもらえないケースがあることを覚えておきましょう。
⑤ 申請までの期間が2年を超えている
出産手当金の申請期限は、休業していた日ごとに、その翌日から2年以内です。そのため、申請するのを忘れて2年を超えてしまった場合は、出産手当金をもらえなくなるため注意しましょう。
出産手当金の支給条件
出産手当金の支給条件は3つあります。
- 勤務先の健康保険に自らが加入していること(被保険者であること)
- 妊娠4ヶ月以後の出産(早産や死産、流産を含む)であること
- 出産のために会社を休業していること
被保険者でなく、被扶養者の場合は支給できません。また、妊娠4ヶ月未満で出産した場合ももらえないため注意しましょう。
休業していない場合、給与の金額によって出産手当金は支給されないことがあるため、確認してください。
出産手当金の支給期間
出産手当金の支給期間は出産日以前42日と産後56日の合計98日の期間です。多胎だった場合は、出産日以前98日と産後56日です。ただし出産日が早まったり、遅くなったりした場合は、支給期間が変動します。
詳しくは出産手当金の受給における注意点の章で解説します。
出産手当金の申請方法
出産手当金の申請方法は2つあります。
- 必要な書類を揃える
- 各種窓口から出産手当金の申請を行う
準備が遅くなれば、申請するのも遅くなります。出産手当金を早くもらいたい場合は、速やかに準備をして、申請を行いましょう。
① 必要な書類を揃える – 書類一覧
出産手当金の申請に必要な書類として、出産した証明になる母子手帳のコピーが必要です。また、産前産後休業の申請を会社の所定の用紙に記入してもらいましょう。
申請に必要な書類は、各健康保険のホームページより、出産手当金の申請書類をダウンロードします。
その書類に、記載する項目がいくつかあります。
- 被保険者の情報
- 手当金の振込口座の記入
- 医師・助産師の記入欄
- 事業主証明書類
医師・助産師の記入欄では、どこの病院でいつ生まれたのか記載してもらいます。
事業主証明書類では、勤務状況や賃金など記入し、出産手当金の金額を決める重要な書類です。
出産時には、医師・助産師の記入する書類を印刷して準備しておくと、スムーズに記入してもらえます。
② 各種窓口から出産手当金の申請を行う
会社員の場合、ほとんどが会社の経理や総務の窓口が申請をしてくれるでしょう。その場合は、医師・助産師の記入欄の用紙のみ、自分で病院へ持っていき、記入してもらいます。
しかし、出産した本人が申請を行う場合は、事業主証明書類をあらかじめ、会社の窓口にお願いして書いて準備してもらいましょう。
医師・助産師の記入は、病院へ持ち込み、書いてもらいます。全部の書類が揃ったら、各健康保険の窓口へ郵送または持参しましょう。
出産手当金の受給における注意点
出産手当金の受給における注意点として、3つ挙げます。
- 退職した場合の支給条件
- 有給を使用した場合
- 出産の予定日がずれた・変わった場合
以下で解説します。
退職した場合の支給条件
退職した場合、退職日まで1年以上継続して健康保険に加入していたことが条件となります。
もし、1年以上加入していない場合は、出産手当金は支給されません。また、退職をして任意継続制度を利用した場合、一定の条件を満たしていなければ受給できないため、注意が必要です。
有給を使用した場合
出産日まで有給休暇で出勤扱いとなった場合、給与が発生するため支給できません。出産手当金は、出産のために休業して、給与の支払いがない場合に支給されるお金です。
有給休暇を使って産前を過ごした場合は、出産手当金の支給対象外となります。
出産の予定日がずれた・変わった場合
出産の予定日がずれた・変わった場合は、出産手当金の支給期間が変わります。
たとえば、出産日より3日早まった場合、出産日が前にずれます。出産予定日42日前まで働いていた場合、早まった日数分の出産手当金は支給されません。そのため、出産日以前42日から3日を引いて39日、産後56日とあわせて95日分が支給期間です。
出産日より遅れて生まれた場合は、その分産前の期間が長くなります。出産日以前42日+遅れた期間+産後56日が支給期間です。
このように、出産の予定日がずれた場合でも、出産手当金は支給されます。
出産手当金をもらえないケースがあるため事前に確認しよう
出産手当金とは、出産のために会社を休んでいて、給与の支払いがない場合に、健康保険からもらえるものです。もらえないケースとして、国民健康保険の加入者や、扶養者、任意継続被保険者があります。
出産手当金をもらう時の注意点として、退職した場合の支給条件や有給の使用、出産予定日がずれた時の3つがあります。
このように、支給条件や支給金があるため、自分はもらえる対象であるか確認しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
定額減税で手取りが増える?いくら増えるかを解説
近年物価の上昇が続いており、国民の生活は厳しいものとなっています。賃上げを行う企業も多く見られますが、それでも物価の上昇は大きな負担となっており、対策が必要です。 当記事では、物価…
詳しくみる扶養手当の条件は?支給対象となる必須要件や家族構成ごとの基準を解説
多くの企業で導入されている「扶養手当(家族手当)」ですが、その支給条件は法律で一律に決まっているわけではなく、会社の「就業規則(賃金規程)」によって定められています。 しかし実務上…
詳しくみるコロナの影響で住民税納税が難しい人向け 徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルスの影響で事業に支障が出ている個人事業者の方、中小企業の経営者の方もおられるでしょう。政府のコロナ対策としては、中小企業者や個人事業者向けの持続化給付金、フリーラン…
詳しくみるアルバイト・パートの給与計算方法は?確認事項と注意点を解説
アルバイトやパートの給与計算は、就業規則・給与規程・タイムカードなどの勤務管理書類を確認しながら進めます。時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた際は、アルバイト・パートに対しても社…
詳しくみるみなし残業は労働基準法違反か?法的根拠と注意点を解説
中小企業などでの導入が多く見られる「みなし残業時間制」。「違法なのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、これは労働基準法によって定められている労働形態です。 ただし、運用に注意を…
詳しくみるアルバイト・パートの有給は何日もらえる?半年の取得条件や最大付与日数を解説
アルバイト・パート従業員の有給日数は、勤続年数や週の勤務日数によって異なります。 また、アルバイト・パートなら誰でも有給が取れるわけではありません。有給の付与には条件があります。 …
詳しくみる