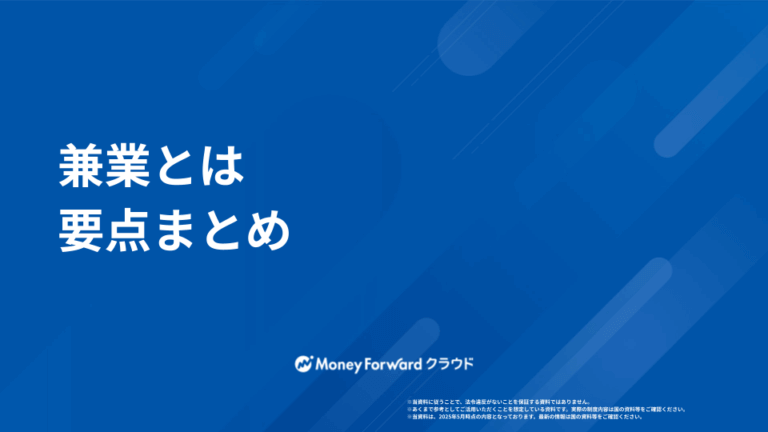- 更新日 : 2025年6月23日
兼業とは?副業との違いやメリット・デメリット、注意点を解説!
兼業とは、本業と同等の他の仕事を掛け持ちすることです。兼業の働き方は、企業などに雇用されるものや、起業して事業主として働くものなど様々です。本記事では、兼業とは何かや副業との違い、メリット・デメリット、注意点について解説します。
兼業とは?
兼業とは、本業と同等の収入や労働時間の他の仕事を掛け持ちをして行うことをいいます。本項では、兼業の定義や副業との違いについて解説していきます。
兼業の定義
兼業という働き方に、明確な法的定義はありません。一般的には、本業の他に同等な他の仕事を兼務していることを、兼業と呼んでいます。
兼業には明確な定義がないため、兼業を禁止する法律もありません。そのため、兼業を認めるかどうかも企業の裁量で決められますが、近年では兼業を認める企業も増えています。
兼業と副業の違い
兼業・副業ともに、本業以外の仕事を掛け持ちして行うことは同じです。しかし、両方とも明確な法的定義がないため、大きな違いはなく区別することもほとんどありません。
一般的に、副業は本業よりも低い収入や短い労働時間でのサブ的な仕事と捉えられていて、兼業は本業と同等の収入や労働時間の仕事として捉えられることが多いです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
人事・労務担当者向け Excel関数集 56選まとめブック
人事・労務担当者が知っておきたい便利なExcel関数を56選ギュッとまとめました。
40P以上のお得な1冊で、Excel関数の公式はもちろん、人事・労務担当者向けに使い方の例やサンプルファイルも掲載。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。お手元における保存版としてや、従業員への印刷・配布用、学習用としてもご活用いただけます。
入社前後の手続きがすべてわかる!労務の実務 完全マニュアル
従業員を雇入れる際には、雇用契約書の締結や従業員情報の収集、社会保険の資格取得届の提出など数多くの手続きが発生します。
本資料では、入社時に必要となる労務手続き全般を1冊にわかりやすくまとめました!
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
兼業が注目される背景は?
近年働き方が多様化して、兼業を希望する方が増えています。収入を増やすため、本業だけでは生活できない、時間を有効活用するためなど理由は様々です。兼業が注目されるようになった背景に、国が働き方改革や人材の流動化のために兼業を積極的に推進していく方針があります。
本項では、兼業が注目されるようになった「副業・兼業の促進に関するガイドライン」「モデル就業規則の改訂」について解説します。
副業・兼業の促進に関するガイドライン
2018年1月に厚生労働省が副業や兼業を促進するために、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成しました。このガイドラインは、兼業を導入する企業や労働者に対して、現行の法令のもとでの注意点や、導入の方法などをまとめたものです。
このガイドラインは、安心して副業や兼業をできるようなルールを明確化するために2020年9月に1度目の改定をしています。また、2022年7月には、労働者が適切な職業の選択と、多様なキャリア形成を図っていくために2度目の改定をしています。
モデル就業規則の改訂
2018年1月のモデル就業規則の改定により、労働者の遵守事項にあった「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」 という規定を削除しています。また、モデル就業規則に、副業、兼業についての規定を新設しています。
兼業のメリットは?
従業員が兼業すると、従業員だけでなく企業も様々なメリットを得ることが可能です。本項では、従業員が兼業することによる企業側のメリットについて解説します。
従業員の知識やスキルが向上し自社へ還元される
従業員が兼業することにより、社内だけでは取得できない知識やスキルを獲得できます。その結果、知識やスキルが社内に還元され、自社の生産性が向上し事業機会の拡大につながるでしょう。
従業員の自律性や自主性を促してモチベーション向上につながる
従業員が自社以外の仕事をすることにより、自律性や自主性を促してやりがいをみつけることができます。また、兼業することで収入が増えたり、成功したり、活躍の場が増えたりすることで、本業へのモチベーションの向上にもつながるでしょう。
優秀な人材流出の防止につながる
企業が兼業を認めることにより、企業を辞めずに兼業として従業員のやりたい仕事ができるようになります。その結果、企業の満足度が上がり、優秀な人材が流出することがなくなって企業の価値も低下せずに済みます。
企業がイメージアップすることで優秀な人材の獲得につながる
兼業を認めている企業ということをアピールすることで、企業のイメージアップにつながります。イメージアップすればその企業で働きたい人が増えて、優秀な人材の獲得につながるでしょう。
兼業のデメリットは?
従業員が兼業することを企業が認めることは、企業にとってメリットだけではありません。本項では、従業員が兼業することによる企業側のデメリットについて解説します。
自社の業務への影響がある
従業員が兼業すると自社の業務以外の仕事に時間を取られることになり、少なからずとも時間や労力がかかり疲労を感じる可能性もあります。その結果、作業効率が落ちて自社の業務に影響する可能性があるため注意が必要です。
労務管理が複雑になる
従業員が兼業している場合、2社に勤務しているなどの状況によっては、自社の労働時間と他社の労働時間を通算します。時間外労働に対する割増賃金についても、自社の労働時間と他社の労働時間を通算して発生し、支払義務があるのは後から雇用契約を締結した企業です。
兼業している従業員の労働時間を把握するためには、他社での労働時間を聴取する必要があり、兼業をしていない従業員よりも労務管理が複雑になります。
機密情報漏洩のリスクがある
兼業をしている従業員が、一方の企業で他方の企業の機密情報を漏らしてしまうリスクがあります。自社の保有している技術や重要な情報などが漏洩してしまった場合には、企業が受けるダメージも大きくなるでしょう。兼業をする従業員には、事前に秘密保持契約を交わしておくことが大切です。
優秀な人材の流出につながる可能性がある
従業員が兼業をすることで、一方の企業に魅力を感じたり、独立や起業につながったりすることがあります。その結果、優秀な人材が流出してしまう可能性もあるでしょう。
企業が兼業を認める場合の注意点は?
企業が兼業を認める場合には、注意しておかなければならない様々な点があります。本項では、企業が兼業を認める場合の注意点について解説します。
就業規則に兼業のルールなどを記載しておく
兼業を認める場合であっても、兼業を認める条件や兼業する場合の届け出、企業秘密の漏洩の禁止など、兼業に関するルールを就業規則に記載しておく必要があります。就業規則にきちんと兼業のルールを記載していない場合、トラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
兼業についての届出制度の制定
兼業をする場合には、適切な労務管理を行うために、他社での業務内容や労働時間の届け出をしてもらう必要があります。また、情報漏洩などのトラブルを防ぐために、自社の業務に支障をきたさないための誓約書などを提出してもらうとよいでしょう。兼業を認める場合には、届出制度の制定をすることが重要です。
秘密保持義務などの確保
従業員が兼業を始める場合に疎かになりがちな、従業員の職務専念義務や秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかが注意点になります。
職務専念義務とは、就業時間中に職務に専念しなければならない義務のことです。秘密保持義務とは、自社の技術や機密情報などを漏洩させない義務になります。競業避止義務とは、自社に不利益になるような競業行為を禁止することです。
兼業に関するルールを徹底することが企業と従業員の双方のメリットとなる
企業が従業員に兼業を推進する場合、ルールを決めずにただ認めるだけでは、お互いの兼業に対する認識が異なりトラブルに発展する可能性があります。
一方、企業と従業員の兼業に対する双方の認識が共有できていれば、従業員のスキル向上による企業の生産性の向上、優秀な人材の獲得や流出防止につながります。
兼業を企業と従業員双方の大きなメリットにつなげるためには、就業規則などの社内規定に兼業に関するルールを記載して徹底することが大切です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
変形労働時間制の種類(1ヶ月単位、1年単位、1週間単位、フレックスタイム制)とは?
変形労働時間制は、企業の業務の忙しさに合わせて労働時間を柔軟に設定できる制度です。しかし、「種類が多くてよくわからない」「残業代が減るだけで、労働者にデメリットしかないのでは?」と…
詳しくみる有給休暇の消滅はいつ?繰り越しルールや違法な場合、計算方法を解説
有給休暇は労働者の権利ですが、忙しい会社ではなかなか消化できないというケースが多いかもしれません。 有給休暇は発生した日から2年経つと消滅するため、注意が必要です。有休の取得は労働…
詳しくみる一人での夜勤は違法?ワンオペのリスクと法的基準を解説
一人での夜勤(ワンオペ夜勤)が、直ちに法律違反となるわけではありません。しかし、適切な休憩が取れない状況や、安全への配慮が不十分な場合は、労働基準法違反や安全配慮義務違反と判断され…
詳しくみる就業規則の固定残業代(みなし残業代)の記載例|厚生労働省の指針をもとに解説
「固定残業代の就業規則への具体的な記載例が知りたい」「固定残業代の明示義務や、記載なしの場合のリスクが不安」といったお悩みはありませんか? 固定残業代は、就業規則への記載方法や労働…
詳しくみる勤怠集計のやり方とは?手計算やExcel、勤怠管理システムで効率化する方法まで解説
毎月の給与計算に欠かせない勤怠集計のやり方は、タイムカードを使った手計算から、Excelや勤怠管理システムを活用した自動化までさまざまです。 この記事では、勤怠集計の正確なやり方に…
詳しくみる有給を使い切った後に欠勤をしたらどう扱われる?月給や評価への影響についても解説
有給を使い切った後の欠勤は、従業員と企業側のどちらにも重要な問題です。 従業員は、欠勤控除で給与が減るだけではなく、評価やボーナスなどさまざまな部分に影響が出るでしょう。 従業員は…
詳しくみる