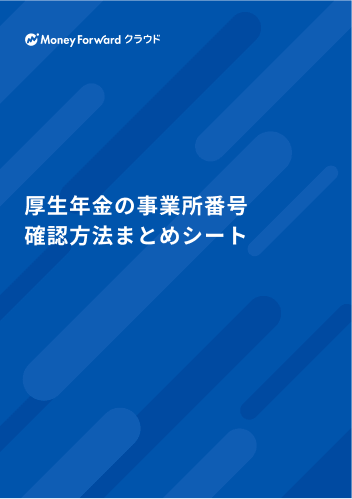- 更新日 : 2025年10月31日
厚生年金の事業所番号とは?わからない時の確認方法は?
従業員を雇用すると、事業主は健康保険や厚生年金保険などの社会保険に関するさまざまな手続きを行う必要があります。
所定の書類を年金事務所などに提出することになりますが、その際は事業所番号と事業所整理番号を記載しなければなりません。
本稿では、これら2つの紛らわしい番号の違いと確認方法などについて詳しく解説します。
厚生年金の事業所番号とは?
法人の事業所と従業員が常時5人以上いる個人の事業所は、原則として厚生年金保険・健康保険両制度に加入することが義務付けられています。
加入後は、従業員の入社、家族の扶養追加、退社などの被保険者資格の得喪関係だけでなく、保険料の納付、保険料額の変更など、さまざまな手続きが発生します。
こうした届出関係の手続きは厚生年金保険に限らず、健康保険も含めて年金事務所が所管しています。
年金事務所に届け出るすべての書類の「提出者記入欄」には、事業所番号と事業所整理記号を記入しなければなりません。

参考:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届|日本年金機構
事業所番号とは、事業所が新規に健康保険と厚生年金保険の適用事業所となったときに年金事務所(日本年金機構)から告知された5桁の数字のことです。
事業所整理記号とは別物
事業者整理記号も、事業所が新規適用事業所となったときに振り出されます。
もともと、健康保険と厚生年金保険の事業は厚生労働省の外局である社会保険庁が所管し、出先機関として各都道府県に社会保険事務所が置かれていました。
しかし、2000年代前半に不祥事が相次いで発覚したことから一連の抜本的改革が進められ、2008年10月に政府管掌の健康保険事業は公法人である全国健康保険協会(協会けんぽ)の発足とともに移管されました。
2009年12月に同庁は廃止され、年金事業は公法人である日本年金機構の設置とともに引き継がれました。
社会保険庁時代に振り出されていた事業所整理記号は、「数字2ケタ+カタカナまたは英数4ケタ以内」や「漢字+ひらがな」の形式で表記されており、冒頭の数字2ケタまたは漢字は保険者の管轄を示しています。
例えば、「01-イロハ」や「港 いろは」という形式です。
事業所番号と事業所整理記号の違い
事業所番号は告知番号とも呼ばれ、健康保険・厚生年金保険の新規適用事業所となったことの証しとして事業所に対して付与される番号です。
一方の事業所整理番号は、社会保険の運営主体である保険者を示すとともに事業所を管理するための番号です。
例えば「港 いろは」であれば、前述の経緯で旧社会保険庁時代の港社会保険事務所が所管していたことを意味します。
旧社会保険庁時代は社会保険事務所が健康保険と年金の窓口になっていたため、従業員に交付される健康保険証(被保険者証)に記載される事業所整理記号(事業所記号)も漢字やひらがなを用いた形で統一されていました。
しかし、健康保険証に記載される事業所整理記号(事業所記号)については、2008年の全国健康保険協会(協会けんぽ)の発足に伴い、従来の「漢字かな」から7桁もしくは8桁の「数字」になりました。
年金事務所では現在でも旧体制での事業所整理記号を使用していますが、従業員の傷病手当金など健康保険の保険給付する際の申請書の提出先は管轄の協会けんぽ支部となります。
その際申請書に記載する事業所整理記号は、協会けんぽで使用する健康保険証に記載されている番号です。
こうしたことから、年金事務所の事業所整理記号を協会けんぽの形式に変換できるよう、変換表が一部の協会けんぽの支部を除いて公開されています。
変換表を用いて、漢字とひらがなの部分をそれぞれ対応する2桁の数字に変換します。
先ほどの「港 いろは」の場合、「港」は「11」、「い」は「01」、「ろ」は「02」、「は」は「03」となり、全体では「11010203」と8桁の数字に変換されます。
参考:東京都内事業所記号の変換方法について|協会けんぽ東京支部
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
厚生年金における事業所番号の確認方法
従業員が新たに入社したときなど、申請書の作成において事業所番号や事業所整理記号の記載が必要になった場合、何を確認すればよいのでしょうか。
協会けんぽで使用される事業所整理記号は従業員の健康保険証で確認できますが、従業員の健康保険の保険給付以外の被保険者資格や保険料関係の諸手続きは、年金事務所が窓口になっています。
事業所整理記号については、協会けんぽの変換表で逆に年金事務所で使用する番号に変換できないわけでありませんが、変換表を公開していない支部もあります。
また、事業所番号は健康保険証に記載されていません。
事業所番号も事業所整理記号も、最初に健康保険・厚生年金保険の適用事務所の手続きを行った際、年金事務所から事業所に送付される「適用通知書」に記載されています。

その他、「保険料納入告知額・領収済額通知書」「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」にも記載されています。


日本年金機構のサイトでは「事業所検索システム」によって厚生年金保険・健康保険適用事業所情報を検索できますが、こちらで確認できるのは適用事業所となった年月日、被保険者数、法人番号などであり、事業所番号や事業所整理記号はわかりません。
厚生年金の事業所番号の確認方法を知っておこう!
従業員の被保険者資格の得喪や保険料の納付、保険料額変更の手続きの際に必要な事業所番号と事業所整理記号の意味、違いなどについて解説しました。
いざというときに慌てないように、これらの番号の確認方法を知っておきましょう。
よくある質問
厚生年金の事業所番号とは何ですか?
健康保険・厚生年金保険の新規適用事業所となったことの証しとして、事業所に対して付与される番号です。詳しくはこちらをご覧ください。
厚生年金における事業所番号の確認方法を教えてください。
「適用通知書」や「保険料納入告知額・領収済額通知書」などで確認できます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
【記入例付】雇用保険被保険者資格取得届とは?書き方や提出先を紹介!
従業員を雇い入れたら、複数の社会保険手続きをする必要があります。 その一つが「雇用保険被保険者資格取得届」です。これは、従業員を雇用保険に加入させるために、管轄のハローワークに提出する書類です。 この記事では、雇用保険被保険者資格取得届の概…
詳しくみる国保と社保は何が違う?対象者や保険料・扶養・給付内容を徹底比較
国民健康保険(国保)と社会保険(社保)の主な違いは、加入対象者や保険料の負担方法、扶養制度の有無、給付内容にあります。社保は主に会社員が対象で保険料は会社と折半、扶養制度がある一方、国保は主に自営業者などが対象で保険料は全額自己負担となり、…
詳しくみる社会保険の扶養はいくらまで?年収130万円・106万円の壁と手取り額
会社員などの扶養家族となっている配偶者や子どもでも、一定金額を超えなければ扶養のまま、パート・アルバイト収入などを得られます。しかし、定められている金額を超えてしまうと、扶養から外れなければなりません。 扶養といわれているものには「税の扶養…
詳しくみる介護保険サービスの自己負担額は?負担割合や計算方法も解説
介護保険サービスを利用することになった際に、気になる点の一つとして「いくらかかるのか?」ということがあります。サービスを安心して受けられるようにするためにも、かかる費用についての目安を知っておくことが必要でしょう。 今回は、介護保険サービス…
詳しくみる労働保険の加入条件や義務、手続きをわかりやすく解説
労働保険の加入は、労働者を雇用するすべての事業者に求められる法的な義務です。とはいえ、「うちはアルバイトだけだから不要」「加入手続き方法がわからない」などといったこともあるでしょう。 本記事では、労働保険の加入条件・義務・手続きについて、わ…
詳しくみる社会保険料の変更に伴う手続きを解説!随時改定の意味など
社会保険料は、月々の給与額ではなく、標準報酬月額をもとに算出されます。毎年1回、7月に算定基礎届を提出することにより決定され、固定的賃金に変動があった場合は月額変更届による随時改定を行います。 今回は、社会保険料の決定方法と変更が必要なタイ…
詳しくみる