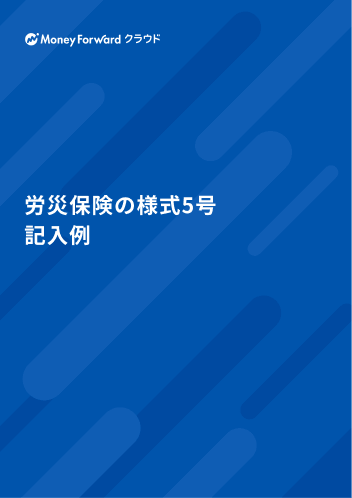- 更新日 : 2025年11月19日
労災保険の様式5号はどうやって手に入れる?そもそも様式とは?
労災保険の様式5号は、療養補償給付の請求に用いる書類です。指定医療機関に提出することで、労災病院や薬局での支払いが不要になります。様式5号には会社名や所在地、労働保険番号のほか、療養を受ける労働者の指名や職種、労災事故の原因や状況などを記入します。指定医療機関以外の場合の療養補償の請求には、様式7号を用います。
目次
労災保険の様式とは?
労災保険(労働者災害補償保険)は労働者の就労にまつわるケガ・病気・死亡に対して、補償として必要な給付を行う公的保険制度です。さまざまな種類があり、多岐にわたる内容の給付を行っています。
労災事故などにより労災保険の給付対象になった際は、所定の手続きで請求することで受給できます。添付書類とともに請求書の提出が求められ、定められたフォーマットを用いて請求しなければなりません。請求書として用いることが定められているフォーマットが、労災保険の様式です。様式は、受けようとする労災保険給付によって変わります。
様式の種類はいくつある?
労災保険の給付を受ける際の請求に用いる様式には、多くの種類があります。業務災害に関する給付を受ける際の主な請求書は、以下のとおりです。
- 様式5号:療養補償給付たる療養の給付請求書
- 様式7号:療養補償給付たる療養の費用請求書
- 様式8号:休業補償給付支給請求書
- 様式10号:障害補償給付支給請求書
- 様式12号:遺族補償年金支給請求書
なぜ様式が違う?
労災保険の様式の種類が多いのは、給付の支給対象や要件がそれぞれ異なるためです。労災保険の給付を受けるためには受給の対象者であること、要件を満たしていることを請求書類にきちんと記す必要があります。様式は、それぞれの給付について必要な情報を記載できるようになっています。記載されるべき情報が給付によって異なるため、請求に用いる様式も異なるのです。
労災保険の様式5号とは?
労災保険の様式5号は、従業員が業務に起因する病気やケガで都道府県労働局長が指定した医療機関(指定医療機関)において治療を受ける場合に、その給付を受けるために使用する書類です。労働者が労災事故などで仕事中にケガをした場合、仕事が原因で病気になった場合、労災保険から療養補償給付を受けることができます。療養補償給付は労災指定などの指定医療機関において、窓口負担なしで診察・治療を受けることができるものです。
労災保険の様式5号はどこで手に入れる?
労災保炎の様式5号は、以下のいずれかの方法で入手できます。
- 労働基準監督署で受け取る
- 厚生労働省HPからダウンロードする
厚生労働省HPには印刷して記入するものと、 Adobe Acrobat Reader DCで 入力してから印刷するものがあります。提出後にOCRで読み取られるため、印刷する際はページの拡大や縮小、回転、中央配置などは行わないようにしましょう。
労災保険の様式5号の記入・申請方法
労災保険の様式5号は定められたとおりに記入し、申請する必要があります。
様式5号への記入方法
労災保険の様式5号には、労働保険番号・労働者・労災事故・事業主証明を記入します。
- 労働保険番号
14桁の労働保険番号を記入します。
- 労働保険番号
- 労働者について
氏名・住所・年齢・職種を記入します。
職種は作業内容がわかるよう、できるだけ具体的に書きます。
- 労働者について
- 労災事故について
災害の原因や発生状況、事実確認者の氏名・職種などを記入します。
災害の原因と発生状況については場所・作業内容・周囲の様子を詳細に、わかりや すく書く必要があります。災害発生日と初診日が異なる場合は、その理由も記入しなければなりません。
- 労災事故について
- 事業主証明
記載内容に間違いがないことの証明として、事業名や事業場の所在地・事業主の氏名などを記入します。
様式5号の申請および提出先
労災保険の様式5号は、治療を受ける労災病院などの指定医療機関に提出します。労災病院などの指定医療機関に様式5号を提出すると都道府県労働局に対して申請が行われ、厚生労働本省から支払いが行われます。
薬局を利用する場合は、別に様式5号を薬局へ提出する必要があります。
労災事故報告書のテンプレート(無料)
以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。
様式5号を理解し、労災事故発生に備えよう
労災保険の様式5号は、療養補償給付を受ける際に用いる書類です。労災病院などの指定医療機関にかかる場合に提出することで、窓口での支払いなしで診察・治療を受けることができます。病院以外に薬局を利用する場合は、別途提出する必要があります。厚生労働省HPからダウンロードするか、労働基準監督署で受け取ることで入手できます。
様式5号には労働保険番号や療養を受ける従業員の氏名・職種、労災事故の原因、発生状況などを記入します。被災した従業員の職種や労災事故については、特に詳しく記入しなければなりません。実際に労災事故が発生した場合に迅速に準備できるよう、記入方法などをきちんと理解しておきましょう。
よくある質問
労災保険の様式5号とは何ですか?
労災保険の療養補償給付を受ける際、労災病院などの指定医療機関に提出する書類です。詳しくはこちらをご覧ください。
労災保険の様式5号は、どこで手に入れることができますか?
厚生労働省HPからダウンロードしたり、労働基準監督署で受け取ったりすることで入手できます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
有給休暇の消滅はいつ?繰り越しルールや違法な場合、計算方法を解説
有給休暇は労働者の権利ですが、忙しい会社ではなかなか消化できないというケースが多いかもしれません。 有給休暇は発生した日から2年経つと消滅するため、注意が必要です。有休の取得は労働者の重要な権利であり、会社には消滅を防止する取り組みが求めら…
詳しくみる特別休暇とは?給料は支払われる?種類や日数も解説!
労働者に与える休暇のうち、法定休暇とは別に企業が任意で付与する休暇を特別休暇と言います。企業は特別休暇の種類や付与日数、給料支払いの有無などについて自由に設定でき、無給としても問題ありません。 代表的な特別休暇には病気休暇や慶弔休暇、裁判員…
詳しくみる長時間労働の基準とは?36協定と過労死ラインをわかりやすく解説
自社の労働時間が「長時間労働」にあたるのか、判断に迷うことはないでしょうか。長時間労働は、従業員の心身の健康を損なうだけでなく、企業の生産性低下や法的リスクにもつながる重要な経営課題です。実は「長時間労働」を判断する基準は一つではなく、法律…
詳しくみるリモートワークとは?テレワークとの違いやメリット、導入のポイントを紹介【報告書テンプレつき】
リモートワークは、会社に通勤することなく、自宅やサテライトオフィスなど、会社以外の場所で働くことです。コロナ禍の影響によって、リモートワークを導入する会社が急激に増えました。本記事では、リモートワークとテレワークの違いやリモートワークのメリ…
詳しくみる労働基準法第36条とは?時間外労働(残業)や休日労働、36協定をわかりやすく解説
労働基準法第36条は、時間外労働(残業)や休日労働を労働者にさせるための条件を定めた条文です。この条文に基づいて締結される「36協定」が、企業と労働者の間で残業を行うための前提となります。 この記事では、36協定の基本的な仕組みや締結方法、…
詳しくみる労働基準法が定める休憩時間とは?取得ルールを正しく理解しよう!
労働基準法の休憩時間に関する決まりとは? 休憩時間に関する規定を定めた労働基準法第34条には「労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分」「8時間を超える場合においては少くとも1時間」の休憩時間を与えなければならないと定められてい…
詳しくみる