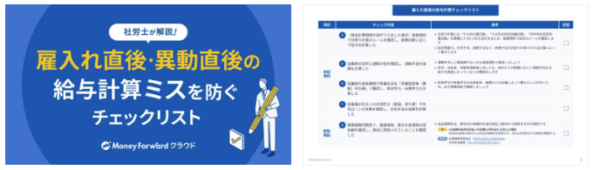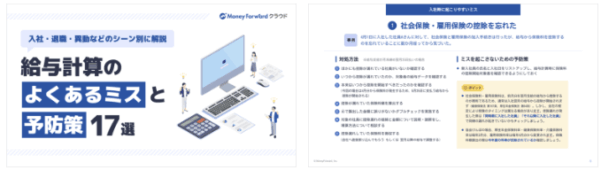- 更新日 : 2025年11月26日
社内異動の手続きと流れは?進め方や人事担当者が知るべき注意点とは
社内異動は、適材適所の人員配置や人材育成を通じて組織を活性化させる重要な人事施策です。しかし、その手続きは内示の伝え方から社会保険関連の処理まで多岐にわたり、担当者にとっては複雑で気を使う業務でもあります。
この記事では、中小企業の経営者や人事・労務担当者の方向けに、社内異動の目的から具体的な手続きの流れ、トラブルを防ぐための注意点までをステップごとに分かりやすく解説します。この記事を読めば、スムーズで円滑な社内異動を実現するためのポイントがわかります。
関連記事|部署異動・社内異動とは?スムーズな進め方や伝え方のポイントを解説
目次
【5ステップ】社内異動の基本的な手続きと流れ
社内異動は、思いつきで進めるものではありません。企業の成長戦略と従業員のキャリアを両立させるため、計画的なステップを踏むことが成功の鍵となります。
ここでは、異動計画の立案から異動後のフォローまで、人事担当者が進めるべき基本的な手続きと流れを5つのステップに分けて具体的に見ていきましょう。
ステップ1:異動計画の策定と目的の明確化
最初に行うべきは、異動計画の策定です。なぜ異動が必要なのか、「新規事業のための人員強化」「欠員補充」「次世代リーダーの育成」といった目的を明確にします。目的がはっきりすることで、異動させるべき人材の要件や異動の規模、時期(一般的には4月や10月が多い)が見えてきます。この段階で、異動に伴う人件費の変動や、転居費用などの予算も概算で把握しておくことが重要です。
ステップ2:対象者の選定と内示の実施
次に、策定した計画に基づいて異動対象となる従業員を選定します。業務スキルや実績はもちろん、本人のキャリアプランや潜在能力、新しい環境への適応力などを総合的に評価して判断します。対象者が決まったら、公式な辞令の前に「内示」を行います。内示は、対象者本人に非公式に異動の意思を伝える重要なプロセスです。情報が正式発表前に漏れると混乱を招くため、慎重な情報管理が求められます。
関連記事|人事異動は拒否できる?拒否された場合の対応やスムーズな異動のポイントを解説
ステップ3:辞令の交付と社内への公表
内示によって本人の理解を得た後、企業が正式な業務命令として「辞令」を交付します。辞令は、異動発令日、異動先の部署、新しい役職などを記載した書面で交付するのが一般的です。辞令交付後、適切なタイミングで関係部署や全社に向けて人事異動を公表します。公表が早すぎると異動前の部署の士気に影響し、遅すぎると業務の引き継ぎが滞る可能性があるため、タイミングの見極めが肝心です。
関連資料|異動辞令テンプレート
ステップ4:人事・労務・経理に関する諸手続きの実行
辞令の交付と並行して、担当者は多岐にわたる事務手続きを進めます。後ほど詳細を解説しますが、具体的には、変更された労働条件の書面による通知、社会保険・労働保険関連の届出、給与計算の変更(通勤手当や役職手当など)、勤怠管理システムの所属部署変更、社内システムのアクセス権限の見直しなどがあります。これらの手続きは抜け漏れなく、正確に行う必要があります。
関連資料|入社・退職・異動の手続きガイドブック
ステップ5:異動後のフォローアップと定着支援
人事異動は、辞令を出して終わりではありません。異動した従業員が新しい環境でスムーズに業務を始め、早期に活躍できるようサポートすることが極めて重要です。具体的には、受け入れ部署の上司による定期的な1on1ミーティングの実施、メンター制度の導入、必要なスキルのための研修などが挙げられます。こうしたフォローアップが、異動後の早期離職を防ぎ、エンゲージメントを高めます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
雇入れ直後・異動直後の給与計算ミスを防ぐチェックリスト
給与計算にミスがあると、従業員からの信用を失うだけでなく、内容によっては労働基準法違反となる可能性もあります。
本資料では、雇入れ直後・異動直後に焦点を当て、給与計算時のチェックポイントをまとめました。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
この資料では、各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にまとめました。
【異動時も解説!】給与計算のよくあるミスと予防策17選
給与計算で起きやすいミスをシーン別にとりあげ、それぞれの対処方法を具体的なステップに分けて解説します。
ミスを事前に防ぐための予防策も紹介していますので、給与計算の業務フロー見直しにもご活用ください。
社内異動の手続きを進める上での注意点
社内異動の手続きは、一つ間違えると従業員のモチベーション低下や不信感を招き、最悪の場合、労務トラブルに発展するリスクをはらんでいます。ここでは、手続きを円滑に進め、従業員との良好な関係を維持するために、人事担当者が特に注意すべき4つのポイントを解説します。
内示を伝えるタイミングと方法
内示は、従業員のその後のキャリアや生活設計に大きな影響を与えるため、伝え方が非常に重要です。タイミングは、一般的に辞令発令の1ヶ月前から2週間前が目安とされますが、転居を伴う場合は、準備期間を考慮してさらに早く伝えるべきです。伝え方は、必ず直属の上司から個別に、対面で行うのが原則です。その際、異動の背景や会社が期待する役割を丁寧に説明し、本人の疑問や不安に真摯に耳を傾ける姿勢が求められます。
就業規則の異動規定を必ず確認する
企業が従業員に異動を命じる法的根拠は、就業規則や雇用契約書に定められた「業務上の都合により、配置転換を命じることがある」といった規定です。異動を検討する際は、自社の就業規則に適切な規定があるかをまず確認しましょう。ただし、規定があれば無制限に命令できるわけではありません。業務上の必要性が低い異動や、特定の従業員を狙い撃ちにするような不当な動機に基づく異動は、権利濫用とみなされる可能性があります。
転居を伴う異動者への十分な配慮
勤務地の変更に伴い従業員が転居を必要とする場合(転勤)、本人だけでなくその家族の生活にも大きな影響が及びます。企業は、こうした負担を軽減するための配慮を欠かしてはなりません。具体的には、赴任手当、引越し費用の会社負担、住宅手当や社宅の提供、単身赴任手当の支給など、就業規則や賃金規程に基づいた経済的サポートを明確に提示することが重要です。家族の事情(育児や介護など)にも配慮し、十分な話し合いの場を持つことがトラブル防止につながります。
関連記事|望まない異動はパワハラになる?判断基準や異動を快諾してもらうポイントを解説
労働条件の不利益変更に該当しないか
異動に伴って、賃金が下がったり、役職が解かれたり、通勤時間が大幅に増加したりするなど、従業員にとって労働条件が不利になる変更(不利益変更)が生じる場合があります。労働契約法では、労働条件の不利益変更は、原則として従業員の個別の同意なく行うことはできないと定められています。やむを得ず不利益変更が生じる場合は、その必要性や変更内容の妥当性を真摯に説明し、本人の自由な意思に基づく明確な同意を得る必要があります。
社内異動に伴う労務手続きの詳細
社内異動では、従業員の労働条件や個人情報に変更が生じるため、法に基づいた正確な労務手続きが不可欠です。これらの手続きは従業員の給与や社会保障に直結する重要な業務です。ここでは、特にミスが許されない3つの労務手続きについて、その詳細とポイントを解説します。
関連記事|従業員が異動(転勤)したら雇用保険の変更はどう行う?手続き方法や電子申請について解説
労働条件通知書の再作成・交付
労働条件通知書は、雇い入れ時に交付される書面であり、異動時には原則として交付不要です。しかし、異動によって勤務地、職務内容、始業・終業時刻、賃金などに変更がある場合は、できる限り労働条件通知書など、書面の交付によって確認することが望ましいとされています。特に2024年4月の労働基準法施行規則改正により、労働契約の締結・更新のタイミングで明示すべき事項に「就業場所・業務の変更の範囲」が追加されました。異動後に関わりうる勤務地や業務内容の範囲を明記することで、将来的な認識のズレを防ぎます。
社会保険・労働保険の変更手続きリスト
転居を伴う異動の場合、健康保険・厚生年金保険の「被保険者住所変更届」を管轄の年金事務所へ提出します。ただし、マイナンバーと基礎年金番号が紐付けされている場合は不要となります。また、異動に伴う昇給・降給により、標準報酬月額が2等級以上変動し、その状態が3ヶ月続いた場合は「月額変更届」の提出が必要です。雇用保険に関しては、転勤があった日の翌日から10日以内に、転勤先事業所を管轄するハローワークへ「雇用保険被保険者転勤届」を提出する必要があります。ただし、一時的な出張や駐在のような場合には、手続きは不要です。
通勤手当や各種手当の変更に伴う給与計算
勤務地の変更で一般的なのが通勤手当の見直しです。新しい通勤経路と費用を従業員から申請してもらい、給与計算に反映させます。その際、所得税の非課税限度額を超えていないかを確認することも忘れてはいけません。また、異動に伴い役職手当や資格手当、地域手当、単身赴任手当などが新たに追加されたり、逆に支給されなくなったりする場合も、給与計算システムの設定変更を正確に行う必要があります。
関連資料|【社労士監修】雇入れ直後・異動直後の給与計算ミスを防ぐチェックリスト
社内異動の手続きを効率化するコツ
社内異動の手続きは複雑で多岐にわたるため、人事担当者の業務負担は大きくなりがちです。しかし、いくつかの工夫を取り入れることで、業務を効率化し、ミスを減らすことが可能です。ここでは、中小企業でもすぐに実践できる、異動手続きをスムーズに進めるための3つのコツをご紹介します。
チェックリストとテンプレートで業務を標準化する
異動のパターン(転居の有無、昇格の有無など)ごとに、必要なタスクを時系列でまとめた「異動手続きチェックリスト」を作成しましょう。これにより、担当者が誰であっても業務の抜け漏れを防ぎ、進捗管理が容易になります。また、辞令書や内示通知書といった各種書類は、あらかじめテンプレート化しておくことで、作成時間を大幅に短縮し、記載内容の標準化を図ることができます。
人事情報を一元管理し、手続きの抜け漏れを防ぐ
従業員の氏名や住所、所属、給与情報などが、部署ごとや担当者ごとに異なるファイル(Excelなど)で管理されていると、情報の更新漏れや転記ミスが発生しやすくなります。これらの人事情報をクラウド型のデータベースなどで一元管理することで、常に最新かつ正確な情報に全部署からアクセスできるようになります。これにより、異動に伴う各種手続きの際に、古い情報を使ってしまうといったミスを防げます。
人事労務システムを活用して申請・承認を効率化する
住所変更届や通勤経路の申請、各種手当の申請などを紙やメールで行っている場合、ワークフロー機能を持つ人事労務システムを導入することで劇的に効率化できます。従業員はスマートフォンやPCから簡単に入力でき、承認者はオンラインで内容を確認・承認できます。手続きの進捗状況が可視化されるため、承認の遅れや書類の紛失といったトラブルもなくなります。
なぜ、社内異動が行われるのか?
日々の手続きに追われていると忘れがちですが、社内異動は企業の成長に欠かせない重要な経営戦略の一つです。ここでは、手続きという実務的な視点から少し離れて、そもそも企業がなぜ社内異動を行うのか、その背景にある3つの大きな目的とメリットについて改めて考えてみましょう。
適材適所による生産性の向上
企業が持つ最も重要な経営資源は「人」です。従業員一人ひとりが持つスキル、経験、そしてポテンシャルを最大限に引き出すことが、組織全体の生産性向上に直結します。社内異動は、従業員を最も活躍できるであろうポジションに配置し直す「適材適所」を実現するための有効な手段です。個人の能力が最大限に発揮されることで、事業の成長が加速します。
計画的な人材育成とキャリアパスの提示
一つの部署で同じ業務を続けるだけでは、得られるスキルや視点に偏りが生じがちです。複数の部署や職種を経験させる計画的な異動(ジョブローテーションなど)は、幅広い視野と多様なスキルを持つ次世代のリーダーや経営幹部を育成するために不可欠です。従業員にとっても、会社が多様なキャリアパスを提示してくれることは、成長機会の提供となり、仕事へのモチベーション向上につながります。
組織の活性化とマンネリ化の防止
どんな組織でも、同じメンバー構成が長く続くと、人間関係が固定化し、業務の進め方や発想がマンネリ化してしまうことがあります。社内異動によって人材を流動させることは、組織に新しい風を吹き込み、既存のやり方を見直すきっかけを生み出します。新しい知識やノウハウが組織内で共有されることで、イノベーションが促進され、組織全体が活性化する効果が期待できます。
適切な社内異動の手続きと流れが、企業の未来を創る
従業員の納得感を得ながら社内異動を成功させるには、目的の共有から丁寧なコミュニケーション、そして正確な事務手続きまで、一連の流れをスムーズに進めることが不可欠です。特に、トラブルを未然に防ぐための注意点を押さえ、ミスが許されない労務手続きを確実に行うことが、従業員との信頼関係を維持する鍵となります。本記事で解説した手続きの流れや効率化のコツを参考に、戦略的な人事異動を実践し、企業の持続的な成長につなげていきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
雇用契約書に変更があった場合の手続きは?変更時の注意点や拒否された際の対処法も解説
私たちが社会で働く際、一般的には使用者と労働者の立場で雇用契約を締結します。さまざまな理由で雇用契約を変更する場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。 この記事では、雇用…
詳しくみるサードプレイスとは?場所はどこがよい?意味や定義も解説
サードプレイスとは、家庭や職場とは異なる「第三の場所」という意味です。日々のストレスから解消され、自分らしく過ごせる場として、家庭や職場以外でリラックスができる居場所が必要だという…
詳しくみる個人事業主でも外国人雇用助成金を申請できる?申請方法や注意点について解説
個人事業主も外国人雇用助成金を申請できます。助成金を活用すれば、支払った費用の一部を回収できる可能性があるため、人材確保や職場環境の整備が可能です。ただし、助成金ごとに対象要件や申…
詳しくみる従業員とは?派遣社員は含まれる?社員や職員との違いを解説
「従業員」や「社員 」、「職員」などは、普段何気なく使っている単語ですが、どのような違いがあるのでしょうか。 本記事では従業員の種類や、雇入れの際の手続き、加入する保険などについて…
詳しくみる就業規則の法的効力は?発生要件や発生日、適用範囲、優先順位などのポイントを解説
就業規則は単なる社内規程ではなく、労働契約の内容を具体的に定め、時には個別の合意よりも優先される法的効力を秘めています。 この記事では、就業規則の法的効力とは何か、どのような条件で…
詳しくみる退職勧奨はパワハラになる?該当する事例と3つの対処法
「退職勧奨をしなければならないが、パワハラにならないだろうか」「パワハラにならないための対策を知りたい」 このように悩む方もいるのではないでしょうか。 退職勧奨自体は違法ではありま…
詳しくみる