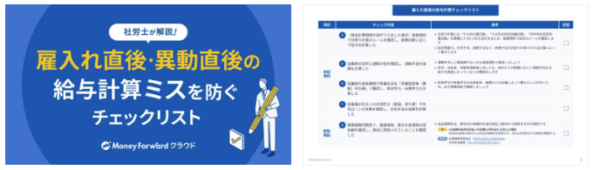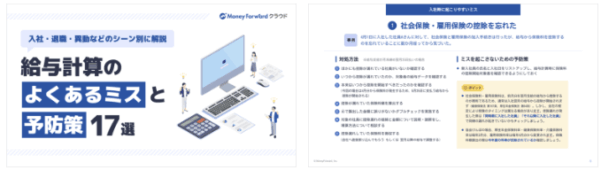- 更新日 : 2025年11月26日
異動者のモチベーションケア、何から始める?効果的な面談と環境づくり
人事異動は組織の成長に不可欠ですが、異動する社員のモチベーションケアは多くの企業が直面する課題です。「何から手をつければ良いのか」と悩む担当者様も多いでしょう。その最初の答えは「効果的な面談」と「安心して働ける環境づくり」にあります。本記事では、異動者の不安を解消し、新たなスタートを成功に導くための具体的なアクションを解説します。適切なケアを通じて、異動を社員と組織、双方にとって前向きな機会に変えていきましょう。
目次
異動者ケアの第一歩は効果的な面談から
異動者のモチベーションケアは、まず丁寧な対話から始まります。面談は、単に辞令を伝える場ではありません。社員が抱える不安や期待を理解し、会社としてのサポートの姿勢を示すことで、信頼関係を築く重要な機会です。異動前後の適切なタイミングで面談を設定し、社員一人ひとりと向き合うことが、スムーズな移行とモチベーション維持の鍵となります。
異動の目的と期待を伝える面談
異動を伝える最初の面談は、特に重要です。ここでは、「なぜ今回の異動があるのか」という背景や組織としての狙いを明確に伝えます。その上で、「なぜあなたなのか」という選出理由と、新しい部署でどのような役割や活躍を期待しているのかを具体的に話しましょう。「あなたのこれまでの経験が、新しい部署でこのように活かせるはずだ」といった言葉は、社員の納得感を高め、前向きな気持ちを引き出します。
不安を傾聴する異動後の1on1ミーティング
異動後は、新しい環境への適応で心身ともに負担がかかる時期です。着任後1週間、1ヶ月、3ヶ月といった節目で1on1ミーティングを設定し、意識的に話を聞く機会を設けましょう。この面談の主役はあくまで異動者本人です。「困っていることはないか」「人間関係で気になる点はないか」など、業務面だけでなく心理的な側面にも配慮した質問で、本音を話しやすい雰囲気を作ることが大切です。課題の早期発見と解決につながります。
キャリアの接続を意識した目標設定
異動をキャリアの断絶と捉えさせないために、目標設定の面談も効果的です。本人の今後のキャリアプランを聞いた上で、今回の異動がその実現にどう繋がるのかを一緒に考えましょう。例えば、「この部署での経験が、将来〇〇のポジションで役立つ」といったように、長期的な視点で異動の意味付けを行います。短期的な業務目標だけでなく、中長期的なキャリア目標と接続することで、仕事への目的意識が高まります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
雇入れ直後・異動直後の給与計算ミスを防ぐチェックリスト
給与計算にミスがあると、従業員からの信用を失うだけでなく、内容によっては労働基準法違反となる可能性もあります。
本資料では、雇入れ直後・異動直後に焦点を当て、給与計算時のチェックポイントをまとめました。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
この資料では、各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にまとめました。
【異動時も解説!】給与計算のよくあるミスと予防策17選
給与計算で起きやすいミスをシーン別にとりあげ、それぞれの対処方法を具体的なステップに分けて解説します。
ミスを事前に防ぐための予防策も紹介していますので、給与計算の業務フロー見直しにもご活用ください。
モチベーションを高める環境づくり
面談による個別のケアと同時に、異動者が安心して新しい環境に溶け込めるような「環境づくり」も欠かせません。どんなに手厚い面談を行っても、配属先の部署が非協力的であれば、異動者のモチベーションは上がりません。組織全体で新しい仲間を歓迎し、サポートする風土を醸成することが、社員の心理的安全性を確保し、早期の活躍を後押しします。
新しい部署でのスムーズな受け入れ体制(オンボーディング)
異動者が着任する前に、受け入れ部署の準備を整えておくことが重要です。具体的には、業務に必要なPCやアカウントの準備、OJT(On-the-Job Training)を担当する教育係の任命、業務マニュアルの整備などが挙げられます。初日に誰に声をかければ良いかわからない、何をすれば良いかわからないといった状況をなくし、スムーズに業務をスタートできる体制を構築しましょう。
気軽に相談できるメンター制度
業務上の相談相手であるOJT担当者とは別に、精神的なサポート役となる「メンター」を付けることも有効な手段です。メンターには、年齢の近い他部署の先輩社員など、利害関係のない人物が適しています。業務の悩みだけでなく、社内での立ち居振る舞いや人間関係といった些細なことでも気軽に相談できる相手がいることは、異動者の大きな心の支えとなり、孤独感の解消につながります。
部署内のコミュニケーション活性化
特にリモートワークが普及した現代では、意識的にコミュニケーションの機会を創出しないと、異動者は孤立しがちです。毎日の朝礼や週次の定例ミーティングで、異動者が発言する機会を設けたり、チャットツールに業務連絡以外の雑談ができるチャンネルを作成したりするのも良いでしょう。小さな工夫が、部署の一員であるという帰属意識を高め、チームワークの向上にも寄与します。
歓迎の気持ちを表すウェルカムランチ
部署のメンバー全員で歓迎の気持ちを伝えるシンプルな方法として、ウェルカムランチの開催があります。対面でもオンラインでも構いません。仕事以外のリラックスした雰囲気で自己紹介や雑談を交わすことで、お互いの人柄を知り、心理的な距離を縮めるきっかけになります。「部署全体であなたを歓迎している」というメッセージが伝わることで、異動者は安心して新しい環境に飛び込めます。
なぜ異動でモチベーションは低下するのか
効果的な対策を講じるためには、まず異動者がなぜモチベーションを低下させてしまうのか、その根本的な理由を理解しておく必要があります。会社にとっては組織戦略の一環であっても、社員個人にとってはキャリアや生活に大きな影響を与える一大事です。異動者が直面する心理的なハードルを知ることで、より的確で共感的なサポートが可能になります。
新しい仕事やスキルへの不安
特に未経験の職種や部署への異動の場合、「自分に務まるだろうか」「成果を出せなかったらどうしよう」といったパフォーマンスに対する不安がモチベーション低下の大きな要因となります。これまで培ってきたスキルが通用しないかもしれないという恐怖や、新たに多くのことを学ばなければならないというプレッシャーは、本人にとって大きなストレスです。
人間関係の再構築によるストレス
慣れ親しんだ上司や同僚と離れ、新しい環境で再び人間関係をゼロから築き上げることには、多大な精神的エネルギーを要します。「新しい部署に馴染めるだろうか」「周囲とうまくやっていけるだろうか」といった不安は、業務そのものへの集中力を削ぎ、モチベーションを低下させる一因となります。特に、既に人間関係が確立されているチームに一人で加わる場合は、孤独感を感じやすくなります。
キャリアプランとのズレ
社員が自身のキャリアについて明確なビジョンを持っている場合、会社の辞令がそのプランと異なると、強い失望感を抱くことがあります。「このまま専門性を高めていきたかったのに」「将来のために今の部署で経験を積みたかったのに」といった思いは、会社への不信感につながりかねません。自分のキャリアが会社によってコントロールされていると感じ、仕事への主体性や意欲を失ってしまいます。
不透明な評価への懸念
新しい上司や環境で、これまでの実績や努力が正しく評価されるのかという不安も、モチベーションに影響します。特に、成果が出るまでに時間がかかる業務や、評価基準が曖昧な部署への異動の場合、「頑張っても報われないのではないか」という疑念が生じやすくなります。公平な評価が期待できないと感じると、仕事へのコミットメントは自然と低下してしまいます。
異動を成長機会にするための組織的な仕組み
これまでは、モチベーション低下を防ぐ「守り」のケアを中心に解説してきましたが、一歩進んで、人事異動を社員と組織双方の「成長機会」と捉える「攻め」の視点も重要です。場当たり的な異動ではなく、戦略的な人材育成の一環として仕組みを整えることで、異動は社員のキャリアを豊かにし、組織全体の力を底上げする原動力となり得ます。
社員の自律的なキャリア形成の支援
年に一度のキャリア面談などを通じて、社員が自身のキャリアについて考え、会社に意思表示する機会を設けましょう。会社が社員一人ひとりのキャリアプランに関心を持ち、サポートする姿勢を示すことで、社員は主体的にキャリアを考えるようになります。こうした対話の積み重ねが、異動の際のミスマッチを防ぎ、本人の納得感を高める土台となります。
挑戦を後押しする社内公募制度
会社がポストを提示し、希望する社員が自ら応募する「社内公募制度」や「FA(フリーエージェント)制度」は、社員の挑戦意欲を刺激する有効な仕組みです。会社主導の辞令だけでなく、社員の「やってみたい」という気持ちを尊重することで、異動に対する主体性が生まれます。結果として、異動後のモチベーションも高く維持され、潜在的な才能の発掘や組織の活性化にもつながります。
異動経験を評価する人事制度
複数の部署を経験し、多様なスキルや視点を身につけることの価値を、人事制度上で明確に評価することも重要です。例えば、管理職への昇進要件として「複数部署での業務経験」を盛り込むことで、社員は異動をキャリアアップのためのポジティブなステップとして捉えるようになります。会社として「異動経験は貴重な財産である」というメッセージを発信することが、前向きな異動文化を醸成します。
注意すべきモチベーションを削ぐ人事異動
最後に、良かれと思って行った人事異動が、かえって社員のモチベーションを著しく低下させ、離職につながってしまうケースについて解説します。どのような異動が「悪手」となり得るのかを事前に知っておくことで、無用なトラブルを未然に防ぐことができます。社員の信頼を失わないためにも、これから挙げるパターンには細心の注意を払いましょう。
本人の意向を無視した一方的な異動
丁寧な事前説明や対話の機会がなく、決定事項として一方的に辞令を伝えるやり方は、最も避けるべきです。社員は自分を「会社の駒」として扱われたと感じ、深い不信感を抱きます。たとえ組織にとって必要な異動であっても、本人のキャリアや生活への配慮を欠いたコミュニケーションは、エンゲージメントを大きく損ない、最悪の場合、優秀な人材の流出を招きます。
説明が不十分な異動
「なぜ自分が異動しなければならないのか」この問いに会社が明確に答えられない場合、社員の心には不満や憶測が渦巻きます。「何か失敗をしたのだろうか」「左遷なのではないか」といったネガティブな感情は、仕事への意欲を削ぎます。異動の背景、目的、そして本人への期待を具体的に説明することは、会社としての最低限の責務であり、社員の納得感を得るための第一歩です。
育成計画のない「丸投げ」異動
異動させた後のフォローアップや教育体制が全く整っていない「丸投げ」状態も問題です。新しい環境で右も左もわからないまま放置されれば、誰でも孤独感と無力感を覚えます。パフォーマンスを発揮できない状況が続けば、自信を失い、セルフイメージも低下してしまいます。異動は「配置して終わり」ではありません。異動先でのスムーズな立ち上がりを支援する育成計画まで含めて、人事戦略と捉えるべきです。
継続的なモチベーションケアが組織の成長を促す
異動者のモチベーションケアは、一度きりのイベントで終わるものではありません。「効果的な面談」と「環境づくり」を起点とし、社員一人ひとりのキャリアに寄り添う継続的な取り組みが、個人の成長を促し、ひいては組織全体の活力を高めます。異動という変化をポジティブな力に変える仕組みを整え、社員が安心して挑戦できる企業文化を築いていくことが、これからの時代に求められる人事戦略と言えるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労働基準法第20条とは?解雇予告についてわかりやすく解説!
労働基準法第20条は、使用者(会社)が労働者を解雇する際の手続きとして「解雇予告」を義務付けており、人事労務担当者にとって必ず押さえておくべき重要なルールです。 この記事では、労働…
詳しくみる中堅社員が辞めるのはなぜ?退職理由や兆候を理解し、会社の損失を防ぐ対策を解説
企業の成長を支える「中堅社員」が辞めることに、頭を悩ませていませんか?経験とスキルを兼ね備え、組織の中核を担う彼らの離職は、単なる人員減以上の深刻なダメージを会社に与えます。 この…
詳しくみるホワイトカラーとは?意味やブルーカラーとの違い
ホワイトカラーとは、事務職や専門職に就く、オフィスでデスクワークを中心とした仕事をする労働者を意味する用語です。対義語として工場や現場で働くブルーカラーがあります。 ここでは、ホワ…
詳しくみる派遣社員も福利厚生は受けられる!派遣会社別の制度内容や活用方法を解説
「派遣社員として働くと、福利厚生が受けられないのではないか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。しかし実際には、派遣社員でも条件を満たせば社会保険、有給休暇、教育支援など、…
詳しくみる深夜業従事者向けの健康診断は年2回必要?実施基準や義務を解説
深夜業は生活リズムが乱れやすく、健康リスクが高まる恐れがあるため、年2回の健康診断が義務付けられています。本記事では、深夜業従事者に該当する人の基準や必要な検査項目について解説しま…
詳しくみるSDGsとは?17の目標や事例を簡単に解説!
SDGsとは、2015年に国連で採択され、2030年までの達成を目指す17の目標が掲げられた「持続可能な開発目標」のことです。貧困や教育、気候変動など広範な課題の解決に向け、持続可…
詳しくみる