- 更新日 : 2025年11月5日
福利厚生とは?法定・法定外の種類から具体例、導入時の注意点まで徹底解説
「従業員のために、もっと何かできないか」。その想いを形にするのが福利厚生です。本記事では、制度の基本や種類、メリット・デメリットから、導入・運用の注意点までを網羅的に解説しました。自社に合った制度設計で、働きがいのある環境づくりを始めましょう。
目次
企業の福利厚生とはどのような制度?
福利厚生とは、企業が従業員の経済的な安定や健康の維持、自己成長などを支援するために提供する、給与以外のさまざまなサービスや制度を指します。これらは従業員のエンゲージメント向上を目指すものであり、多くの調査で企業の生産性との関連性が示唆されています。
従業員の生活安定と仕事への意欲向上が目的
福利厚生の根本的な目的は、従業員が生活の不安を感じることなく、健康で意欲的に仕事に取り組める環境を提供することにあります。例えば、住宅手当で住居の負担を軽減したり、育児支援制度で仕事と家庭の両立をサポートしたりすることで、従業員は安心して業務に集中できます。結果として、これは従業員の満足度や企業への帰属意識(エンゲージメント)を高めることに直結します。
企業が負担する費用は「福利厚生費」
福利厚生費とは、福利厚生を提供するために企業が支出する費用のことです。会計上、福利厚生費は経費として計上できます。ただし、福利厚生費として税務上取り扱われるには、「全従業員を一律に対象とする」「社会通念上妥当な金額・内容である」「現金による支給でない」ことなどが必要です。一方で、役員だけに限定した給付や、現金・商品券など換金性の高いものは、給与や交際費として扱われ課税対象となる場合があるため注意が必要です(国税庁 No.5261等参照)。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
エンゲージメント向上につながる福利厚生16選
多くの企業で優秀な人材の確保と定着が課題となっており、福利厚生の見直しを図るケースが増えてきています。
本資料では、福利厚生の基礎知識に加え、従業員のエンゲージメント向上に役立つユニークな福利厚生を紹介します。
令和に選ばれる福利厚生とは
本資料では、令和に選ばれている福利厚生制度とその理由を解説しております。
今1番選ばれている福利厚生制度が知りたいという方は必見です!
福利厚生 就業規則 記載例(一般的な就業規則付き)
福利厚生に関する就業規則の記載例資料です。 本資料には、一般的な就業規則も付属しております。
ダウンロード後、貴社の就業規則作成や見直しの参考としてご活用ください。
従業員の見えない不満や本音を可視化し、従業員エンゲージメントを向上させる方法
従業員エンゲージメントを向上させるためには、従業員の状態把握が重要です。
本資料では、状態把握におけるサーベイの重要性をご紹介いたします。
福利厚生にはどのような種類がある?
福利厚生は、法律によって企業に提供が義務付けられている「法定福利厚生」と、企業が任意で独自に設ける「法定外福利厚生」の2つに大きく分類されます。
法定福利厚生は法律で義務付けられた6つの制度
法定福利厚生とは、法律で企業に従業員への提供が義務付けられている福利厚生のことです。実務上、主に以下の6種類で説明されることが一般的です。ただし6つと定義した単一の法律があるわけではなく、それぞれが個別の法律に基づいています。
- 健康保険:従業員やその家族が病気や怪我をした際の医療費を補助する制度
- 介護保険:被保険者は「65歳以上の方(第1号被保険者)」と「40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)」に分かれる。企業が保険料の半額を負担するのは第2号被保険者で、その保険料は健康保険料と一体で徴収される。
- 厚生年金保険:従業員の老齢や障害、死亡などに対して年金や一時金が給付される制度。
- 雇用保険:従業員が失業した場合や育児・介護で休業した場合に給付金を受けられる制度。
- 労災保険(労働者災害補償保険):業務中や通勤中に起きた事故による怪我、病気、死亡などに対して保険給付を行う制度。
- 子ども・子育て拠出金:児童手当や子育て支援事業の財源となるもので、厚生年金保険の加入事業主が全額負担。
法定外福利厚生は企業が独自に設定する魅力的な制度
法定外福利厚生とは、法律上の義務はなく、企業が従業員満足度の向上や人材確保などを目的に、任意で導入する制度のことです。企業理念や従業員のニーズに合わせて多種多様な制度があり、企業の個性をアピールする重要な要素となります。
【具体例】福利厚生にはどのようなものがある?
法定外福利厚生には決まった形がなく、時代や従業員のニーズに合わせて様々なものが存在します。ここでは、一般的な福利厚生制度をカテゴリー別に紹介します。
健康・医療に関する福利厚生の例
従業員の健康維持をサポートする制度です。生産性向上への貢献が期待されるため、多くの企業で導入されています。
- 人間ドック・各種健診の費用補助:法定の健康診断に加えて、より詳細な検査の費用を補助。
- フィットネスクラブ・スポーツジムの利用料補助:従業員の運動習慣を支援。
- インフルエンザ予防接種の費用補助:感染症の蔓延を防ぐ。
- メンタルヘルス相談窓口の設置:ストレスチェックやカウンセリングを提供。
住宅に関する福利厚生の例
生活の基盤である住宅に関する補助です。特に、若手従業員や地方出身者にとって魅力的な制度です。
- 住宅手当(家賃補助):従業員が支払う家賃の一部を補助。
- 社宅・独身寮の提供: 相場より安価な家賃で住居を提供。
- 住宅ローン補助:従業員の持ち家取得を支援。
- 引越し費用の補助:転勤や入社に伴う引越し費用を補助。
育児・介護支援に関する福利厚生の例
仕事と家庭の両立を支援する制度です。多様な人材が活躍できる環境づくりに不可欠だといえるでしょう。
- 短時間勤務制度:法定を超える柔軟な時短勤務を可能に。
- 企業内保育所の設置・保育料補助:子育て中の従業員の負担を軽減。
- ベビーシッター利用補助:国の補助制度(こども家庭庁の割引券など)と連携する企業も。
- 介護休業・休暇制度:法定を超える日数の休暇や給付金を提供。
慶弔・災害に関する福利厚生の例
従業員のライフイベントや万が一の事態に寄り添う制度です。企業と従業員の信頼関係を深め、安心して長く働ける職場づくりに繋がります。
- 結婚・出産祝い金:従業員の結婚や出産を祝福。
- 傷病見舞金:病気や怪我で長期療養する従業員を支援。
- 災害見舞金:地震や水害などで被災した従業員を支援。
- 弔慰金:従業員やその家族が亡くなった際に支給。
自己啓発・スキルアップに関する福利厚生の例
従業員の自発的な学習やスキル向上を後押しする制度です。個人の成長が組織全体の競争力向上に直結し、企業の持続的な発展を支えます。
- 資格取得支援制度:受験料や研修費用を補助。
- 書籍購入費用の補助:業務に関連する書籍の購入をサポート。
- セミナー・研修参加費用の補助:社外の学びの機会を提供。
- eラーニングの導入:いつでもどこでも学べる環境を提供。
休暇に関する福利厚生の例
福利厚生における休暇制度は、法律で定められた「年次有給休暇」とは別に、企業が任意で設ける「特別休暇(法定外休暇)」を指します。これは従業員のエンゲージメントやリフレッシュを目的としたもので、企業独自の様々な休暇があります。
- リフレッシュ休暇:勤続年数が一定に達した従業員に対して、心身のリフレッシュを目的に付与される長期休暇。
- アニバーサリー休暇:従業員本人や家族の誕生日、結婚記念日などに取得できる休暇。
- ボランティア休暇:従業員が社会貢献活動に参加する際に取得できる休暇。
- シックリーブ:病気や怪我をした際に、年次有給休暇とは別に取得できる休暇制度。
近年のトレンドとなっている福利厚生の例
一般的な制度に加えて、近年はそれらをさらに進化させた、より戦略的な福利厚生に注目が集まっています。
- 自己成長支援の「海外・最先端への拡張」:従来のセミナー参加費補助などに加え、国内外の先進的なカンファレンスへの参加費・渡航費までを支援し、グローバルな視点を持つ人材を育成。
- 資産形成サポートの「インセンティブ強化」:一般的な従業員持株会に、会社が拠出金に対して奨励金を上乗せするインセンティブを加え、従業員のエンゲージメントと資産形成意欲を同時に高める。
- 休暇制度の「パーソナライズ化」:全社一律の夏休みなどだけでなく、個人の記念日に取得できるアニバーサリー休暇を導入するなど、従業員一人ひとりの事情に合わせた柔軟な休み方を支援。
- 両立支援の「法定基準超え」:法律で定められた基準を上回る日数の育児・介護休暇や、より柔軟な短時間勤務制度を設けることで、多様な人材が安心して長く働ける環境を積極的に構築。
これらの制度は、目先の満足度だけでなく、従業員と企業が未来に向かって共に成長していくための、重要な戦略的投資といえるでしょう。
その他の一般的な福利厚生の例
上記の他にも、日々の業務やプライベートでの生活を豊かにする、多様な支援制度があります。社内のコミュニケーションを活性化させ、働きがいのある職場風土の形成に繋がるでしょう。
- 食事関連:社員食堂の設置、食事代補助、オフィスコンビニの設置など
- 財産形成関連:財形貯蓄制度、従業員持株会、企業型確定拠出年金(企業型DC)など
- その他:社員旅行、部活動・サークル活動の補助、レジャー施設の割引利用など
福利厚生を充実させるメリットとは?
福利厚生の充実は、従業員という最も重要な経営資源への投資であり、組織全体の活性化を通じて企業の持続的な成長を支える重要な経営戦略です。以下、具体的なメリットを紹介します。
従業員満足度とエンゲージメントの向上
魅力的な福利厚生は、従業員が「会社から大切にされている」と感じるきっかけとなり、仕事への満足度や貢献意欲(エンゲージメント)を高めます。これにより、生産性の向上やサービスの質の向上が期待できます。
人材の採用競争力強化
求職者は給与だけでなく、働きやすさや企業の姿勢を示す福利厚生も重視しています。特に法定外福利厚生が充実している企業は、他社との差別化を図ることができ、優秀な人材にとって魅力的な選択肢となるでしょう。
従業員の健康増進と生産性の向上
従業員の心身の健康をサポートすることは、組織全体の生産性向上に繋がります。健康診断の補助やフィットネスジムの割引などは、従業員の健康維持を支援し、病気による休職や労働能力の低下(プレゼンティーズム)の軽減が期待されます。
従業員の定着率向上と離職率低下
従業員の生活を支え、働きやすい環境を提供することで、離職率の低下に繋がります。特に、育児や介護といったライフステージの変化に対応できる制度は、長期的な人材定着に大きく貢献するでしょう。
社内コミュニケーションの活性化
社員旅行や社内イベントといった福利厚生は、部署や役職の垣根を越えた、従業員同士の繋がりを深めるきっかけになります。こうした業務外のコミュニケーションが、風通しの良い職場環境をつくり、チームワークの向上や新しいアイデアが生まれる土台となるのです。
企業のブランドイメージ向上
従業員を大切にする企業姿勢は、社外からの評価にも影響します。充実した福利厚生は、健康経営を目指す包括的な取り組みの一環として「健康経営優良法人(経済産業省が制度を設計し、日本健康会議が認定)」といった企業の社会的価値向上に貢献します。
企業の社会的責任(CSR・ESG)への貢献
従業員のウェルビーイングを重視する福利厚生への投資は、企業の社会的責任(CSR)を果たす上で重要な要素です。近年注目されるESG(環境・社会・ガバナンス)経営の観点からも、従業員への配慮(Social)は、投資家や社会から企業価値を評価される上での重要な指標となります。
税制上の優遇措置
税務上の要件を適切に満たした福利厚生費は、経費(損金)として計上することが可能です。黒字経営の企業であれば、これにより実質的に法人税の負担を軽減する効果が生まれます。給与や交際費と区別して正しく運用することで、税制上のメリットが期待できます。
福利厚生を導入するデメリットとは?
計画的な制度設計を行わないと、かけたコストや手間に見合う満足度が得られず、一部の従業員しか利用しない形骸化した制度になる可能性があります。以下のデメリットを理解した上で、慎重に制度設計を行いましょう。
制度導入・運用にコストがかかる
福利厚生の導入には、直接的な費用(補助金など)だけでなく、管理部門の人件費といった間接的なコストも発生します。企業の経営状況を圧迫しないよう、費用対効果を十分に検討する必要があります。
全ての従業員のニーズを満たすのは難しい
従業員の年齢層やライフスタイルが多様化する中で、全ての人が満足する福利厚生を提供することは困難です。一部の従業員しか利用しない制度は、他の従業員から不公平感を持たれる原因にもなり得ます。
管理・運用の手間が増える
新たな福利厚生制度を導入すると、その手続きや問い合わせ対応、利用状況の管理など、人事労務担当者の業務負担が増加します。外部のアウトソーシングサービスなどを活用することも一つの解決策です。
給与アップと福利厚生、従業員満足度を高めるのはどちら?
従業員の処遇改善は、給与アップと福利厚生をバランス良く組み合わせるのが最も効果的です。安定した生活基盤は給与で保障し、プラスアルファの働きがいや企業文化を福利厚生で提供する、という考え方が重要になります。
給与アップは、従業員にとって最も分かりやすく満足度に直結しますが、税負担が増え、効果が短期的に終わりやすい側面があります。
一方、福利厚生の充実は、企業の姿勢を伝え、非課税の恩恵も期待できる反面、全従業員のニーズを満たすのが難しいという特徴があります。
福利厚生の提供方法にはどのような選択肢がある?
福利厚生制度の提供方法には、大きく分けて「自社で直接提供する方法」と「福利厚生の代行サービスを利用する方法」の2つがあります。目的や内容が決まったら、それぞれを比較して「どうやって従業員に提供するか」を検討しましょう。
1. 自社で直接提供
自社で提供する方法とは、企業の人事部などが独自に福利厚生の企画から運用までをすべて担う形態です。例えば、社員食堂の運営、特定のジムとの法人契約、住宅手当や家賃補助制度の設計・管理などがこれにあたります。
メリット
- 企業文化の反映:企業理念や経営方針を色濃く反映した、オリジナリティの高い制度を設計できる。
- 柔軟な制度設計:従業員の意見や要望を直接ヒアリングし、制度内容を柔軟に、かつスピーディに変更・改善しやすい。
- コストコントロール:提供するサービスを限定的にすれば、代行サービスよりも費用を抑えられる可能性がある。
デメリット
- 担当者の負担増:制度のリサーチ、業者選定、契約、日々の運用管理など、人事担当者の業務負担が大きくなる。
- サービスの限定:提供できるサービスが、担当者の知識やマンパワーに依存するため、内容が画一的・限定的になる可能性がある。
- 不公平感の発生:全国に支社がある場合、本社と地方で利用できるサービスに格差が生まれ、不公平感を生む原因になることがある。
2. 福利厚生代行サービス(アウトソーシング)を利用
福利厚生代行サービスとは、専門の外部企業に委託して、包括的な福利厚生プログラムを従業員に提供する方法です。代表的なサービスには、以下のような形態があります。
パッケージプラン
従業員が自由に割引価格などで利用できるプラン。あらかじめ提供会社が複数のサービスをパッケージ化していることが特徴。提供されるメニュー数は事業者により大きく異なり、数十万件以上の豊富なサービスを提供する大規模なプランも。
カフェテリアプラン
企業が従業員に一定のポイント(補助金)を付与し、従業員はそのポイントの範囲内で、用意されたメニューの中から自分に必要な福利厚生サービスを自由に選んで利用できるプラン。注意点として、ポイントを利用する場合でも、商品券など換金性の高いものは給与として課税される可能性があるため、制度設計には事前の確認が必要。
メリット・デメリット
メリット
- 豊富なサービス内容:従業員は年齢やライフスタイルに関わらず、多種多様なメニューから自分に合ったサービスを選べるため、満足度が高まりやすい。
- 担当者の負担軽減:サービスの選定や管理、問い合わせ対応などを代行会社に一任できるため、人事担当者はコア業務に集中できる。
- 公平性の担保:全国どこに住んでいても均一のサービスを受けられるため、従業員間の公平性を保ちやすい。
- スケールメリット:代行会社が多数の法人と契約しているため、個別に契約するよりも割安な料金でサービスを利用できる。
デメリット
- コストの発生:従業員数に応じた月額費用や年会費が発生する。利用率が低い場合でも固定費が発生するため、費用対効果の検証が必要。
- 独自性の欠如:提供されるサービスはパッケージ化されているため、自社ならではのユニークな制度を導入しにくい側面がある。
- 利用率の課題:導入しても従業員に周知されなければ利用されず、コストだけがかかる状態になり得る。積極的な利用促進が不可欠。
福利厚生制度を導入・見直しする際に注意するべきことは?
効果的な福利厚生制度を構築するためには、計画的な導入プロセスが不可欠です。以下のステップを参考に、自社に合った制度を検討しましょう。
ステップ1. 導入目的を明確にする
まず「なぜ福利厚生を導入するのか」という目的を明確にします。「若手人材の定着率を上げたい」「女性従業員の活躍を推進したい」「従業員の健康意識を高めたい」など、具体的な経営課題と結びつけることが重要です。
ステップ2. 従業員のニーズを把握する
目的を達成するためには、従業員が実際に何を求めているかを知る必要があります。アンケート調査やヒアリングを実施し、年齢層、性別、職種ごとのニーズを分析しましょう。
ステップ3. 公平性と利用しやすさを考慮する
制度設計においては、できるだけ多くの従業員が公平に利用できることが望ましいです。特定の従業員だけが恩恵を受ける制度にならないよう配慮し、利用手続きが煩雑にならないような工夫も求められます。
ステップ4. 費用対効果を検証する
導入にかかるコストと、それによって得られるメリット(離職率低下による採用コスト削減、生産性向上など)を予測し、費用対効果を検証します。スモールスタートで試行し、効果を見ながら拡大していく方法も有効です。
ステップ5. 導入後の周知と定期的な見直しを行う
せっかく制度を導入しても、従業員に知られていなければ意味がありません。社内報やイントラネットなどを活用して積極的に周知しましょう。また、導入後も定期的に利用状況を分析し、従業員のニーズの変化に合わせて制度内容を見直していくことが大切です。
アルバイトや個人事業主の福利厚生はどうなる?
アルバイトやパートタイマーは一定の要件下で福利厚生の対象となりますが、個人事業主自身は原則として対象外となるなど、働き方によって扱いが異なります。正社員以外の働き方における福利厚生についても理解しておきましょう。
アルバイト・パートタイマーの福利厚生
アルバイトやパートタイマーであっても、労働時間や日数などの要件を満たせば、健康保険や厚生年金保険、雇用保険といった法定福利厚生(社会保険)の加入対象となります。法定外福利厚生については企業の任意ですが「同一労働同一賃金」の原則(不合理な待遇差の禁止)に基づき、正社員との間に待遇差を設ける場合には、その性質や目的に照らして合理的かどうかが個別に判断されます。
個人事業主の福利厚生
福利厚生は、基本的に企業がその従業員に対して提供するものであるため、個人事業主自身は対象外です。ただし、個人事業主が従業員を雇用した場合は、その従業員に対して法定福利厚生を提供する義務が生じます。個人事業主自身が利用できる制度としては、国民年金や国民健康保険のほか、退職金制度の代わりとなる小規模企業共済などがあります。
自社に合った福利厚生で従業員と企業が共に成長する環境づくりを
本記事では「福利厚生とは何か」という基本的な問いからその種類、メリット・デメリット、具体例、導入の際の注意点までを詳しく解説しました。福利厚生は、単なるコストではなく、企業の持続的な成長を支える重要な経営戦略です。従業員のニーズを的確に捉え、自社の理念や経営課題に合った福利厚生制度を構築・運用することで、従業員満足度を高め、変化の激しい時代を勝ち抜く強い組織を作ることができるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
異動挨拶のメールやお礼のスピーチの内容は?社内外の例文をもとに解説
異動の挨拶は、社内の立ち位置を明確にし、スムーズな人間関係を築いていくために重要なステップです。この記事では、異動の挨拶の目的や基本的なマナー、メールやお礼のスピーチの例文などを解…
詳しくみる育休は勤続年数に含まれる?有給や退職金、賞与への影響などを解説
育児休業(以下、育休)を取得する際、多くの方が気になるのが「勤続年数」の扱いです。勤続年数は、昇進昇格、退職金、年次有給休暇の付与日数など、様々な労働条件に影響を与えるため、その正…
詳しくみるシンパシーとは?エンパシーとの違いやビジネスでの活用例
シンパシーとは、相手と同じ感情・気持ちになることを指す言葉で、よく「シンパシーを感じる」と用いられます。エンパシーもシンパシーと同じ意味の共感や共鳴を指す言葉ですが、シンパシーはネ…
詳しくみる雇用契約書とは?法的な必要性や項目、作り方をひな形付きで紹介
雇用契約書とは、企業と労働者の合意を証明し、トラブルを防ぐための重要な書類です。2024年4月からは就業場所や業務の「変更の範囲」の明示が義務化されるなど、最新の法改正への対応が不…
詳しくみる懲戒処分とは?受けるとどうなる?種類や進め方、転職への影響を解説【通知書テンプレつき】
従業員が職場の規律を破り秩序を乱すような行為をした際、ときには会社はその従業員に対して懲戒処分をせざるを得ないこともあるでしょう。ただし、懲戒処分は、法律や就業規則に従って適切な取…
詳しくみる人的資本経営の開示項目とは?情報開示の19項目や具体例を解説
人的資本経営の情報開示は、企業の競争力向上のために重要です。 2023年から上場企業等には開示義務が課されており、とくに「7分野19項目」に基づく情報開示が求められています。本記事…
詳しくみる
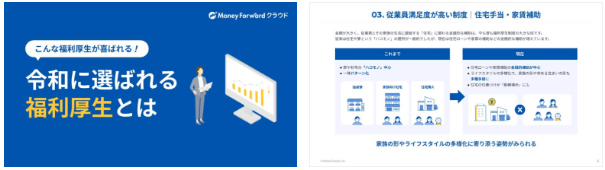
.jpg)
