- 更新日 : 2025年9月26日
退職金制度の種類とは?税制優遇や制度選びのポイント
退職金制度は、従業員の長期的な活躍を支え、企業の魅力向上にもつながる大切な仕組みです。しかし、退職金制度は、種類によって税金の扱いや将来の受取額が大きく異なります。自社に最適な制度を選ぶには、それぞれの仕組みを正しく理解することが欠かせません。
この記事では、退職金制度の代表的な4つの種類について、それぞれの仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説します。中小企業に適した制度や、自社に合った制度を選ぶための視点も紹介しますので、ぜひ制度設計の参考にしてください。
目次
退職金制度の主な4つの種類
退職金制度は、企業が直接管理・支給する「退職一時金制度」と、外部機関も活用しながら資産を形成する「企業年金制度」に大別されます。結論として、これらはさらに給付額が確定しているか(DB)、拠出額が確定しているか(企業型DC・退職金共済)によって分類でき、それぞれに特徴があります。ここでは、代表的な4つの種類について、その仕組みと違いを解説します。
1. 退職一時金制度
退職一時金制度とは、企業の利益などから将来の支払いに備えて資金を準備し、退職時に一括で支払う、古くから多くの企業で採用されてきた制度です。税制面では「退職所得控除」が適用され、たとえば勤続35年の場合、控除額が1,850万円になるため、退職金がその範囲内であれば所得税・住民税はかかりません。それ以上の場合は超過分に対して課税されます。
2. 確定給付企業年金制度(DB)
確定給付企業年金制度(DB)とは、将来の給付額が企業の規約によって約束されている制度です。掛金は企業が全額負担し、外部の金融機関で管理・運用するため、従業員は安定した将来設計ができます。受け取りは年金が基本ですが、一時金として受け取る選択も可能で、その場合、税負担が軽減される退職所得控除を適用できます。
3. 企業型確定拠出年金制度(DC)
企業型確定拠出年金制度(DC)とは、企業が拠出する掛金を従業員自身が運用し、その成果で受取額が変わる制度です。最大の税制メリットは、運用期間中の利益がすべて非課税になる点です。通常、投資の利益には約20%の税金がかかりますが、この制度内では非課税のため、複利効果を最大限に活かした資産形成が期待できます。
4. 退職金共済制度(中退共など)
退職金共済制度(中退共など)とは、国の機関などが運営する社外積立型の制度で、とくに中小企業が導入しやすい仕組みです。掛金は企業が負担し、税法上その全額を損金として扱えるため、企業の法人税負担を軽減する効果があります。従業員は、会社の経営状況とは別に資産が保全される安心感があり、退職所得控除の対象となる一時金として受け取ります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
エンゲージメント向上につながる福利厚生16選
多くの企業で優秀な人材の確保と定着が課題となっており、福利厚生の見直しを図るケースが増えてきています。
本資料では、福利厚生の基礎知識に加え、従業員のエンゲージメント向上に役立つユニークな福利厚生を紹介します。
令和に選ばれる福利厚生とは
本資料では、令和に選ばれている福利厚生制度とその理由を解説しております。
今1番選ばれている福利厚生制度が知りたいという方は必見です!
福利厚生 就業規則 記載例(一般的な就業規則付き)
福利厚生に関する就業規則の記載例資料です。 本資料には、一般的な就業規則も付属しております。
ダウンロード後、貴社の就業規則作成や見直しの参考としてご活用ください。
従業員の見えない不満や本音を可視化し、従業員エンゲージメントを向上させる方法
従業員エンゲージメントを向上させるためには、従業員の状態把握が重要です。
本資料では、状態把握におけるサーベイの重要性をご紹介いたします。
退職一時金という種類の退職金制度
退職一時金制度とは、企業が自社で資金を積み立て、従業員の退職時にまとめて支給する従来型の制度です。企業にとっては制度設計の自由度が高く、従業員にとっては「退職所得控除」による税負担の軽減が大きなメリットです。
社内で資金を積み立てるシンプルな仕組み
退職一時金制度の原資は、企業の内部留保によって準備されます。特別な金融商品を必ずしも利用する必要はなく、自社の資金計画の中で積み立てていくことが可能です。支給額の計算方法は、退職時の基本給に勤続年数に応じた支給率をかける「最終給与比例方式」や、役職や等級に応じたポイントを積み上げる「ポイント制」など、企業が自由に設計できます。
メリットは制度設計の自由度の高さ
この制度の大きなメリットは、法律による厳しい規制が少なく、企業の実情に合わせて柔軟に制度を設計できる点です。たとえば、勤続年数が長い従業員を手厚く遇する設計や、企業業績への貢献度を反映させる設計もできます。また、外部機関への手数料などが発生しないため、管理コストを抑えやすい側面もあります。
また、従業員にとっては、「退職所得控除」という仕組みによって税負担が軽減され手取り額が多くなる点が最大のメリットです。
退職所得控除の計算
控除額は勤続年数に応じて、以下のように計算されます。
- 勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円)
- 勤続20年超: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)
課税所得の計算と具体例
退職金から上記の控除額を差し引き、さらに残額を半分にした金額が課税対象となります。
- (退職金額 – 退職所得控除額) × 1/2
たとえば、勤続35年で1,600万円の退職金を受け取る場合を考えてみましょう。控除額は「800万円 +70万円 × 15年」で計算され、合計1,850万円となります。 この控除額が退職金額を上回るため、課税所得は0円となり、結果として所得税・住民税はかかりません。
デメリットは将来の財務負担
一方で、退職金の支払いが将来に集中した場合、企業の資金繰りを圧迫する可能性があります。とくに、定年退職者が一度に複数発生する時期には、多額の資金が必要になるでしょう。また、将来の支払いに備えた計画的な資金確保が経営上の課題となります。
確定給付企業年金(DB)という種類の退職金制度
確定給付企業年金(DB)は、従業員が将来受けとる給付額をあらかじめ約束する制度です。従業員にとっては将来設計がしやすい安心感がありますが、企業側には約束した給付額を支払うための運用責任が伴います。
将来の受取額が約束されている
DB制度では、規約に基づいて「勤続◯年ならいくら」というように、将来の給付額が保証されています。掛金は企業が全額を負担し、信託会社や生命保険会社といった外部の金融機関に預けて運用・管理されます。
従業員が受け取る給付額は、企業の規約で定められた計算式(給与や勤続年数に基づくなど)によって決まっており、その約束された額を支払えるように企業が運用責任を負います。もし運用実績が予定を下回った場合、企業は不足分を穴埋めする責任を負います。
従業員にとってのメリットは生活設計のしやすさ
従業員から見ると、自分で運用を行う必要がなく、退職後の受取額が決まっているため、安定した生活設計を立てやすいのが大きなメリットです。市場の変動リスクを個人で負うことがないため、安心感につながるでしょう。
また、受け取り方として「年金」だけでなく「一時金」を選択することも可能で、一時金で受け取る場合は税負担が軽減される「退職所得控除」を適用できます。
企業にとってのデメリットは運用リスクとコスト
一方で、企業は資産運用の責任をすべて負います。予定していた利回りを下回るなど運用実績が悪化した場合、約束した給付額を支払うために不足分を企業が追加で拠出しなければならないリスクがあります。また、制度を運営するための外部機関への手数料といった管理コストも継続的に発生します。
企業型確定拠出年金(DC)という種類の退職金制度
企業型確定拠出年金(DC)とは、企業が毎月一定の掛金を拠出し、その資金を従業員自身が運用する制度です。企業にとっては将来の追加負担リスクがなく、従業員にとっては大きな税制優遇を受けながら運用次第で資産を増やせる可能性がある点が特徴です。(元本割れのリスクもあるため注意が必要)
企業が掛金を拠出し、従業員が運用する
DC制度では、企業は毎月一定の掛金を従業員ごとの口座に拠出します。従業員は、企業が提示する複数の金融商品(投資信託、保険商品、定期預金など)の中から、自分の判断で運用先を選びます。将来の受取額は、この運用成績次第で増えたり減ったりします。原則として60歳まで引き出すことはできません。
企業のメリットは掛金負担が一定で運用リスクがないこと
企業側の大きなメリットは、毎月の掛金負担額が確定しており、将来の追加負担が発生しない点です。DB制度のように、運用実績が悪化した際に不足分を補う必要がありません。そのため、退職給付に関する将来の財務的な見通しが立てやすくなります。
従業員のメリットは運用次第で受取額が増えること
従業員は、自身の運用がうまくいけば、将来の受取額を大きく増やせる可能性があります。また、転職する際には、年金資産を次の会社のDC制度や個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換できる「ポータビリティ」があるため、キャリアの柔軟性を損ないません。ただし、運用結果によっては元本割れするリスクがある点は理解しておく必要があります。
また、資産形成の各段階で手厚い税制優遇が受けられます。
- 拠出時: 企業が拠出する掛金は、従業員の所得として課税されません。
- 運用時: 通常、投資で得た利益(運用益)には約20%の税金がかかりますが、DCの口座内ではこれがすべて非課税になります。これにより、複利効果を最大限に活かせます。
- 受取時: 一時金で受け取る場合は「退職所得控除」、年金で受け取る場合は「公的年金等控除」が適用され、税負担が軽減されます。
デメリットは従業員の投資リスク
資産運用の成果によって受取額が変動するため、そのリスクはすべて従業員自身が負うことになります。運用がうまくいかなかった場合、将来の受取額が拠出した掛金の総額を下回る「元本割れ」の可能性もあります。そのため、企業には従業員に対する継続的な投資教育の機会を提供することが求められます。
退職金共済という種類の退職金制度
退職金共済制度とは、国の機関などが運営する、とくに中小企業が導入しやすい社外積立型の制度です。企業にとっては管理が手軽で掛金が全額損金扱いになる点、従業員にとっては会社の経営状況から独立して資産が保全される安心感が特徴です。
社外機関に掛金を積み立てる仕組み
代表的な「中小企業退職金共済(中退共)」を例にすると、企業は従業員ごとに掛金月額(5,000円〜30,000円)を選択し、中退共へ毎月納付します。掛金は企業が全額を負担し、従業員の給与から天引きされるものではありません。従業員が退職した際は、中退共から直接、退職金が支払われます。
中小企業退職金共済(中退共)
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する、国の退職金制度です。事業主が中退共と契約し、従業員ごとに掛金を納付します。従業員が退職した際は、中退共から直接、従業員に退職金が支払われます。
- 掛金の一部を国が助成: 新規加入時や掛金増額時に、国からの助成を受けられます。
- 管理が手軽: 掛金の納付は口座振替で行え、個別の資産運用の必要もありません。
- 税制上の優遇: 納付した掛金は、法人税法上、全額損金として算入できます。
特定退職金共済(特退共)
商工会議所や商工会などが、地域の税務署長の承認を得て運営する制度です。基本的な仕組みは中退共と似ていますが、運営主体が異なります。こちらも掛金は全額損金に算入できるなど、税制上のメリットがあります。加入できる従業員の資格などは、各団体によって定められています。
メリットは中小企業の導入しやすさ
企業にとっては、国の制度である安心感と、掛金が全額損金に算入できる税制上のメリットがあります。また、新規加入時には国からの助成も受けられます。従業員にとっては、万が一会社が倒産した場合でも、それまでに積み立てられた資産は全額保全されるため、確実に退職金を受け取れる点が大きなメリットです。受け取りは原則として一時金で、「退職所得控除」が適用されます。
デメリットは制度設計の自由度の低さ
一方で、掛金の額はあらかじめ決められた選択肢の中から選ぶため、従業員個人の役職や会社への貢献度などを給付額に細かく反映させるような、企業独自の実情に合わせた柔軟な制度設計はできません。
自社に最適な退職金制度の種類の選び方
ここまで解説したように、退職金制度にはそれぞれ異なる特徴があります。どの制度が自社にとって最適かを見極めるためには、「企業の状況」「従業員のニーズ」「経営方針」という3つの視点から総合的に検討することが大切です。
企業の規模や体力で考える
企業の財務状況は、制度選択における最も基本的な判断基準となります。
- 財務に余裕があり、運用リスクもとれる企業:
DB制度を導入し、手厚い福利厚生で人材を確保するという選択肢があります。 - 将来の財務負担を確定させたい企業:
DC制度や退職金共済制度が適しています。とくにDC制度は、拠出額が一定のため、将来のコスト管理が容易です。 - まずは着実に始めたい中小企業:
国の助成もある中退共などの退職金共済制度が、導入のハードルが低くおすすめです。
従業員のニーズや年齢構成で考える
どのような従業員に長く働いてほしいか、という視点も大切です。
- 若手従業員が多い企業:
転職時のポータビリティがあり、自ら資産形成に関与できるDC制度への関心が高い傾向があります。 - 安定志向の従業員や中高年層が多い企業:
将来の受取額が確定しているDB制度や退職一時金制度は、安心感につながります。
退職金制度の種類を導入・変更する際の注意点
新しい退職金制度を導入したり、既存の制度を見直したりする際には、法的な手続きや従業員への配慮が必要です。スムーズに進めるために、いくつかの注意点を押さえておきましょう。
就業規則(退職金規程)を整備する
退職金制度を設ける場合は、その内容を就業規則に明記する義務があります。支給対象者、計算方法、支払時期などを定めた「退職金規程」を別途作成し、就業規則に「退職金は退職金規程による」と記載するのが一般的です。作成・変更した際は、労働基準監督署への届出を忘れないようにしましょう。
従業員に丁寧な説明をする
とくに既存の制度を変更する場合、従業員にとって不利益な変更にならないよう、慎重な手続きが求められます。制度変更の理由や新しい制度の内容について、説明会を開くなどして従業員の理解と同意を得ることが、後のトラブルを防ぐ上でとても大切です。とくにDC制度を導入する場合は、従業員が適切な運用判断を行えるよう、継続的な投資教育の機会を提供することが企業の責任として期待されます。
不利益変更にあたる場合の注意点
既存の制度を見直す際、単に支給額を引き下げる、支給率を悪化させるといった変更は「不利益変更」と見なされ、原則として企業が一方的に行うことはできません。このような変更を行うには、従業員一人ひとりから個別の同意を得るのが基本となります。
就業規則の変更によって対応する手法もありますが、変更に合理的な理由があり、周知が徹底されているなど、法的に高いハードルが課されるため、慎重な対応が求められます。
専門家への相談とパートナーの選定
退職金制度の設計は、労働法、税法、資産運用など専門的な知識を要するため、専門家の協力が欠かせません。規程の作成や法的手続きについては社会保険労務士、税務上の取り扱いや企業の損金計上については税理士に相談するのが一般的です。
また、DBやDC制度を導入する場合は、制度を管理・運用する金融機関の選定も、長期的に安定した制度運営を行う上で重要なポイントとなります。
多様な退職金制度の種類を理解し自社に合った選択を
この記事では、退職金制度の代表的な4つの種類として、「退職一時金制度」「確定給付企業年金(DB)」「企業型確定拠出年金(DC)」「退職金共済制度」について解説しました。それぞれに異なるメリット・デメリットがあり、企業の体力や人材戦略によって最適な制度は異なります。
退職金制度の選択は、従業員のモチベーションや定着率、ひいては企業の持続的な成長にも関わる重要な経営判断です。今回紹介した比較表や選び方の視点を参考に、ぜひ自社にとって最良の退職金制度をご検討ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
仕事が遅いと言われるのはパワハラ?パワハラに該当するケースや対応方法を解説
部下や後輩がいると「仕事が遅い」と言ってしまうという方もいるかもしれません。これの言動は実は要注意であって、パワハラに該当する恐れがあります。 本記事では「仕事が遅い」と言うのがパ…
詳しくみる労働契約法第10条とは?就業規則や不利益変更、違反例をわかりやすく解説
就業規則の変更を考えているものの、労働者の同意が得られない、または労働者に不利益になる内容を盛り込みたいといった悩みは、多くの人事・労務担当者や経営者が抱える問題です。 労働契約法…
詳しくみる高齢者の雇用延長65歳、70歳の義務とは?2025年改正や企業の手続きを解説
少子高齢化が進む日本では、高齢者の雇用延長が企業経営の課題となっています。2025年の法改正により、65歳までの雇用義務に加え、70歳までの就業確保が努力義務として求められるように…
詳しくみるアルコールチェック義務化に対応した就業規則の記載例・サンプル|車両管理規程も紹介
2022年から始まったアルコールチェックの義務化。安全運転管理者を選任している事業所では、業務で自動車を使用する運転者へのアルコールチェックが必須業務となりました。この法改正を受け…
詳しくみる人事とは?役割や仕事内容、労務との違いなどを解説!
企業が成長するためには、優秀な人材を獲得することが必要です。人材採用を担当する部署である人事が有効に機能していなければ、優秀な人材を獲得できず、企業の成長も望めないでしょう。 当記…
詳しくみるハロー効果とは?ピグマリオン効果との違いや具体例を紹介!
ハロー効果とは、特定の印象に引きずられて全体を判断してしまうことを指す心理学用語です。たとえば「優秀だ」と判断した相手なら、優秀ではない分野も優秀だと判断することを意味します。ハロ…
詳しくみる
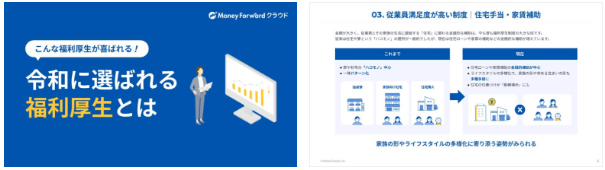
.jpg)
