- 更新日 : 2025年11月19日
役員報酬の給与明細は必要?テンプレートをもとに書き方を解説
役員報酬は給与明細の発行が必要です。役員は労働者ではありませんが、役員報酬は所得税法上の給与所得に該当するため、明細の発行が義務付けられています。従業員を雇わない一人社長であっても、明細を発行しなければなりません。
本記事では、役員報酬の給与明細に使える無料のテンプレートを紹介するほか、書き方の注意点や記入例も合わせて解説します。
目次
役員報酬も給与明細の発行が必要
役員報酬にも、給与明細の発行が必要です。その理由は、所得税法によって発行が義務付けられているためです。役員報酬は給与所得に該当し、給与などの支払いをする者は支払いを受ける者に支払明細書を交付しなければなりません。
給与などの支払いをする者とは、会社です。支払いを受ける者は役員であるため、役員にも給与明細が必要ということになります。
参考:所得税法|e-Gov
一人社長の場合も役員報酬の給与明細は必要?
従業員を雇わず社長が一人で事業を行っている、いわゆる「一人社長」の場合でも、給与明細は発行しなければなりません。
一人社長は、法人から給与所得を受けているためです。一人社長として事業を行っている方は、法人と社長を区別して実感する機会が少ないかもしれません。しかし一人社長は、従業員を雇っていないというだけで、給与明細の発行については従業員を雇用している法人と同じです。
なお、個人事業主は一人社長とは異なります。個人事業主は法人から報酬を受けている立場ではないため、給与明細は必要ありません。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
給与明細電子化マニュアル
こちらは「給与明細電子化マニュアル」の資料です。給与明細の電子化をご検討中、または導入を進めている企業様向けの資料となります。
情報収集や実務の参考資料として、ぜひご活用ください。
給与明細(自動計算できる計算式入り)
こちらは「給与明細(自動計算できる計算式入り)」の資料です。給与計算を自動で行うための計算式が設定されています。
日々の給与計算業務の参考資料として、ぜひご活用ください。
給与計算 端数処理ガイドブック
給与計算において端数処理へのルール理解が曖昧だと、計算結果のミスに気づけないことがあります。
本資料では、端数処理の基本ルールをわかりやすくまとめ、実務で参照できるよう具体的な計算例も掲載しています。
給与計算がよくわかるガイド
人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。
複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。
そもそも役員報酬とは?
役員報酬とは、会社との委任関係に基づいて支払われる報酬です。役員と株式会社は「株式会社である法人が業務の執行や経営方針の決定を役員に委任している」という委任の関係にあります。
一方、従業員の給与は、雇用契約に基づいて支払われます。従業員と株式会社は雇用契約に基づく雇用関係にありますが、役員と株式会社の間には雇用関係はありません。
参考:会社法|e-Gov
役員報酬と給与を両方もらえることはある?
役員報酬と給与は、原則として同時にもらうことはできません。ただし、例外があり「使用人兼務役員」に該当する場合は、役員報酬と給与を同時に受け取れます。
使用人兼務役員とは「役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事する者」です。たとえば、取締役営業部長として取締役(役員)の地位がありつつ、営業部長として従業員の業務も行う場合などが該当します。
使用人兼役員として役員報酬と給与を同時に支払う場合、役員報酬の部分と給与の部分を明確に区別して算定しなければなりません。たとえば「役員と従業員の業務でまとめて1,000万円」といった決め方は不可能です。役員報酬は株主総会など役員報酬の規定に則り決定し、給与は従業員の報酬規程などに則り決定します。
参考:No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人|国税庁
役員報酬と給与はどっちが得?
企業の節税という観点で考えると、役員報酬で支払うよりも給与で支払うほうが得です。給与は全額を損金として経費計上できますが、役員報酬は条件を満たしたときにのみ経費計上が可能なためです。
役員報酬を経費計上できる条件は、以下のとおりです。
- 定期同額給与や事前確定届出給与、業績連動給与に該当するように支払うこと
- 同業他社と比べて著しく高額でないこと
- 期限内に金額を決定すること
役員報酬は脱税につながらないよう、会社法や所得税法で支給のルールが定められています。著しく高額であったり、金額が頻繁に変動したりする場合は、損金として経費計上できなくなる可能性があるため注意しましょう。
また社会保険料の会社負担率は、役員報酬として支払っても給与として支払っても同率です。ただし、役員は原則として雇用保険に加入できないため、役員報酬で支払う場合は雇用保険料の会社負担がありません。
もらう側からすると、役員報酬は雇用保険料の控除がないため、支給総額が同じであれば役員報酬のほうが手取りは多くなります。ただし、失業した際の基本手当など(いわゆる「失業手当」)がもらえない点に注意が必要です。
参考:No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁
参考:取締役、監査役等、法人役員の雇用保険の適用について|厚生労働省
以下の記事では、役員報酬についてより詳しく解説しています。
役員報酬の給与明細にも使える無料テンプレート
マネーフォワード クラウドでは、役員報酬の給与明細にも使えるテンプレートをご用意しております。無料でダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。
役員報酬の給与明細の書き方
役員報酬の給与明細も、従業員の給与明細と同じフォーマットを利用できます。ただし、役員に適用されない一部の項目は、明細にも記載しません。ここでは支給項目、控除項目、勤怠項目の3つに分けて解説します。
| 支給項目 | 控除項目 | 勤怠項目 |
|---|---|---|
| 役員報酬 (通勤手当など) | 健康保険料 所得税 | 空欄 |
支給項目には役員報酬と各種手当を記載します。役員報酬は原則定額であり、給与締め期間の途中から就任した場合でも、日割支給にはなりません。各種手当を支給する場合は、手当が定期同額給与に該当するかを必ず税理士などに確認しましょう。定期同額給与に該当しない場合、手当を損金に算入することは不可能です。
時間外手当は定額、変動のいずれであっても役員には支給されません。役員は勤怠の管理を受けない立場であるため、欠勤控除や休日出勤手当など、勤務時間に対する手当や控除の対象外です。
社会保険料と税の源泉徴収は、雇用保険を除いて従業員と同じ取り扱いになります。健康保険料と厚生年金保険料は年齢を問わず徴収されますが、介護保険料は40歳以上65歳未満の場合のみ徴収対象です。役員は原則として雇用保険の被保険者にはならないため、雇用保険料も徴収されません。
なお、役員報酬を0円と定めた場合は、社会保険に加入できないため健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料とも徴収されないルールです。代わりに、役員が個人で国民健康保険や国民年金保険に加入し、それぞれ保険料を納付します。国民健康保険や国民年金保険料は役員報酬から源泉徴収ができないため、役員報酬の明細に記載する必要はありません。
勤怠欄は、役員報酬の明細では空欄にします。役員は勤怠管理を受けない立場なので、出退勤の打刻など勤怠管理自体が不要です。もし本人が記録していた場合でも、記載する必要はありません。
代表取締役の給与明細の記入例
役員報酬の給与明細について、具体例を参照して解説します。従業員向けの明細との違いや注意点を確認してみてください。
記入例
- 役職:代表取締役
- 年齢:41歳
- 扶養親族:なし
- 役員報酬:50万円
- 役員報酬とは別に支払われる手当:通勤手当(1万円)
- 加入健康保険組合など:全国健康保険協会

- 支給
支給欄には役員報酬と通勤手当を記載しています。通勤手当は報酬規程によって役員報酬と別に支給する場合は通勤手当として記載しますが、役員報酬に含む場合は記載しません。家賃手当などそのほかの手当がある場合も、通勤手当と同様です。 - 社会保険料
社会保険料は従業員の場合と同じく、年齢と標準月額報酬額、加入している組合などによって決定されます。会社負担率も従業員の場合と同じく折半です。標準報酬月額は、会社宛てに届く標準報酬月額決定通知書を確認しましょう。
今回は代表取締役が41歳のため介護保険料も控除していますが、40歳未満の場合は控除の対象外です。また代表取締役は雇用保険が適用されないため、雇用保険料の控除もありません。 - 税金
所得税と住民税の取り扱いも従業員と同じです。所得税は、課税支給額の合計から社会保険料の控除額を差し引いた額に、所定の所得税率を乗じて算出します。住民税は居住自治体からの住民税通知書を確認して記載します。 - 勤怠
勤怠欄はすべて空欄です。
参考:令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表|全国健康保険協会
参考:取締役、監査役等、法人役員の雇用保険の適用について|厚生労働省
役員報酬用のテンプレートでミスなく明細を発行しよう
役員報酬にも給与明細の発行が必要です。記載事項は従業員とほとんど同じであるため、従業員用のテンプレートを流用してもよいでしょう。
ただし一部の項目では、役員報酬は従業員と異なる取り扱いをしなければなりません。専用のテンプレートを利用すると、手作業でのミスを防ぎ、業務負荷も軽減できます。マネーフォワードクラウドでは、役員報酬にも利用できるテンプレートを用意していますので、ぜひご活用ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
給与計算の業務内容は?労務を新しく担当する方向け
給与計算の担当者は、従業員に毎月賃金を支払う役割を果たすほか、国に税金を正しく納める業務を担います。責任が大きい分、やりがいも感じられる仕事といえるでしょう。 初心者が給与計算の業…
詳しくみる千葉県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
千葉県は国際貿易港である千葉港や成田空港を有し、物流や輸出入業が活発です。また、農業や観光業も盛んで、多様なビジネスが展開されています。こうした多岐にわたる業種では、給与計算の正確…
詳しくみる有給の理由を聞かれる場合の対応は?私用じゃダメ?しつこく聞かれるのはパワハラかどうかも解説
有給休暇は労働者の正当な権利ですが、取得時に「なぜ休むのか?」と理由を聞かれた経験がある方も多いのではないでしょうか。実は、労働基準法では有給休暇の取得理由を会社に伝える義務は明確…
詳しくみる代休と有給休暇の違いとは?給与計算の方法や運用のポイントを解説
休日出勤をした場合、代わりの休日として代休を取得してもらうことがあります。しかし、従業員が代休ではなく有給休暇を申請するケースもあり、どのように対応するべきか迷う担当者の方もいるで…
詳しくみるアルバイト・パートの給与計算方法は?確認事項と注意点を解説
アルバイトやパートの給与計算は、就業規則・給与規程・タイムカードなどの勤務管理書類を確認しながら進めます。時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた際は、アルバイト・パートに対しても社…
詳しくみる転勤の引っ越し費用は給与課税?非課税の範囲と支度金の扱いを解説
従業員の転勤。新たな門出は応援したいけれど、税務上の判断はあいまいで不安…。このような悩みを抱えていませんか? この記事では、転勤の引っ越し費用に関する給与課税のルールを分かりやす…
詳しくみる
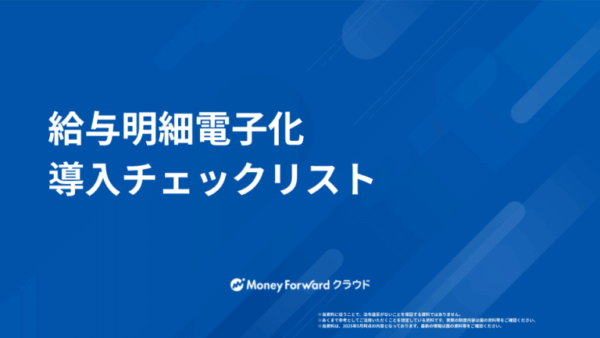
.png)

