- 更新日 : 2025年12月11日
休職のまま退職した場合の荷物の引き取り方!そのままはNG!
休職中に退職を決意した場合、会社に残している私物や業務関連の荷物の扱いについて整理する必要があります。
具体的には、自分で荷物を取りに行く手段や、上司や同僚に処分してもらう選択肢があります。また、会社から支給された物品については、退職日までに返却する義務があるため、その対応も忘れてはいけません。どのように進めるかを考えていくことが大切です。
目次
休職のまま退職した場合、荷物はどうする?
1.自分で取りに行く
休職中に退職を決めた場合、会社に残っている自分の荷物をどのように回収するかは大きな問題です。自分で荷物を取りに行く方法には、いくつかのポイントがあります。以下にその手順や注意点を詳しく説明します。
荷物を取りに行く前の準備
荷物を引き取りに行く際は、事前にいくつかの準備が必要です。これにより、スムーズに荷物を受け取ることができます。
- 退職日や訪問日を確認する: 自分の退職日や荷物を取りに行く日を明確に決めましょう。
- 会社の規定を確認する: 会社によっては、荷物を取りに行く際の規定や手続きがある場合があります。事前に確認しておきましょう。
- 連絡を入れる: 事前に上司や人事部門に連絡を入れて、荷物を取りに行く旨を伝えておくと安心です。
荷物の回収手順
実際に荷物を取りに行く際の流れは以下のとおりです。
- 訪問日時に会社へ行く: 事前に決めた日時に会社に赴きましょう。
- 受付での対応: 会社の受付で名前や目的を伝え、何か特別な手続きが必要か確認します。
- 荷物の確認: 自分の荷物を見つけたら、破損や不足がないかチェックしましょう。
- 必要書類の処理: 荷物を回収する際に、書類へのサインや手続きが求められる場合もありますので、指示に従ってください。
持ち帰りのポイント
荷物を持ち帰る際には、以下のポイントにも留意してください。
- 運搬用具を準備する: 大きな荷物や多数の荷物がある場合は、ダンボールや袋などの運搬用具を持参すると便利です。
- 時間に余裕を持つ: 荷物の確認や手続きに時間がかかることもあるため、余裕を持ったスケジュールでお願いします。
- 感謝の気持ちを忘れずに: 最後に同僚や上司に直接お礼を言っておくと良いでしょう。良好な関係を保つためにも大切です。
荷物を自分で取りに行くという選択は、後々のトラブルを避けるためにも非常に有効です。正しい手順を踏んで、ストレスの少ない回収を心がけましょう。
2.上司や同僚に処分してもらう
休職のまま退職する際、自分の荷物を取りに行くことが難しい場合、上司や同僚に処分してもらう方法もあります。この方法では、信頼できる人に依頼することが大切です。以下に、具体的な手順や注意事項を説明します。
依頼する際の手順
上司や同僚に荷物の処分をお願いする際は、以下の手順を参考にしてください。
- 信頼できる人を選ぶ: 自分の荷物を預けるので、信頼できる上司や同僚を選びましょう。
- 事前に連絡を取る: 希望する処分方法や、自分の意思を伝えるために、事前に連絡をします。電話やメールなど、相手が確認しやすい方法を選びましょう。
- 具体的な指示を伝える: どの荷物を処分してほしいか、またその方法(捨てる、寄付するなど)を具体的に指示します。
- 感謝の意を示す: 依頼が終わった際には、必ずお礼の言葉を伝えましょう。信頼関係を築くためには、感謝の気持ちが重要です。
処分の方法と注意点
荷物の処分方法にはいくつかの選択肢があります。以下の方法を検討し、必要に応じて選んでください。
- 廃棄: 使わない荷物は、廃棄することが一般的です。ただし、会社の規則やゴミの分別方法には注意が必要です。
- 寄付: まだ使える物品は、寄付することも考えてみましょう。使用する際には、事前に所定の手続きを確認してください。
- 友人や知人に譲る: 友人や知人に必要な物品を譲るのも良い方法です。この場合も、事前に連絡を取り、相手の意向を確認しましょう。
また、上司や同僚に依頼する際には、彼らの負担にならないよう配慮が必要です。無理なお願いにならないように、相手の状況を考慮しましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
実務ステップで学ぶ!休職者対応ガイドブック
この資料は、メンタルヘルス不調による休職者対応にスポットをあてた実務ガイドです。
突発的に発生する休職対応に戸惑うことなく対処できるよう、原則的な手順や対応のポイントをわかりやすくまとめました。
復職願・復職申請書(エクセル)
従業員の方が休職から復帰される際には、復職の意思を確認する書類が必要となる場合があります。
本資料は、「復職願・復職申請書」のテンプレートでございます。 Microsoft Excel(エクセル)形式のため、ダウンロード後すぐに編集してご利用いただけます。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
人事・労務担当者向け Excel関数集 56選まとめブック
人事・労務担当者が知っておきたい便利なExcel関数を56選ギュッとまとめました。
40P以上のお得な1冊で、Excel関数の公式はもちろん、人事・労務担当者向けに使い方の例やサンプルファイルも掲載。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。お手元における保存版としてや、従業員への印刷・配布用、学習用としてもご活用いただけます。
会社支給物品は、退職日までに返却する必要がある
退職する際には、会社から支給された物品を忘れずに返却しなければなりません。
ここでは、会社支給物品についての具体的な内容と返却方法を解説します。
1. 会社支給物品の例
退職時に返却が求められる物品には、以下のようなものがあります。
- 名刺ホルダーや名刺
- 社用パソコンやタブレット
- 携帯電話やスマートフォン
- 社員証や入館カード
- 制服や作業着
- その他のオフィス用品(例:文房具など)
これらの物品は、会社の資産であるため、円満な退職をするために必要な手続きとして返却が必要です。
2. 返却のタイミング
物品の返却は退職日までに行うことが求められます。具体的なタイミングについては以下のポイントを考慮してください。
- 退職日の数日前から計画的に返却を進める。
- 上司や人事部門に返却方法や日時を確認する。
- 返却時に物品の状態を確認し、記録を残す。
これにより、返却漏れや紛失を防ぎ、スムーズに退職手続きを進めることができます。
3. 返却方法
物品の返却方法は、会社によって異なる場合があります。一般的な流れとしては以下のようになります。
- 個別返却: 直接上司や人事部門に手渡す方法。
- 集団返却: 退職者が一定の日に集まり、一括で返却する方法。
- 郵送: 会社が指定する住所に郵送する方法。
返却方法については、事前に確認し、指示に従うようにしましょう。
4. 返却しない場合のリスク
返却を忘れたり、意図的に返却しなかったりすると、以下のようなリスクが考えられます。
- 未返却物品に対する請求が発生する可能性がある。
- 会社との信頼関係が損なわれる。
- 今後の職業生活において、前職の評価に影響を及ぼす恐れがある。
このようなリスクを避けるためにも、支給された物品は必ず退職日までに返却するよう心がけましょう。
休職証明書のテンプレート(無料)
以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。
休職のまま退職で荷物を引き取りたいですが、勇気が出ません…
休職のまま退職した場合に荷物を引き取るのが難しいと感じるのは、感情的に非常に理解できる状況です。以下のアプローチが役立つかもしれません。
1. 気持ちを整理する
退職に対する不安や躊躇は、職場での関係や経験が影響していることがあります。まず、自分の気持ちを整理し、「なぜ勇気が出ないのか」を考えてみると、少し気持ちが軽くなるかもしれません。
2. メールや電話で連絡する
職場に直接行くのが難しい場合、まずは上司や人事担当者にメールや電話で連絡し、荷物を取りに行く日程を調整してもらう方法があります。もし心配であれば、荷物をまとめて郵送してもらうことも可能かもしれません。
3. 第三者に依頼する
職場に行くことがどうしても負担であれば、家族や友人に荷物を取りに行ってもらうのも一つの方法です。これにより、心理的な負担を軽減できるでしょう。
4. タイミングを選ぶ
職場が空いている時間や他の人が少ない時間帯を選ぶことで、他の人との対話や気まずさを避けることができます。
5. 自分をいたわる
退職や荷物の引き取りがストレスに感じるのは自然なことです。小さなステップで進むことを自分に許し、無理をせずに行動してください。
このような状況では、無理をせず、できる範囲で進めることが大切です。どんな選択をしても、自分を大切にすることを忘れないでくださいね。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
就業規則への福利厚生の記載例|厚生労働省のモデルに準拠したテンプレートを無料配布
従業員のエンゲージメントを高め、魅力的な職場を築くために欠かせないのが「福利厚生」です。しかし、慶弔見舞金や住宅手当といった制度を導入する際「就業規則にどこまで書けばいいのか?」「…
詳しくみる福利厚生による節税の仕組みとは?経費になる条件や節税効果の高い制度も解説
福利厚生は、従業員の働きやすさや満足度を向上させる制度として広く認識されていますが、実は企業にとって法人税を軽減する「節税対策」としての側面も持っています。特に、法定外福利厚生費の…
詳しくみる会社都合での解雇とは?種類や他の離職理由との違い、企業の注意点、手続きの流れなど徹底解説
人事労務担当者にとって、会社都合による解雇は、法的な制約が非常に厳しく慎重な対応が求められるテーマの一つです。本記事では、会社都合解雇の基本的な定義から、自己都合退職との明確な違い…
詳しくみる外国人労働者雇用労務責任者講習とは?講義の内容や受講するメリットを解説
外国人労働者雇用労務責任者講習は、外国人雇用に関する法令や適切な労務管理の方法を学べる講習です。日本で働く外国人労働者は年々増加しており、適切な雇用管理の需要性が高まっています。 …
詳しくみる人事とは?役割や仕事内容、労務との違いなどを解説!
企業が成長するためには、優秀な人材を獲得することが必要です。人材採用を担当する部署である人事が有効に機能していなければ、優秀な人材を獲得できず、企業の成長も望めないでしょう。 当記…
詳しくみる育休の期間は何ヶ月?制度別に取得できる日数の計算方法を解説
育児休業(以下、育休)は、子育てと仕事の両立を支援する重要な制度です。近年、男性の育休取得促進や働き方の多様化に伴い、育休制度もより柔軟なものへと変化しています。しかし、「産後パパ…
詳しくみる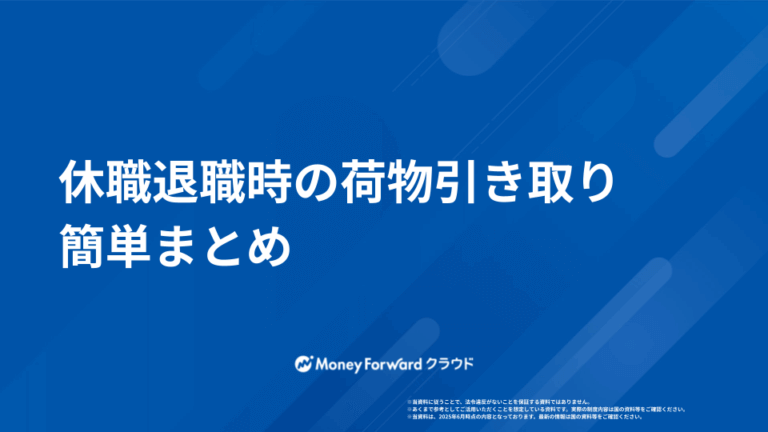

-e1762261509691.jpg)

