- 更新日 : 2024年8月29日
ピアボーナスとは?導入するメリット・デメリットや失敗しないポイントを解説!
給与や賞与などの報酬は、従業員の業務に対するモチベーションを維持するためにも重要な要素です。近年では、通常の報酬とは別に従業員同士が報酬を贈り合えるピアボーナスと呼ばれる制度を設ける企業も存在します。
当記事では、ピアボーナスについて横断的な解説を行います。導入事例も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
ピアボーナスとは?
「ピアボーナス」とは、同僚や同輩、仲間といった意味を持つ英単語の「Peer」と、手当や賞与を意味する「Bonus」を組み合わせた造語です。従業員同士が業務の成果や、貢献を称えるとともに、少額のインセンティブを贈り合う仕組みを指します。上司ではなく従業員同士が評価を行うのが特徴で、新しい人事評価や報酬の制度として注目されています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
エンゲージメント向上につながる福利厚生16選
多くの企業で優秀な人材の確保と定着が課題となっており、福利厚生の見直しを図るケースが増えてきています。
本資料では、福利厚生の基礎知識に加え、従業員のエンゲージメント向上に役立つユニークな福利厚生を紹介します。
令和に選ばれる福利厚生とは
本資料では、令和に選ばれている福利厚生制度とその理由を解説しております。
今1番選ばれている福利厚生制度が知りたいという方は必見です!
福利厚生 就業規則 記載例(一般的な就業規則付き)
福利厚生に関する就業規則の記載例資料です。 本資料には、一般的な就業規則も付属しております。
ダウンロード後、貴社の就業規則作成や見直しの参考としてご活用ください。
従業員の見えない不満や本音を可視化し、従業員エンゲージメントを向上させる方法
従業員エンゲージメントを向上させるためには、従業員の状態把握が重要です。
本資料では、状態把握におけるサーベイの重要性をご紹介いたします。
ピアボーナスが注目されている背景は?
ピアボーナスが注目を集める背景には、従業員のモチベーションの維持向上が存在します。従業員のモチベーションが高まれば、生産効率が上がり、企業の業績も向上します。モチベーションの維持向上を図る新たな評価・報酬制度として、ピアボーナスが注目されているわけです。
ピアボーナスが注目を集める背景には、コミュニケーションの円滑化も挙げられます。ビジネス活動は、ひとりではなく複数人によるチームで行われることも多く、互いの貢献を称え合うピアボーナスは、メンバー同士の円滑なコミュニケーションも促進するでしょう。
ピアボーナス制度を導入するメリットは?
適切にピアボーナスを制度として導入すれば、企業に多くのメリットをもたらします。メリットごとに見ていきましょう。
協力関係の強化
ピアボーナスは、従業員同士がお互いに賞賛と報酬を贈り合う制度です。贈り合う従業員は、同じ部署やチームだけでなく、他部署や他チームの場合も存在します。ピアボーナス制度を導入すれば、所属する部署内だけでなく、他部署等との協力関係も構築できるようになるでしょう。
コミュニケーションの円滑化
ピアボーナスとして、賞賛と報酬と贈り合えば、贈り合った回数分のコミュニケーションが発生します。コミュニケーションの内容は、達成した成果や貢献に対するものであり、ポジティブなものです。互いにピアボーナスを贈り合い続けていけば、意思の疎通を図りやすくなり、コミュニケーションが円滑化される好循環が生まれます。
従業員のエンゲージメント向上
給与や賞与の額を引き上げることは、従業員のエンゲージメント向上に有効な施策です。しかし、給与額等の引き上げによるエンゲージメント向上は、永続的なものではありません。また、高い給与だけを目的としていては、職場の雰囲気もギスギスとしてしまうでしょう。
ピアボーナスによるお互いへの賞賛は、会社の雰囲気を明るくし、風通しを良くする効果も期待できます。明るく風通しの良い職場であれば、従業員も「ここでずっと働きたい」と考え、エンゲージメントが向上するでしょう。
人材流出の防止
従来型の評価制度では、契約金額や達成率といった定量的な成果や、上司が実際に把握した仕事ぶりから評価を下されてしまいがちです。評価者である上司と被評価者である従業員の間で、評価に対する乖離が生じ、離職や転職につながることも珍しくありませんでした。
一方のピアボーナスでは、目に見えない貢献や表面に出にくい成果も評価可能です。そのような貢献や成果を評価されれば、従業員の満足度が高まり、離職率を低下させる効果も期待できるでしょう。
ピアボーナス制度を導入するデメリットは?
メリットの多いピアボーナス制度ですが、デメリットも存在します。デメリットを把握することで、ピアボーナス制度のメリットを最大化しましょう。
制度導入や運用のコスト
ピアボーナス制度を導入するために、専門的なシステムやツールを用いれば、初期コストが掛かってしまいます。新しいシステムであれば、運用者に対する負担も大きくなるでしょう。また、ピアボーナス制度における報酬を現金とした場合には、その原資も用意しなければなりません。
評価への固執
ピアボーナス制度は、従業員のモチベーションや満足度の向上に役立ちます。しかし、より高い評価を得るために、評価されやすい仕事ばかりを選んだり、本来の業務を蔑ろにしたりしてしまう従業員が出る可能性も否定できません。
人間関係の悪化
ピアボーナスは、従業員同士が評価し合う制度です。上司ではなく現場の従業員同士が評価しているため、従来であれば気づかれないような貢献も評価可能です。
しかし、従業員がお互いを適切に評価できる場合ばかりとは限りません。「自分だけ評価されていない」「こちらは評価したのに、相手は評価してくれない」といった不公平感が生まれる場合もあります。そのような不公平感は、チーム内の人間関係を悪化させてしまいます。
ピアボーナス制度の導入に成功した企業事例は?
メリットの多いピアボーナス制度を導入する企業も少なくありません。導入企業事例を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
株式会社メルカリ
株式会社メルカリは、人事制度やエンゲージメント向上の施策の一環として、「メルチップ(mertip)」と呼ばれるピアボーナス制度を導入しています。メルチップは、従業員同士がリアルタイムで感謝や賞賛し合うとともに、インセンティブ(一定額の金銭)を贈り合える制度です。
導入後の社内調査においても、87%と高い満足度が示されており、期待以上の効果を上げています。また、アンケートでも、「他部署との調整ハードルが下がった」「お互いにお礼を言いやすくなった」といった意見が挙げられています。
参考:贈りあえるピアボーナス(成果給)制度『mertip(メルチップ)』を導入しました。|株式会社メルカリ
株式会社日阪製作所
株式会社日阪製作所は、「働きがい支援室」を立ち上げるなど、従業員のウェルビーイング向上に取り組む企業です。同社では、ウェルビーイング向上施策の一環として、ピアボーナスツールである「Unipos」を導入し、従業員同士が感謝を伝え合うために役立てています。
Unipos導入後の利用率は、70%を達成し、好意的な反響も多く得られたそうです。また、Uniposの表彰制度を活用することで、経営理念を体現した従業員を表彰するとともに、メルマガを発行し、さらなる制度の浸透を図っています。
参考:男性が多い環境でも定着!社内の雰囲気が変わった|Unipos
ピアボーナス制度の導入に失敗しないためのポイントは?
ピアボーナス制度を導入するためには、いくつかのポイントを踏まえたうえで行うことが必要です。導入の効果を高めるポイントを紹介します。
モデルチームの作成
導入事例も増えているとはいえ、ピアボーナス制度に馴染みがない企業も多く存在します。導入しても従業員が「褒め合う」という行為に不慣れで、効果を発揮できない場合もあるでしょう。このような事態を避けるためには、導入を推進するためのモデルチームを作成し、同チームが率先してピアボーナス制度を利用する姿勢を示すことが重要です。
運用の工夫
ピアボーナスは、制度を導入して終わりではありません。制度導入後に運用を工夫し、従業員に利用してもらう必要があります。ただ導入して終わりでは、期待した効果を上げることも叶わず、失敗に終わってしまうでしょう。
そのような事態を避けるためには、年末年始をはじめとした季節ごとの行事とピアボーナスを紐付けるのが有効です。一年の始まりや終わりに感謝を伝え合うようにすれば、ピアボーナスの習慣化につながり、制度も浸透しやすくなるでしょう。
事例の紹介
制度を浸透させ、利用率を向上させるためには、従業員に「ピアボーナスは良い制度である」と思ってもらわなくてはなりません。そのためには、全体会議といった多くの従業員が集まる場で、良い投稿を取り上げ紹介するような取り組みが必要です。良い事例の紹介は、利用を躊躇う従業員に対して、背中を押すことにつながります。
適切なシステム・ツールの採用
ピアボーナス制度に用いられるシステムやツールは、複数存在します。直感的な操作ができず利用しづらいツールでは、制度の浸透を図れず、導入は失敗に終わってしまいます。どのツールを用いるのも自由ですが、制度を正しく機能させるために適切なツールを選択しましょう。
ピアボーナス制度の導入におすすめのツールは?
どのようなツールを用いてピアボーナス制度を導入するかは、非常に重要です。適切なツールを選択しなければ、制度導入の効果を最大限に発揮することができません。おすすめのツールを2つ紹介します。
Unipos(ユニポス)
「Unipos」は、Unipos株式会社が企業に向けて提供しているピアボーナスツールです。基本給やボーナスだけでなく、同僚からの感謝の気持ちとともに少額のインセンティブを、スマートフォンなどを通し、手軽に送受信できるシステムが特徴です。
投稿はタイムラインでの共有のほか、ハッシュタグによって、行動指針と紐づけることも可能です。拍手機能でも賞賛できるため、ピアボーナス制度を簡単に利用できます。
参考:人と組織の行動力を引き出し、カルチャーを変える|Unipos
THANKS GIFT(サンクスギフト)
「THANKS GIFT」は、株式会社Take Actionが提供するピアボーナスサービスです。従業員同士の「感謝」のコイン化や、自由に贈り合える「サンクスカード」などのサービスが特徴です。
コインは、導入企業ごとにカスタマイズ可能で、経営理念などと紐づけすることで、企業文化の浸透にも寄与します。掲示板機能も備えており、社内におけるコミュニケーション促進にも役立つでしょう。
ピアボーナス導入によって新たな評価制度を
企業における活動では、表に出やすい目立った功績ばかりが評価されがちです。しかし、目立った功績を挙げる従業員ばかりが評価されれば、それを支える周りの従業員は不満を溜めてしまいます。不満の蓄積は、業務に対するモチベーションを低下させ、最悪の場合は離職にもつながってしまいます。
貴重な人材を流出させないためにも、新たな評価制度の構築が必要となるでしょう。その際には、当記事で紹介したピアボーナス制度が、選択肢のひとつとなります。適切に導入・運用すれば、離職率の低下をはじめ、多くのメリットをもたらす制度のため、ぜひ導入を検討してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
最低賃金を下回ってない?確認するための計算方法を紹介
最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額です。最低賃金以上であることを確認する計算方法は、時給制、日給制、月給制など、給与形態によって異なります。また、夜勤…
詳しくみる同一労働同一賃金とは?目的や根拠法などをわかりやすく解説
働き方改革の重要施策の1つに「不合理な待遇差を解消するための規定の整備」があります。これが、いわゆる「同一労働同一賃金」であり、その目的は、同一企業内での無期雇用のフルタイム労働者…
詳しくみる確定拠出年金で運用できる商品の特徴とリスクを比較
確定拠出年金では、加入者自らが年金資産を運用しますが、資産運用と聞いても、初めての方には何をどのようにしたらよいのかイメージしにくいかもしれません。 しかし、確定拠出年金には「運営…
詳しくみる60歳以降の再雇用の給与相場とは?業種や男女の違い、企業の取り組みを解説
60歳以降の再雇用が進む中、年齢に伴う給与の減少や、業種ごとに異なる給与水準が影響を与えています。この記事では、60歳以降の再雇用における給与相場、減額される理由や実際の事例につい…
詳しくみる昇給の稟議書の書き方は?テンプレートや例文でポイントが分かる!
昇給稟議書の例文やテンプレートをお探しの方も多いのではないでしょうか。本記事では、昇給の稟議書の書き方を具体的に解説し、テンプレートや例文を交えてポイントを分かりやすく紹介します。…
詳しくみる従業員の所得税はいつ払う?納期や納付方法、納付期限を過ぎた場合を解説
従業員の給与には所得税が課せられます。企業は、給与から徴収した所得税を納付期限までに納めなくてはなりません。 当記事では、所得税の納付期限や納付方法、特例などについて解説します。納…
詳しくみる
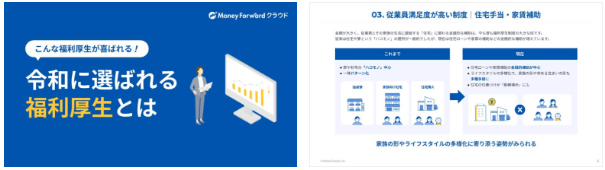
.jpg)
