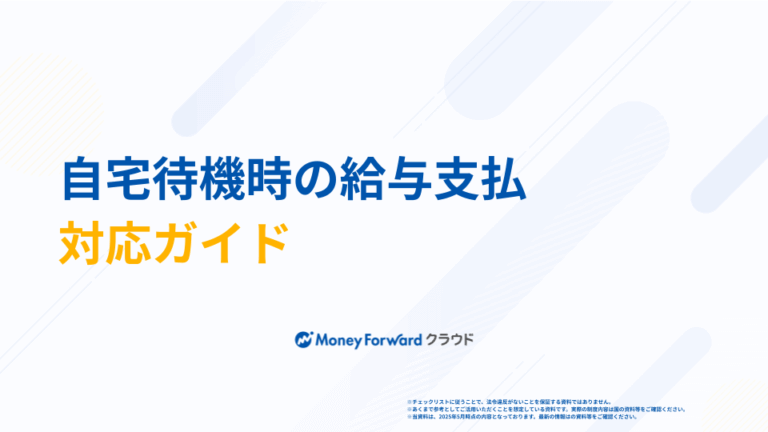- 更新日 : 2025年11月20日
自宅待機とは?給与は発生する?出勤停止との違いも解説!
自宅待機とは、会社が従業員の出勤を禁止し自宅で待機させることです。自宅待機は従業員の働く権利を制限することになるため指示するときは注意が必要です。
本記事では、自宅待機の意味と具体的なケースについて解説します。待機中に給与が発生するかどうか、指示するときの注意点も紹介しますので、人事労務担当の人は参考にしてください。
自宅待機とは?
「自宅待機」とは、従業員に出勤を禁止して自宅で待機するように命じることです。自宅待機を命じる理由はさまざまです。また、間違いやすい「出勤停止」とは、法的根拠や給与支給の取り扱いが異なります。両者の違いや、自宅待機の種類について解説します。
出勤停止との違い
出勤停止とは、従業員が就業規則や企業秩序に違反した場合に制裁として行われる「懲戒処分」の1つです。認められるのは、就業規則に記載された懲戒理由に該当するときだけです。
一方、自宅待機は会社からの「業務命令」です。業務上の必要性があれば、就業規則に具体的理由が記載されていなくても自宅待機を命じられます。
給与については、出勤停止は従業員の懲戒を目的とすることから原則無給です。就業規則に「出勤停止中は無給とする」旨の規定が設けられているのが一般的です。
一方、自宅待機は会社が業務上の必要性から行う業務命令で、従業員に違反などがないことが前提となるため給与は支払われます。
病気の場合の自宅待機と懲戒処分等の自宅待機の違い
自宅待機を命じる代表的な理由は、病気によるものと懲戒処分を前提としたものです。
病気による自宅待機は、従業員が病気で就業すると本人だけでなく周囲に迷惑をかける恐れがある場合などに行われます。たとえば、病気の感染を防ぐために、新型コロナウイルスにかかった従業員の出勤を一定期間認めないケースなどが該当します。
また、自宅で療養が必要な状況で従業員が無理して仕事をしようとしたとき、会社が自宅待機を命じることもあります。会社には従業員の健康と安全に配慮する義務があるため、正当な業務命令であるといえます。
一方、懲戒を前提とした自宅待機は、懲戒理由に該当するかどうか、どの程度の懲戒処分を下すかを判断するための時間を確保するために行います。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項
労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。
本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。
時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール
年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。
本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。
労働時間管理の基本ルール【社労士解説】
多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。
労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。
労働条件通知書・雇用契約書の労務トラブル回避メソッド
雇用契約手続きは雇入れ時に必ず発生しますが、法律に違反しないよう注意を払いながら実施する必要があります。
本資料では、労働条件通知書・雇用契約書の基本ルールをはじめ、作成・発行のポイントやトラブル事例について紹介します。
自宅待機を指示するケース
前述の「病気の場合の自宅待機」と「懲戒処分等の自宅待機」のほかにも、会社が自宅待機を指示することがあります。主なケースは次の通りです。
- トラブルや不正調査のための時間が必要なケース
- 会社都合により業務が停止するケース
- 自然災害など外部要因により業務が停止するケース
- 退職者による情報漏洩防止を図るケース
- 復職の可否判断が必要なケース
それぞれのケースについて解説します。
トラブルや不正の調査のための時間が必要なケース
社内でトラブルや不正が発生した場合、関係者に自宅待機を命じて調査することがあります。自宅待機させるのは、セクハラやパワハラが発生した場合は加害者による被害者への嫌がらせを防止すること、盗難事故の場合は証拠の隠滅を防ぐことなどが目的です。
懲戒処分の可能性があるトラブルや不正の場合、懲戒処分を前提とした自宅待機となります。
会社都合により業務が停止するケース
部品の不足や設備の故障などによって会社の業務が停止し、従業員に自宅待機させるケースがあります。この場合、会社に責任があるため、従業員には給与を支払わなければなりません。
会社の判断で給与が全額支払われることもありますが、労働基準法では最低限、平均賃金の6割以上の「休業手当」の支払いを会社に義務付けています。
自然災害など外部要因により業務が停止するケース
自然災害が原因で就業が危険であったり、会社の建物や設備に被害が発生して業務を停止せざるを得なくなったりすることで、自宅待機に至るケースもあります。
ただし、天変地異による休業は会社に責任のある休業とはみなされないため、法律上、企業に休業手当の支給義務はありません。
退職者による情報漏洩防止を図るケース
退職者による企業情報や機密情報の漏洩事件が話題となり、退職者が機密情報などを社外に持ち出さないように自宅待機にする企業も出てきました。情報漏洩リスクを避けるための会社判断によるもので、退職者には責任がないため給与は全額支給されます。
復職の可否判断が必要なケース
病気やけがなどで休職していた従業員から復職の申し出があった場合、復職して問題がないかを判断するために一定期間の自宅待機を命じることがあります。就業可能である旨の診断書を提出してもらったり、面談したりすることによって判断するのが一般的です。
病気やけがでの休職中は次の手当が支給されますが、自宅待機を命じられた期間が休職中に含まれるかどうかは医師の診断などによって決まります。
- 労災による病気やけが:労災保険から休業補償給付
- 労災以外による病気やけが:健康保険から傷病手当金
自宅待機を指示する際の注意点 – 給与の支払いは発生する?
会社が従業員に自宅待機を指示する場合、注意すべき点がいくつかあります。主な注意点について解説します。
自宅待機の場合には給与の支払いを継続するのが一般的
従業員に自宅待機を命じる場合、待機期間中の給与は全額支給するのが一般的です。責任のない従業員に、経済的負担を負わせることはできません。懲戒を前提とした自宅待機についても、懲戒処分で制裁を課すため処分前の自宅待機中は給与を支払うのが一般的です。
ただし、会社都合による業務停止の場合、通常の給与より低額の休業手当を支給するケースがあります。また、自然災害による業務停止の場合、無給にすることもできます。
不当・不合理な自宅待機命令は違法になる可能性がある
従業員を雇用する会社は、自宅待機など業務命令を下す権限を持っています。しかし、自宅待機を命じる理由や、待機期間が不当・不合理である場合は、従業員の働く権利を害するとみられ違法になる可能性があります。
たとえば、退職者の業務内容から情報漏洩のリスクはないにもかかわらず情報漏洩防止を理由として自宅待機を命じるケースや、不正調査を目的とした自宅待機期間が不必要に長期となるケースなどです。
自宅待機の処分決定までの期間は?
自宅待機の処分が決まるまでの期間は、業務上の必要性が生じたら非常に短いのが一般的です。新型コロナウイルスに感染したと従業員から連絡を受けたときや、台風で工場の操業ができなくなったときなど、判明次第、自宅待機となることもあります。
不正調査のための時間が必要なケースや退職者による情報漏洩防止を図るケースでも、経営者や責任者が判断すれば短期間で処分が決まります。
一般的に自宅待機は何日程度?
自宅待機の期間は、自宅待機の必要性に応じて決まります。自宅待機が必要な理由に応じて、待機期間の目安は次の通りです。
- 不正調査のための自宅待機:調査と処分決定が終わるまで
- 会社都合による業務停止:業務停止事由がなくなるまで など
自宅待機が正当になる理由とは?
従業員の法令違反や就業規則違反などを理由として自宅待機を命じるには、正当な理由が必要です。それぞれについて解説します。
懲戒処分のための調査
懲戒処分の可能性がある事案が発覚した場合、懲戒処分が決定するまでの調査期間中、従業員に自宅待機を命じることは、正当な理由があると判断できます。該当の従業員の出勤によって職場に悪影響が出たり、調査妨害のリスクがあったりするためです。
証拠隠滅の可能性を排除するため
従業員に不正があったかどうか調査が必要な場合、自宅待機が証拠隠滅の可能性を排除する目的であれば、正当な理由があると判断できます。自宅待機によって、不正を隠すため関係者に口止めをしたり、証拠となる書類を隠匿したりすることを防止します。
自宅待機は法令や就業規則を基に慎重に判断しよう
自宅待機とは、業務命令として従業員に自宅で待機させることです。会社が自宅待機を命じるには正当な理由が必要であり、原則給与も支払わなければなりません。
自宅待機の理由や内容によっては、従業員が反発したり、違法と判断されたりする可能性もあるため、人事労務担当者は法令や就業規則を基に自宅待機の可否を慎重に判断する必要があります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
外国人雇用の注意点 – 関連する法律や手続きを解説
少子高齢化による労働人口の減少に歯止めが効かないなか、外国人の雇用を検討している人事担当者もいることでしょう。外国人労働者の受け入れ状況は、現時点では増加傾向で推移しています。一方…
詳しくみる正社員の勤務時間を変更するには?自己都合・会社都合のルールと手続きまとめ
正社員として働く中で、育児や介護、自身の健康状態の変化といったライフステージの変化により、「勤務時間を変更したい」と考える場面は少なくありません。また、会社側も経営状況の変化から勤…
詳しくみる在宅勤務等テレワーク導入にあたっての実務上の注意点とは?【報告書テンプレつき】
在宅勤務等テレワークにおける労働時間管理・残業時間の把握 在宅勤務等テレワークの導入にあたり、労働時間の管理や業務の進捗管理、人事・労務管理など、実務上の注意点は多岐にわたります。…
詳しくみる就業規則への中抜けの記載例|制度を運用する上でのポイントも解説
近年、働き方改革やライフスタイルの多様化に伴い、勤務時間中に一時的に業務から離れる中抜けのニーズが高まっています。役所での手続き、子どもの送迎、通院など、従業員が中抜けを必要とする…
詳しくみる2026年最新 – 勤怠管理システムおすすめ比較!機能・料金・クラウド対応など
勤怠管理システムを導入すると、タイムカード(打刻)機能により従業員の労働時間を正確に把握することができます。シフト管理機能など、その他にも多くの機能が備わっているため、勤怠管理業務…
詳しくみる高年齢者及び障害者雇用状況報告書の記入・申請方法
高年齢者及び障害者雇用状況報告書は、毎年7月15日までに対象企業からハローワーク宛てに提出するものです。未提出や虚偽の報告をした場合、企業名を公表されたり罰金の対象となったりするこ…
詳しくみる